
今週のkinologue【11/14-20】
秋の深まりを感じるようになった今週、なかなか手離れしていかない仕事たちが、絡んだ糸が解けていくかのように少しずつ動いてきた。先ずは次回配給作品のポスターのアプルーバルが拍子抜けするほどあっさり通った!めでたい。それに伴って、色々と動き出してきた。準備期間は十分だと思われていたのに、気づくとあまり時間がなくなっている。これからはどんどん巻いていかねばならない。
今週は3年ぶりに復活したカフェゼミにて、『〈主婦〉の学校』上映会ワークショップが開催された。カフェゼミは法政大学長岡研究室が大学を飛び出してオープンに開催しているゼミで、会場は大手町の3×3 Lab Future。30名くらいの学生さんたちの半分は長岡ゼミから、半分は他大学も含めて様々な接点から参加。そして10名くらいの社会人を合わせて約40名が集まって映画の鑑賞、「家事」についての対話、長岡先生による経営学的(と一口には言えないが)問いかけがあった。コロナ禍でゼミに入った学生さんたちにとっては「これがカフェゼミか!」と初めてのリアル開催に嬉しそう。みんなで集まって、映画観て、話すって楽しいんですよ。そんな細やかな楽しみも奪われていたのだなぁ。対話セッションでは「家事」について近くにいた人とグループになって語る。共有して貰う時間がなかったので、どんな対話になったのかよく分からなかったが、後で書いて貰ったコメントから、「家事」について考えたり話したりすること自体がとても新鮮だったことが伝わってきた。この映画から「家事を丁寧に行うライフスタイル」「生活の非経済的側面を大切にするライフスタイル」「非消費的な生活を楽しむライフスタイル」というトピックでの長岡先生の問いかけも興味深かったので、今回のワークショップについては改めてまとめたいと思う。というのも、最近読み直していた『くらしのアナキズム』と被るところがあったからだろう
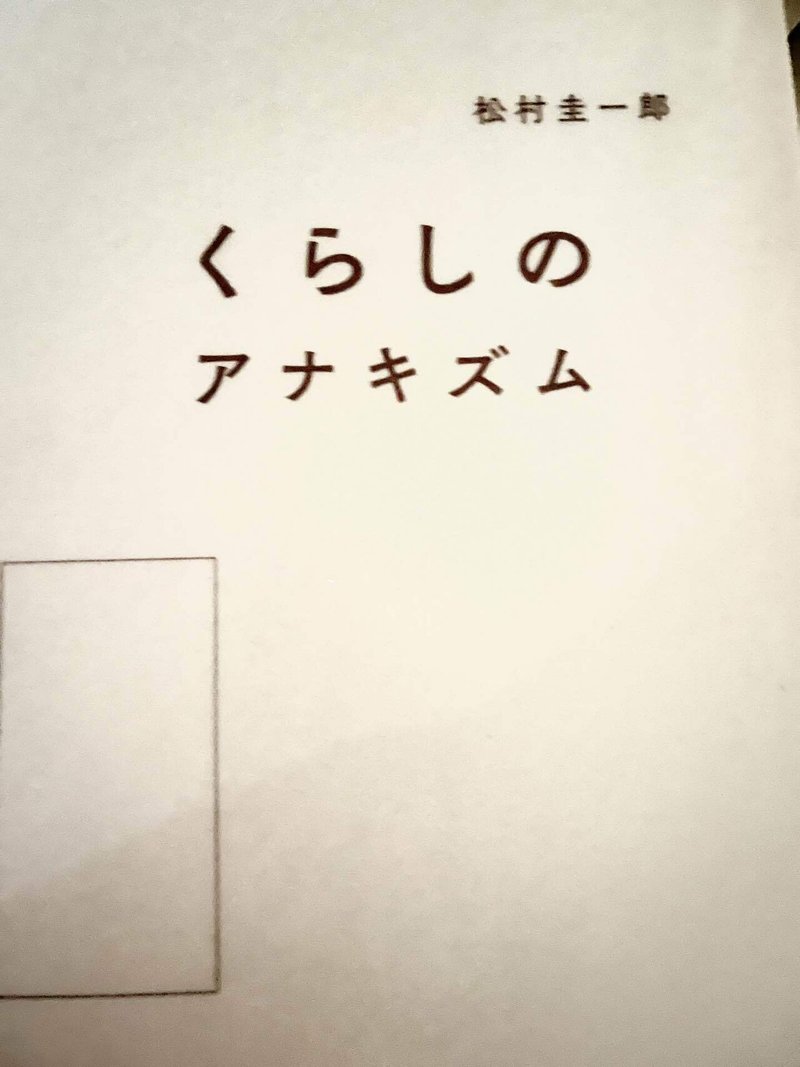
その中で、イリイチの『コンヴィヴィアリティのための道具』が引かれているが、経済的側面を重視してきた社会ではコンヴィヴィアリティ=自立共生の機会がいかに奪われてきたのか、コロナ禍で露わになったことの一つだ。今いる自分が、これからの自分が何に重きをおいて生きていきたいのか、この映画を観て考える機会になっていたら良いなぁと思っている。
ずっと見逃していた『秘密の森の、その向こう』をやっと観ることが出来た。監督が丁寧に隅々まで心を配って作っているのが感じられる。子どもも大人もフランス人の思慮深さに久々やられたなぁ。朝から素敵な映画を観て心が洗われた。

この日の午後は、フィールドワーク先で葉っぱのアートワークショップ。子どもたちに混ざって、生き物の下絵を描いて、葉っぱを切らずに貼って形作る。絵も苦手だし、葉っぱをペタペタ貼ってるだけで、何の生き物か分かって貰えるのかしら、と心配していたら、しきちゃんという女の子に「目をつけたらなんとかなるんだよ」と勇気づけられた。ありがとう!しきちゃん。赤や黄色の葉っぱの色がホントに美しくてうっとり。今年は紅葉を楽しんでないことに気づき、少し持ち帰った。これからどこかで見られるかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
