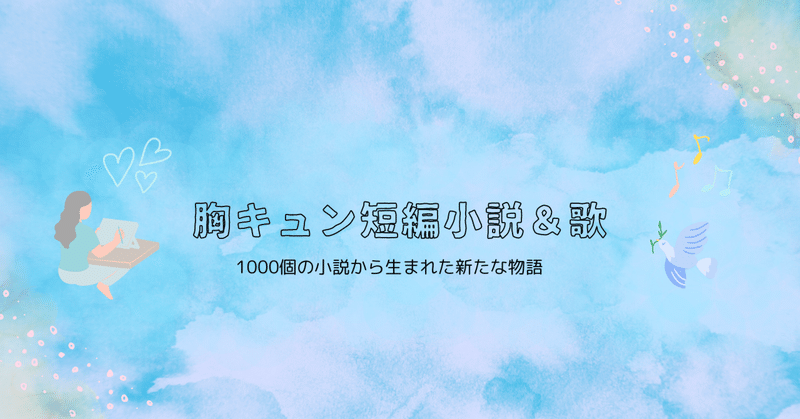
8 歌姫
いい子だねって言われる私。でもやっと気がついた。私が人気者なのは私が何者でもないからだって。何か大きなことがしてみたい。生きてる確かな証が欲しい。「いい子じゃなくてもずっと好きだよ」彼氏に言われてほっとして、とりあえず髪を切ってみた。キラキラ光る未来の私。まずはそのための第一歩。
「ねえ、こないだから独りぼっちだよね」
教室での昼食タイム。
私は同じグループの一人に小声で言った。
視線の先には窓ぎわで一人、イヤホンを耳に突っ込んでパンをかじっているクラスメイトがいる。
黒髪のボブで大人しそうな横顔。数日前から単独行動が多い。お弁当まで一人で食べているんだから、一緒に行動していたメンバーにハブられていると思っていいだろう。
「あー、歌姫ってことがバレたからね」
友人も小声で教えてくれた。
そう。彼女は顔出しなしでシンガーソングライターをやっていたらしい。
音楽に疎い私は名前を聞いても全然ピンとこなかったんだけど。
「しかもトップアイドルとコラボしてたでしょう。親友がガチ恋してたらしい」
「へえええ。なるほど、複雑なんだね」
とりあえず、元々のお仲間たちはしばらく戻ってこない雰囲気である。
私は声をかけてみることにした。
「ねえ、良かったら一緒に食べない?」
煙たそうな視線が私に向かい綺麗な眉根が寄せられる。
「別に、いい」
やっと聞き取れるぐらいの小声で言うと、がたん、と音を立てて彼女は席を立ち、お弁当をまとめて教室から出ていった。
(私、なんか悪いことしたかな)
ぼーっとしている私の肩を友人がぽん、と叩く。
「うーん。あんたに悪気がないのはわかるんだけどさ、断ってくれてホッとした。正直、来られても困るもん」
「えっ? そうなの?」
意外だった。みんな、すごく優しくて、逆に声をかけないのが不思議なくらいだったから。
「歌姫なんかとねえ、どうやって話していいかわかんないしさ」
「普通に話せばいいんじゃないの?」
ポカンとしている私に、みんなは顔を見合わせて苦笑する。
「ほんと、あんたはいい子だから、こういうのってわかんないよね」
「ね。マジでいい子だもん」
なんだか、言いにくそうだけど、空気を読まない行動をしてしまったことは、歌姫だけでなくそんなみんなの態度ではっきり分かった。
翌日の土曜日、遊びにきた隣の家に住む彼氏にその話をしたら
「へえええ。昨日まで自分と同じって思ってた子が実は凄い奴だった、ってなったら嫉妬とかもあるんじゃないの? 俺だってびっくりしたもん」
と言った。
「え? 彼女の歌、聞いたことあるの?」
「もちろん。てか、流行ってるじゃん」
私は彼氏の立ち上げた動画サイトを覗き込む。
ギターを手にしたボブカットの少女が飛び込んできた。顔にはモザイクがかけられている。
(これが彼女なんだ)
スマホ動画とはいえ、芸能人みたいだなあ、なんて思っていたら
「ちなみに1億再生な」
しれっと彼氏が情報を差し込んでくる。
「それって……凄いんだよね?」
「当たり前だろ? まあ、見ろよ。始まるぞ」
あきれ顔で促され、私はスマホに視線を戻した。
ギターから始まる静かなイントロ。
わー、歌上手いなあ、なんて思ったのは最初だけ。
透明感があるけれど、がつん、とハートに響く声。
ざわつくメロディ。そして刺さる歌詞。
なにこれ。
なんか、一瞬で気持ちを持っていかれた。
なにこれ、ちょっと、凄いんですけど!
彼女の声に、トリップする。
ここはどこ?
もしかして宇宙?
「おーい、生きてる?」
机の上に突っ伏した私の頭を、彼氏がちょんちょん、と指でつつく。
「死んだ」
私は低い声で言った。
笑わせたいわけじゃなく本当にそんな気分だった。
頭に血が上っている。
足の裏がむずむずする。
なんだかすごく……心が燃え盛っていた。
いてもたってもいられないくらいに。
「ねえ、私ってね、昨日、いい子って言われたの。みんなにね」
顔をあげないまま、地を這うような声で言う。
「そりゃそうだろ。いい子だよ。お前は」
「嬉しくない」
「ん?」
私は顔をあげた。
「嬉しくないよ。だってそんなの、私が何ものでもないからじゃない!」
わかってしまった。
みんなが彼女を避けるわけ。
彼女は燃え盛る太陽で、近くにいると焼けこげてしまう。
死んじゃう。だから死なないように、距離をとる必要があったんだ。
それなのに、私ったら。
教室でひとりぼっちの彼女を見て、「かわいそう」なんて思ってた。
中学時代の自分と重ねて見てた。
その頃の私はあんまり人と絡めなくて、いつもぽつん、としてたから。
話し相手は、目の前にいる彼氏だけ。心強くはあったけど、やっぱり女子たちに馴染めないのは辛かった。だから高校にあがって友だちが沢山できたのは奇跡みたいに嬉しかった。
そんな過去の自分に、ついシンクロしちゃったんだ。
バカだよ。私。
彼女は全然かわいそうなんかじゃない。
だって彼女はどこから見ても、プライド高き孤高の太陽神で。
はるか高めから私たちを見下ろす存在で。
同情なんて……全然似合わない。
それなのに私は、そんな神に。
お姫様に。
下女の分際で、救いの手を差し伸べようとしていたんだ……!
羞恥心に、のわああああともだえ苦しむ私に向かい、
「まあ、凡人は嫉妬されないよなあ」
どこか嬉しそうな顔で彼氏が言う。
「いい子、って『どうでもいい子』なんて言うしなあ」
いつもの軽口が妙にひりひりと痛く感じるのは、図星を感じているからだろう。
私は拳を握りしめ叫んでいた。
「決めた。私、いい子なんてやめる!」
「は?」
「だって変わりたいんだもの!」
友だちが欲しい、程度の夢しか持たなかった私。
でも、今までの私じゃいられないって、心と体がもがいている。
「面白そうじゃん。がんばれ」
彼氏が、今度はまっすぐな笑顔を私に向ける。
「というわけで、髪の毛切ってくる! 歌姫とおんなじ髪型にする!」
「てか、推し活かよ」
「うん! とりあえずそこから!」
「……なんかさあ、お前ってズレてるよなあ。けどまあ、そんなお前も好きだけどな」
「ありがとう!」
優しい全肯定を背に頬を赤らめ家を飛び出す。
肩まで届く髪の毛が風になびく。
ずっと伸ばしてきた、この髪を切る。
私にとってはそれが冒険の第一歩。
彼女に会ったらこう言おう。
「真似してごめんね」って。
そして、歌のこと、もっと聞きたい。
教えて。私に。
あなたの見ている輝く世界を。
キラキラと目に映る赤い夕陽に聞いたばかりの曲が思い出されて、私の心をギュッとしめつける。
私は思わずジャンプしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
