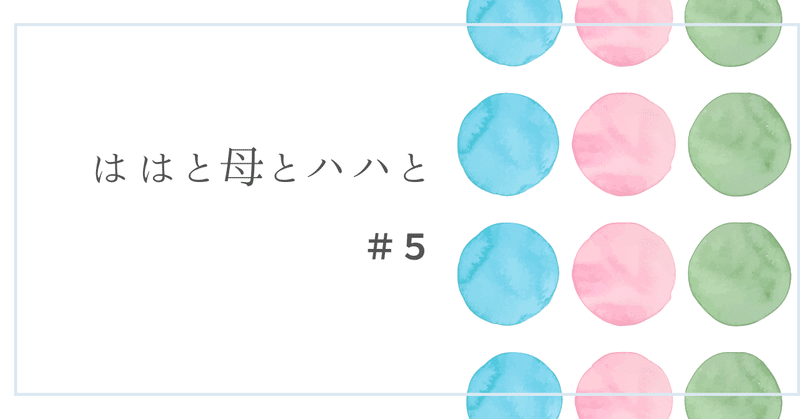
いつまで自分を偽るのか
近くのATMに向かい車を走らせた。
駐車場に車を停め、抑えていた感情が溢れ出した。
何年かぶりに本気で泣いた。
泣いて泣いて、泣いて。
気持ちを吐き出した。
『なんで・・・』
結局は、「なんで」という思いしかなかった。
私は頑張っていたはず。
どこでどう、間違えた?
一生懸命働いていたのは、私自身のためだったはず。
自分の気持ちを表に出さないようにして、何事もなく平穏に暮らしてきた。
それは将来の自分のためだった。
高校時代の奨学金だって、親に頼らず自分で返済している。
自動車学校だって、義姉が親に出してもらっているのを横目に自分で出して、免許も取った。
これ以上、これ以上はもう、限界だ。
私は親のために居るわけじゃない。
怒り、悲しみ、落胆・・・言葉では表すことの出来ない感情。
今の自分はこの感情を受け止められない。
ふと、時計に目をやると、びっくりすることにそんなに時間が経っていなかった。
『人間は泣き続けることができない。』
あの言葉が、再び、脳裏に蘇った。
ATMで、貯金を下ろした。
新社会人の私の給料はたかが知れている。その中から毎月微々たる貯金をしてきた。高校時代から続けてきたが、それも、今日でなくなる。
お札を握りしめ、車に戻り、鏡をみる。
もう、私は泣いてない。泣いてたことも悟られたくない。
お金を貸す、ということは、彼らに貸しができるということだ。
そうだ。
私はこのお金で彼らの優位に立てるのかもしれない。
私が何をしようと、
『あの時お金を貸したのは誰だっけ?』
と、言えば、彼らだって何も言えなくなるはず。
ミラーに映る自分をまっすぐ見た。
お金を貸そう。
それは自分の意思だ。
義姉には出来ないことだ。
一人暮らしは出来なくなったけど、今、私のこのお金がなければ、義姉は
退学。家に戻ってくることは絶対に阻止したい。
義姉のためじゃない。
あくまで、両親にお金を貸そう。
そして、
あなた達が、いずれ介護が必要になったときは喜んで介護をしよう。
私がいなければ何も出来ない状態になっていただこう。
私に感謝の言葉を言ってもらおう。
きっと、それが、一番の苦痛だろうと思う。
中学生の時といい、今回といい、どういう思考回路なのかはわからないけれど、そう、思った。
おそらく、憎しみも芽生えたと思う。
大人になってから思うと、本当に、よく耐えたと思う。
大人になった今でも、自分の思考回路が理解できないけれど、でも、そのときは、そう、思ったんだ。
家に戻り、両親にお金を渡した。
私は笑っていた。
ありがとう、ありがとう、と、何度も両親は口にしたが、その時の両親の顔は未だに思い出せない。
私の視界はぐにゃり、と歪んでいた。
人間関係はお金が絡むと複雑になる。
そう、教えてくれたのは義母えいこさんではなかっただろうか。
なのに、その後も何度もお金の無心をされた。
義姉の授業料もそうだけれど、給料日になると決まってパチンコ屋に呼び出された。理由は
『この台、打っておいて』
財布に入っているなけなしのお札を入れて、パチンコをする。
全然楽しくなかった。
それでも、なぜか毎回勝ち、入れた分のお金は戻ってきた。
買った分のお金は『食費』と言われてしまい、もらえることはなかった。
お財布にお金をいれることもなくなっていったが、そういうことは勘が良く働くようで、たまたま財布にお金を入れた時に限って誘いが来た。
時には飲みに行くときに誘われることもあった。
私を傍らに置き、飲み屋に行く。
なんてことない、運転手だった。
『社会勉強』
と、にやりと笑って、ニューハーフバーなどに連れて行かれたこともある。
勘違いしないように必死だった。
私を認めているわけではないはずだ、と自分に言い聞かせていた。
楽しい時間を一緒にすごせたことも、事実。
楽しくなかったとしても、自分だけでは経験できないようなことを体験させてくれたことは、素直に嬉しかった。
要求はどんどんエスカレートしていった。
消費者金融にも手を出し始めた義母は、私にも同じようにカードを作るように言ってきた。キャッシングをして欲しい、とのことだった。
あっというまに借金が増えていく。
悔し涙を流しながら、給料日のたびに手元にはほんのわずかしか残らない預金通帳を眺めながら、いつかきっと、いつかきっと、私は親を裏切ろうと思う。
自分が自由になるために、夜のアルバイトを始めた。
両親は
『そんなの許さない』
と、言っていたが、
『もう、成人だから、自分で決めてもいいよね。それに今の給料じゃ返済できないから。』
と、突っぱねた。
おそらくだけど、私が夜にいないと、子守する人がいなくて両親が飲みに出かけられないからだと思う。家事をする人がいないからだと思う。
妹のことは気にかかったけれど、実際、お金は足りなかったし、まだ、一人暮らしの希望は捨てたくなかった。
いつまで、自分を偽るのか。
いや、違う。
いつのまにか、自分を主張することをあきらめたんだ。
自分は自分だけで、それで精いっぱいだったんだ。
感情に蓋をしていたほうが楽だったんだ。
親の前で、自分は自分じゃない。
自己防衛をしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
