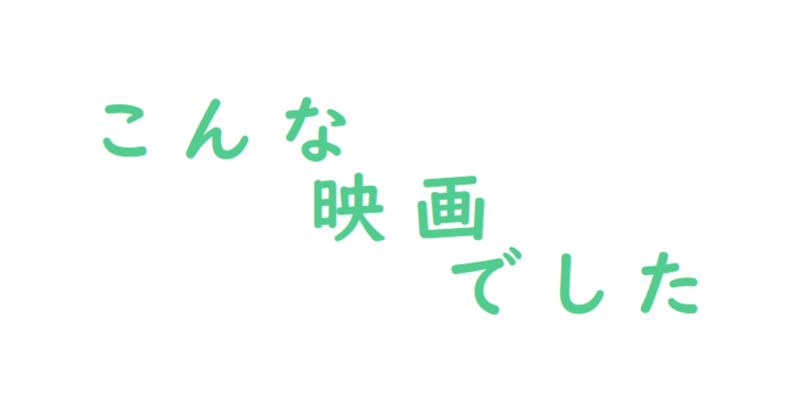
【こんな映画でした】486.[炎のランナー]
2020年 2月 5日 (水曜) [炎のランナー](1981年 CHARIOTS OF FIRE イギリス 124分)
ヒュー・ハドソン監督作品。なるほどこんな映画だったのか、と。実話の映画化のようだ。ポイントとしては、まず「宗教」の問題。宗教国にあっては、どう頑張っても避けることのできない・逃げることのできない問題だ。そしてもう一つは「ユダヤ人」ということ。
舞台は1978年(映画の中での現在)のケンブリッジ大学のシーンから始まり、1919年に遡る。ということで、実在の人物をモデルに脚色された映画。
二人の主人公は、ケンブリッジ大学の生徒であるから、イギリスにおける特権階級に属する。だからここでは労働者階級に属する者は出てこない。一人はエリック・リデルでスコットランドの宣教師の息子。今一人はユダヤ系リスアニア人の息子ハロルド・エーブラムスである。
映画の開始早々、彼がユダヤ人であるということで、その苦悩をリデルに切々と語るシーンがある。これだけでも私にはとても衝撃的で、ヨーロッパにおけるユダヤ人差別の凄まじさの一端を垣間見る思いである。
競技では、リデルが横を走るランナーに肘打ちを喰らわされ転倒するシーンがあった。なかなかフェアプレイとはいかないようだ、勝つためには。後にハロルドが結婚するシビル・ゴードンの弟は「僕にとっては遊びだ。勝敗は関係ない。だがハロルドには命懸けの勝負だ」と姉に言うシーンがある。なおこのことでリデルは、「走ることは遊びではない。御名をたたえるためだ」と言っている。
ラストシーンではこの二人の、1924年パリオリンピック後の人生のことがテロップで表示される。
*
(27分~、ハロルドが友人オーブリーに話す)
ユダヤ人であることは、痛みと絶望と怒りをもつことだ。屈辱を感じることだ。"妄想だ"と思おうとしても、人々の顔色に、言葉の端々に、握手する手の冷たさに感じてしまう。(飾られている写真を指して)あれが父だ。ユダヤ系リスアニア人。この国では全くの異邦人だ。/でも異星人じゃない/僕は敬愛している。父は英国を愛し、息子たちを真の英国人にしたと思い込んでる。兄は医者だ。その道の権威だ。父は財を成し、そして僕は英国最高の大学に在学中。だが父は1つ忘れている。英国はキリスト教徒とアングロ・サクソンの国であり、彼らが権力の回廊を占め、嫉妬と憎悪で他の者を閉め出している。/立派な弁護士になれるぞ。/この説得力は民族的才能さ。/笑って耐えるのか?/いや、僕は偏見に挑戦する、偏見を持つすべての人に。そして、ひざまずかせてやる。
【観ていて気持が重く、暗くなるシーンだ。ここまでユダヤ人について描かれたものは観たことがなかった。本当になぜだ、と思う。そして権力者たちの邪悪な思想の酷さ・残酷さ・酷薄さ。】
*
(44分~、シビルとレストランで。ハロルドが話す。)
走るのは好き?/中毒以上だ。戦いの武器だ/敵は?/ユダヤ人であること/本気なの?/君はユダヤ人じゃないから/誰も気にしてないわ。どんな害があるっていうの?/潜在的差別がある/難しいのね。どういう意味?/水辺に行けても、水は飲めない/あなたって変わった人ね。でも魅力的/うれしいよ/人生、いいことあるわ/今夜のように(と、ここで料理が運ばれてくる。「豚の足」が。豚肉は、ユダヤ教では食べてはいけないものの一つである。)
【自らがユダヤ人でありながら、そのユダヤ人であることを敵として憎んでしまうという自己矛盾。本当に悲しく辛いことだ。ここでの「水辺」の喩えは見事だ。これが差別だ。】
*
(ハロルドが大学の寮長に召喚され、それは形は食事に招かれたわけだが、その内実は彼がプロのコーチに指導を受けていることを非難するものであった。)「競技は、人格を形成し、勇気と誠実さと指導力を培う。とりわけ大事なのは忠誠心と友愛と団結心だ」とハロルドに諭す。あるいは「エリートにはエリートのやり方がある」、と。それにハロルドが反論して退出した後、彼らは「あれがユダヤ人というものだ。神が違えば、人生の目標も違う」と捨て台詞を言う。
【教育者であって、なおこの弁である。いかに宗教というものによって、まともな思考が妨げられているか。そういうことに気がつかないくらい・気がつかせないくらい、宗教が生活に密着・浸透しているのだろう。私には耐えられないことだ。】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
