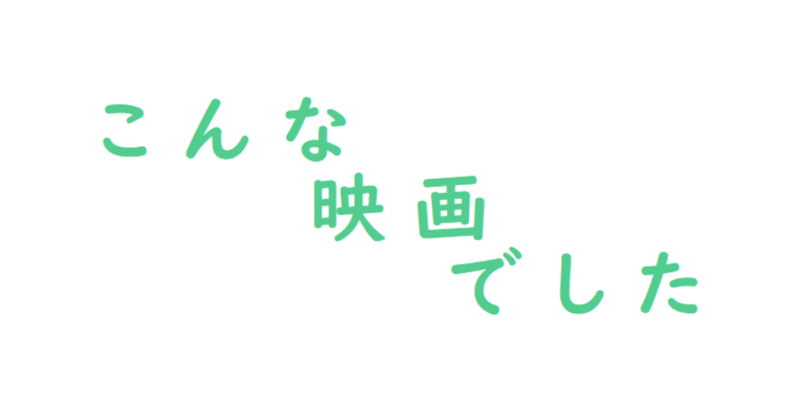
【こんな映画でした】451.[津軽じょんがら節]
2022年10月 6日 (木曜) [津軽じょんがら節](1973年 103分)
斎藤耕一監督作品。「旅の重さ」(1972)を観ている。カメラアングルなど撮り方に特徴があった。今ならフランス映画などでよく観る撮り方(人が去った後のドアをしばらく映す、など)が見られた。当時、私はこの映画に気が付かなかったのだろうか。いや、今、観てこそこの映画の良さが分かったのかもしれない。男女間の愛情を中心に、人生というものを描いている。それにしても日本海の荒波は厳しい。映画の中味、いや人生の厳しさを象徴するものだろう。
主人公イサ子を江波杏子、撮影当時30歳。若い男を織田あきら、撮影当時25歳。盲目の女性ユキを中川三穂子、撮影当時24歳。若い男と漁をすることになる塚本為造役を西村晃、撮影当時50歳。やはり渋い味がある。
塚本は、イサ子の父と兄が船を難破させて保険金を騙し取ろうとしていたのを目撃している。またそれ以前に彼の息子がイサ子にそそのかされて(?)東京へ駆け落ちしたが、その後捨てられている(別れている)というのが前提としてある。
*
この映画を観る切っ掛けとなったのは、双葉十三郎氏の『日本映画 ぼくの300本』(文藝春秋)に紹介されていたので。それも「満点」で。この満点で紹介されているのはあと[砂の器]をはじめとして数点しかなかった。
*
オープニングシーン(荒海を前にして、ユキと津軽三味線を教える女性)は、見終わってからもう一度見てようやく意味が分かった。よくある手法だが、最初のシーンこそ、最後のシーンの一部だったことが分かる。
次いでバスが到着し、イサ子と若い男が降り立つ。イサ子の家に向かう。自然の厳しさとその土地の貧しさがすぐに見て取れる。女に面倒をみてもらうということ、辺鄙(パチンコ屋までバスで二時間)なために時間をもてあます男を描いていく。
このイサ子という女性の愛情とは、一体何だったのだろう。東京に居られなくなった若い男を、一種の母性愛で助けてやろうとして帰郷したのか。はたまた父と兄の死亡にともなう保険金の受け取りと、その墓を作るためだったのか。他に何かヤケになるようなことがあったのか。
その後、塚本の証言により、父と兄とは偽装して保険金を詐取しようとしたことが判明する。もっとも船を難破させて、彼らは小船で帰り着こうとしたようだが溺死してしまうことに。イサ子は粗末な木の端くれで作った墓の前で慟哭する。そんなにも海での生活は大変だったのか、と。かくしてイサ子はもはやこの村に存在する理由はなくなる。そのような経緯の間に、若い男には変化が見られた。
飲み屋で働き出したイサ子の留守の間に、男はユキと出会う。ちょっかいを出すのだが、初めはユキが盲目であるとは気が付かない。その後何回かユキとの出会い・やりとりを通して、この男にも情が湧いてくる。ユキもそうだ。そんな中で漁師の塚本との出会いがある。彼は村人達を批判する。出稼ぎに行き、失業保険をもらう怠惰な生活振りを批判するのである。昼間から酒を飲み、花札をしている有様を。もちろん東京から来たこの男にも、批判の矢がいく。
男はユキのこともあり発憤して(最初は時間つぶしだったかもしれないが)、この漁師と漁に出ることになる。シジミ取りのようだ。労働の喜びを彼は感じることになっていくのであろう。毎日のように漁に出ることになっていく。つまり堅気の生活、女に依存しない生活がゆっくりと定着していく。とはいえもう一方では、飲み屋の主人に唆されて、ユキに売春をさせようとしたりもするのだった。
そんな中でイサ子は、男のユキとの関係を嗅ぎつけ、村を出ようと提案する。しかしその当日、飲み屋にユキを連れていき売春をさせようとしていたところだった男は、急に身を翻して飲み屋に向かう。ユキを救い出して彼女の家に戻す。イサ子は怒り、飲み屋の主人といちゃついているところを男に見せつける。男はもうイサ子の元には帰らず、ユキのところで過ごすことに、夫婦のように。イサ子はついに村を出て行く、捨て台詞とともに。これは伏線であろう。
平和な幸福な日々、漁とユキとの生活。そんな日々が永遠に続くはずはない。ついにある日、漁から戻ってくると浜辺にユキがおり、「あんちゃの友だちが来てるよ」、と。目の見えないユキには分からなかったのだろう。彼らは刺客であった。男は逃げようとするが狭い場所で囲まれていた。ナイフで刺され、船の横の水面にうつぶせに浮かぶシーンが男の最後であった。
*
ラストの方での江波杏子と西村晃のバス停近くでのすれ違いシーンは、キャロル・リードの[第三の男」のラストシーンを思いださせるものだった。このとき塚本は、イサ子に誘惑されて上京し、そこで捨てられた息子の骨箱を左手に持っている。東京の工事現場で、事故死した息子の遺骨を引きとって帰ってきたところだったのだ。イサ子もそれを聞いて知っているが、ともに無言ですれ違うことに。イサ子は若い男を捨てて、どこかへ行ってしまうところだった。
またエンディングで若い男(織田あきら)が殺されるのは、ルキノ・ビスコンティの[夏の嵐]の最後を連想させる。こちらは密告だが、イサ子が密告したのかどうかは、はっきりとは映画は描いてない。しかしおそらく彼女の捨て台詞、「私とこの村を出て行かなければ、何をするか分からないよ」といったことからすると、十分に密告の可能性がある。それは[夏の嵐]のアリダ・ヴァリ同様の嫉妬からくるものだろう。また、ついに自分のものにならなかった男への恨みでもあろう。
真っ当な幸せな人生を送ろうと決心した矢先に、過去に犯した罪の償いをさせられるとは。何とも悲惨である。死んだ若い男は、死んでしまったので、それでいいかもしれないが、残されたユキはどうしようもない。オープニングシーンで早く忘れろと言われているのではあるが、そんな簡単なものではない。おそらくユキは生涯、この名前も知らない若い男のことを思い続けて生きていくことになるのだろう。残酷なものだ。それが人生か。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
