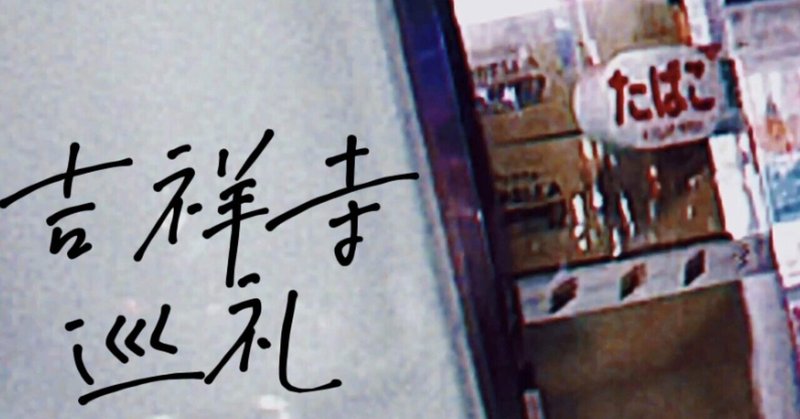
吉祥寺巡礼
吉祥寺は、私が人生においてとても重要な時期を過ごした大切な街だ。
住んでいた期間は長くないけれど、とにかく濃かった。
一生のうち人間に降り注ぐ幸福と厄災が一気に濃縮して訪れたような、そんな時間を、過ごした。
だけど、というべきか。
だから、というべきか。
とにかく私は、吉祥寺を離れてから、もう一度この街に来ることが怖かった。
この街には、あまりにも甘くてあまりにも苦い思い出が蔓延っている。
目の当たりにしただけで、そのときの気分、匂い、音。すべてがフラッシュバックされるだろう。
だから、怖かった。
でも、来てしまった。
理由はない。
なんとなく、来たくなったのだ。今日だという気がした。今日しかないという気がした。
どうしようもなく退屈で平凡な物語の聖地巡礼。
吉祥寺、巡礼。

「待ち合わせ場所は?」
「バスキンロビンス前」
で通じる友達とは仲良くなれた。
いつもここで人を待っていた。
緊張したときは、必ず好きなフレーバーの話をしてやり過ごした。
ロッキーロードが嫌いな人はいない。
ポッピングシャワーは意外と好き嫌いが分かれる。
夏はオレンジソルベ。
冬はキャラメルリボン。
「オレンジソルベなんて頼むやついんの」と言ったあの時のあいつ、覚えおけよ。ここにいるんだから。
12月24日はこの店のクリスマスケーキを予約した。
受け取りが予約時間を少し過ぎてしまったから、店員のお姉さんが少し不機嫌だった。
気にしている私に友達が「自分たちがクリスマスに楽しそうだったから嫉妬してたんだよ」とぶっきらぼうに言ってくれた。
心の底から優しい人だと思った。それは目に見えないタイプの優しさだった。
そういうタイプの優しさを持っている人に、私は今日まで出会えていない。

パルコ地下1階のディスクユニオン。
正直行ったことは一度もない。
いつもそのもう一つ下の階にある映画館「アップリンク」に行く途中で見かけるだけだった。
だからこの壁を見ながらエスカレーターを下るときは、そわそわと浮き足立っていた記憶しかない。
上るときの気持ちは無論、その映画に対する極めて個人的な評価によって変わった。
いつか行ってみようと思ってたんだけどな。
そういう場所に限って、二度と行かないものだ。
これからも行くことはないだろう。
第一私は、レコードプレーヤーなんて持っていない。

それでこれがその「アップリンク」。
青い洞窟みたいな作りが大好きだった。
数ある映画館の中でも、特に好きだ。
この映画館があるから、私は住処に吉祥寺を選んだのかもしれない。
たくさんの映画を観た。
「スウィング・キッズ」も「ソング・トゥ・ソング」も、「クーリンチェ少年殺人事件」のリマスター版さえもここで観た。
主にレイトショーだった。
徒歩で帰れるから終電を気にしなくてよかった。
あまりにも素敵なものを観た日は、帰り道の彩度が高く感じられた。好みの映画がこぞって冬にやっていたせいもあるだろう。
唯一の心残りは「バナナパラダイス」。
あの映画を見ている途中でトイレに行きたくなり途中離席した。
青年だった主人公が、戻ってきたら中年になっていた。
数分で何があった? いまだに分からない。二度と分からないだろう。もはやもう、分からなくて良い。
謎は謎のまま。それがセオリーだ。

商店街の景色はいつ見ても安心する。
ここは良い意味で変わらないのだ。
8時前には店は閉まるし、「さとう」のメンチカツはいつも長蛇の列。
お茶屋も和菓子屋もドラッグストアも、ずっと変わらない。まるで演劇の書き割りにように、常に吉祥寺の街に常駐しているべき存在だ。
戯曲「吉祥寺巡礼」。
かつてそんな物語があったのだろうか。
この街の建造物はすべて、そんな物語のための装置なのだろうか。

感染対策を怠らないこの街のぺこちゃんとは、顔馴染みだ。
もちろんこの街のぺこちゃんだけで、違う街のぺこちゃんとは友達ではない。
この街のぺこちゃんは愛想が良いのだ。
ところでマスクをしているせいで、自慢のキュートな舌ぺろが見られないことはちょっと残念である。
10月末だったこともあり、この日はハロウィンの仮装をしている。とても似合っているよ。私がこの街で初めてできた、可愛い友達。

ハーモニカ横丁は、閑散としている時の方が好きだ。
街を独り占めしているような気持ちになるから。
もちろん、そんなことはないのだけれど。
この街は誰のものでもないし、誰のものでもある。

存在自体がグレーな喫煙所は、もう無くなってしまったようだ。
最初はどこかアングラな雰囲気が好きになれなかったけれど、徐々に馴れていった。
帰り道、いつもここに寄ろうか迷った。
特にいけすかなかった日は、どうしてもここに寄りたくなった。
寄らない方が、いくらか気分良く帰れるのに。争い難い魔力により7割の確率で来てしまった。
ここで数本のパーラメントを犠牲にした後は、いつも苦味の後悔だけが残った。
きっと、行き場のない幾多の煙がくすんだ空に消えていっただろう。
仕事をさぼったサラリーマンたちの憩いの場は、人生のつまらない側面を常に私に突きつけてきた。
ここには何もないよ。
知ってるよ。
ここには何もないから、来るんだよ。
みんな。きっと。
でもそうか、なくなってしまったんだなあ。
寂しいかと言われるとそうでもない。
だけどまあ、あってもよかったんじゃないかな。
性懲りも無く地面に転がった空き缶を灰皿がわりにして、こそこそとタバコに火を付けるサラリーマン横目に、去る。

吉祥寺は決して穏やかで住み心地が良い街というだけではない。
光が強ければその分、闇も深いのだ。
吉祥寺に住んでいると、そのほの暗い部分をたびたび垣間見ることがあった。
印象に残っているのは、異国の青年のことだ。
私はパルコ内にあるスターバックス2階の窓から、街を歩く彼をたまたま見かけた。
あれは妙に曇った夏の昼下がりだったはずだ。
浅黒い肌と痩せこけた頬、よれたワイシャツを身につけた彼は今にも倒れそうで、それでも歩を進めるのをやめなかった。
どこに向かっているのだろう。
それが気になって、私は見知らぬ異国の人を目で追った。
ゆっくり、ゆっくり、振り絞るように歩く彼を、誰も目に留めなかった。
誰にも見えていないようだった。
この街の人々は、見たくないものは見ないようにしているのかもしれない。結局賢いのだ。
彼は、自動販売機に辿り着いた、
ジーンズのポケットから不器用に小銭を取り出し、ミネラルウォーターを一本買った。
そしてそのまま自動販売機の前に座り込み、ミネラルウォーターを一気に飲み干した。なるべく早く水分を摂取するためペットボトルを握りしめて飲んでいたからか、最後はぐしゃぐしゃに丸まっていた。
彼は自販機の前に座り込んだまま、目を閉じた。
そのまま、動かなかった。
私は気分が悪くなった。見てはいけないものを見たと思った。
皆のように見なければよかったのだが、見てしまった。
それはこの街を去る予兆だったのかもしれない、と書いてはみたものの、妙にご都合主義っぽくてこういうのは嫌いだ。
その時はそうは思っていなかったかもしれないが、今考えると、という話だ。つまり後付けである。
私は急いで荷物をカバンに投げ込み、スターバックスを出た。
すぐに白いカラーシャツを着た若者が私の席に座った。この人は、彼を見ただろうか。今でも少しだけそれが気になる。
彼はどうしてこの街に来たのだろう。
どうしてこの街のミネラルウォーターでなくてはいけなかったのだろう。
その日から、私はこの街を少し不気味に感じるようになった。

余談であるが、巡礼の最初の地は井の頭公園だった。
この公園の隠しきれない暗さが、好きだった。
吉祥寺を訪れた友人たちとは、ほぼ必ずここに来た。主に食事のあと、なんとなく帰るにはまだ早いよねってときに訪れた。
池を横断する橋からは、マンションが見える。素敵なマンションだ。
マンションの窓の黄色い灯りが、綺麗だった。いつも灯りがついている窓とついていない窓のバランスが、良い塩梅だった。
池に映るぼやけたマンションもまた一興だった。
なんとなく、いまだにあのマンションが実在していて、誰かが住んで生活しているということが信じられない。
やはりこのマンションも、吉祥寺という街を演出する書き割りに過ぎないのではないか?
この仮説にびびっと来た人とは、少しだけ仲良くなれそうだ。

話は戻るが、巡礼の日、ここで不思議な光景を見た。
夕方で、公園全体オレンジ色で、やはり少し不気味だった。
池に、何かが浮かんでいた。
目を凝らしてもそれが何かはっきり分からなかったが、細長かった。
私は反射的に、死体だと思った。
池のそばには警察が二人いて、それを細目で見ていた。
何人か、写真を撮っている通行人もいた。
しかし皆、いやに穏やかな顔をしていた。
浮かんでいるものを気にも留めず、犬の散歩に邁進している人もいた。
だから、これは死体ではないんだと思った。
でも私には、死体に見えた。
この街に住んでいるとき何度もここを訪れたのに、一度もこんな不思議な体験をしたことがなかった。
離れてみて、ふいに思い立って来てみた日に限ってこんな体験をするとは皮肉である。しかし、それは全うである気もした。
後日、いくら検索しても井の頭公園の池に死体が浮かんでいたなんてニュースは存在しなかった。
つまり事実はこうである。
私はここで、死体を見たいと思ってしまった。そういう気分だった。
だから、見た。
それだけの話である。
私はこれからも、この街を訪れることはあるだろう。
しかし、二度と住むことはない。そんな気がする。というかきっと、そうなるだろう。
未来は分からない。しかし、予感というのは当たるのだ。
まあそれにしても、忘れがたい街になってしまった。
これからもどこかへ引っ越すたび、そこが忘れられない街になるのだろう。
去ってから再び訪れたとき、どうしたって甘い痛みを感じてしまうような。
住んだ街の数が増えるということは、傷が増えていくということに似ている。
擦り傷の場合も、生傷の場合も、割と重症な場合もあるだろう。
そうやって私たちは住処を変えるごとにぼろぼろになっていって、それで結局、最後は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
