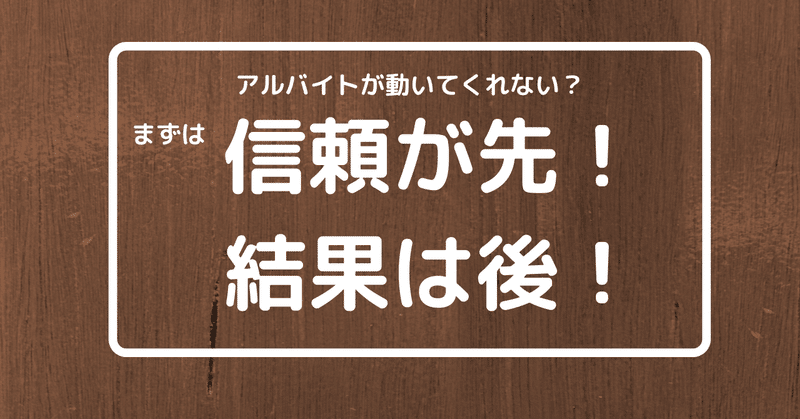
【店長マインド】信頼が先、結果は後
Q.店長や上司の皆さん、従業員や部下を信頼してますか?
もし「信頼したくても信頼できる従業員や部下がいない」と答えてしまった方は要注意です。
もしあなたの仕事が中々進んでいない場合、それは部下を信頼しないことに起因している可能性が高いです。
_____________________
私は仕事柄、店長に対し「アルバイトに仕事を任せていますか」とよく尋ねるのですが、かなりの頻度で「仕事を任せられる人がいない」という返事が返ってきます。
私がこの質問をする対象者は、仕事に追われて店の管理どころか自身の仕事もままならない方です。
こういった店長に共通することは、従業員を信頼していないことです。
そして、彼らはある勘違いをしています。
それは「信頼というのは心の内側から湧き水のように自然と出てくるものだ」という勘違いです。
しかし、少なくとも仕事上においてその考えは正しくありません。
なぜなら、仕事上の信頼は「できる」ものではなく「する」ものだからです。
状態ではなく、行動です。
もっと具体的に「信頼する」とは、「従業員や部下に対し何らかの権限を与え、その責任は自分が負うのだと示す行為」を指すのです。
この考えに対し、賛同できない方もいるかもしれません。
実際、店長には「あなたの考えは正しくない、現実的に出来る奴は誰もいないんだ」と反論されることもあります。
しかし、これは正しい正しくないの問題ではありません。
人は信頼を糧にして成長します。
物理的には権限を与えることで経験を積む機会が生まれますし、精神的にも信頼されていることでやる気と責任感が芽生えます。
したがって、「信頼する」という考えで従業員に権限を与えれば、実際に従業員は成長して仕事を覚え、結果的に店長の業務負担は減るというメリットをもたらします。
能動的に「信頼する」という「行動」を取ることは非常に有益なのです。
一方、信頼せずに何も言わずとも仕事をしてくれる従業員が現れるのを待つ場合、運よくその人が現れるまで何カ月も何年も辛い現状は続くでしょう。
すなわち、「信頼できない」という「状態」は何も現状を変えないのです。
それどころか、従業員の成長のための機会損失を生み、信頼した場合よりも優秀な従業員が現れる可能性は減るでしょう。
例えば発注なども一度従業員に教えてしまえばあっさり覚えてしまうものです。
たしかに、最初は間違いやミスもあるでしょうが、それは店長の指導とチェックで防ぐことが出来ます。
この指導やチェックには労力を要するでしょうが、今後発注をずっと自分がし続ける労力を思えば軽微なものです。
■まとめ
以上から、仕事上の信頼は「出来る出来ない」ではなく「するかしないか」という風に考えるべきです。
その理由は、そう考えた方が利益が大きいからです。
余談ですが、有名な「GIVE&TAKE 与える人程成功する時代」という本があります。
私はこの本はとても参考になるので、もし読んでいない方がいれば読んで頂きたいと思います。
まさに信頼をギブできる人は結果をテイクできるということではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
