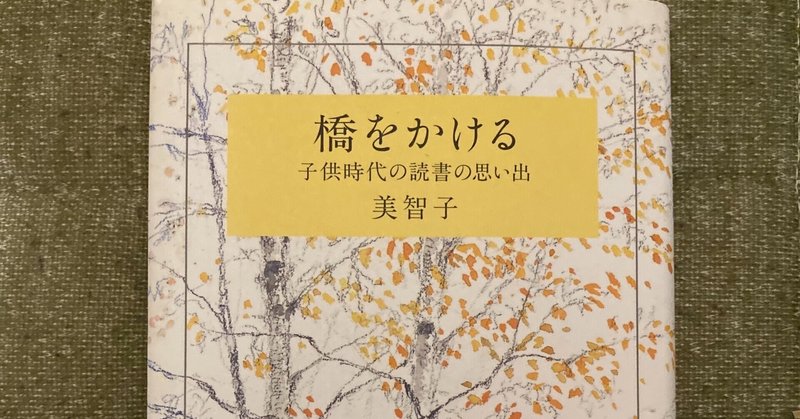
橋をかける
『橋をかける~子供時代の読書の思い出』 美智子 2009年4月刊 文春文庫
本書、美智子上皇后の講演をまとめたものとなります。
本書のボリュームは、解説や注釈を含めて140ページほどとなり、インドで開催された「国際児童図書評議会」にて「橋をかける」と題され、美智子様の講演内容が記されたページはわずか30ページばかりでした。
しかし、内容は素晴らしかったです。
会のテーマである「子供の本を通しての平和」について、美智子様のいままでの読書体験を踏まえながら、丁寧に語られており、美智子様が本から得た喜び、感動のエピソードが丹念に綴られておりました。
美智子さまが小学生になられた頃、ちょうど戦争がはじまり、疎開先の田舎では本は貴重品で、たまにお父様が東京から持ってきてくれる本がとてもうれしく、惜しみ惜しみ読んでいたとのことでした。
その本の中の一つに忘れられないお話があるということで、倭建命(やまとたけるのみこと)と弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)のエピソードを紹介してくださっておりました。
日本の古代の物語で、倭建命のために海神のいかりを鎮めるようと、弟橘比売命が入水(水中への身投げ)をし、別れを告げるというお話なのですが、生贄という酷(むご)い運命を弟橘比売命が自ら進んで受け入れながらも、倭建命への愛と感謝に満たされた思い出を歌い、去ってゆくその姿に、こどもながら強い衝撃を受けたというのです。
それは愛と犠牲という二つのものが、美智子さまのなかで、同じく近しいひとつのものに感じられた不思議な経験でもあったといいます。
このように、本は楽しみや喜びだけでなく、ときに苦しみや悲しみも感じさせてくれ、自分では経験することのできない、他者の感情や存在に思いを巡らすきっかけを与えてくれたとも語られておりました。
また、本書のタイトルでもある「橋をかける」という行為に以下のようにも記されておりました。
「生まれて以来、ひとは自分と周囲との間に、一つ一つ橋をかけ、人とも、物ともつながりを深め、それを自分の世界として生きています。この橋がかからなかったり、かけても橋として機能を果たさなかったり、時として橋をかける意思を失った時、人は孤立し、平和を失います。この橋は外に向かうだけでなく、内にも向かい、自分と自分自身との間にも絶えずかけ続けられ、本当の自分を発見し、自己の確立をうながしていくように思います」
そして、その橋をかける際の大きな根っことなったのが、子供時代の読書であったと結びます。
中でも、お父様のくださった日本神話や伝説の本は本当によい贈り物であったと仰っていたのが大変、印象的でした。
戦争が終わり、教育方針が大幅に変わった現在では、歴史教育の中から、神話や伝説は全く削除されてしまったことを憂えているようにも感じたのは私だけでしょうか。
美智子さまはこうも語ります。
「一国の神話や伝説は、正確な史実ではないかもしれませんが、不思議とその民族を象徴します。これに民話の世界を加えると、それぞれの国や地域の人々が、どのような自然観や生死感を持っていたか、何を尊び、何を恐れたか、どのような想像力を持っていたか等がうっすらと感じられます(中略)その後、私が異国を知ろうとする時に、何よりもまず、その国の物語を知りたいと思うきっかけを作ってくれました」と。
自国の神話や伝説を知るということは、他国の風土、民族性に関心をもつ重要なきっかけともなり、国と国の間に橋をかける重要な根にもなるのです。
最近、耳にするグローバル教育、ダイバーシティ教育もいいですが、まずは自国の歴史、神話、伝説を知ることから始めることが何よりも重要であると美智子さまが仰っておられるようでもあり、心に沁みましたね。
最近、江戸時代以前の子供たちへの教育方法の一つであった素読、音読をあらためて学んでいるのですが、その際、古事記、万葉集を大きな声で発声していると体中に力がみなぎり、活力が湧いてくることを実感します。
ただ単に大声で読み上げて、ドーパミンが出ているからだとも言われるかもしれませんが、1000年以上の時を経て、現代にまで残ってきた言葉の持つ力は言霊としか言いようのないエネルギーを感じてなりません。
私自身、神話や古典、児童文学等、子ども時代の読書を通じ、自身の世界を切り開いてきたことからも、時代と時代を超え、今も残る神話や古典といった遺産を次世代のこどもたちへの橋渡しが出来るよう、微力ながらも自分も頑張っていこうと改めて思いました。
本書『橋をかける』子供たちの読書離れが進む昨今、多くの人々に読まれ、幼少期の読書の重要性が伝わることを切に願います。
いくさ馬に育つ仔馬の歌ありて幼日は国戦ひてありぬ
人の世に熱あれ、人間(じんかん)に光りあれ。
