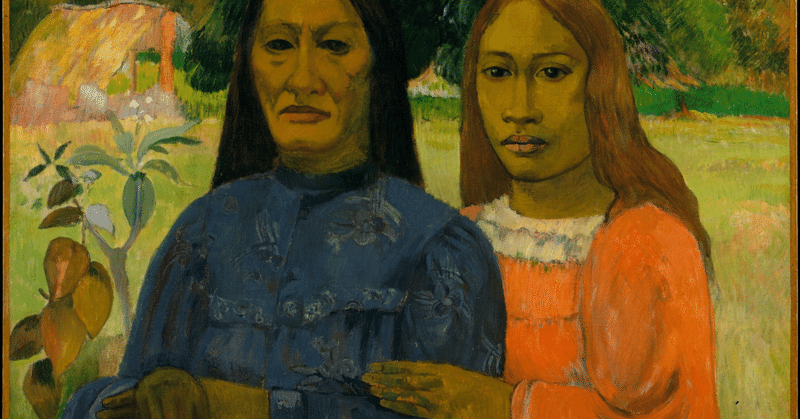
川上未映子の『夏物語』をどう読むか⑤ 夜の姉妹のながいおしゃべり①
女というのはおしゃべりとパンが好きな生き物だ。女のお喋りには脈絡がなく、夏目漱石の『倫敦塔』のように時空の制限を受けない。
午後八時過ぎ、きんこん、と音がして大家が二か月溜まった家賃を取りに来る。月末に払うと約束して支払いを断固拒否して夏子は巻子とビールを飲む。家賃は水道費込みで四万三千円(!)。これは2008年の家賃相場としてはかなり安い。
わたしがびっくりしたんは、じつは女の人が死んでも成仏ができんのらしい。そのわけが、ひとくちでいうと女の人というものが汚いからやと。昔のえらい人らがなんこもなんこも女の人がなんで汚いか、なんであかんかってことをずらずら書き残してるんやと。で、どうしても成仏したい場合は男に生まれかわる必要があると。なんやねんそれ。
緑子の日記には変成男子(へんじょうなんし)の話が出てくる。卵子の話、生理用品の話、子どもを作りたくない話と、彼女の日記は女であることの不合理と向き合っているかのようだ。
緑子が眺めた本棚には2008年現在三十歳の文学少女らしい、つまり七十年代生まれの文学少女らしい本が並んでいる。
「緑子、夏は、小説書いてるねんで」
そんな巻子の言葉に夏子はワナビーらしい逡巡が隠せない。すでに世界的大作家となった川上未映子の等身大の過去の話として読むといささかうさんくさい。恐らく彼女自身はもっとがつがつしていて、自信もあった筈だ。ただこの小説のテーマが貧乏ならば、夏子は未来の見えないワナビーに留まるべきか。
これが自分の一生の仕事なんだと思っている。わたしにはこれしかないのだと強く思う気持ちがある。もし自分に物を書く才能というものがないのだとしても、誰にも求められることがないのだとしても、そう思うことをわたしはどうしてもやめることができないでいる。
これは語順のトリックだ。新人賞の審査員なども務める川上未映子こそが、ものを書く才能がなく、誰にも求められない小説を書き続ける人々の「これが自分の一生の仕事なんだと思っている。わたしにはこれしかないのだと強く思う気持ちがある」という信念の無意味さをさんざん見てきたはずだ。どうしてこの人はこんなに苦しそうに意味のない作品を毎年送ってくるのだろうという感想は下読みのアルバイトだけが知りうることなのか。そうではあるまい。候補作として挙がってきても、「ふーん」としか言えない作品を幾つも見てきたはずだ。
それにしても川上未映子は今更何で物書きのワナビーなんかを持ち出してきたのだろうか。これはまるで自身のワナビー時代の回顧のようでさえある。しかしそんなに単純なことをして来るだろうか?
冷蔵庫にはどういうわけか卵がたくさんある。どんな話の流れ?
「せやけどなんかお腹すかん。なんかさっと炒めもんとか、なんか作ろか」巻子は台所の様子を窺うように首をくっとのばした。
「巻ちゃんごめん、うちなんもないねん」わたしは言った。
「卵しかない」
「ほんまか」巻子はうーんと大きな伸びをして、あくびまじりの声で言った。「卵だけあってもなあ」
こうして「卵」全否定してくる。これは本物のプレーンオムレツに拘る村上春樹への反旗ではなく、エルサレムでの「壁と卵」のスピーチ批判でもなく、卵の無力さの確認であろう。まさに作家の卵でもある夏子が「卵しかない」と言ってみる。精子がないのだ。
これは絶対確信犯である。卵料理の五つ六つできないものが、そんなに卵ばかり買ってくるわけはないのだ。それは勿論現時点では想像ができないほど卵が安定して安かった時代の貧乏人の冷蔵庫の象徴かもしれないが、「卵だけあってもなあ」なんていう女は普通おらんで。
卵があればなんぼでもつまみはできんねん。
だし巻き卵とまでは言わん。目玉焼きかスクランブルエッグでええねん。適当に火を通せば卵は料理になるねん。茹で卵にマヨネーズつけて福山雅治が食べてたやん。「ウフ・マヨネーズ」いうてたやん。おつまみはそんなんでええねん。
それを「卵だけあってもなあ」って絶対わざとやん。
やってきよんなー。川上未映子。
ボカコレ聴いててふと思ったこと⬇️ pic.twitter.com/nIL1LP2Jun
— tange(たんげ)_ボカコレ間に合ってヨカタ!!!! (@NORIBAND_tange) August 6, 2023
[余談]
大学で流行ってるのか🫢 pic.twitter.com/CfRGA0XWLA
— まるお2号🇯🇵(羊の皮を被った猫) (@maruon22) August 7, 2023
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
