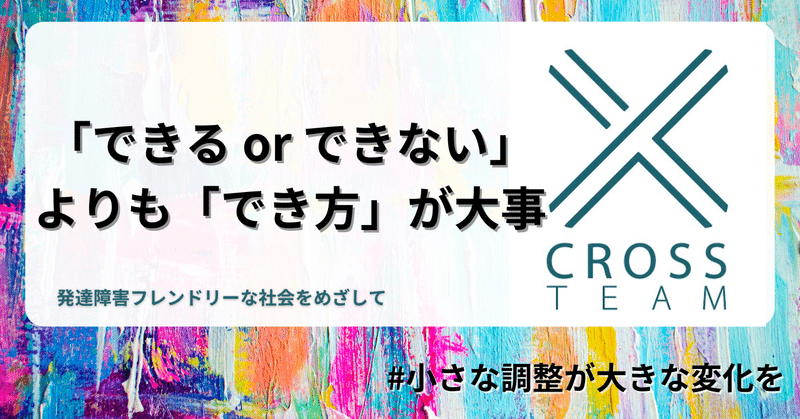
「できる or できない」よりも「でき方」が大事
この記事は1,477文字あります。個人差はありますが、3分〜4分でお読みいただけます。
このnoteではVoicy(音声配信)で配信した内容のテキスト版(要約版)です。詳しくはVoicyで聴いて頂ければと思います。
ちなみに、Voicyは下記チャンネルで毎日更新しています!
今回のテーマは、「できる or できない」よりも「でき方が大事」です。
どうぞお付き合いください。
できればいいってもんじゃない
昨日のVoicyの放送では、「車でイヤホン使わずに拝聴させていただきました。ノイズリダクションがしにくいとにう自閉症の方の聴こえ方をリアル体験できました。疲れました。この世界で情報をとるってホント大変だろうなと思いました」とコメントをいただきました。
ちなみに、昨日の放送はこちら↓
今日はこのコメントから話を広げたいと思います。
昨日は、収録環境がいつもと違い駅のホームで新幹線を待っている間に収録しました。というのも、コンサルテーションのため県外に移動する予定があり、朝も早かったので自宅では収録する時間がなかったためです。
そのため、雑多な音が入り込んで、時々電車が通ると、僕の声よりもノイズが大きく聞こえていたという環境でした。
この話は、発達障害の方々にとっても関係があります。たとえば、ASDの場合には感覚の偏りが診断基準に含まれており、その中でも聴覚の敏感さがあると、昨日の放送のように周囲の音が入り込むと、よりうるさく感じるということもあるでしょう。
昨日の放送では、僕の声が全く聞こえないわけではありません。でも聴き取りにくいのはその通りで、より声を拾いやすくするために音量を上げるとノイズ音も増えて、耳が疲れるかもしれません。一方、音量はそのままで、僕の声に集中しようすると、それはそれで疲れます。普段は無意識に聴き取れるることも、集中しなければならないと疲れるものだと思います。
たとえば、TVをなんとなく眺めて入ってくる音声と講演会の音声、どちらの方が疲れるかといえば後者だと思うのです。後者の場合には「せっかく講演会に来たんだから、ちゃんと聴かなきゃ!」みたいになりませんか?
こうした理由から、コメントにあったように「疲れました。この世界で情報をとるってホント大変だろうなと思いました」というのは、まさにその通りだろうなと思います。
同時に、大事なポイントとしては、「できるかどうかだけではなく、どのようにできているか」です。昨日の放送も「聴けるか、聴けないか」で言えば、「聴ける」とは思います。でも、疲れるんです。使うエネルギーが違うんですよね。いつもは60%くらいの力で聴き取れることが、それ以上の力を使わないといけない。
ASD特性を持つ方々もそうです。
日頃、多数派の人が60%くらいの力でできていることが、100%、120%のエネルギーを注いてくださっているのかもしれない。だから、日々の生活を過ごすだけで疲れ具合が違ったりもします。
でも、こうしたことはなかなか理解してもらえないこともあります。僕らは、どうしても自分の感じ方が基準になりますから、自分とは違う感じ方や聞こえ方を想像するのは、難しかったりします。
まとめ
昨日の放送を経験していただければ、今日の話がもっと分かりやすくなると思いますので、ぜひ昨日の放送を聴いた上で今日の放送を聴いて頂ければと思います。発達障害の方々は、多数派の人と違ったものごとの捉え方や情報処理の仕方をするため、私たちとは違う疲れ方をすることもあります。
このことについてもっと考え、知ろうとし、そして発信していくことが大切だと思います。
より詳しくはVoicyを聴いてもらえればと思います。
では。
佐々木康栄
災害時に役立つさまざまな情報
これまでnoteにまとめていましたが、TEACCHプログラム研究会東北支部のホームページに集約しました。宜しければご活用ください。
その他お知らせ
オンラインサロン「みんなで考える発達障害支援」
SNS
▼Voicy
▼stand.fm
▼X
https://twitter.com/KoeiSasaki
https://www.instagram.com/koei.sasaki/
https://www.facebook.com/koei.sasaki.5
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
