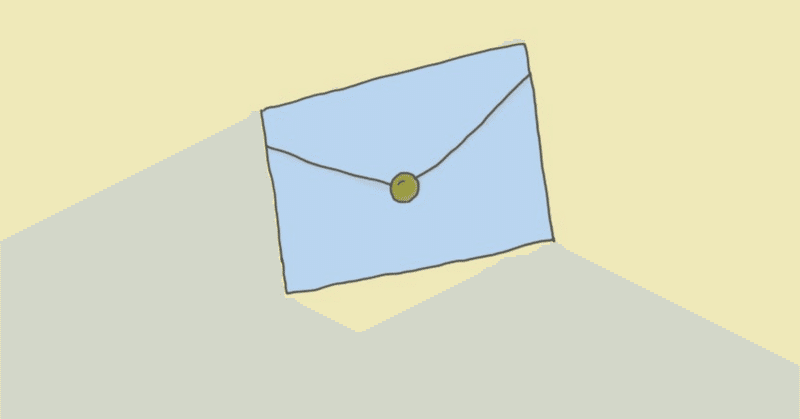
平凡社員のビジネスパーソンノウハウ③(How(どのように):メール、電話、プレゼン、会議)
本稿は、『仕事をするうえで重要な2つのこと』のうち「1.その仕事のゴールは何かを常に意識する」の中の「How(どのように):メール、電話、プレゼン、会議」について触れる。(↓前々回の投稿)
◇How(どのように):メール、電話、プレゼン、会議
本内容については、以下の順で触れていく。
■アウトプットにおける全般的な考え方
■具体対応(ハウツー)
ここで、アウトプットにおける全般的な考え方では、アウトプットの手法を問わず意識すべきマインドセットについて触れ、具体対応(ハウツー)では、それぞれのアウトプットにおける対応手法について触れたい。
■アウトプットにおける全般的な考え方
どのようなアウトプット手法をとる場合でも重視したいことは、説明の順序である。これが説得力(相手の理解しやすさ)を高める。
あらゆる書籍や教育等で語られる所であるが、推奨したい説明の順序は、結論から話す、である。具体的には、結論 → 理由 → 結論。
<結論から話すべき理由 → 聞き手のストレス軽減>
この順序の優位性は、人間が同時に複数のことを覚えるのが困難である特性にも起因する。仮に、理由 → 結論 の順で説明を行うとしよう。この時、聞き手は、ゴールの分からないまま複数の理由をすべて聞いてから、それらの理由が後から聞かされる結論とどう結びつくかを、結論を聞いた段階で再検証することになる。1つや2つの理由ならまだしも、3つ以上となると困難を極める。
結論 → 理由 → 結論の順であれば、聞き手は最初に結論を聞くことで、ゴールを見据えることができ、聞く準備が整う。理由を聞いている間は、最初に提示された結論と都度、その妥当性を検証することができるので、一つ一つの理由を覚えておいて最後の結論で再検証する必要は無い。
このように、聞き手側のストレスを軽減し、説得力を高められる順序として、結論 → 理由 → 結論を推奨するものである。説明が上手く理解されないときは、相手が悪いのではなく、自分が悪いことが多い。ぜひとも注意してほしい。
またよく、人によって説明の順序は変えた方がよい、という話を聞くが、余程、『理由から話せ』と強要されるような相手でなければ、基本的にはどのような相手でも結論から話すことが望ましいと考える。大抵の人の脳の仕組みは、大体同じであるから。
そして、この説明の順序は、メール、電話、プレゼン、会議、どの場合でも活用すべきものである。
■具体対応(ハウツー)
・メール
メールは大きく、件名、宛先、本文で構成される。ここで重要視したいのは、件名である。メールはまず、読まれなければ意味がない。何をしたいのか、何をしてほしいのかが、一目でわかるようにすることが望ましい。忙しい人に読み飛ばされてしまわないように、分かりやすい件名としよう。確認してほしいのか、報告なのか、質問なのか。要するに結論は何?ということを記載しよう。
<件名の具体例>
NGの表題:全社会議資料について
良い表題:【確認依頼 9/25(月)まで】全社会議資料の確認のお願い
次に意識するのは、本文である。
本文では、まず冒頭に何の目的のメールなのかをシンプルに明示することが望ましい。冒頭でパッと読んで何のメールか分からないものは、読み飛ばされたり、その分かりにくさに読む側はストレスがたまる。
<本文の具体例>
NGの本文:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〇〇部の〇〇です。
10月30日に全社会議があるため、現在その会議資料案を作成しています。会議資料案は▽▽様にも確認いただく必要がある箇所があるため、資料のうちのP5,6,7について、資料案の確認をお願いします。期日は、9/25までにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
良い本文:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〇〇部の〇〇です。
10月30日の全社会議資料案を作成していますので、以下の通り資料の確認をお願いします。
<確認箇所>
▽▽様の所掌するP5,6,7の記載内容の正誤
<確認期日>
9/25(月)まで
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メールに関してはここまでとする。
電話、プレゼン、会議については別途次稿以降で説明することとしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
