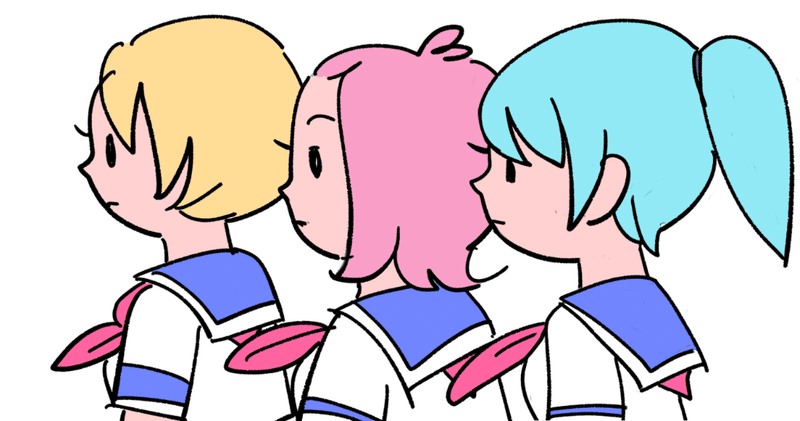
(134) 自分の授業を研究する方法(後半)
2021年5月6日(木)
2020年度の「教える技術オンライン研究会(OGOK)」(全10回)から、研究トピックや研究スキルを紹介するシリーズの第8回目です。今回は研究スキルとして「自分の授業を研究する方法」の後半です。最後には、そのレクチャービデオ(25分)を紹介しています。
前回は、授業を実施して、その成果を測る方法として次の4つを紹介しました。
(1) 受講生の最終的なパフォーマンス
(2) 受講生の体験としての授業評価データ
(3) 心理尺度で測られる態度の変化
(4) 自己評価ではないパフォーマンスデータや行動データ
今回は、授業データのとり方として、アンケートにおける自由記述データの扱い方と、パフォーマンスデータの扱い方について話したいと思います。
・心理尺度と自由記述を組み合わせる
授業についてのアンケートを学生に実施する場合、最後に自由記述による質問を入れておくことはよくあります。たとえば、「この授業を受けて良かった点、改善すべき点を自由にお書きください」というような質問です。これは、アンケート内の尺度による質問で拾いきれなかったことを拾うことができます。また、全体的な評価を把握するためにも有効です。しかし、この自由文によるテキストデータは特に分析されずに終わってしまうこともよくあります。
ここでは、このような大まかな自由記述質問ではなく、特定の側面を測る態度尺度と組み合わせた形での自由記述質問の設定を提案します。
たとえば、自分の授業において、特にグループワークのやり方について工夫を加えた上で、その効果を測りたいとします。グループワークについての態度尺度を用意して事前事後で測定します。そうすれば、この授業のグループワークを体験したことが、その態度を変えたかどうかを検証することができます。グループワークについて態度尺度は既存のものがあれば、それを使ってもいいですし、適当なものがなければ、自分で開発することもできます。
ここから先は
ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。
