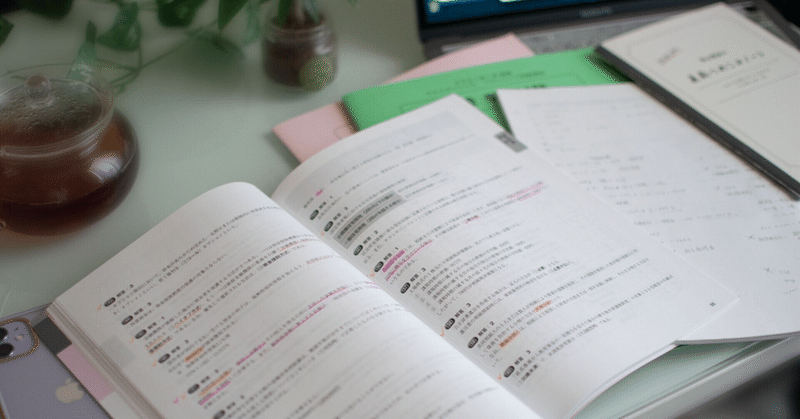
【勉強法】どんな試験にも最短ルートで合格するための共通メソッド~本当は最初にやるべきこと~
多忙な社会人こそ勉強方法について真面目に考えるべき
こんにちは。
いつも御覧いただきありがとうございます。
今回は私が自らの経験と実績(?)から導き出した、
どんな試験にも共通するメソッドについて書いてみたいと思います。
一口に「勉強」と言ってもぼんやりするので、
ここでは「試験に受かるため」の勉強という前提で書いてみたいと思います。
今回の記事では、毎日多忙な日々を送りながらも、
「昇進昇格のために何とかしてTOEICで800点採らなければ…」
「不動産会社に勤めており宅建を採らなければ…」
「今後キャリアのためにも●●の資格を取りたい!!」
といったように、
仕事や家事育児の合間にどうにか絞り出した貴重な時間を使って、「なるべく効率よく勉強したい」という方々を念頭に置いています。
試験勉強など、これまで「とにかく頑張る」というアプローチをされていた方々も多いかと思いますが、今回の記事をお読みいただくと
合格(or目標点獲得)に向かって何からどうやって取り組めば良いか
テキストや問題集はどんな視点で選び、どうやって取り組めば良いか
勉強を実行するための仕組みづくりの仕方
…といったことの根本を学んでいただき、一度読んで理解してしまえば大抵の試験に応用できるメソッドを習得していただけると思います。
ちなみに、この後もお読みいただくとご理解いただけるかもしれませんが、ここで紹介する勉強法は、世に出る「一部の天才や秀才だからできる」系のものではなく、地道に、しかし確実に試験合格まで辿り着くための基本メソッドです。
言葉を選ばずに言えば「凡人の必勝法」です。
私自身が極々平凡な人間であるが故に試行錯誤してもがいた結果抽出したものですので、ちゃんと役に立つメソッドであると自負しています。
自分の勉強歴(どうでも良いので飛ばしていただいても結構です)
一応前の見出しのように偉そうなことを書きますので、自分自身がこれまでどのように勉強に向き合ってきたかも簡単に書いておきたいと思います。
中学校の期末試験
だいぶ遡りますが、初めて真面目に勉強に向き合ったのがこの時でした。
中学の定期テストで、小学生の名残で何も試験勉強などせずに臨んだ結果、親友は学年2位だったのに対して自分は30位くらいと、かなりショックを受けました。
親友は両親が教師だったので油断がなかったのでしょう…
当の私は油断どころか試験勉強をするものだという認識すらなく…
ここから一念発起して次の期末テストではがむしゃらに勉強し学年3位まで辿り着きました。
ここが私が勉強と向き合う原点です。
大学受験
まだ皆様に共有するようなメソッドは何ら確立されておらず、
とにかく我武者羅に勉強し、自分で自分を追い込みすぎて体調に現れることも…。
今思えばかなり効率の悪い勉強法(はっきり言ってしまえば無駄な努力)をしていましたし、プレッシャーにも押しつぶされそうになりましたが、おかげで勉強の仕方を見つめ直したり、プレッシャーに対してどう向き合うべきかを真剣に考える良いきっかけとなりました。
学生時代
前述のように必死こいてどうにか合格した身分でしたので、周りは自分よりも頭の良い学生ばかりでした。
「どのようなコミュニティに移っても上位1/3にいるべし」
という自分の中のこだわりもあり、
とにかくたくさん本を読む
周りの学生の勉強法を盗む
ということをひたすらやりました。
読書に関しては、親書を中心に年間100冊以上読んでいました。
※私なりの読書の仕方もどこかで書いてみたいと思います。
公務員試験
自分の中に蓄積してきた勉強法を始めて真剣に実践したのがこのタイミングだったと思います。
将来についてうだうだと考えていたら、試験まで半年くらいしかなく、
「効率よく最短ルートで辿り着かなければ!」
ということで、今まで勉強してきた勉強法を実践しました。
おかげで無事に合格し、中央官庁への就職も決まりました。
TOEIC 880点
社会人になってからも、細々色々な試験を受けましたが(ちゃんとすべて合格していますよ!)、一番皆さんに馴染みのありそうなTOEICのお話をします。
もともとは600点台でしたが、何度か受験しながら延べ半年くらいで880点まで上げました。
ちなみに私は生まれも育ちも全く英語とは縁のない純ジャパで、留学経験は当然なし。海外旅行も社会人になってから初めて行ったくらいです。880点を採った時点で行ったことのある海外はバンコクのみでした(笑)
本題に入ります~試験勉強に向けた下ごしらえ~
前置きが長くなってしまいましたが、本題に入ります。
といっても、勉強をはじめる前に…
締切の設定
まずはあなたが受けるべきor受かりたい試験に申し込みましょう。
「バカにするな」
「当たり前だろ」
というツッコミが聞こえてきそうですが、
本当に当たり前でしょうか?
お勤め先などから指定されていたり、自分の意志とは無関係に試験日が決まっている場合は別として、
「勉強する時間ができたら申し込もう」
「コツコツ勉強を続けて受かる自信がついてきたら申し込もう」
と思いながら早2年…というケースも多いのではないでしょうか?
はっきり言いますが、
忙しい社会人にそんな時間は永遠に訪れません。
ですので最初にやるべきことは、
自信があろうがなかろうが、
勉強する時間があろうがなかろうが、
準備ができていようがいまいが、
とにかく自腹で受験料を払って申し込み、「やるしかない」という状況を作りましょう。
締切を設定してしまいましょう。
過去問を手に入れる
強制的に締切を設定したら、次は敵と己を知りましょう。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」
と孫子も言っています。
まずは敵と己を知りましょう。
「それはわかったがどうやって…?」
「私が受けようとしている試験は模試なんてないし…」
大丈夫です。
どんな試験でもほとんど存在するものを使います。
「過去問」です。
またの名を「カコモン(←ポケモンみたいですね)」
試験運営団体のHPなどで実際の問題が掲載されている場合は、それをそのままダウンロードしてくれば良いですが、公式に公開されていない場合は書店などで模試や予想問題のようなものを購入するしかありません。
後者の場合は、とにかく「本番に限りなく近いもの」を探しましょう。
例えば、
問題の構成
問題の形式
問題の難易度
問題用紙のレイアウト
解答用紙のレイアウト
英語などの音声がある試験であれば、アナウンスもなるべく本番に近いもの…
などです。
例えばTOEICであれば、本番の問題は非公開となっていますが、市販されている「公式問題集」というシリーズが本番とほぼ同じで、リスニングの音声も本番と同じ話者となっています。
このように可能な限り本番に近いものを入手しましょう。
いきなり過去問を解く
過去問を入手できたら、早速解いてみましょう。
「え、いきなり…!?」
「試験に申し込んだばかりで解ける訳ないんですが…」
そう、いきなりです。
解けるわけない?…そんなのわかってます!!
「何も勉強する前に、チンプンカンプンのままいきなり過去問を解いてどうするの…?」
と思う気持ちはごもっともです。
私もかつてはそうでした。
でもそれで良いんです。
何もわからないチンプンカンプンな状態で向き合った結果を分析し、しっかり作戦を立てることが重要なのです。
要するに
現状(今の自分と敵=自分が試験日までに到達しなければならない水準がどこなのか、それは今の自分とどれくらい距離があるのか)を理解することから始めるということです。
いきなり解いてもできないことなんてわかっています。
もしいきなり解けるのならそもそも勉強する必要なんてない。
あるいはそんな試験受ける価値がない。
(それはさすがに言いすぎか…)
だいぶ長くなってしまったので、具体的にどうやって「いきなり過去問」を解くのか、次回以降の投稿でご説明したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
