
「鬼芥子姫」
阿瀬みち編
人魚アンソロジー『海界』より
「鬼芥子姫」
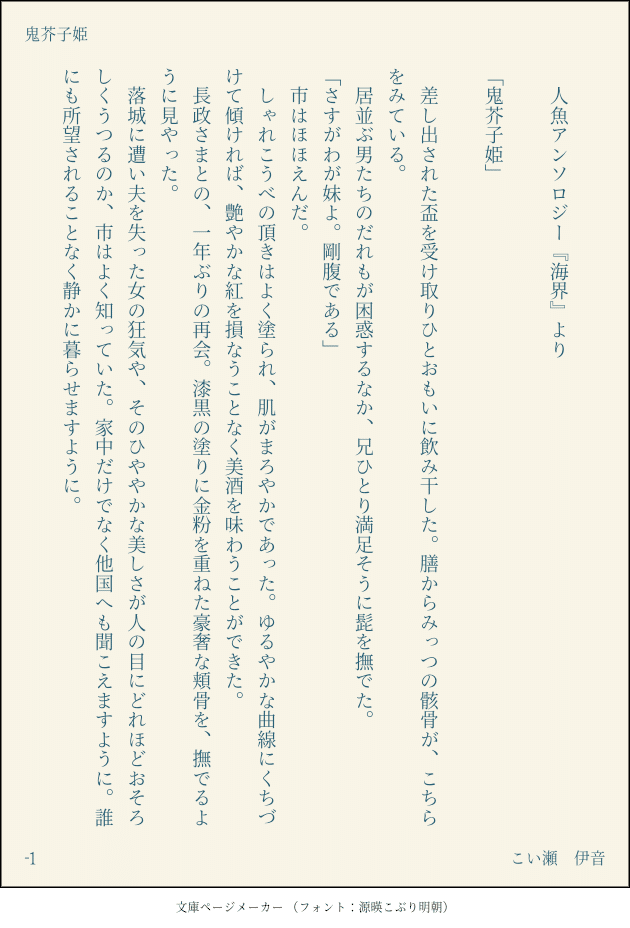
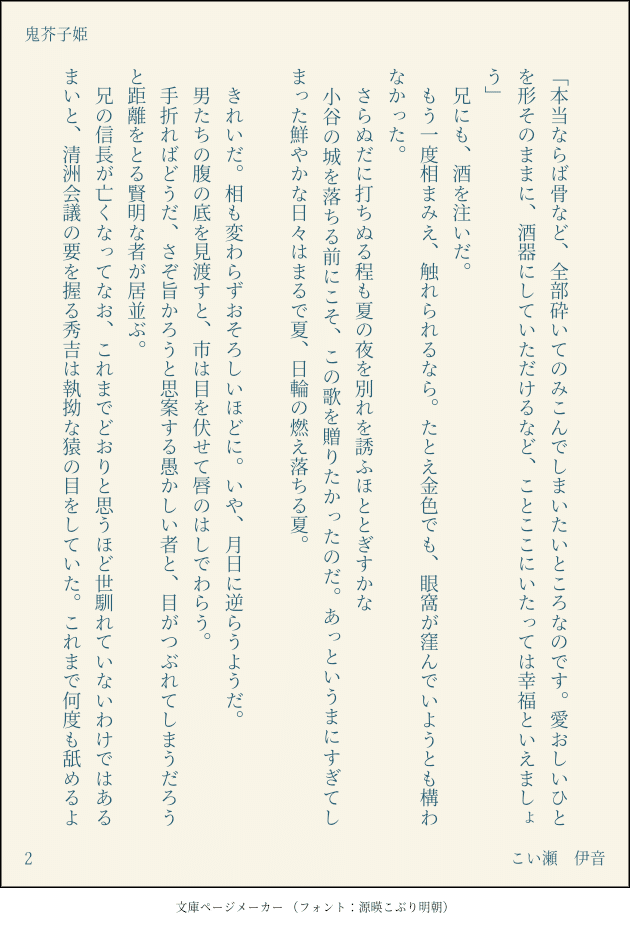

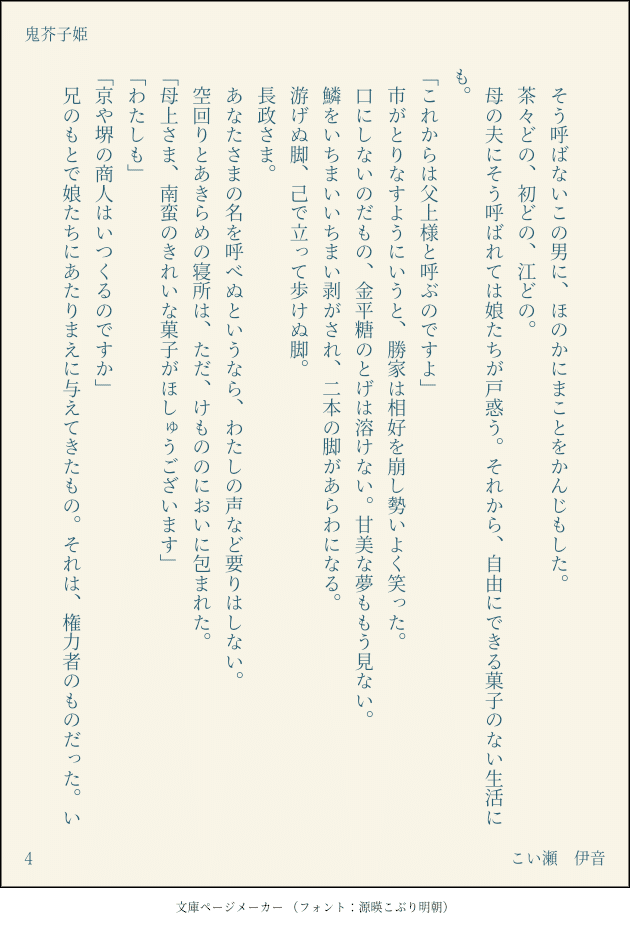
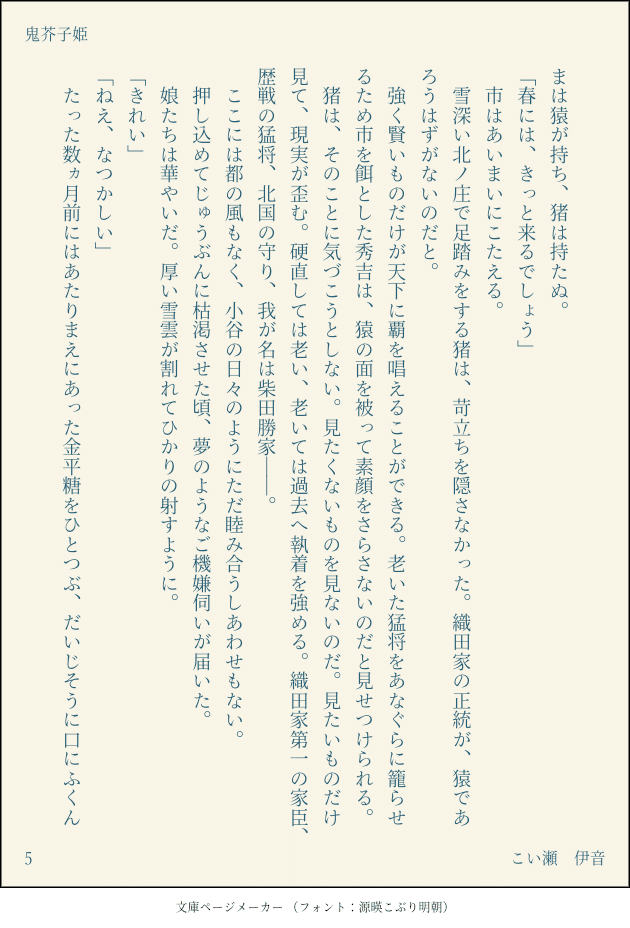
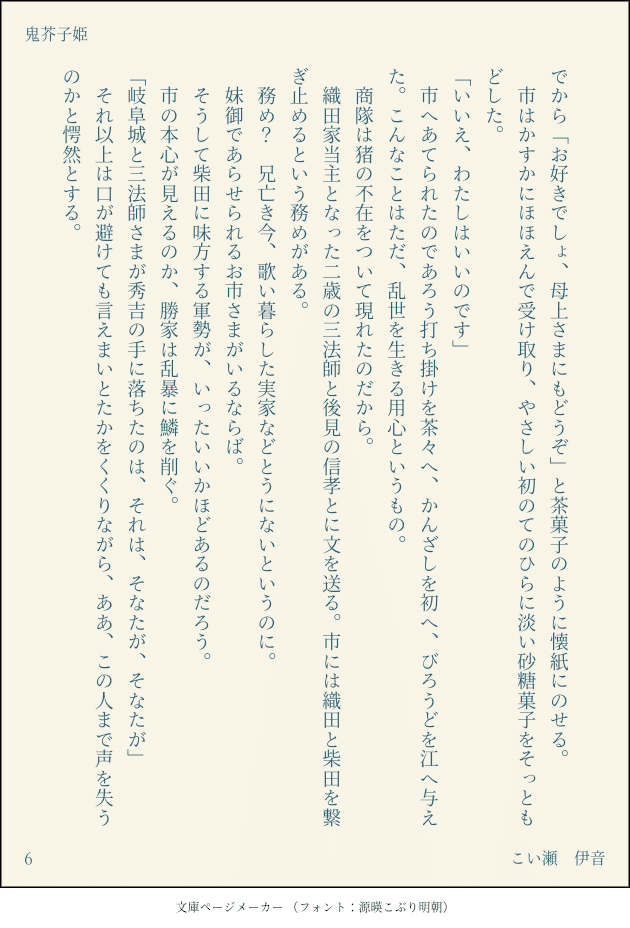
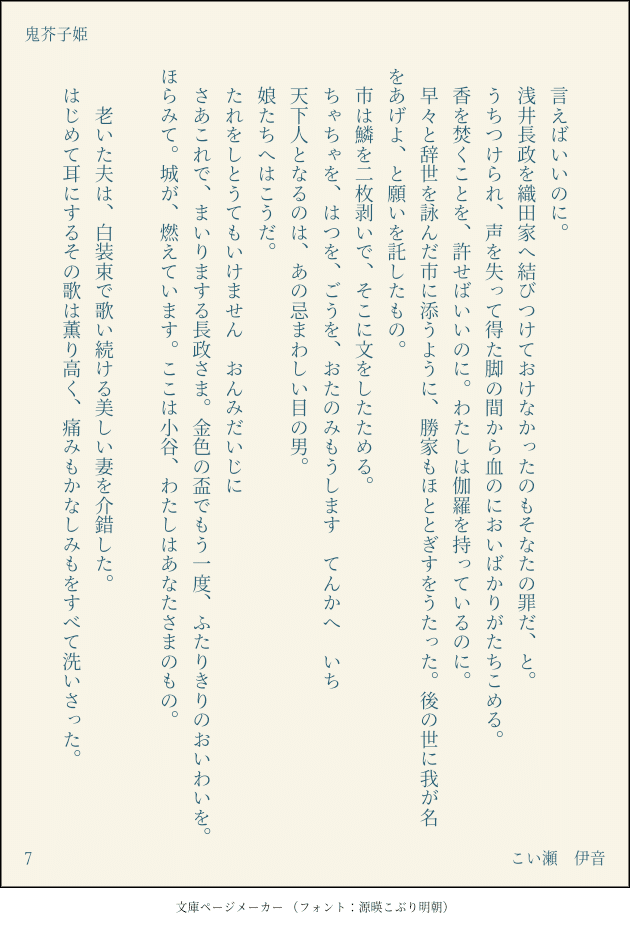
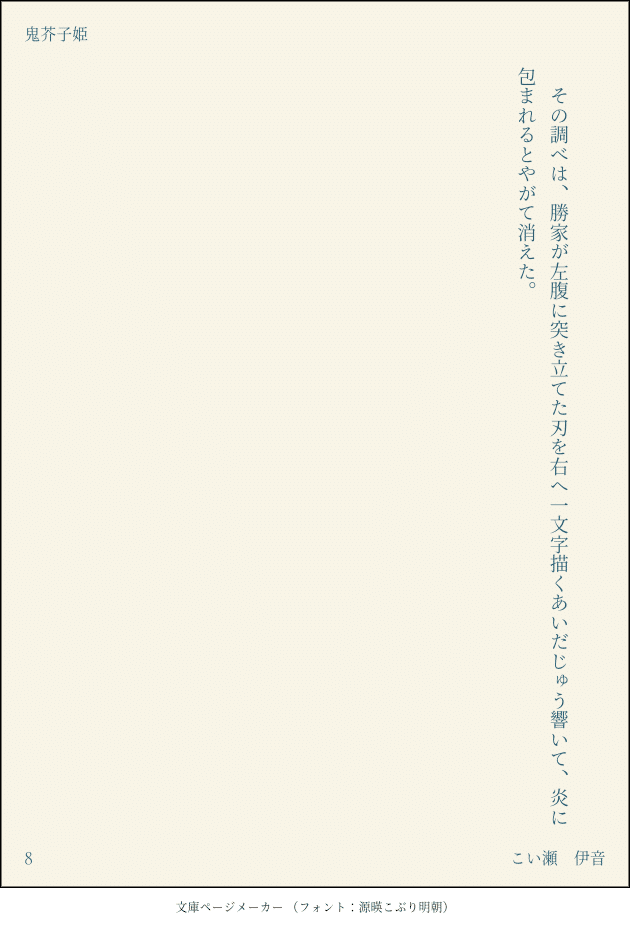
差し出された盃を受け取りひとおもいに飲み干した。膳からみっつの骸骨が、こちらをみている。
居並ぶ男たちのだれもが困惑するなか、兄ひとり満足そうに髭を撫でた。
「さすがわが妹よ。剛腹である」
市はほほえんだ。
しゃれこうべの頂きはよく塗られ、肌がまろやかであった。ゆるやかな曲線にくちづけて傾ければ、艶やかな紅を損なうことなく美酒を味わうことができた。
長政さまとの、一年ぶりの再会。漆黒の塗りに金粉を重ねた豪奢な頬骨を、撫でるように見やった。
落城に遭い夫を失った女の狂気や、そのひややかな美しさが人の目にどれほどおそろしくうつるのか、市はよく知っていた。家中だけでなく他国へも聞こえますように。誰にも所望されることなく静かに暮らせますように。
「本当ならば骨など、全部砕いてのみこんでしまいたいところなのです。愛おしいひとを形そのままに、酒器にしていただけるなど、ことここにいたっては幸福といえましょう」
兄にも、酒を注いだ。
もう一度相まみえ、触れられるなら。たとえ金色でも、眼窩が窪んでいようとも構わなかった。
さらぬだに打ちぬる程も夏の夜を別れを誘ふほととぎすかな
小谷の城を落ちる前にこそ、この歌を贈りたかったのだ。あっというまにすぎてしまった鮮やかな日々はまるで夏、日輪の燃え落ちる夏。
きれいだ。相も変わらずおそろしいほどに。いや、月日に逆らうようだ。
男たちの腹の底を見渡すと、市は目を伏せて唇のはしでわらう。
手折ればどうだ、さぞ旨かろうと思案する愚かしい者と、目がつぶれてしまうだろうと距離をとる賢明な者が居並ぶ。
兄の信長が亡くなってなお、これまでどおりと思うほど世馴れていないわけではあるまいと、清洲会議の要を握る秀吉は執拗な猿の目をしていた。これまで何度も舐めるように値踏みしてきた忌まわしいあの目だ。
この男は夫を殺した。夫を殺して、わたしを殺した。
もしも自分のものになれと言われたら、衆目を集めるなか舌を咬みきる準備はできていた。
うつくしいと称賛されうつくしいと蔑まれる。
この九年、三人の娘たちと、美しい歌を歌って過ごした。鏡台をあければいつでも金平糖があったし、それをこっそり口に入れていくのを見ても目こぼしできる余裕があった。物憂さのとげをねぶり甘美な夢にかえて。あのひとのいる海へ還ればいい。こころだけでも。
覚悟を決めた市へ、秀吉は柴田勝家へ嫁ぐのがいいといった。勝家は岩のような、老いた猪のようなからだをちいさく縮め頬を染めた。
市が初めての妻であると告げたその男は、粗野で、そのことをすこし恥じていた。ながく風雪にさらされた手は樫の木のように乾き、ほんのすこし曲がった指先で不器用に触れた。
市。
そう呼ばないこの男に、ほのかにまことをかんじもした。
茶々どの、初どの、江どの。
母の夫にそう呼ばれては娘たちが戸惑う。それから、自由にできる菓子のない生活にも。「これからは父上様と呼ぶのですよ」
市がとりなすようにいうと、勝家は相好を崩し勢いよく笑った。
口にしないのだもの、金平糖のとげは溶けない。甘美な夢ももう見ない。
鱗をいちまいいちまい剥がされ、二本の脚があらわになる。
游げぬ脚、己で立って歩けぬ脚。
長政さま。
あなたさまの名を呼べぬというなら、わたしの声など要りはしない。
空回りとあきらめの寝所は、ただ、けもののにおいに包まれた。
「母上さま、南蛮のきれいな菓子がほしゅうございます」
「わたしも」
「京や堺の商人はいつくるのですか」
兄のもとで娘たちにあたりまえに与えてきたもの。それは、権力者のものだった。いまは猿が持ち、猪は持たぬ。
「春には、きっと来るでしょう」
市はあいまいにこたえる。
雪深い北ノ庄で足踏みをする猪は、苛立ちを隠さなかった。織田家の正統が、猿であろうはずがないのだと。
強く賢いものだけが天下に覇を唱えることができる。老いた猛将をあなぐらに籠らせるため市を餌とした秀吉は、猿の面を被って素顔をさらさないのだと見せつけられる。
猪は、そのことに気づこうとしない。見たくないものを見ないのだ。見たいものだけ見て、現実が歪む。硬直しては老い、老いては過去へ執着を強める。織田家第一の家臣、歴戦の猛将、北国の守り、我が名は柴田勝家ーー。
ここには都の風もなく、小谷の日々のようにただ睦み合うしあわせもない。
押し込めてじゅうぶんに枯渇させた頃、夢のようなご機嫌伺いが届いた。
娘たちは華やいだ。厚い雪雲が割れてひかりの射すように。
「きれい」
「ねえ、なつかしい」
たった数ヵ月前にはあたりまえにあった金平糖をひとつぶ、だいじそうに口にふくんでから、「お好きでしょ、母上さまにもどうぞ」と茶菓子のように懐紙にのせる。
市はかすかにほほえんで受け取り、やさしい初のてのひらに淡い砂糖菓子をそっともどした。
「いいえ、わたしはいいのです」
市へあてられたのであろう打ち掛けを茶々へ、かんざしを初へ、びろうどを江へ与えた。こんなことはただ、乱世を生きる用心というもの。
商隊は猪の不在をついて現れたのだから。
織田家当主となった二歳の三法師と後見の信孝とに文を送る。市には織田と柴田を繋ぎ止めるという務めがある。
務め? 兄亡き今、歌い暮らした実家などとうにないというのに。
妹御であらせられるお市さまがいるならば。
そうして柴田に味方する軍勢が、いったいいかほどあるのだろう。
市の本心が見えるのか、勝家は乱暴に鱗を削ぐ。
「岐阜城と三法師さまが秀吉の手に落ちたのは、それは、そなたが、そなたが」
それ以上は口が避けても言えまいとたかをくくりながら、ああ、この人まで声を失うのかと愕然とする。
言えばいいのに。
浅井長政を織田家へ結びつけておけなかったのもそなたの罪だ、と。
うちつけられ、声を失って得た脚の間から血のにおいばかりがたちこめる。
香を焚くことを、許せばいいのに。わたしは伽羅を持っているのに。
早々と辞世を詠んだ市に添うように、勝家もほととぎすをうたった。後の世に我が名をあげよ、と願いを託したもの。
市は鱗を二枚剥いで、そこに文をしたためる。
ちゃちゃを、はつを、ごうを、おたのみもうします てんかへ いち
天下人となるのは、あの忌まわしい目の男。
娘たちへはこうだ。
たれをしとうてもいけません おんみだいじに
さあこれで、まいりまする長政さま。金色の盃でもう一度、ふたりきりのおいわいを。ほらみて。城が、燃えています。ここは小谷、わたしはあなたさまのもの。
老いた夫は、白装束で歌い続ける美しい妻を介錯した。
はじめて耳にするその歌は薫り高く、痛みもかなしみもをすべて洗いさった。
その調べは、勝家が左腹に突き立てた刃を右へ一文字描くあいだじゅう響いて、炎に包まれるとやがて消えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
