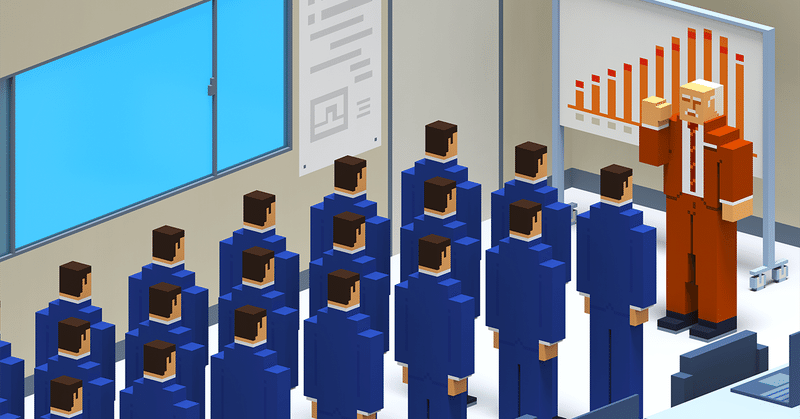
セクハラ研修をするほどセクハラが増える?-わかるようでわからないハラスメント(3)-
今回のエントリはハーバード・ビジネス・レビューの最新号である3月号の記事「職場のセクハラ対策はなぜ裏目に出るのか」を読んで得られた知見を踏まえて書いている。個人的には驚くべき結論であり、今着手している研修設計の組み直しも必要と感じたほどだ。セクハラの話だが、ハラスメント全般に読み替えてもよいだろう。
伝わるためには具体的にいうことが大切...だが?
僕の仕事では研修の開発をすることが多い。研修では、抽象的なことばかりでは聴衆に伝わらないことがある。だから、できる限り具体的に言うことが求められるし、その方が伝わる(実は僕の苦手分野)。
ハラスメントの研修で具体例を挙げるとハラスメントが増える?
それが故に、ハラスメントの研修でも禁止行為の具体例を挙げると効果的な気がするが、実にやりにくい。ハラスメントの禁止行為の具体例を挙げてほしいといわれたら「ピーでピーをピーしてピーピーピー」といった長渕剛ばりの表現になってしまう。放送禁止になりかねない。今書いているこの記述をするのですら勇気がいる。
想起させるのもダメなのでは?
想起させることがダメという側面もある。扇情的な身なりや、猥褻な図画が禁じられているのだってそういうことだ。だから、研修テキストにそんなことが赤裸々にかかれていたら、それを配ること自体がハラスメントと言われてしまう。ほら、この絵のこんなところがハラスメントなんですよといって、見せることもハラスメント的だ。自分が口に出さなくても、自分の作った資料にそれがあるのも下品で嫌だ。ろくなもんじゃねぇ。
研修会社に言いにくいことを言ってもらう、のは可能か?
研修を行う会社には「言いにくいことの代弁者」としての役割が期待されることがある。「あの研修の会社もこんなことを言っている。」という権威づけで使っていただけるのは嬉しいことだ。しかし、あの研修会社が「ピーでピーをピーしてピーピーピー」と言っていたと言われるのは嫌だ。
「ピーでピーをピーしてピーピーピー」ということだけを専業とするカテゴリーキラーの会社なら良いかもしれないが、曲がりなりにも、偉そうな研修をしている以上、変な風評は避けたい。
禁止行為の具体例を示す研修をすると、人が辞める
それでも、「線引がわからないから線を示したほうがよいのではないか」という声もある。
では、そうした線引を示したハラスメント研修に効果はあるのか。セクハラの研修で試した結果、「女性管理職が辞める」ことがわかったそうだ。実に5%も。逆効果だ。この因果関係についてはやや特殊な統計を用いて出した信頼できるものだ。
なぜ、逆効果になるのだろうか。それは。。。
あなたたちは、潜在的なハラスメントの加害者であり、かつ、線引もわかっていない。だから、研修を受けさせられているのだ。
というメッセージが伝わり、身構えてしまう結果、ハラスメント問題解決への抵抗勢力になるのだという。
その結果、研修の事例をネタにしたりすることが起きたりするらしい。セクハラ傾向のある男性は、さらにセクハラ傾向に肯定的となるらしい。まさに逆効果だ。
これを聞いて、少しホッとしたのは、「ピーをピーしてピーピーピー」という開発はしなくて良さそうだということだ。
---
前回の記事はこちら
超久々の続編はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
