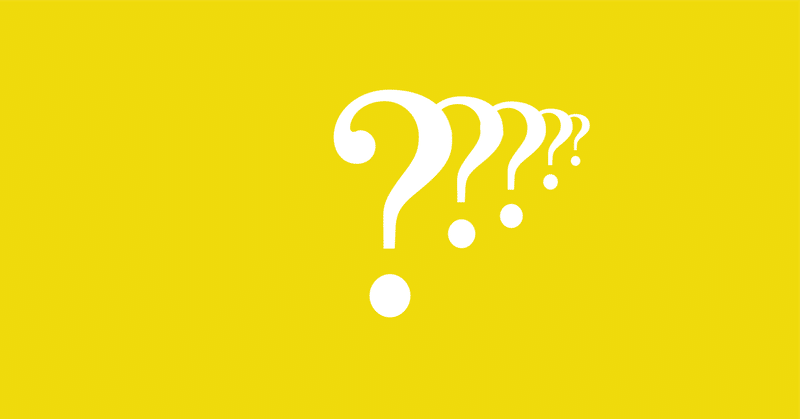
問いと質問
先日、スライドを作成している際に、自分が無意識に「問い」と「質問」の2つをを使い分けていることに気づいた。ただ、それは言語化されていない。
また、質問と詰問などについてもポジティブ、ネガティブという違いは感じるが、意味はわかっていない点があった。
今回はこのあたりを整理したい。
質問の意味
まず、質問とは文字通り「問い質すこと」という意味である。
辞書で質問を引くと、わからないこと、疑わしいことを問い質すこととある。
同じく、質問と意味の近い問いただすには、問い質すと問い正すがある。疑問・不審の点について、納得するまで質問し、明らかにするとのことだ。
正すと表記する場合、間違いを直すこと、質すと表記する場合、不明な点を明らかにするという使い分けになる。
質問は、疑問、不信、不明を明らかにするための問いと考えて良さそうだ。ただ、それでは問いの全てを網羅しない。質問はいずれも内発的なもののように感じる。自分が疑問に思う、不信に思う、不明に思うという内発的なものがあるから行うものが質問だ。また、その方向は他であり、自分に質問は普通はしない。となると、質問は、疑問、不信、不明を明らかにするための内発的問いとなる。
では、お仕事で質問をするという場合、内発的と言えるかというと、必ずしも内発的と言えないこともあると思う。その場合、必要に迫られて行うこととなるから、「質問」よりも「問い」がふさわしい。
次に、念のため、「質(シツ、シチ)」についても考えた。しつといった場合、質すという意味からは遠いように見える。ただ、これは質すところがない、つまり質が高いという意味だから、シツといった場合が完全度という意味になるのだろう。質が悪いといった場合、完全度が低いわけだ。更にそれが転じ質が高いものは価値を持つようになった。伴って質屋などが生まれ、価値の交換がうまれた。
そんなことをつらつらと考えた。
医者は仕事だから、問診というけど質問とは言わないなとか。
反証ができそうな話ではあるけど、自分なりの整理だ。多分、あとで追記する。
質問と詰問
質問と詰問についてだ。質問については書いたので、ここでは詰について書く。
詰というのは、詰めると読まれる。詰めるというのは逃げ場がなくなることだ。詰め将棋は相手の逃げ場がない状態に導くことだし、部下を詰める、上司に詰められたといった場合が選択肢が1つしかない状態に至ったということだ。また、箱詰めといった場合、出てこない、つまり他に行き場がない状態になることである。つまり、詰問とは、問によって、選択肢のないところに導く行為なのである。理詰めというが、理、つまりルールによって詰めることである。
質問は、問によって不明確さをなくすこと(明確にするとは不明確をなくすこと)だから、意味合いが確かに違う。詰問は相手の逃げ場、質問は問によって自分の理解が相手の意図と一意になることだと言える。
--
この話は「ファシリテーション」や「対話(ダイアログ)」周りにとも関わり、なかなか面白いと思っている。
類似するところでは、以下もある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
