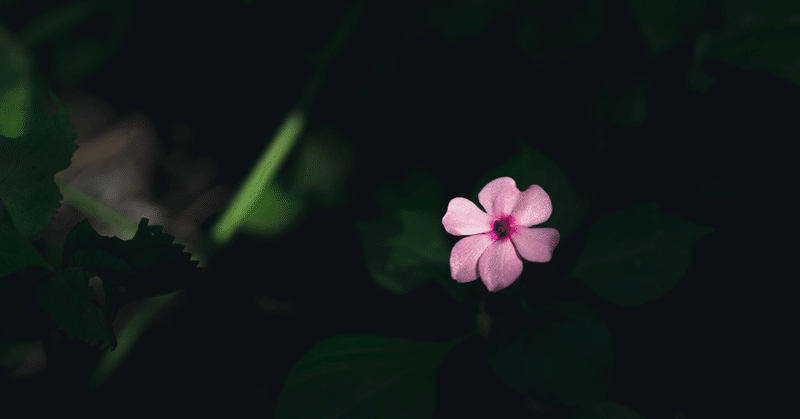
図書館で夢を読む
私が村上春樹作品と出会ったのは、中学2年生14歳の冬休みだったと記憶している。国語の宿題でノルウェイの森が課題図書として指定されたのがきっかけだった。
当時はあまり引きこまれなかった気がしているが(何しろ三角関係や惚れた腫れたといったことにはちっとも興味がなかったので。)、その翌年15歳のときに海辺のカフカを読んで、すっかりその世界観に引きこまれてしまった。
たぶん、主人公と年のころが同じだったことも影響しているのだろうけど、なんというか何がどうなってこうなって…という展開ではないし、それぞれの出来事に明確な意味や定義も示されていないし、(だいたいの場合において)最終的に何かはっきりとした答えや結果が示されることはないのだが、なぜか読むのをとめられなかった。
当時受験生としてそれなりに悩んだりもしていた私にとって、少なくとも人間は皆迷う、それでも誰かとかかわって何かに気がついたりするんだろう、そうやって生きていくんだろう、現実からは逃げても逃げ切ることは出来ないのだ、ということを改めて突きつけられたような気がした。
私はどちらかというと数多くの作品の中で、現実世界よりももうひとつの世界のパートにぐっと引きこまれていた。もしかすると、私自身もそこにいるような、こんな世界にいられたらどんなにいいだろうか、しかしその代償をわたしは受け入れることができるのだろうか?と考えながら日々を過ごしている。
以降この10数年の間にいくつかの作品を読むたびに、そして読み返したくなるタイミングはいつも迷ったりしているときなのだけど、それはどうしてなんでしょうね。
まあ、それはいいとして、今、ちょうど新刊を読んでいる途中ではあるのだけど、湧き上がってきた感情を今は取り除かないと仕事に差し支える恐れがあるため、全体のまとまりや順序などはいったん無視して書き進めたい。
ひとまず、まず言いたいのは、タイトルに示した通り、『図書館で夢を読む』ことがいったい何のことかこれだけでわかったときの、うわ~!という言葉にならないあの感じを言い表したいのだけど、申し訳ないのだが私の乏しい語彙力では適切に表現できない。それも、その関連性を示唆するお話は、私が一番好きな世界のことなのであるから、余計になんともいえぬ感情が湧き出てきたのである。
なんだろうなあ、何がいいとかを説明するのはこれまた少し難しいのだけど、あるセンテンスに出会ったとき、それが救いとなって気持ちが少しだけ軽くなる経験っていうのは、群を抜いて村上春樹作品からだと思う。
あたりまえなんだけど、なかなか言わないことってあったりするし、そっか、この登場人物たちにとってしてみてもそんなもんなんだ。そうやって割り切ったり、一方であきらめなくたっていいんだって思ったときに自分だけじゃないというか、表には出さないけど誰しも何かしら抱えているんだろうな。悩んでいるのは私だけじゃないんだなと思えたから、本を開けばそこにいつでもいるんだと思えるってのがいちばんかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
