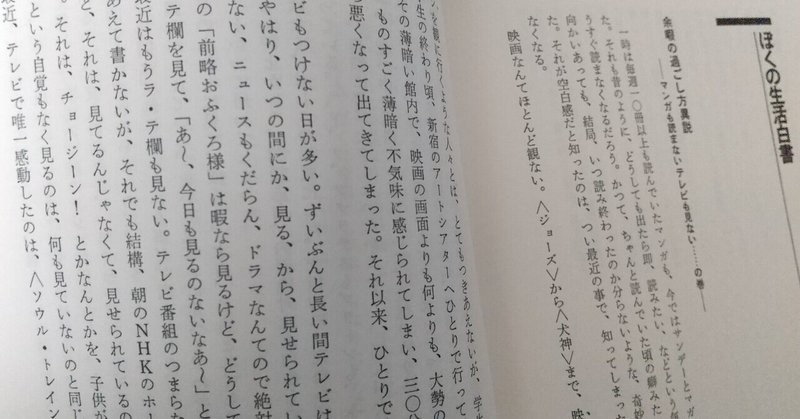
「企画書」読書メモ20
Ⅲ.
「ぼくの生活白書」
余暇の過ごし方異説ーマンガも読まないテレビも見ない・・・・・・の巻ー
青少年の大半が、幸福だと感じているらしい。だけど、多分それは、幸福になった、のではなくて、幸福にさせられてしまったのだ。(p.219)
強いられた幸福なるものが果して不幸すら自覚し得ない程の不幸、なのかどうか分らないが、すくなくとも、ぼくは幸福にも不幸にもなりたくない。ただ自覚的な生を楽しみたいだけだ。(p.219)
私自身、子供の頃から、生きていることの「手応え」を何より欲していた。表面的な明るさ、みたいなものとか、観念的な、感謝、だとか、そういった美辞麗句のようなものがとても気持ち悪く感じられる子供時代を送っていて、だからして、幸福にも不幸にもなりたくない、ただ自覚的な生を楽しみたいという文章に深く共感する。ある時期、「幸せになりたい」という欲望をもったりして、でもそれはじきに、「幸せにならなければ」に変わって自分自身を苦しめた。今振り返ってみると、「(自分だけが)幸せになりたい」と思っていた時期が、私にとって、最も不幸な時期で、「もう幸せとかどうでもいいかな」「なるようになれ」「不幸、どんとこい」と思い始めた今の方が、よほど晴れ晴れとした気分で、幸せな時間を過ごせている。単純に期待値が上がれば上がるほど失望も大きい、という問題なのかもしれないが。あんまり幸・不幸という状態に気持ちをもっていかれないで、ただただポジティブもネガティブさえも、面白がり楽しみ、そうやって生きたほうがかえって豊かなような気がする。
映画とかロックとかいうモノを通してではなく、時が、時だけが真のメディア。時をまっさらな空白へと一度帰そう。具体的なメディアはそれからです。(p.221-222)
時だけが真のメディア、かあ。メディア、媒介、みたいな意味だとすれば、確かに、時間だけが真に私たちを媒介しているというのは確かだ。情報というのはある人の主観によって編集されてしまっているから、どうしたって偏りが出てきてしまうから。
赤ちゃんがやってきた
もっといろんな局面で、親としてのぼくは、物事の在り方とか、関係の在り方に対する視線の不明確な部分が多い事を、今度知りました。その不明確な部分を、習慣だとか風習だとか、みんながやってる事だとか、そういう形でゴマ化したり曖昧にしたままで、ヒステリックに子供をしかりたくない。そういう意味で、子育て、とは、ぼくにとって、新たな、自己検証の場となるのだと思います。(p.227)
親になったことも、子育てしたこともない私は、この文章について、経験的に語ることはできないけれど、自分が試される機会になるってことなんだなと理解しました。
死者の財布
1.老人たちの死
老人問題は以前のように、それぞれの<家庭内>問題から大きくはみ出し、今は、都市の問題、社会の問題となってきたようだ。(p.228)
老人問題は個人的・家庭内的な問題ではなく、構造的な問題ということのよう。
それは別に具体的に病気になった時のために残しておく、とかそういう意味ではなく、精神的に、きわめて観念的に自分を支えてくれるものなのである。事実、この種の老人は、たとえ病気になっても、金を使ってまで医者にかかる、という事はない。(p.228)
それは完全に宗教であり、金が神の代理という事である。(p.228)
そもそも国家とは、何かしらの宗教団体であり、資本主義国家とは、金が神であることによって成立しているのだろう。(p.228-229)
この老人たちの生と死が示した事は、もしかして、この国に生きるぼくたちの内部意識の極端な抽象化なのかもしれない。(p.229)
私たちが、お金と引き換えにして、大事なものを見失ってしまっている可能性について、考える価値はあるかもしれない。
2.田中角栄
正確な言い方をすれば、越後の人にとって角栄が神なのではなく、角栄は神を呼ぶ事のできる人、なのである。(p.229)
金がぼくたちの神としてあるのなら、外的な理念や恣意的な暴力によっては、神を殺す事はできない。神を殺すのではなく、神を神として在らしめているところのぼくらの諸々の幻想をこそ殺さなければならないのであって、金に対する感覚を、億とか兆とかいう観念的なものではなく、生活感覚のものですましてしまう事が、今はとりあえず大切なのではなかろうか。ぶくぶくに肥った観念(=宗教)などを、誰も欲しがらないようになれば、生活的国家程度のものはできるのではないだろうか。(p.231)
億とか兆とかいう単位のレベルの話になると、皮膚感覚でとらえられなくなり、宗教性を帯びてくるという話。重要そうな指摘だ。
4.とりあえずの結論
すべての労働の成果や、意識的肉体的成果が、金という曇ったフィルターを通してでしかぼくたちに届かない、というシステムが、逆に、ぼくたちの<労働>というものを、きわめて観念的なもの、真の労働の意味(=必要であるから喜びであるような労働)とは無縁なものへと追いやっているのではないか。それは、ぼくたちの本来の生の内実とか欲望の質すらも、とりあえず金を手中にしてから展開しよう、という具合に屈折させられてはいないだろうか。(p.231)
生活のために金が要る、という誰もの社会生活の初期発想が、いつか、金のために生活する、というふうに逆転してしまうところに、金というものの宗教性(=女神としてのマネー)、ぼくらの中途半端な観念の脆弱さがあるのだと思う。(p.231-232)
貨幣というのは、今の社会生活の基礎にある事は事実で、基礎に対する不断の点検をなおざりにしたり、無自覚であったりしては、一切の生活論もマーケティング論も、単にチャラチャラした見張番の目うつりにしかすぎないだろう。(p.232)
私自身、まだまだお金とうまく付き合えていないと感じている。
5.佐藤雅子さん
<「お金はたいせつだが、いやなもの」というのが私の気持ちで、人間がいちばん誘惑されやすいものです。だから、きびしい心でのぞまないといけないと思います。お金をどう考えるかということは時間や品物をどう扱うかということにも通じますし、それよりも、もっと人間の生き方、心の問題にもつながると思うのです>佐藤雅子/私の保存食ノート/文化出版局(p.233)
お金をどう考えるかということは時間や品物をどう扱うかということ、人間の生き方、心の問題につながる、かあ。人生をしっかり大切にすることと、お金はつながっているということかな。
突然だが世代論をぶちかましてみよう
世代論の不潔さ、世代論を語る者の不潔さを暴露し、あの、ところどころに群なしている連中から逃れたいと思うのです。(p.233)
世代論の不潔さは、それを語るものの自己肯定がそのまま拡大される事ばかりではなく、生まれたばかりの赤ちゃんから、息をひきとる寸前の老人までに、共通にのしかかる時代意識というものを、時代の共有意識、ではなく個人の特権意識へと囲い込むものだからである。(p.234)
世代論のような、ちっぽけな自己肯定ではなく、もっと大きな、歴史肯定意識とでもいうべきものをぼくたちは獲得しなくてはならなくなってきているのではないだろうか。(p.234)
自己肯定感なんて言葉が流行りまくった昨今だけど、この本は1980年代出版の本。その時点で自己肯定という言葉を使い、世代論で自己肯定してしまう、その安易さを端的に指摘している。愛国心で自己肯定することの安易さも、どこか似ているような気がする。自己肯定という個人的肯定ではなく、人類愛につながるような、歴史肯定意識の獲得をめざすべき、とも。
世代論=風景論は普遍性を持たないから、第三者にとっては何の事やら分らない。そして、普遍性を持たないがゆえに、個人の特権意識を増長させるものでしかない。(p.235)
世代論、思い出話で内輪っぽく盛り上がっている人たちの姿って、関係ない人間からすると、とてもうすら寒くみえるものなんだよなー。
世代とは単に時間によってぼくたちに与えられたものにすぎない。与えられた時代というものを、あるいは与えられたものとしての自分というものを、風景として語るものでも描くのでもなく、それは奇跡的な素材なのだから、あくまでそれは前提として後ろへ追いやり、そこからこそ出発していくべきなのだろう。(p.236)
世代を、時代を、前提として後ろに追いやり、そこからこそ出発するべき、か。わかったようなわからぬような。
ぼくたち自身が自己規定しないかわりに(自分を規定するとは変化の否定だから)別の人間たちがずいぶんと命名してくれた。(p.236)
危険な十七歳、狂気の十九歳、全共闘世代、戦無派、しらけ世代、ニューファミリーetc、それこそ一年単位でやたらとつけられたが、どれも、当人が言ったらバカみたいなのばかりだ。(p.236)
当人が言わなくても、充分バカみたいです。
当たり前だが、時代のもっとも時代的な部分は、個人の沈黙の中にしかなく、そして、それを語るべき言葉は、その個人の、次の行動(=思考とか表情とか日常的仕草とかを含めた)にしかないのだ。(p.236-237)
このへんは私にはよくわからない感覚だが(なんでも言語化したがるタチなので)、重要そうなので抜粋した。
世代論を語るものは、それが積極的であれ、消極的であれ、それを語れば語るほど、現実の自分を希薄化しているようなもので、一種のゆるやかな自殺であり、だから、世代論が一番多く語られるのは酒場である。(p.237)
まさに、そのとおり、と思う。
機械とのつきあい方ーマシーン・ヘッドー
しかし、機械の方は、人間のそうした感傷を許さず、大股に進歩していく。人間の技術とは個人史的なもので他人に譲れないが(昔の名人は盗め!と言ったが、それはそうとしか言いようがなかったのだ)、機械の進歩は個的な枠を超え、体系全体をまるごと吸収して累積的に進歩していくから、これからは生産の場面では、人間はますます無力になるだろう。(p.241)
おそらくどの業界でも、このような<人間の個々の技術が無効になる時代>への予兆なり現実なりは進展しているのだと思う。(p.241)
機械がやるべきことを人間がやっていたから、この一〇〇年間というもの、どの人間も機械の部品のように灰色の顔をしていたのだ。(p.241-242)
機械の精巧な部品として生涯を終え、その道の達人になったり、職人としての矜持を保つ事も、それはやはり、よくできた機械の満足感であって、人間としての満足感ではないのだろう。(p.242)
世界中の、あちこちから人間が押し出されて来る。奥さんは家事労働の電化によって家から押し出され、サラリーマンは週休二日三日制で会社から押し出されている。経済学をやるために大学に残った男の話では<今時の経済学なんてプログラマーと一緒だよ>だそうだ。東京ではオンラインシステムも充実に向かっているし、商店もスーパーなりコンビニエンスなりに集合化している。将来的には無人店舗になるだろう。いたるところで人間が消えていく。機械だけが残る。消えた人間はどこへ行くのか?(p.243)
みんなどこへ行くのか? 人間ー機械系社会のあり方は、機械が出て来たので人間は追いやられる、のではなくて、機械が出て来たことによって人間も出て来る、であるべきなのだ。どのように出るのか?それは子供がおきたら尋ねてみる事にしましょう。(p.244)
「機械が出て来たことによって人間も出て来る」、この在り方を、必死に模索すべきですね。
ぼくの生活真情
ぼくら大人が赤ちゃんに教えるという事といえば、「あっ!そっちへ行くと危ないからダメだよ」とか「そんなもん口にするんじゃないよ」とか、そういった種類の事で、どうも、本質的な事は、教えるとかそういう質の事ではないようだ。だって、赤ちゃんは、最初っから試すという事を知ってるわけだし、なるべく、いろんな事を本人自身に試させた方が正解みたいだ。(p.244)
「教育」なんて、もう死語にしてしまえ。ともに育つ。それ以上のことなどないのだ。一方的に教えることなんて、きっとひとつもないのだ。
家庭の仕事の中で、掃除とか料理とかは合理化できるけど、育児だけは合理化できないわよね、とカミさんは続けた。(p.245)
「育児だけは合理化できない」この事実に、きっと人間の大事なことが潜伏している。
<子供は自分で育つ>という当り前の発想が<子供は育てるもの>という思い込みに変わった。(p.245)
もう一度言おう。「教育」を死語に。育ち合うほかないのだ。わたしたちは。
例えば、三〇年前だったら、子供が父親を尊敬します、と言ったらば、それは単に個別的な、自分の父親そのものだけではなくて、その裏側にそれとは別の、もっと強固な<父親という価値観>があって、それを含めて尊敬という言葉があったんだ。今は、まだ残滓はあるにしても、三〇年前ほどの、強固な客観的価値観などは喪失しているから、今の子供が父親を見る視線は具体的なひとりの父親という人間性でしかなく、それはすごく良い方向だと思う。いつまでも、客観的な父親像、あるべき父親の姿、みたいなものに固執していると、足をもがれた案山子みたいに部屋に転がってるしかなくなるぞ。(p.246)
<父親という価値観>というものがあった時代があったんだな、というのは話として聞いたことはあるけど、その時代を生きていなくて、思いっきり、父親=自分の個人的な父親、でしかないという感覚で生きてきたから、想像でしかないけど、まあ、観念的な時代よりは、マシな時代に生まれることができたのかな。
隣の芝生で遊びたい
赤ちゃんの笑顔というのは、どこへ行ってもメディアそのもので、これまで会っても知らんぷりの近所のおばあちゃんも話しかけてきたし、電車に乗れば、隣のおじさんが話しかけてくるし、スーパーへ行けば店のおばさんが「赤ちゃん! こっち見て」と呼んだりする。(p.249)
橘川幸夫さんにとって、真のメディアは、「時」であり、「赤ちゃんの笑顔」なんだなー。メディアのイメージが、この本で随分変わった。
斎藤次郎さんは、主婦の労働組合(だったかな?)を作って子供のあずかり合いを、と提唱されてるらしいですが、賛成します。(p.249)
保育所などは、企業が社内に作るべきだ、という意見があるけど、本当に保育施設を必要としているのは、それを作る余裕のある大企業の社員ではなくて、中小企業で働かなければならない人たちである、というのが現実なのだから、保育施設は、生活地域的な所に社会的に作られるべきだ。(p.249-250)
育児を単に親が子供を育てる事ではなく、育児する事によって、育てる人間が自分自身を教育し、子供を産みの親に帰属させないで、子供を社会的に閉じた、自閉症的な子供にしないための運動の例として、<育児労働銀行>という発案がある。(p.250)
「社会的親」みたいな言葉もある。
主に高校生とか大学生(もちろん男女不問)に登録してもらって、その人の近所に赤ちゃんが生まれたら、自分の暇な時間を使って、育児労働、あるいは、母親が育児労働をするのを助けるための家内労働をやってもらう。そのかわりに、自分が親になった際は、また、近くの人に頼む、という具合です。学校で受験勉強するより、よっぽど勉強になると思いますが。(p.250-251)
アイディアとしては賛成です。
特定の人にしか自分の心を開けない、助け合えない、なんて、全然不自然。(p.251)
これは本当にそう思う。けど、特定の人にしか、という人が多いと感じる。そういう人って、そこそこ恵まれた人間関係の中で生きてきたんだろうなと思う。一度いじめを被害者として経験すると、特定の人にしか心を開けない人たちの残酷さを嫌と言うほど感じるから、私はそういう人間にはなりたくない、と思う。まあ、「勝ち組」になりたくて、いじめられないように、特定の人にしか心を開けない派閥に自ら入信する人も結構いるようだけど。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひとまず、「企画書」読了しました。
とても刺激的な本でした。アウトプットした読書メモを読み返し、メディアについて自分なりに考える機会を改めて作りたいと思います。
サポートして頂いたお金は、ライターとしての深化・発展のために大切に使わせていただきます。
