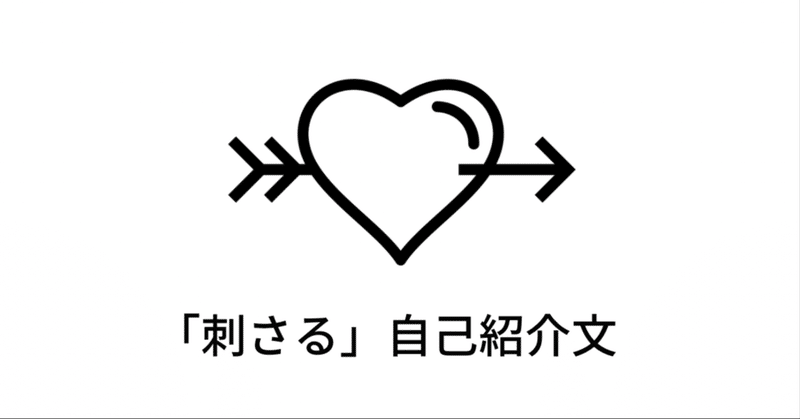
「刺さる」自己紹介文|”自分”を売り込む企画書
はじめまして、新卒3年目かけだしコンテンツプロデューサーのこにたんです。現在、某エンタメ企業にてコミュニティ形成のための施策を企画したり、『逃走中』の生みの親である元フジテレビプロデューサー髙瀬敦也さんのもとでコンテンツプロデュース業に携わったりしています。
SNSやアプリなどオンライン上で、書く機会が多くなった自己紹介文。今回は、「刺さる」自己紹介文について、「企画書」になぞらえながら、その書き方のポイントをまとめていきたいと思います。
ここでは、私が髙瀬さんとお仕事をするきっかけとなった自己紹介文を例に、そこでも意識したポイントを4つピックアップしてみました。
”自分”というコンテンツを売り込む”企画書”
「企画書」を書いたことない方もいらっしゃるかもしれません。企画書とは、なにか新しいコンテンツやプロジェクトを提案する際に、上司やクライアントに向けて提出するものです。
私は、これを「巻き込みたい相手」を口説くためのラブレターだと捉えています。この企画によってなにをしたいのか、なぜあなたと一緒に実現させたいのか、これによってどんな効果が得られるのかをひたすらに綴るからです。
自己紹介をする際も、相手からなにかしらを得ようとしているはず。マッチングアプリなら、恋人になってほしい!就活のエントリーシートなら、採用されたい!など。
当たり前すぎて忘れがちですが、自己紹介文も相手に自分をアピールするという目的があるので、私はこれも企画書であると考えます。
髙瀬さんとの出会いからオファーまで
『逃走中』や『ヌメロン』など数々のヒットコンテンツを生み出してきたコンテンツプロデューサー・髙瀬敦也さんを知ったきっかけは、2021年に発売された著書『企画「いい企画」なんて存在しない』でした。
この本を読んで、「絶対、一緒に仕事をしたい!」と思い立った私。
なんとか接触できないかとたどり着いたのが、髙瀬さんのオンラインサロン『コンテンツファクトリー2030』です。
入会すると自己紹介チャネルに投稿するのですが、ここでも「企画力」が求められると思った私は、iPhoneのメモで自己紹介文を練り上げます。
実際に投稿した自己紹介文がこちら。



そして、髙瀬さんよりコメントをいただきました。

無事、刺さったようです。笑
サロンでの初めての雑談会の直後、髙瀬さんより、「改めて、お話ししましょう」とのメッセージが。なにごとかと思って、話を伺うと、
「これから企画できる人が求められる」
「一緒に自転車を漕いでくれる人がほしい」
「小西さん、そういうの好きそうだよね」
ということで、早速、オファーをいただきました。
あっさりすぎて、内心きょとんでしたが、もちろん即答でYES。
そんなこんなで、一緒にお仕事をさせてもらう機会をいただきました。
※髙瀬さんとのお仕事の中での学びや考えについても、今後、記事として発信していきたいと思います!
4つの「刺さる」ポイント
①「だれに」「なにを」伝えたいのか
企画書やプレゼンをつくるとき、「目的」の明確化ができていないと、なにがしたいのかが受け手にも伝わらないし、当の本人もなにを伝えたいのか途中でわからなくなってしまうと思います。
私は、自己紹介にもこれがあてはまると思います。
私も以前は、目的意識がとても低くて、上司に「で、これやる目的はなんなの?」「目的が甘い」と詰められる日々でした。それ以来、めちゃくちゃ意識して「なんのためにこの企画が存在するのか」と考え続けていると、自然と考えるクセがつきました。
冒頭で、自己紹介文も企画書であると述べました。
・自分について知ってほしい相手は「だれ」なのか
・その人に「なにを伝えたい」のか
・そこから「なにを得たい」のか
を改めて書く前に考えてみましょう。
就活のエントリーシートなら、この会社に採用してもらいたいから、会社の求める人材であることをアピールする。マッチングアプリなら、自分と相性のいい人と付き合いたいから、自分の性格や理解してほしい価値観などを書く。というアプローチができますよね。
特に、「だれ」の部分は、具体的な「あの人」(みたいな人)を思い描くといいです。私の場合は、髙瀬さんという明確なターゲットがいましたが、いなかったとしても「だれか」をイメージします。例えば、この記事は、オンラインサロンのメンバーを想像しながら書いています。
②「読みやすい」構成
特にオンライン上での自己紹介文においては、文章の第一印象があなたの第一印象になる、ということを意識する。これは企画書にもあてはまることで、パッと見の印象で、読む側の心構えも変わってきます。
文章の「デザイン」について、とてもわかりやすい記事を見つけたので、こちらも参考になるかと思います。
私の場合は、段落分けと箇条書きでデザインしようと決めました。
次は、どこでなにを言おうとしているかをわかりやすくするため、各段落の冒頭にキーワードを持ってくるようにします。「見出し」のようなものです。
私自身がせっかちなので、文章を読んでいても「要点」だけをとりあえず知りたいと思ってしまうんですね。なので、冒頭を見出しとすることで、読み手を誘導できるように工夫しました。<本業について>のように括弧を使うのもよいと思います。
③「面白そう」と思わせるつかみ
仕事で、スタートアップのピッチを見ることも多いのですが、「つかみ」が上手いプレゼンは「続きも聞きたい!」と思わせてくれます。だいたいの場合は、その企業が成し遂げたいことや、業界の意外な課題を提示します。
序盤で「つかむ」ことは、それ以降の注意を持続させる上で、とても効果的です。
つかみ方は、なんでもいいと思います。今回の私は、「企画」というテーマにあてはまりそうな自分の目標を書きましたが、他にも「No 麻雀 No Lifeな27歳OL」とか「本当はコミュ障な演技派コミュニティマネージャー」とか、なんでも書けます。
「自分は平凡すぎて、なにも書くことがないよ〜」という方は、「平凡すぎる」ということを自虐して書くのもありだと思います。笑
④親近感と差別化
このふたつのバランスを考えながら自己紹介をします。
まずは、親近感を持ってもらうために、「自己開示」「共通点になりそうなキーワード」「話しかけやすい雰囲気」を意識します。
【自己開示】
自分の情報を先にさらけ出すことで、相手の安心感や信頼を引き出します。そうすると、「自己開示の返報性」といって、相手も情報を出してくれることが多いです。こんな性格、こんなことが苦手などより個人的な話を盛り込むといいと思います。
【共通点になりそうなキーワード】
私の場合は、事前に髙瀬さんが興味を持つ分野や最近メディアで話されていたトピックをリサーチできたので、それらに関係しそうなものはできるだけ盛り込みました。不特定多数が相手の場合は、「想像上のだれか」に刺さりそうなキーワードを考えてみるといいでしょう。
【話しかけやすい雰囲気】
文字のテンションからも伝わりますが、写真をつけられる場合は、絶対につけたほうがいいです。「楽しそうな人」に見える写真は、一気に親近感を高めてくれます。
※ちなみに、私の男友達は、マッチングアプリのプロフィール写真で、1枚目を雪の中でエルサのコスプレをした写真、2枚目を愛犬とのツーショット写真にしたところ、マッリング率が爆上がりしたそうです。笑
それと同時に、「なにやら、すごそう」「この人、違うな」と思ってもらう、差別化も大事です。これは、”すごい”アピールで、マウントをとれというわけではありません。なにか、人と違う経験や経歴、人と違う視点をさらっと書けばいいんです。
さいごに|”企画者”として
企画者やプロデューサーというと、YouTubeの動画の企画者やテレビのプロデューサーなど、専門職のようなイメージを持たれるかもしれません。私も仕事でイベントの企画などを担当するまでは、そう思っていました。
でも、やってみると、「これは、だれでもできるな」と思い始めました。というより、「企画」とは特別なものではなくて、日常の中でだれしもがやっていることなんだなと。
今回紹介した「自己紹介」についてもそうです。なにか自分がやりたいことや、なにかの目的のためにやろうとしていること、そのすべてが企画なんだと考えます。
なにごとにも「企画者」として取り組んでみましょう。やることなすこと全部「企画」だと思ったら、なんだかワクワクしませんか?笑
「自分」というコンテンツを売り込む「企画」として、自己紹介を捉えてみることで、魅力的なプロフィールが増えて、より多くのマッチングが生まれる世界になればいいなと思います。
私は企画とは、「決めること」だと思っています。厳密にいえば、「何かを実行するまでの過程で決まった結果」に過ぎないと考えています。ですから、企画には「先天的なセンス」も「神がかったひらめき」も必要ありません。「決める」だけで企画になります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
