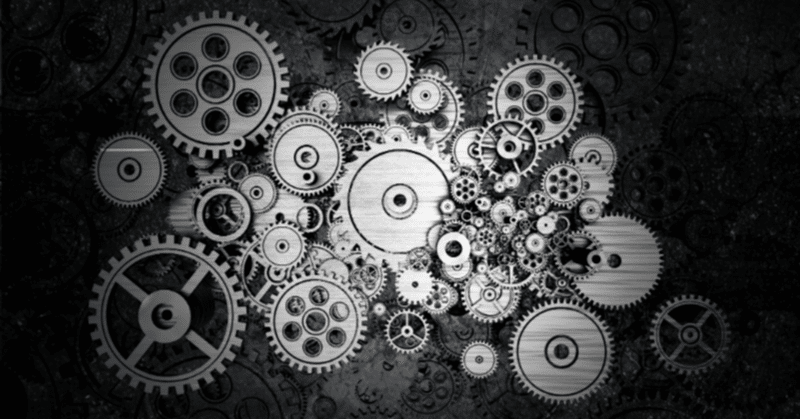
【小説に語り手は必要?】作者・語り手・登場人物の関係性を探る(2011年10月号特集)
作者・語り手・人物
小説を書くうえでは押さえておかなければならない人がいます。語り手です。
ただ、小説ではこの語り手の存在が希薄で、しかも、作者や人物と一人二役だったりしますので、意識しないと分かりにくい。特に現代小説では暖昧です。
《「作者=語り手=主人公」》
山の手線の電車に跳飛ばされて怪我をした、その後養生に、一人で但馬の城崎温泉へ出掛けた。
『城の崎にて』は=「自分は」という一人称で語っています。しかも、志賀直哉自身の実体験をもとにした私小説です。
これは「作者=語り手=主人公」という一人三役の形式です。
《「作者≠語り手=主人公」》
朝、食堂でスウプを一さじすっと吸ってお母さまが、
「あ」
と幽かな叫び声をお挙げになった。
太宰治の『斜陽』です。『斜陽』も一人称で書かれていますが、『城の崎にて』とは違い、私小説ではありません。語り手の「私」は没落貴族の娘であり、「作者≠語り手」です。しかし、一人称ですから「語り手=主人公」です。
《「作者≠語り手≒主人公」》
ライオン像にもたれるように背の高い女の子がひとり立っていた。(中略)これがあの親しげなメールを十数通も書いてくれた有希なのだろうか。瑞樹の声は自然に低くなった。
語り手は「作中にはいない誰か」ではありますが、作者の石田衣良ではありません。「作者≠語り手」です。
しかし、語り手と主人公の瑞樹は同一人物と言っていいくらい近い存在です。
出来事が済んだあとの瑞樹が、まさに出来事に遭遇している自分に密着して語っているともいえます。ですので、この場合は「語り手≒主人公」と言えます。
《「作者≠語り手≠主人公」》
クリスマスが終わって二日目の朝、ぼくは時候のあいさつを兼ねて、友人のシャーロック・ホームズのもとを訪ねた。
ホームズは紫のガウンをはおって長椅子に横たわり、右手の近くにパイプラックを据えて、くしゃくしゃになった新聞の朝刊を手元に置いていた。
「シャーロック・ホームズ」シリーズは、ワトスン博士を語り手として、実質的な主人公であるホームズの活躍を描いています。「作者≠語り手≠主人公」です。
同時的と回想的
ほとんどの小説では、語り手は作中にいる特定の人物(多くは主人公)に密着して語っています。
この語り手を、口承文芸、たとえば落語における落語家のようなものだとすれば、落語家と与太郎は別人ということになりますが、語り手は主人公に窓依した感じでぴったり同化しています。
電話ボックスのガラス越しに、渋谷の街がかすんでいた。水気をふくんで重くなった春の空気のせいだろうか。道玄坂を駅へおりる金曜夕がたの人波が、旧い映画のようにぼんやりと煙っていた。
この小説の主人公はヒロトといいます。
語り手はヒロトの目(知覚)を借りて語っており、《渋谷の街がかすんでいた。》と感じたのはヒロトですが、語っているのは語り手です。ヒロトの心を代弁していると言えばいいでしょうか。
一見するとヒロト自身が語っているかのようですが、語っているのは背後霊のようにヒロトに密着している誰かです。
誰かが、ヒロトの「今」をリアルタイムに追っている感じです。
この語り方を「同時的」と呼ぶことにします。この場合、語り手の存在がはっきりしないため、主人公を通さずに、《このときは……であるとは知らなかった。》と書くと違和感が出たりします。
昔々、といってもせいぜい二十年ぐらい前のことなのだけれど、僕はある学生寮に住んでいた。
『ノルウェイの森』第二章にある文章です。第一章で三十八歳だった「僕」は、ここでは十八歳になっています。
語うているのは「三十八歳の僕」です。
「十八歳の僕」が語っているのであれば、《せいぜい二十年ぐらい前のこと》とは言いません。「三十八歳の僕」が「十八歳の僕」を「回想的」に語っています。
この場合、語り手は「十八歳のときの僕に関しては全知」という存在ですから、《このときは……であるとは知らなかった。》と書いても大丈夫です。
次は小説の視点について解説!
特集「仕組みがわかれば書ける! 小説の取扱説明書」
公開全文はこちらから!
※本記事は「公募ガイド2011年10月号」の記事を再掲載したものです。
