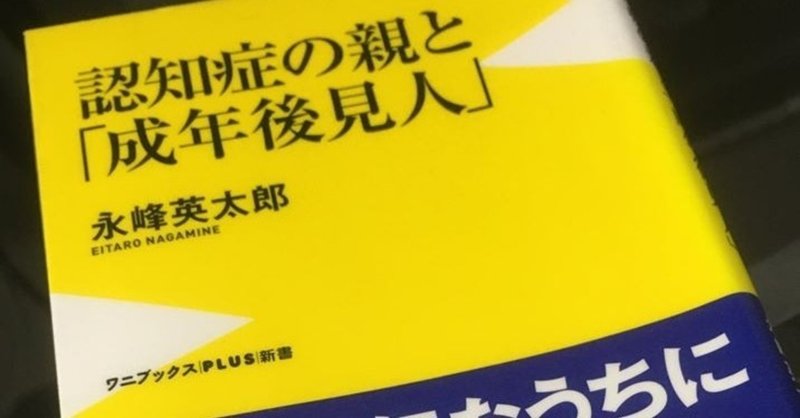
認知症の親と「成年後見人」 #塚本本棚
親である自分が狂ったときの対処を考えておくのも、子への愛情。いろいろ叩かれている成年後見人制度の赤裸々な体験記であり解説本です。
今日は「認知症の親と「成年後見人」( https://amzn.to/2UdZuCk )」永峰 英太郎 (著) #塚本本棚
子供ができる→かわいい→何としても子の笑顔を維持や!→親の経済状況は割と子供を直撃するで!→ライフプラン大丈夫か?→ライフプラン立てても執行者がボケたらだめなんちゃう?→というわけで本書です
めちゃくちゃ気が早いですが、今年42歳なので今のうちから記憶に入れておくのもいいかなと思いました。
【本を読んで考えた】
・自分が認知症になった時、子供が僕の口座情報を知らなければ医療費などが子供の手出しになるし、介護や相続などの手続きも僕が認知症だとできなくなるので、子供には言伝(委任状など)をしておく必要がある
・しかし!いろんな家族の形があるので、家族関係がいびつであれば、家族がそれをやってくれるかわからない、だから成年後見人という制度がある
・親が認知症になり、財産を不当に着服する親族がいるなどあったために出来た「判断能力が衰えた人を支援する制度」との事
・後見人になると「日常生活に関する行為を除く」すべての法律行為を代行できてしまう
・最終的に任命するのは家裁
・子供が後見人になっても、ほとんどの場合において後見監督人がつく。その監督人報酬が約年24万@死ぬまで続くか、後見制度支援信託を利用する(手数料20万ほど)。ちなみに後見人申請代行の手数料は10万円ほど。
・僕のために使う事にのみ、お金が引き出せる。たとえ子供が僕のためと思った行為でも、僕の口座からは引き出せない
・暦年贈与は計画的に
・紙面で残っていないものは”言ってない”と同じ。相続税対策などできるはずもない
・不正を防ぐことが絶対条件となっており、まだまだ融通の利かない未熟な制度となっている
・本来なら遺言なり証書なりで、認知症になる前にしっかりと子供へ指示出しをしておくことが大事だと感じる。後見人制度はそれらをほったらかしにしたときにおこる後追いの”最終処置”なイメージ
・たとえ任意後見人を選定していても、上記監督人が付く
・遺言による相続は、法定相続に優先する
・任意後見人よりは家族信託の方がましの声も
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
