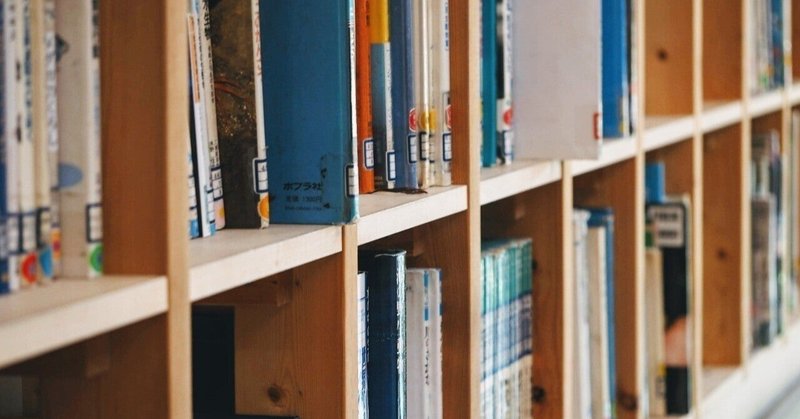
本屋大賞のまわりをうろつく
もう随分、ハートウォーミングは妻が読んでくれているのをあとからあらすじだけフィードバックしてもらって読んだ気になっています。『かがみの孤城』辻村深月や『52ヘルツのクジラたち』町田そのこはそんな感じで概要は理解しました。
本屋大賞、「蜜蜂と遠雷」(恩田陸)とか「羊と鋼の森」(宮下奈都)あたりで、どちらの作家も嫌いじゃないけど、イヤに少女漫画くさいのが受賞しちゃったなあと思っていたが、「そして、バトンは渡された」で、もうこの賞は本を買うアテにはしない決意ができた。あ、「かがみの孤城」は良かったです。
— morningstar (@morningstar0212) November 27, 2021
立て続けに有名ツイッタラーが本屋大賞に懐疑的な視点を向けてくれて、なんとなく嬉しかった、という話です。
本屋大賞、賞が出来たばかりの頃はしがらみだらけの既存の賞とは違う、本当に良いものを発掘して世に届けようという気概が感じ取れたけど、賞自体が権威化した今となっては出版業界のしがらみを煮詰めたような出来レースになってて存在価値を失った感がある。ニッチからマスへの展開は難しいですな。
— 窓際三等兵 (@nekogal21) November 28, 2021
羊と鋼の森/宮下奈都
これは割と高評価。本屋大賞受賞作で旬俳優投入の映画化という時点で食わず嫌いしない方が良い。
「ふたごJK姉妹のピアノに感動して青年は調律に目覚めていく」という筋ではない。「和音と由仁という協奏のモチーフを込められたキャラに引っ張られてピアニストと調律師の二人三脚に目覚める」という話でもない。
繊細な自然描写、比喩、擬音を駆使して、音楽で世界を掴み、さらに言葉によって音楽を掴むという二段構えを、主人公と調律師の3人の先輩たちが誰ひとりとして諦めずに語らう、人生の成り行きを語りながら音との向き合い方を、先輩たちもリアルタイムで吟味している。
質問し、言語化し、ときに背中で語るエピソードがフラットに塗り重ねられる。それこそが和音となっている。そうした交感と合わせて、日日刻苦する透明な自我、北海道の山奥深く、森に分け入りながら世界にゆるされている、世界と調和している感覚を生得した環境という主人公の造形を、透明無垢に描き出すことによって、文化資本の貧困に対するアンチテーゼをもう一つの軸にしている。
だから成長物語ではあるが、劇的な成長が見せ場なのではない。キャンバスの無垢に、丹念に色を重ねるプロセスに着目した作品。音楽の話がなんで絵の比喩やねんと思うが、それが一番私の理解に近いです。
そして、バトンは渡された/瀬尾まいこ
映画興行も一段落したので、改めてまとめておきます。主としてこれを書きたかった。
半日、苦痛とともに読んだ。現在幸せで暇な女子が作り話の他人の人生に出歯亀して悦に入るくらいの読み方ならちょうど良いだろうが、「本屋大賞」の冠を被せてさも社会のどのレイヤーにもウケるかのようにマーケティングするのは詐欺である。
「どんな逆境でも愛情があれば子どもはまっすぐ育つのだ」みたいな、現実がツラい人たちにとって、救いをもたらす余地がある・・・のかね??
アマゾンレビュー見たらだいたい悪評価で一貫しているので安心したが、特に2つだけ指摘すると、まずどう考えても優子の人格形成過程に強い影響を持つのは森宮よりも梨花であり、実父からの手紙を隠匿するなど梨花の内面の歪みの片鱗は見えているのに、なぜかそれを後景にして、終章で穏やかに振り返るだけに留める。ここもっとコンフリクト書けるでしょ。
結局梨花の奔放さを「多数のステップファミリーを渡り歩く」という設定の為の都合の良い理由付けに留めていて、そこから形成されるダイアログやコンフリクトから逃げているだけである。代わりに森宮との愚にも付かない食事のやりとりを繰り返す。ケーキ食べるしか能がないのか??もっと起伏を。
つまり「コンフリクト→解決のプロセスによって獲得された幸福」というストーリーを読みたいのに、「最初からみんないい人。だからステップファミリーでも幸せは先天的に獲得できる」みたいな荒唐無稽なストーリーがダラダラと続けられて怒りを覚えながら読み進めることになるということです。
もう一つが「バトンは渡される」の着想で、「結婚することで新しい家庭を築いて、夫となる男にバトンを渡す」というラストシーンは目に見えている訳で、そこに至る語り口を感動に向けていかに説得的に書くかという観点でも、前述のように「渡す側」の森宮のストラグルの痕跡が全く見えないのと、「渡される側」の夫にも全く共感できない。
これは「奔放な性格」が悪いのではなく、高校時代から現在に至るまでの積み重ねが不足していることと、「バトンを渡すことを認めるプロセス」でようやくコンフリクトめいたストーリーを仕立てているのだが、森宮との心の底からの交感を避けて、プレゼント作戦でなんとかしようとするいい加減さが見えていることが原因。だから「ふたりの未来」とか言われても「???」となる。
まとめると設定倒れ、共感ゼロ、「バトン」着想は中途半端という感じでした。
蜜蜂と遠雷/恩田陸
この作品はピアノがテーマなので音を聴いた方が良いかと思い、原作を読まず映画だけ観た。
何もかもが中途半端。ピアノシーンに一定の尺がいるし、長大な原作を纏めようと思うと仕方ないのか。世界観の導入とかはすっきり工夫されていたのに、それが継続せず。
各コンテスターのエピの消化不良感がひどい。せめて松岡茉優のエピくらいはもっと掘り下げるべきでは…あなたが世界を鳴らすのよとか言われてもなんでそれが再生のワードに成るのか意味不明だし、天才同士で音で会話してるのか知らんが、独白とかでいいからもうちょいテキスト情報をくれ。
ほんで松岡茉優の泣き笑い演技は松岡茉優でしかない、ワンパターンやなこの女優は。キャラもブレブレや。無表情の間が長いし、天真爛漫なのか神経質なのか姉御肌なのか分からん。ご都合で動かしすぎ。人は関係性によってキャラを変容させるってことか?
【おまけ】みかづき/森絵都
ハートウォーミング枠で、私の感想と妻の感想を並べておきます。
教育業界に生きた家族三世代の大河小説。涙あり楽しく読めた。特に中盤、次から次へ文部省の方針転換に翻弄されるあたりは「またお前かw」的な笑い声が出た。学制、国民学校、民主教育、逆コース、中教審答申、ゆとり…と、表(太陽)の教育史と並行して展開した裏(月)の塾業界。
家族史としてのエモみは他のレビューに譲るとして、物語の構造へのコメントをすると、登場人物紹介を見てまず、この家族は「様々な方法で」教育に関わる/関わらないことを体現する者たちで構成されるのだな、と察する。特に長女蕗子の「母とは別の道」というのがそれ。
しかし物語上、蕗子の視点が徹底的に無視されているのが気になった。一人称視点が吾郎→千明→一郎と移るとき、蕗子の世代が捨象されている。それ自体はテクニカルな問題なので、二人称、三人称で書けばいいのだが「公教育」を体現し、最も分かりやすいはずの蕗子がどの視点でも後景に退いている。
まず、吾郎は千明よりもむしろ蕗子の「瞳の法則」にこそ自分の運命を変えた原動力を感じている(し、後年に助平吾郎の対象が蕗子になっても別に驚かないと思った)のだが、吾郎の「追放」に蕗子が「殉じた」ことの精神的繋がりは語られず、吾郎は蕗子の「内心が分からない」ままに去る。
次に、千明は秋田に蕗子を訪ね、公教育を離れて私学教育に引き抜こうとする。両者の理念を対照させる絶好のシーンだが、千明の理念が「文部省の理念」とパラレルである皮肉を描きこそすれ、蕗子の側から「落ちこぼれ」論を覗く明快な公教育への期待は提示されず、再会のわだかまった空気の消化不良。
最後に、一郎は学習支援という場を構想するが、そこで一郎を鼓舞するのは、祖母であり亡き父である。かつて「落ちこぼれ」という同じ眼差しを持ったはずの蕗子は、改正教育基本法の理念を唱え、貧困問題を経験知ではなく数字で語る言葉少なな母親に留まっている。聡明な瞳はどこに行ったのだろう。
また「文部省の官僚と恋に落ちる」母娘のアナロジーは、劇的な対決ではなく手紙という決着で済ませ、結果として吾郎と蕗子の相互理解を阻害している。実父に関わる事柄を避けるのはリアリティはあるのかもしれないが、吾郎の人生に対する決着が曖昧になり、ラストのパーティも素直に祝えないのでは。
以上のように、本来であれば「教育」と「家族」という両方のテーマにおいて核となり結節点にいるはずの蕗子に著者が向き合っていないことが、全ての違和感の元凶になっていると感じた。
逆にいうと、蕗子にまつわる「落ちこぼれ」や「ステップファミリー」といったテーマを読みたかったということ。それは、居宅併設型教室で夢を語った60年代や、ベビーブームに乗って過渡競争に陥った70〜80年代は歴史的興味として楽しく読めるものの、現代に通底する問題に想いを馳せながら読むには、やはりそうした観点が欲しいと思うからである。
だから一郎のエスノグラフィは良かった。蕗子のそれが欲しかった。
あとは蛇足だが、大河小説としての人間の繋がりを家族のみに置いているのも気になった。勝見先生は大手塾に去り、上田先生は事故で死に、突然現れた国分寺が塾を差配し、藤浦社長がスポンサーをする。リアリティはあるのだが、周辺キャラが物語の奴隷すぎて、感情移入できる魅力がほとんど無い。勝見先生と藤浦社長は統合できないの?上田先生と国分寺さんは統合できないの?井上阿里は、例えば蕗子や蘭の同級生の娘、みたいな運命的繋がりを作れないの?一郎の章が余りにも過去の人間関係と切断されていて、全く別の短編を読んでいるように感じたのは私だけだろうか。
色々言ったが、御多分に漏れず私も学生時代は塾業界に関わって(「補習塾」と類型化される場所だったようだが)入口は僅かに知る世界として楽しめたように、この小説が塾業界をタテヨコに深く描いているのは間違いないので、読者の裾野は広く、誰でも楽しめる小説だと思います。
<以下は妻の感想>
小説を書く際、舞台設定を詳述するための下調査が行き過ぎると、調べたことを詰め込む為に登場人物を都合よく動かす書き方になってしまうことがある。しかしこの作品は塾業界の今昔を緻密に調べていることを充分読者に伝えながら、それでいて家族の物語を中心に据えるという軸を絶妙なバランスで保っている。
それでいてやはり「夫は浮気した、娘は反抗的だ、でもやっぱり家族は家族だよね」という感動はするけれど薄い印象になりがちなハートウォーミングなストーリーに、塾業界の光景というスパイスを添えることで重厚感が加えられている。結局はそこのバランスは難しいよねということではあるけれど。
だから『革命前夜』須賀しのぶなんかに対しても思ったけれど、「本当に作者はこの時代を生きていたのか!?」と読者に驚きを与えながら、「私はこれだけ調べた、ドヤ。」ともならない絶妙の踏み込みの間合い。それを成立させている作品ではあると評価できると思う。
満月の夜にみかづきを読み終わった。確かに最終章要った?とは思うけど、人と人とを結びつけるはずの教育が、その解釈の多様性ゆえに家族をバラバラにする逆説が前半で描かれているのなら、最終章で提示されるのはやはり、繋ぎ直しが必要だし、若い力によってそれが可能だという希望だったのかな。
あんたのいう千明と蕗子のコンフリクト不足ってのもわかるけど、母と娘の関係はそんなに単純じゃないで。千明という月と太陽を同居させる母親に焼かれた3人の娘たちが、それぞれに対抗と逃避の入り混じった選択を行動で示すのが見所であって、そこに論理的な緻密さは別に必要ないねん。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
