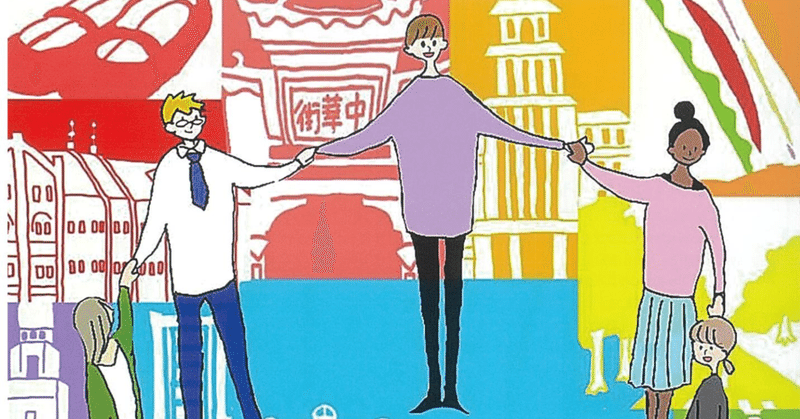
第31回学生文化奨励賞 英語英文学科学生 入選!
神奈川大学外国語学部英語英文学科です。英語英文学科、鈴木宏枝ゼミナール(4年)の菊池暖さんの作品「未草」が第31回学生文化奨励賞、小説・エッセイ部門で入選し、『PLUSi』Vol. 20(2024年3月15日)(pp.103-109)に掲載されました。菊池さんは1年生の時から毎年応募していて、2年生の時は「遮光」が同じく小説・エッセイ部門で佳作として『PLUSi』Vol. 19(2023年3月15日)(pp.154-160)に掲載されました。
菊池さん、おめでとうございます!
菊池さんの「未草」、ぜひ読んでみて下さい。また、最後には菊池さんからのコメントも載せてありますので、それもあわせて読んでみて下さい!
『未草』
菊池暖
かわいそうなあなたを助けたかった。ここで見て見ぬふりをすれば、私が助けなければ、あなたが消えてしまうと思ったから。あなたには幸せになってほしい。どうか、真綿に包まれて、その脆い身体を外気に晒さずに日だまりで眠っていてほしい。
哀れなあなたに二本しかない手の片方を差し伸べる。私は、この気持ちが一体どこからわき上がってくるのか分からなかった。
講義を終えた人の流れに乗って大学の外に出ると、太陽は雲によってほとんど隠されていた。夏のくせに微妙な天気が続いている。でもそのおかげで、適度に涼しく過ごしやすい。電気代は節約できてラッキーだし、しかも公園で読書をするという有意義な日課ができた。家にまっすぐ帰ってもやることがない。いや、やらなくてはいけないことはたくさんあるがどうにも気乗りしなかった。何よりも帰っても家には私一人しかいない。何だか物寂しいのだ。
大学からそう遠くないところにその公園はある。入口に近づくと子ども達の楽しそうな声が聞こえる。すごく大きな公園と比べたら遊具も比較的充実しているし、小学校の近くにあるためそこそこ子どもが集まる。
早速今日も読書をしようといつも座るベンチを見ると、そこには見慣れぬ先客がいた。中学生ぐらいの子だろうか。ぼうっとひとりで座っている。ほかにも場所があるのにいきなり隣に座るのは何だか申し訳ない。そこは入口に一番近いお気に入りの席なのにな、と思いながら私はそれの反対側の木陰にあるベンチに座ることにした。
今日は最近気になっていた小説を大学の図書館で借りた。やっと気になっていた本が読めると、その楽しみだけで今日一日を生きたと言っても過言ではない。この本は今日一日の私の道標となったのだ。カバンからそれを取り出し表紙を眺めて、その流れで反対側にいるベンチの先客をもう一度見る。その子は先程と全く変わらない様子で、肩より少し長い黒髪を揺らしてただ、ぼうっとどこか遠くの方を見つめている。遊び疲れてしまったのだろうかと思うと少し微笑ましい。
小説の紙が、薄らいだ赤を含む。それから目線を外すと、親と手を繋ぐ子の影が揺れていた。また明日ねという言葉が熱気をはらんだ空気のなかで、笑い声と共にまっすぐ飛んでいる。かちゃかちゃと揺れる重さのない水筒と遊び道具がたくさん入っているであろうリュックは、彼らの今日の充実具合を表しているように思う。
可愛らしい喧嘩はあっという間に消えてしまった。しかし、例の先客はまだベンチに座っている。色とりどりの道具の前、爪先で灰色の砂をいじっている。
公園には私と彼女と、ゆっくりと杖をつき歩く一組の老夫婦しかいない。そこまで幼くはないしさすがに迷子ではなさそうだ。……友達と喧嘩でもしたのだろうか。
ひとり考えを巡らせる中で、「いじめ」という単語が一瞬だけ脳裏に浮かび鼓動が早まる。思い返してみる。ここについてから、いくつか集団を見たが、彼女が誰かに話しかけられているという様子は一切なかった。
そんな風に勝手に彼女の事情を想像して、戸惑って、気付かぬうちにしおりを挟まぬまま小説を閉じてしまった。声をかけてみた方がいいだろうかと思ったが、不審者だと思われるかもしれない。何より私は彼女の背景を全く知らない。おせっかいもいいところじゃないか。
でもそろそろ帰ろうとは思っていた頃合いだ。入口の方に歩いていって、あまりにも様子がおかしかったらそれとなく声をかけることにしよう。そう決め、重たい腰を上げ彼女めがけて数歩進んだときだ。ぱちりと、彼女と目があったような気がした。冷たい目だと、思った。そして私が近づききる前に、ベンチにひとり座るその子はそそくさと公園を出ていってしまった。
一人残された公園、頭上でカラスが鳴いている。ベンチの周りには、その子がずっと描いていたであろう絵が広がっており、ここにずっといたのだということが表れていた。彼女の事情はよく分からないが、あの子が何か問題を抱えているとするならば、それがどうか解決してほしいと思った。
ここ最近でも一二を争うような雨の強い日であった。夜には止むと聞いたが、どうにもその気配はない。今日は公園で本を読めないなと溜め息をつきながら、傘にあたる雨粒の音を聞いていた。靴はずいぶん水を含んでしまって、肩にのしかかる荷物がさらに重たく感じる。少し苛立ちを覚えながらいつもの公園の横を通ろうとすると、こんな天気なのにベンチに人がいるのが見えたような気がした。見間違いだろうと思ったが、もう一度確認するまでは何だかもやもやしてしょうがない。私は踵を返してそのベンチをもう一度見に行った。
そこには昨日見かけた子が静かにひとり、座っていた。ベンチには雨を防ぐものなどないので、その子は雨に打たれっぱなしだ。言葉では形容しがたい衝動に襲われた。
一体何をしているんだ。不審者だとか何だとか考えるより先に私は動き出していた。そしてずぶ濡れのその子に私は傘を差し出していた。風邪をひいてしまうと思ったので「これ、使って!」とカバンを引っ搔き回して急いでタオルを渡した。目の前のその子はあまりの突然さに驚いているようだ。そうして数秒してはっと我に帰ったかのようにひゅうと小さく息をした。細い腕が伸びて差し出したタオルを弱々しく受け取る。「いきなりごめんね。風邪、ひいちゃうと思って」と言うと、黙ったままゆっくり肌の水滴を拭き始めた。
「昨日も、ここにいたよね」
「……」
静かに頷く。
「……ねえ、名前はなんていうの?」
沈黙が生まれる。さすがに踏み込みすぎただろうか。不審者だと思われたかもしれない。発言を撤回するべきだろうか。でも変に撤回したら逆に怪しく思われる気もする。
「……世良、です」
とりあえず謝ろうとすると、呼吸音が微かに耳を掠めて、凛とした声が傘の中 に渦巻いた。その名は嘘かもしれなかったがどうでもよかった。ただ、かわいそうなこの子が、逃げずに私に口を聞いてくれたのが嬉しかった。
「そっか、ありがとう。私は真澄って言うの」
また沈黙が生まれ、ぶつぶつという雨粒の音だけが傘の中のあなたに降り注ぐ。
「傘とタオル、使っていいよ。返さなくて大丈夫だから。風邪ひかないようにね」
濡れる前髪を拭いながら視線を落とす。細い腿に置く手から覗く青紫と、薄汚れた洋服。彼女は人並みの扱いをされていないのではないか、という断片的な考えが頭をよぎった。
それから私はいつも通り公園に通った。あの子も変わらない様子で公園にいた。最初の数日はお互い気まずさがあったのだろう、軽く会釈をするだけで貸したものを律儀に返されたこと以外は何も起こらなかった。決まって公園の両端にあるベンチにそれぞれ座った。やはり彼女の周りには誰もいなかった。特に何かするわけでもなかったが、なんだか彼女が心配だった。
一週間が経った頃、彼女は自ら私の隣に座るようになった。どんな心境の変化があったのかは分からないが、拒む理由もないためそれを受け入れ、他愛もない会話をした。出会った時よりずいぶん喋るようになった姿に、安堵を覚える。私は彼女を「世良」と呼び、彼女は私を「真澄さん」と呼んだ。
聞くところによると、彼女は中学生ではなく高校生らしい。瘦せ細り、あまり大きくない身体は彼女を幼く見せている。影がかった瞳は、きっと長いまつ毛のせいじゃない。
家庭か、それとも別のものか。何が彼女をそうさせているのか、聞けなかった。それを口にした瞬間なぜか関係が終わってしまうような気がしていた。特に思い入れのある関係性ではないのは確かだが、それでもわざわざと壊すほどの、彼女から取り上げるほどのものでもないと思った。
彼女がこのような状態に陥っているのを誰か知っているのだろうか。周囲の大人は?このことを知っているのは私だけなのだろうか。公園の中を走り回る幼い子ども達を親が優しげに見つめる。もし、ここで私が世良から目を離したらどうなるのだろう。
きっと、彼女はいなくなってしまう。だって、服から覗く身体は細くてこんなにも弱々しい。
緩やかに続いていた会話は、少しすると停滞を見せた。そのため、あの雨の日のことを再度謝ると、「逃げようと思ったけど、逃げられなかった。真澄さんの目がすごく真剣で、動けなかったんです」と控えめに世良さんは微笑んだ。そんなのを見て、ごく普通に育ってきた私は何とも言えぬ感情に襲われた。
私は世良に色々な経験をさせてやりたいと思った。ただ漠然と、この子は幸せにならなくてはいけないと思った。
大学が終わると一番に講堂を出て公園に向かう。
ある日、アイスを買っていくと目を輝かせながらおぼつかない手でそれを受け取り頬張った。ある日、宿題だと握りしめていたプリントの解説をすると、たいして頭の良くない私に天才だ天才だと言った。そりゃあ大学生だから、と調子に乗って言うと「じゃあ私も早く大学生になりたいです」と言う。
世良は出会った頃よりも随分と笑うようになり、元気に走り回るようにもなった。くたびれた白いシャツは薄汚れていたけれど、青空の下、あなたの皮膚を透かしていてすごく色鮮やかに見える。最近は天が良い。夏のきらめきを一心に背負って、懸命にそれを飲み込もうとする彼女はまだ幼い子どものようで可愛らしい。
ある日、私は服を買い与えた。世良は遠慮して何度もそれを返してきたが、なけなしのバイトの給料で購入したその服を私はどうしても世良に受け取ってほしかったため、何度も攻防を繰り返した。そして最後に彼女の方が折れた。申し訳なさが勝ったのか、世良は嬉しそうな顔はあまりせず何だか苦い顔をしていた。
「本当に、何から何までごめんなさい」
「そんな。いいんだよ。ただのプレゼントだから」
「……私は、真澄さんに、何もあげられない」
「本当に気にしないで。ね?ほら、いつも話、聞いてもらってるしさ」
「……これ、ありがとうございます」
彼女から私に向けられる言葉の一つ一つが嬉しいのではない。彼女が私を有害だと見なさず、少しずつ心を柔らかくしていくその過程が嬉しかった。
この日からだろうか、世良に「もう、私にお金、使わなくていいですから」と言われることが増えた。それを遠慮であると知っていたため、私はその言葉を無視した。
ある日、もう日も暮れてきた頃。私がいつも通り大学やバイトの愚痴をこぼしていると、世良が自分のことをぽつりと話し始めた。それは初めてのことであったため私は注意深くそれに耳を傾けた。
彼女は小さい口で、親に酷い扱いを受けているのだと、言った。学校では誰に何を言われるわけでもなく、ひっそりとひとり生きているらしい。そんな世良のことを誰も別に気にかけていないのだという。
出会った時のような冷たい瞳。少し乱れた呼吸と肌をさする音。一気に弱々しくなる彼女。夏の夜風よりも、その背を優しく、優しくさすった。
ある日、私は家族の話題をわざと出した。
世良がこの話題を嫌がることも、話したくないことも知っていた。けれど世良を知りたいという好奇心が勝った。勝ってしまった。世良は私がその話題を出したことに憤慨することなく、この前よりも少し詳しく家族の話をしてくれた。
「なんで、分からないんだろう。世良はなにも悪くないのに。その痛みが伝わればいいのに」
私はその話の途中、心底腹が立ったのでそう言った。
「伝わるはずがありませんよ。だって、私の痛みは私だけのものですから」
彼女は静かに腕を撫でていた。そして、「やっぱりやめましょう。こんな話」と笑った。
「世良。もっと私を頼っていいんだよ。私は世良の味方だよ」
思い詰めていそうなその表情に耐えられなくて、私は世良にそう呼びかける。彼女は何も言わず、爪先で砂に円を描いていた。そしていきなり立ち上がって伸びをした。
「私、あなたの子どもになりたかった」
切れかけの電灯。消えかけの昼間の足跡。背中を向けたまま、世良はそんなことを呟く。
「真澄さんって、神様みたいですね」
なぜ、あなたがこんなにも辛い目に遭わなくてはいけないのか。家族の話題を口にするときの彼女はどんな時よりも痛々しい。でもこの瞬間、それを引きずり出したのは私だ。
触られたくないところを、触る。これを拒まれないのは友好の印、ではないけれど。でもなぜか、そうやって真っ黒に沈んでしまうあなたに、心を掴まれたような感覚を覚えている私がいる。目を奪われている。
私がいるからこの子はこうやって消えないでここにいるって、思っていいのかな。遊具の影に私たちの影は消されている。
今日最後の講義が終わった。もう夕方だ。何回時計とにらみ合いをしただろう。急いで荷物をまとめて大学を出る。何もない日々に、明るく光が降り注いだ感覚がある。
ショーウィンドウに並べられた商品を横目に、路地に入り公園が見えてくる。
しかし、ベンチに世良がいない。
疑問を抱きながら公園の入口まで行くと、ブランコに世良が座っていた。今まで一度も見たことない、制服を身に纏っている。友達、なのか。隣に誰かいる。
世良が、笑っている。隣の子も笑っている。口元に手を当てて、体を揺らして。なんだかそれを直視できなくて私は目線を下に落とす。二つの影が、ゆっくりと揺れている。それに伴いきぃきぃと、軋む音。小学生の笑い声より、二人の笑い声が鮮明に聞こえてくる気がする。世良が笑っている。
どうして、こんなにも自分に価値がないような感覚になるのだろう。
友達のことなんて一言も聞いたことがなかった。自分のことを全て共有するような仲ではないけれど。同年代の方が話しやすいことは当然だと、わかっている、けれど。それに、毎日公園で会おうなんて約束はしていない。世良に声をかけずに私は公園を去った。
帰りの道の電柱がやけに高く見える。
電柱の広告を何気なく眺めていると、夕焼けを背景に鳥が二羽、飛んでいるのが視界に入る。その鳥の片方は前に富んでいる片方の鳥の尾をつつくようにして追いかける。尾をつつかれている鳥は、何とか距離を取ろうとその羽を羽ばたかせ飛んでいる。どちらも止まることはしない。二羽は、色々な方向に飛んだ後、ゆっくりゆっくりその高度を落としていく。羽毛の輪郭を光らせている。きらきら、落ちていく。歩きながらそんなのを観察していると、あの二羽がじゃれ合っているのか、それとも片方の鳥がもう片方の鳥をいじめているのか分からなくなった。
家に帰っても、心はざわめきを逃せないでいた。その感情の出どころもわからないので、どうすることもできなかった。
そして無駄な行為だと分かっていながらも私は公園へと向かった。もしかしたら友達と別れた世良が一人でいるかもしれない、と願望を抱きながら。時計は夜の十時を指している。道中で羽虫の群がる自販機から水を一つ買って、公園のなかへと進む。やはり誰もいない。虫の鳴き声が昼間の喧騒を再現している。私はとりあえずベンチに腰をかけた。地面を見つめる。
そして、適度に冷静になった頭で世良と自分のことについて考えようと思った。この、奇妙な関係についてを。
しかしその思考を進める暇なく、小さく砂利を踏む音がした。音がした方向を見る。
世良だ。世良が来てくれた。
「あ、真澄さん。いたんですね」
こんなに夜遅くに世良と会うのは初めてだ。いや、私が来ていないだけで、彼女は夜もここにきているのかもしれない。名を呼び返そうとしたが、光が当たる彼女の顔を見て私は声が出せなかった。
該当に照らされた彼女の顔は、赤く腫れていて、目は開ききっていなくて。世良は何も言わない私を一瞥して、その状態を見せないようにするためか自身の顔を覆った。
「父に殺されそうになったんです」
「……え?」
あまりにも衝撃的な言葉に声が裏返る。のどが焼けるように痛くて、うまく言葉が出てこない。
「今まで特にやることもなかったんで、家事とかちゃんとやってたんですけど、最近ちょっと疎かになっちゃってたみたいで。虫の居場所が悪かったのでしょうね。父がいきなりキレてその勢いで刺されそうになりました」
彼女は顔を隠すのをやめ、伸びきった襟を掴み、私の前に立ったまま淡々とそう話し続けた。
「私、最近、人とうまく喋れるようになりました。そしたら友達もできて」
夕方の光景を思い出す。
「全部真澄さんのおかげなのかなあって思いました。真澄さんは私にたくさんの物を与えてくれたので。でも変わる私を父は許してくれなかった」
切れた唇の端を指でなぞり、世良は私の目を見た。
「真澄さんはどうして私を気にかけるんですか」
「どうしてって……」
言葉を選ぶのが難しくて私は即答できなかった。自分でも何でこんなに彼女に肩入れしているのか、明確ではんかったし言語化が難しかった。
「真澄さん」
言葉として機能しない私の掠れた返事。
「私たち、もう会うのは止めにしませんか。私、もうこの公園には来ないです」
その言葉は、脳での咀嚼が終わると一瞬で私を苦しくした。いきなり酵素を奪われてしまったような感じさえもした。なんで、急にそんなことを言うのか。なんでなんだ。第一、今までこれで、幸せだったじゃないか。
「な、なんで」
「あなたの優しさのようなものに触れていると、辛くなる。それに甘えてしまう自分が、醜く思えるんです。私は私の面倒も見れないんだって」
「そんなこと考えなくていいんだよ、世良。私は世良に幸せになってほしいんだよ」
「……私は、何もあげられないから苦しいんです! その事実で、私は、すごく惨めになる」
「それに……」と彼女は続ける。
「真澄さん。私に幸せになってほしいってよく言いますけど、本当はそんなこと思ってないんでしょ。かわいそうな私を下に見て、痛みを理解するふりをしていたんでしょう?」
冷静ではない頭ではその言葉の意味を完璧に理解することができなかった。彼女の目は、吸い込まれてしまいそうなほどに暗くて、私をしっかりと捉えている。
その後、世良は何か言っていたが、言語としてちゃんと聞き取ることができなかった。形あるものとして捉えられなかった。ただ、ああ、この子は今私に反抗しているのだなと、ただそれだけが。
「ふふ……あはは。ごめんなさい。こんなの、酷い八つ当たりだ」
彼女は笑う。
「でも、あなたにはきっとわからないと思います。私の痛みは私だけのものだから」
骨張った身体が、全体で息をしている。声は、力が入りすぎて不安定だ。シャツをぐっと握りしめた彼女の腕は震えている。
「さようなら、真澄さん」
世良はそういうとふらふら、歩き始めた。遊具の大きな影から、世良の影が出ていって、彼女は姿を消した。追いかけられなかったのは、私に覚悟が足りなかったからなのだろうか。
今は、確実な喪失感が私の腰を重くしている。
家の鍵を開ける。当然のことながら迎え入れてくれる者はいない。何も気力がわかずソファーの上にそのまま倒れ込む。
一回、二回。呼吸をとりあえずする。暑さで乱れた呼吸を整えると、先ほど打ち切られた思考が、あの一瞬の出来事を含んで、活発に再開する。
「痛みを理解するふりをする」。私は世良を追い詰めてしまっていたのだろうか。可能な限り、与えられるものを与えて、空虚なあなたの心を純粋に満たしたかっただけだったのに。
本当に? 彼女が返せない物を与え、見返りを望み、私の生活の一部に無理やり食い込ませようとしたのではないのか。
いや違う。心配だった。だから、あなたに纏わりつく感情を、飲み込んであげたかっただけ。
豆電球が辺りをぼんやりと照らしている。
世良のことが脳裏から離れない。綺麗で、美しくて、浮世離れをした面持ちをしている世良。笑う世良。悲しそうにする世良。目に光の宿らぬ世良。
今までの行為は誰のための行為だったのか、私は自信を持って答えられない。だって、本当に彼女を思っていたのなら、彼女が家族の話をしてくれた時にでも警察なり何なり行っていただろう?
違う。本当に助けたかった。でも彼女の心境も考慮しなくちゃいけないし、どうすればいいかわからなかった、だけ。
暑い。エアコン、つけっぱなしで出て行ったはずなのに。
支配、慈愛、恋。名前の分からぬ感情。
醜い感情を抱え蓮華座で胡座をかく。ここからは遠くとおくに行き交う人々が見える。あなたがそのなかでひときわ輝いている。泥まみれのあなたはこんなにも美しいのに、なぜみんな見向きもしないのか。あなたを拾い上げたことに、あなたを正すことに何かを見出していたのは間違いない。助けたいという思いはいつしか歪んでいった。「幸せになること」。それをいつしか義務として課して。
私はいつから間違えたのだろう。傘を差し出したあの瞬間からなのか。確か最初は汚れのない祈りからだったのに。静かな水面を揺らした。鍵をこじ開けた。それは幼子が蟻の頭を千切るのと、猫の尾を掴むのと一緒だった。
鼻血を出して、赤く腫れた顔を見せまいと必死に隠そうとする世良が酷く心を刺激するもののように思えた。救いをちらちらと彼女に見せたとき、瞳に一筋薄い光が入るのが可愛らしかった。
彼女が自らの力で歩むべき道を、善意に見せかけた欲で舗装する。私の悦があなたの手を引く。その手はいつの間にか両手になっている。ここには光なんてひとつもありはしない。
世良には頼れる人がいなくてかわいそうだった。世良は普通の人が何気なく受け取っているものを受け取れていなくてかわいそうだった。世良は不当な扱いを受けていてかわいそうだった。あなたに触れて、それらの事実を反芻して、そこから生まれたものを飲み込んで、私自身も合わせてかわいそうになって、そして気持ち良くなる。誰かを救う、という普通は与えられない役目が、それをさらに助長する。そうすると、皮膚をその快感が縁取って私ができる。
「……かみさまみたい、か」
絡まる思考の中でいつの日かの言葉を思い出す。私を神様のようだと、彼女は言った。でも、きっとそれは違う。彼女は私に食物を、知恵を、衣服を与えなかった。でも私に、かたちを与えた。彼女の聡明で、死んでしまいそうなほどに打ちのめされた綺麗でかわいそうな姿が、何もない私をも高潔なものにしてしまうような感覚。
本当に神様のようだったのは。
結局のところ、縁取られ形作られたのは私ではなくて、孤独と欲望そのものであった。
悪い夢を、いや、ほどよく良い夢を見ていたような気がする。呼吸が乱れている。何かから逃げようとするように寝返りを打つ。ゆっくりと目を開けると、オレンジ色の豆電球の光を背景に、世良がこちらを見つめているような気がした。心臓に固いものが食い込むような違和感がある。寝汗に不快感を抱きながら、何とか落ち着こうと深呼吸をする。世良の幻影はそんな私をそっと見下ろすだけで首を絞めたりへし折ったりはしてくれない。
「せら」
か細い声は蒸し暑い夜のなかに静かに消えていった。
『未草』 コメント
最後まで読んでくださった方、ありがとうございます。
人間の感情というものはとても複雑なものだと、日々思います。
「かわいそう」「救いたい」「救われたい」。求めたり、求められたりして、存在意義を見出していく……全てがそうであるとは思いませんがそこには本人も自覚できないような、認めたくないような欲望がどうしても存在しているように思います。その渦巻くものに振り回されたり、傷つけたり、傷つけられたり、はたまた救われたり。
この刺々しい複雑さはきっと、人間ならではのものだろうと強く感じます。かたちを求める人の様は醜かったり暴力的に映ったりすることもありますが、そのようにしてなんとか生きていこうとする姿は「一つの人間の姿」として綺麗なものだなとも思っています。
元記事はこちら!
2028.pdf (kanagawa-u.ac.jp)
『PLUSi』Vol.20(2024年)はこちら!
鈴木教授のゼミナールはこちら!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
