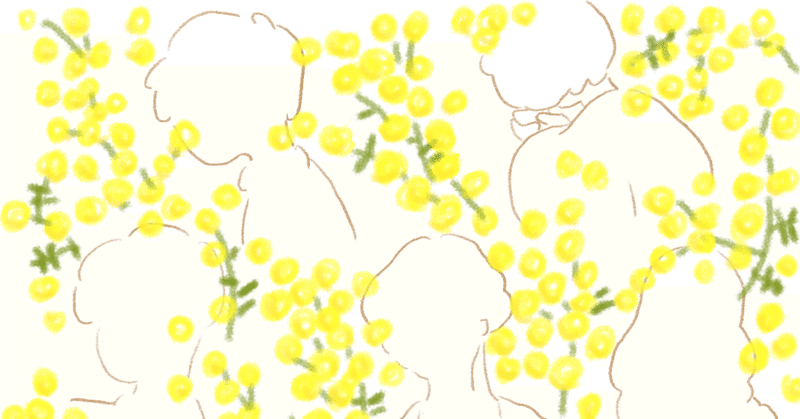
しゃべりばは10代だけではないのです
ポリティカルコンパスについて、昨日はじめて知りました。
ポリティカル・コンパスは、政治思想の傾向(政治的スペクトル)を点数化して二次元座標に表したもの。
興味のある方はやってみてください。
私はごく僅かにリベラル左派でした。ほぼ真ん中に近いのですが。
左か....意外だなぁと思ったり。
そうかもなぁと思ったり。
(たぶん福祉関係の解答が影響してそうな予感もしてる)
(右か左かとかあえて考えたこともなかった)
リベラルはそうかなぁと思ってたけども。
政治の話って、タブーというか。
仕事中もあまりしないにしましょう的な話はあったんですよね。忘れたけども....たぶん学生の頃の実習中に言われたのかな。政治とか宗教とか....あまり話さない方がいいよみたいな。
政治的な話は傷つくよねって話を永井玲衣さんがポッドキャストで話してまして。
じゃあ、どこで話すんだ!みたいなものもあって。
どこで話してますかね。
みなさま。
話さないのか、むしろ.....。どうなんだ。
まあ、小学校のお母さん同士の井戸端会議的なものでは話しませんよね。聞いたことないですもの。そんな切り口で話すお母さんたちは。いや、私も切り出しませんけども。
話さないのはなんでだろうとか思ったり。どのように自分が社会にコミットしていくのかを考えた時に、そこは外せない領域だと、個人的には思ったりはしてるのです。
全然知識がないものだから、もっと知りたいなというのもありまして。
私が一番そういう内容を話しているのは
おそらく食事の時間なのです。
で、相手はわが子たち。
昨日の夕飯どきは、政治と少し離れましたが
ポリコレと
ジェンダーと
男尊女卑について
話しました。
息子が「ポリコレってなに?」と言い始めたのが話題の発端。
ポリコレについて、夫や私や娘からの見解を話してみまして。
下記、ポリコレこと「ポリティカル・コレクトネス」について、おさらいの文章。
特定の言葉や所作に差別的な意味や誤解が含まれないように、政治的に(politically)適切な(correct)用語や政策を推奨する態度のこと。政治的妥当性。「PC」と略される。西洋的な白人男性中心主義とマイノリティの価値観が衝突し、さまざまな社会的問題が露呈したアメリカで前景化した概念だが、1980年代以後に一般化し、今日では世界各国に広まっている。日常的に使われている言葉には、現代の人権感覚や歴史認識を基準にすると不適切なニュアンスを持つものが数多く存在しており、PCはそうした言葉の使用によって人種・民族・ジェンダー・職業・宗教・ハンディキャップなどに対する差別意識を助長することを防ぐ立場として一般に理解されている。大航海時代の名残で長らく「インディアン」と呼ばれていたアメリカの先住民を「ネイティヴ・アメリカン」と表記することや、肌の色による呼称である「ブラック(黒人)」を「アフロ・アメリカン」と改めることなどは、PCに基づく言葉の是正の代表的な事例である。日本における具体例としては、「保母」という名称が、対象を女性のみに限定するような印象を与えてしまう可能性を考慮して男女の別なく用いることのできる「保育士」に変更されたことなどが挙げられる。また、言葉の用法を正すことだけではなく、社会問題への意識を改めるための政治的なアクティヴィズムに従事する人々の態度を広く指し示すこともある。一方で、ポリティカル・コレクトネスの追求が逆差別や度の過ぎた自主規制や、表面的な「言葉狩り」のような事態を引き起こすこともある。とりわけ文学・映画・漫画などにおいては、古い作品に含まれている差別的な用語や表現が無闇に害のないものに置き換えられる場合があり、その際に作品が本来有していた内容や文脈が損なわれることが問題視されている。
夫が「今は『肌色』とか『母子手帳』とかも言わないよね。」という話をする。
娘は「なんでもかんでもポリコレポリコレって、わーっとなる。むしろそういうものから離れたくなる自分もいる」と言っていて、私はおもしろいなと思う。彼女はかなり率直な意見を話していると感じる。
たぶん映画や漫画などに彼女が積極的に関わる中で、上記のポリコレに対する説明文の下部の文章のように、ポリコレに少々食傷気味になっているのかもしれないな、なんて思う。
映画の「リトル・マーメイド」の話も当然ながら出てくる。
私は、なんでこんなに世の中が「ポリコレ」って言ってるのか、背景を調べて色々また考えてみようね〜なんて話をしてみたりだとか。
そもそもフェミニズムのことも、同じような対立が起こっているような印象も受けることとか。
マイノリティ側の主張がなぜとがりやすいのか、とか。
(とがらないと、つきささらないと、目につかないし、届かないのかなぁとか、逆になぜそんな構造になってるんだろうね....みたいな投げかけをしたり)
暴力的な対立構造に陥らないように、お互いが話すことができないかなぁなんてことを話したりしました。
もっとやさしく関わりたいよね。
うーん。
難しいものです。
あとは、特権についても話しました。
娘が「私よりもっともっとつらい人がいる。恵まれない立場の人がいると思うと、自分がつらいって言いづらい」という話から発展しまして。
それは「つらい」って言っていいんだよ。あなたのつらさは誰とも比較できるものではなくて、自分がつらいと感じてるなら、話せる人がいれば、自分が話したければ話せばいいと伝えました。娘は「それができないんだよー」と話し、息子は「僕はやるようにしてる」と話してました。
まあ、そうなんだろうなという思いで母は聞いておりましたが。
そもそもマジョリティ側は困らないからずっと違う世界に気づかない。気づかないから、知らないうちにマイノリティ側を傷つけたりするのかもしれないよと伝えると
娘は「じゃあ、どうしたらいいのかなぁ」と話すので。
そこに対して、逆に自分を過度に責めることもなくて
まず、知ることかなという話をしました。
知った上でお互いに将来に向けてどうしていくのか、未来のことを話し合えればいいのでは、と伝えました。
人が人と思い合って共にあること。
そこに関して、話せばいいのかなと思うのです。
ジェンダーの話は「性自認」と「性的指向」について、簡単に私から説明すると、息子は「知らなかったー」と話してました。
男性が男性を好きになる
女性が女性を好きになるにも
たくさんの種類があって
それぞれ性自認が違ったりするのよ。
体の性と心の性が一致してない人もいるしみたいな.....いわゆる「トランスジェンダー」の話もしてみました。
3人の結論としては。
まず、身近な誰かがそのようなことを抱えているかもしれないことを忘れないこと。
そして身近な誰かや、もしかして将来的には自分自身が、ジェンダーの問題やマイノリティの問題で苦しんだ時に、排他的にならずに、共に一緒に考え続けることができればいいなというところに着地しました。
うん。
身近な人がいいと思います。
願わくばそのような経験を重ねていってほしいなと、親として心より願っているのです。
「真剣10代しゃべり場」みたいな番組が昔あったような気もするのですが
40代でも、10代と日々、あまり真剣ではない時も多いけど習慣的に「しゃべり場」してますという話でした。
サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。
