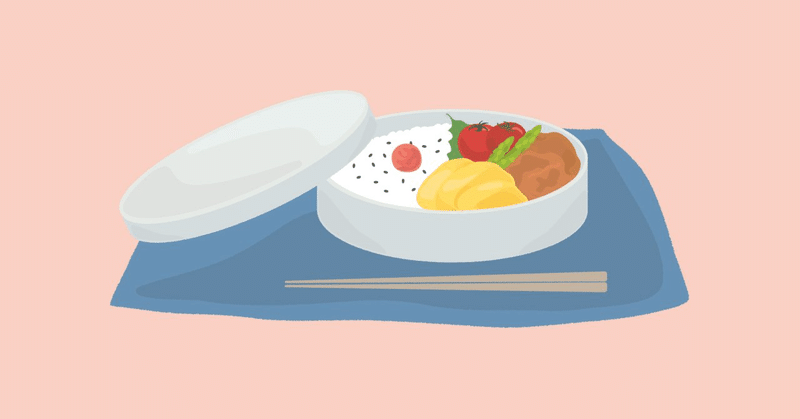
愛なんか、知らない。 第1章 ⑥涙のお弁当
日曜日は、7時前に起きてリビングに降りると、お母さんがいた。
「あら、早いわね」
「おはよう」
食卓にはトーストにプリン、インスタントのコーンスープ、コーヒーが並んでいる。
お母さんは結婚する前から料理が苦手だったって、お父さんが話していた。
結婚したら少しは料理するだろうって思ってたら、全然しないから、「失敗した」って思ってたって、小学生の時にぼやいていた。
だから、私が起きて来ても朝ご飯を作ってくれることなんて、ない。「料理を作ったら負け」ぐらいに思ってるかも。いつも、「自分の好きなことを伸ばすほうが効率的。苦手なことをムリにできるようになるのは、ムダな努力」って言ってるし。
それを聞くたび、「家事は苦手だからって、全部やろうとしないのはどうなんだって感じだけど。仕事だけ頑張って、僕たち家族との生活で頑張るのはムダな努力になるってこと?」と、お父さんは半分呆れた口調で諭す。
それでも、「そう思うなら、あなたがやれば?」とお母さんは考えを変えない。
私は自分でベーコンエッグを焼き、パンをトースターで焼いて、インスタントのコーンスープを作った。うん、今日の目玉焼きの焼き加減はいい感じ。火を通しすぎないように、黄身の上がうっすら白くなったらすぐに火を止めた。
おばあちゃんと暮らしている時に、簡単な料理を教えてくれた。それがどれだけ助かっているか……。
「どこか出かけるの?」
お母さんの斜め前に座ると、スマホを見たまま話しかけてきた。
「うん、バイト」
「バイトって弁当屋の?」
「そう」
お母さんは顔をしかめる。
「なんで、そんなバイトのために朝から出かけるの?」
「えっ、パートのおばさんに、今日だけ変わってほしいって言われて」
「そんなの断りなさいよ。わざわざ朝早くからやるような仕事じゃないでしょ。そんな時間があったら勉強しないと。それとも、弁当屋の正社員になるつもりなの? そんな底辺の人間になったら、今までかけた教育費が全部ムダになるから、やめてよね、そういうの」
朝から人を全否定するようなことを平気で言うお母さん。うん、いつもの朝だね。
お母さんはそんな話をする時も、スマホから目を離そうとしない。
私は反論する気になれなかった。何か言ったら、倍になって返って来るから、黙って聞いてるのが一番なんだ。
「ほどほどにしなさいよ、そんなバイト」
お母さんはこちらをチラリとも見ないで、洗面所に顔を洗いに行ってしまった。
せっかく上手にできた目玉焼きも、全然おいしく感じない。
こんな朝、今まで何百回も過ごしてきた。
大丈夫。何も感じないから。何も、感じないから。
今日は、バイトは早く終わる。
だから、帰ったらミニチュアを作ろう。ミニチュアを作っている間は、嫌なことは全部全部、忘れられる。
ミニチュアを作っている間だけ、私は自由でいられるんだ。
お店から支給されたエプロンをつけて8時に店に入ると、すでに店長さんやパートのおばさんたちが来ていた。
「おはようござ」
「ちょっと、南野さん、先にご飯をセットしてよ! 材料切るのは後でいいから!」
既に店長さんが全開モードで怒っていた。
「店長さん、朝はいつも以上にピリピリしてるから。気にしないでね」
ベテランパートの山本さんがこっそり教えてくれた。
いつも10時からバイトに入ってるから知らなかったけど、開店前は店長さんは怒鳴りっぱなしみたい。朝から元気だなあ。。。
いつもは優しくて冗談をたくさん言っている店長さんの奥さんも、「これをこんなところに置きっぱなしにしないで!」とトゲトゲしている。
「後藤さんは材料を切って。南野さん、教えてあげて」
奥さんに言われて、パートの中では経験が浅い南野さんが、私に教えてくれることになった。
南野さんはまな板の前に立って、キャベツを切っていた。
「今、焼きそば用のキャベツと、メンチカツととんかつの下に敷くキャベツを切ってるところ。千切りはできる?」
「……できません」
「えっ、そうなの? 千切りはこれぐらいの幅で切ってくの」
「イヤだ、南野さん、それじゃ太すぎ。千切りじゃなくて百切りじゃない」
奥さんがすかさず嫌味を言う。
「高校生に間違ったことを教えないでね」
南野さんは瞬間的に眉をしかめた。南野さんとは、時々シフトが一緒になるけど、たぶんあんまり器用じゃなくて、しょっちゅう店長さんから怒られてる。私以上に怒られてる。大人でもこんなに怒られるんだなあって、見ていてかわいそうになってしまうぐらい。
奥さんが素早く、見本の千切りを作ってくれた。
「ここまでできなくてもいいけど、南野さんのをマネしないでね」
うわあ。キッツぅ。南野さんの顔をまともに見れないよ……。
私が千切りをしてみると、「うん、いいんじゃない? 南野さんより上手。南野さんは、もういいから外を手伝って」と奥さんは厳しく言い渡した。南野さんは無言で売り場に出て行く。
これって、イジメ……っぽいよね……。
「まったく、あの人、何教えてもトロいんだから」と、奥さんはブツブツ言ってる。まわりのおばさんたちは見ないフリ、聞こえないフリをしてる。
学校の教室と、あんま変わらないよね。大人の世界でも、こんな感じなんだ。
私は何とかキャベツを切り終えたけど、それだけで時間がかかってしまった。
「まあ、最初は仕方ないから。慣れてきたら、もっと早く切れるようになるでしょ」
奥さんは、私には結構優しいんだよね。大学生の娘さんがいて、時々店を手伝いにくるけど、娘さんにも激甘だし。
「じゃ、次は玉ねぎをお願い。山本さん、教えてあげて」
そんな感じで言われた仕事をこなすうちに、あっという間に開店時間になって、お客さんもすぐに買いに来た。
「ここのお弁当は、できたてがおいしいのよね」と、お弁当を買いだめしていく人もいる。
私の切ったキャベツが使われているメンチカツやとんかつが買われるたびに、「それ、私が切ったんですよ!」と心の中でアピってた。
お昼前に、市原さんが店に来た。
「あら、試合はもう終わり?」
奥さんが尋ねると、「これからお昼を食べるところ。これを葵ちゃんに渡したくて」と私を手招きした。
「これ、朝番に入ってくれたお礼」
それはお弁当だった。青いナプキンでお弁当箱を包んで、黒いお箸箱が結び目に刺さっている。
「うちの息子のお弁当と同じなんだけど。多めに作ったから、よかったらどうぞ。うちの息子は肉食だから、がっつり系なんだけど」
「えっえっ、い、いいんですか!?」
「うん。いっつもここのお弁当じゃ飽きちゃうでしょ?」
小声で囁いて、いたずらっぽい笑みを浮かべる。
私は何度もお礼を言いながら受け取った。
「弁当箱を返すのは、いつでもいいからね」
「ありがとうございます!」
市原さんは手を振って、足早に去って行った。
誰かが作ったお弁当。幼稚園や小学校のイベントでおばあちゃんが作ってくれてから、すっごく久しぶりに食べる気がする。中学は給食だったし、高校に入ってからは自分で冷凍食品を詰めたお弁当を作るか、パンを買って食べるかだし。お弁当。手作りのお弁当。嬉しいなあ。
お昼はいつも社員食堂の隅で食べる。
他の店舗のスタッフさんや社員さんたちも、ここで食べている。
学校だと「ぼっちって思われたらヤダな」って思うけど、ここではお弁当屋のバイトのことなんて誰も気にかけないから、気がラク。
市原さん作、お弁当。
ナプキンを解くと、ロボットの絵が描いてあるお弁当箱が出てきた。箸入れにも同じイラスト。息子さんが子供の頃に使ってたお弁当箱かな。
ワクワクしながら蓋を開ける。
焼肉と卵焼き、ポテトサラダとミニトマトがキレイに詰めてある。焼肉には千切りキャベツが敷いてあって、彩りもバッチリ。ご飯にはふりかけ。
「おいしそう……」
食べる前にスマホで何枚か写真を撮った。こんな素敵なお弁当、ミニチュアを作って永久保存するしかないでしょ!
「いただきます」
心の中の市原さんに手を合わせてから、お箸を手に取る。
まずは焼肉から。お肉がやわらかくて、味もしっかりついている。ゴマをまぶしてあるのが、香ばしくていい感じ。卵焼きは甘め。お弁当の玉子焼きって感じでいいな、好きだな。ポテトサラダは小さく切ったリンゴが入っていて、シャキシャキしてる。
「おいしい……」
いいなあ。なんか、息子さんのために、丁寧に作ってるのが、伝わって来る。
「いいなあ」
声に出してみたとたん、じわっと涙がにじんだ。
いいなあ。いいなあ。
こんなに素敵なお弁当を作ってもらえて、いいなあ。
こんなにお母さんに想ってもらえて、いいなあ。
頬に涙が伝う。大丈夫。誰も私のことなんて、見てないし。
私は涙を拭きながら、箸を口に運んだ。
おいしい。今まで食べたお弁当の中で、きっと、一番おいしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
