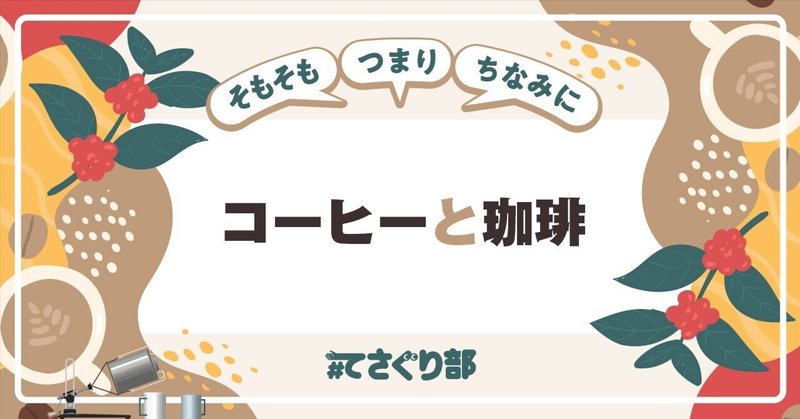
珈琲という言葉はどのように生まれた?
レトロな喫茶店などでよく見かける「珈琲」。コーヒーを漢字で表した言葉ですが、そもそもいつから使われているのでしょうか。また、誰が考えたのでしょうか。コーヒーにまつわる言葉のルーツを紐解いてみます。
そもそも:誕生したのは江戸時代末期
コーヒーが、日本に入ってきたのは江戸時代です。言葉としては、オランダ語の「koffie(カッフィー)」に由来すると言われています。その頃、日本は鎖国政策を実施していましたが、オランダとは特別な貿易関係を維持し、オランダ人居住区であった長崎の出島を通じて西洋の物や文化を取り入れていました。

オランダ語のカッフィーという言葉に対して、当時は「可否」「架非」「加非」「黒炒豆」など、さまざまな当て字が使われていました。とはいえ、もともと緑茶の文化が根付いていた日本では、コーヒー文化そのものが定着しづらかったといいます。
江戸時代末期にそうした状況が変わりました。そう、「珈琲」という言葉の誕生です。
つまり:名づけ親は一人の蘭学者
「珈琲」という漢字を考案したのは、幕末の津山藩医で蘭学者の宇田川榕菴です。榕菴は、西洋の医学や化学の知識を日本語に翻訳し、当時はまだ使われていなかった「酸素」「水素」などの新しい言葉を次々と発案しました。今でいう名コピーライターですね。
では、榕菴はなぜコーヒー(当時はオランダ語でカッフィー)という言葉に、「珈琲」という漢字を当てたのでしょうか。実は、そこには深い理由がありました。
医学や化学だけでなく、西洋の植物学にも精通していた榕菴は、コーヒーの実が赤いことを知っていたのでしょう、赤い果実がたわわに実ったコーヒーの枝を、当時の女性の髪飾りである「かんざし」に見立てました。実際、「珈」という漢字には一文字で女性の髪につける玉飾り、同じく「琲」には玉飾りの紐という意味があります。

もちろん、本物のコーヒーの果実が当時の日本で簡単に手に入ったとは考えられませんし、それを髪飾りにしたわけでもないでしょうが、おそらく西洋の文献か何かで形や色を知った榕菴は、想像を膨らませて女性の髪飾りをイメージしたのです。なんてロマンチックな人なのでしょう。
そうした美しい日本語のおかげもあって、コーヒー=珈琲は少しずつ日本に定着していきました。
ちなみに:コーヒーの語源はアラビア語
ちなみに、コーヒーそのものの語源は何でしょうか。有名なのは、アラビカ種のコーヒーの発祥地であるエチオピア西南部の地方名「Kaffa(カッファ)」に由来するという説です。しかしこれは有力ではありません。なぜならエチオピアではコーヒーのことをブンナと言うからです。もしカッファがコーヒーの語源なら、エチオピアでもコーヒーのことをカッファというはずですよね。
有力なのは「アラビア語起源説」です。アラビア語でコーヒーを意味する「qahwa(カフア)」は古代アラビア語では「ワインや香りのするお酒」を意味していました。イスラム教ではお酒を飲むことがタブーとされているので、興奮作用を持つカフェインを含むコーヒーがお酒の代用品として昔から飲用されていたのです。

その後、コーヒーが世界中に広がっていく過程で、コーヒーの呼び方は様々に変化していきました。トルコ語では「Kahve(カフヴェ)」、イタリア語では「caffè(カッフェ)」、フランス語では「café(カフェ)」、ドイツ語では「Kaffee(カッフェー)」、そして英語ではご存じの通り「coffee(コーヒー)」と呼ばれています。
くるくるカンカンの焙煎缶詰には、ブラジル、マダガスカル、インドネシア、コロンビアなど世界有数のコーヒー産地の豆が3種類ずつセレクトされており、同封されているカードには産地や豆の情報が一目で分かるよう、地図入りで概要が簡潔にまとまっています。

それぞれの地域でコーヒーがどのように呼ばれているか想像しながら味わってみるのも楽しそうですね。
くるくるカンカンの焙煎缶詰についての記事はコチラ

