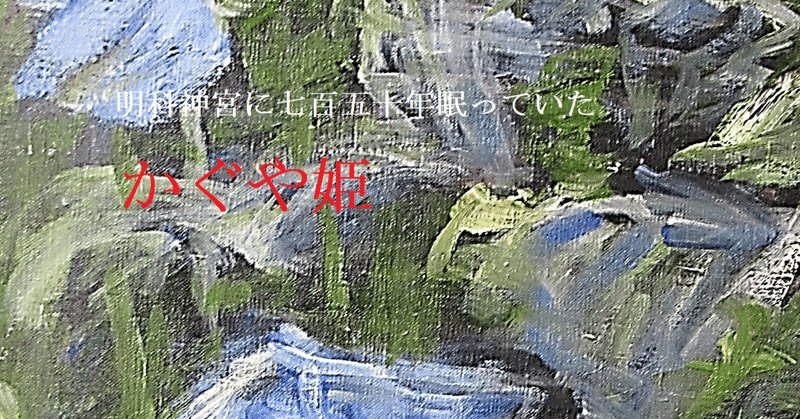
竹取村のかぐや姫 二の章

二の章
五人の皇子たちの求婚
辺鄙な村里に忽然と巨大な御殿がつくられたという噂は、またたくまに日本中にひろがっていって、近在の村や町からもう毎日のように御殿見物する人がやってきた。反り返った屋根に瓦が黒くひかる華麗な御殿、そのなかにかぐやなる姫が住んでいる。その姫はたとえようもなく美しく、ひとたび姫の笑顔にふれると、たちまち病も癒えていくなどというおひれまでついていたものだから、御殿をたずねる人がひっきりなしだった。
その噂はやがて都まで広がっていくと、貴族や武者たちが競うようにこの村にやってくる。彼らがそんな情熱にとらわれたのは、もうこれはただひとつ、姫に求婚するためだった。白く輝く高き峰をだれもが征服してみたいと思うのが人の常。はるか山奥の村に、たとえようもなく気高く美しき人がいるときいては、男たちの心が燃えないわけはないのだ。
たいていの訪問者は土壁にぐるりと取り囲まれたその屋敷のなかに一歩も入れなかったが、しかし都からくる高い位の人々はさすがに門前払いなどできない。爺さんは仕方なく門をあけ、それらの方々を館のなかに招きいれる。本殿の客間に通された貴族たちは、そこで熱烈なる求婚の歌を、さらさらと書き、応対している爺さんに手渡して、姫からの返事の待つのだが、爺さんはいつも、
「いま姫の気分がすぐれず、床についております。まことに申し訳ございませぬが、ご返事はまたの日に」
といって追い返すのだ。それでたいていの者は、脈はないものだとあきらめるが、しかしそれを真に受けて、再度訪れる皇子もある。するとまた爺さんは、
「姫は、あれからいぜんとして気分がすぐれず、床についております。まことに、まことに申し訳ございませぬが、ご返事はまたの日に」
こんな返事になるのは、遠路はるばる都から足を運んできた皇子たちを傷つけまいとする爺さんの優しいこころづかいからだった。これでたいていの皇子たちはきっぱりとあきらめるが、それでもこりずに三度四度と訪ねてくる五人の皇子たちがいた。
なかでも一番声が大きく、態度もまたひどく横柄な大伴御行(おおとものみゆき)という方がいた。この人物は、もう雨が降ろうが槍が降ろうが、まっしぐらに突き進み、欲しいのものはなんでも手に入れてきた。大納言という高い地位もまたこの馬力でつかみとったのだ。
その馬力で今度は姫をせしめんと、この日もまた何十人もの武者たちを引き連れてやってきたのだ。もうすっかり勝手がわかっている館に、ずかずかと上がってくると、客間にどかっと座りこみ、平伏する爺さんに命令するのだ。
「姫の文を今日こそは、受け取りにまいた。さあ、姫の文を出してくれ」
爺さんが、いつものように、のらりくらりと逃げようとすると、
「おい、爺。わしがここにくるのは、今日で何度目なんだ?」
「はあ、たしか、三度目、いや四度めかと」
「ちがう。五度(ごたび)だ。五度だぞ。それなのにいまだ姫のご返歌がないとはどういうことだ。そちはちゃんとわしの歌を姫に渡しているのか。わしの歌を読めば姫が心を動かさぬわけはない。愛の歌なのだ。熱烈なる求婚の歌なのだ。わしの歌はどんな女でさえもころりとまいるのだ。それなのになんの歌もよこさぬとは、そちが握りつぶしたのであろう。いいか、今日は帰えらんぞ。姫の歌をこの手に渡してもらうまでここに座りこむぞ」
その時代、殿方が姫君たちに会うには、まず歌を交換することからはじまるのだ。その歌の交換によって互いの心がかよいあうと、それならばお会いしましょうということになる。そんなわけだから、とにかく大伴大納言(おおとものだいなごん)は姫の歌がほしかったのだ。
この要求にほとほと困り果てた爺さんは、回廊をわたって姫の住む館にかけこみ、どうしたものかとたずねると、かぐや姫もしばらく思案をしている風であったが、やがて途方もないことを爺さんに言いだしたのだ。
「どんなにお断りしても、その方を納得させることはできないのでしょうね。仕方がありません。お爺さん、その方にこういって下さい。唐の国に龍という動物がいますが、そのなかに五色に光る珠を、首に巻いている龍がいるのです。その珠を取ってきて下さるならば、そのときあらためてお話を考えてみましょう。ただし三年後です。三年後にその珠をお持ち下さいとおっしゃって下さい」
爺さんは、それはなかなかの名案だと思った。第一に唐の国だ。その時代、唐の国に渡るとは、命を捨てる覚悟が必要だったのだ。もうそれだけで姫に求婚する情熱もさめていくだろう。しかも三年の月日という条件もつけてある。のぼせあがった恋の熱を冷ましていくには、たっぷりの年月である。とにかく爺さんはこんな横柄で物騒な人物とは、金輪際かかわりたくなかったから、客間にもどり憤然とすわっている大納言に、もうこれっきりにしてくれという意味をたっぷりこめて、姫の伝言を伝えたのだ。
するとなぜか大納言の顔がぱあっとひかって、
「よっしゃ、わかった。その珠を取ってくれば、姫はわしの嫁になるんだな。たしかに姫はそういったのだな。わしの嫁になるとな。よっしや、わかった。明日にでも、わしは唐の国にむけて旅立つぞ」
というと大納言は、うっししし、うっひひひひ、とあやしい笑いをつくって帰っていった。なんだか奇妙なことになったなと爺さんは首をかしげたが、しかしまあそれで、その場はひとまずことなく終った。
阿部のみむらじという右大臣がいた。この皇子はまだ三十そこそこの人物であったが、こんなに若くて右大臣という地位にかけあがったのは、この皇子が途方もない金持ちだったからだ。父親から受け継いだ唐の国との貿易が近年いよいよ盛んになって、唐の国から貿易船がひっきりになしにやってきては、唐の物産を下ろし、帰りの船には日本の物産を唐の国に運んでいく。この二重の取引によって、莫大な富をつくっていったのだ。
この皇子はいつも何十頭もの馬に荷をのせて村に入ってくる。くるたびに荷をつんだ馬の数がふえて、その五度目の訪問のときは、なんと三十頭もの馬をひきつれてきたのだ。そうして通された客間に、その荷を山のように積み上げる。この贈物に爺さんはすっかり困惑して、
「姫は困っておりまする。こられるたびに、山のような贈り物をいただき……」
「まあまあ、そういわずに。とにかく姫には着物が一番だ。どうだろうか。そろそろ私がお贈りした着物をきて、そのお美しいを姿をみせてくれんだろうか。姫にはもう私の思いは十分に伝わっていると思うが、これからのさきざきのことを姫とじっくりと話してみたいのでな。本日はその決意でまいったのだよ」
と右大臣はのたまう。
爺さんはまた姫の館にかけこみ、どうしたものかと姫にたずねると、ちょうどそのとき庭から、チョロチョロと鼠が走ってきた。それをみた姫はこれだと思い、
「では右大臣様にはこういって下さい。唐の国にはきらきらと光る皮をつけた火鼠という獣がいるのです。その火鼠の皮で織った着物をお持ち下さったら、さきざきのことを考えてみましょうと。ただし三年後ですとお伝え下さい」
それもまた名案だと爺さんは、客間にもどって、右大臣にそのこと伝えると、右大臣はちょっと首をひねりながら、
「そんな鼠が、かの国にいるのだろうか」
という疑問の声をあげる。しかし爺さんはすかさず、
「あの国には、なんでもあるようでございますよ。とにかく広い広い国のようですから」
といってみた。爺さんは、これは実際ばかげた話でありますよ、そんな鼠などおりませぬよ、どうかそのことに気づいて、姫への求婚をきっぱりとあきらめて下されという願いをこめてそういったのだ。ところが右大臣の顔は、ぱあっと輝き、
「そうだなあ。あの国にはなんでもある。姫は不思議を行う人だときいておる。きっと唐の国のことも、その不思議な力によってご存じなのだろう。よろしい。その火鼠とやらをとらえて、その皮で姫に着せる着物をつくってこよう。そうすれば姫は、私の妻になるのですね。よろしい、やってみよう。さっそく唐の国にまいる準備をはじめます」
というとぽんと膝をたたいて立ち上がり、あふれるばかりの決意を顔にみなぎらせて館をあとにするのだった。
三人目が車持皇子(くるまもちのおうじ)という人物だった。この皇子もまた贈り物を欠かさずにもってくる。しかもくるたびに、その品物が高価になっていくのだ。高価なものをプレゼントをしたら女の心は傾いてくると錯覚している男はいまの時代にもいるが、その時代にもそういう男はいたのだ。その日もまた金と銀でごてごてとかためた装身具をもってくると、
「これを姫にあげてくれ」
と爺さんに命ずる。差し出された爺さんは、こういう贈物はもう迷惑だという意味をたっぷりとこめて、
「もうどうか、このようなお気遣いをなさらないで下さい。もう贈物はいっさい受けとらないでくれと、くれぐれも姫にいわれておりますので……」
すると皇子はきっとなって、
「なに、断る。それはどういうことだ。このおれの気持ちを断るというのか。この物はおれの気持ちだ。おれがどんなに姫を思っているか、この物におれの気持ちをこめているのだ。それを断るとは何事だ。今日はどんなことがあっても姫に会わねばならん。そう決意してまいったのだ。もう歌などどうでもいい。姫に直接に会って、おれの思いを伝えることにする。ここに姫をよんでくれ」
と車持皇子は刀を手にして、なにかいまにも斬りつけてくるばかりの気配だ。爺さんはすっかり怖くなって、姫の館にかけこみ、その皇子の様子を伝えると、姫は少しもあわてずにこういった。
「それならばこうしましょう。はるか東の海に、ぽっかりと浮かぶ蓬莱という島があります。その島に、金と銀の枝に宝石をつけた木があります。その宝玉の枝をひと枝おってお持ち下さるならば、そのときあらためて皇子様のお話とやらを考えてみましょう。ただし三年後ですとお伝えて下さいますか」
爺さんはなるほど名案だとうなずいてみたものの、はたして刀を抜いて斬りつけてくるばかりに興奮しているその皇子を納得させられるだろうかと客間にもどり、恐る恐る姫の話を伝えてみた。すると案の定、皇子は疑いの失を放ってくる。
「その枝をもってくれば、姫はおれの妻になるというのだな。しかしその三年後とはどういうことだ」
「それはでございますね、三年という月日をおいてでございますね、皇子様のお気持ちを確かめるということではございませぬか」
「おれの気持ち、おれの気持ちは変わらんぞ。おれの心は姫まっしぐらだ。姫を思う心は山のように不動だ。どうしてそんなことをためす必要があるのだ」
「それは姫の側にも、三年という月日が必要だからでございますよ。皇子様の妻となるには、いろいろと準備をせねばなりません。立派な妻となるために、用意せねばならぬことが山ほどあるじゃありませんか」
それを聞くと、こわばっていた皇子の顔も急にほぐれて、
「そうか。そういうことか。よくわかった。それでようくわかった。よし。そうしょう。おれはその蓬莱の島とやらに出向いて金と銀でできた枝を取ってこよう。待っておれと、姫に伝えてくれ」
となにか浮き浮きした様子で、姫の館を後にするのだった。
四人目が石作皇子(いしづくりのおうじ)という人物だった。この皇子は求婚した五人の皇子のなかでもっとも地位の低い人であったが、一番頭の切れる人物だった。頭が切れる人物というのはひどく計算高い人が多いが、しかしこの皇子にはロマンにあふれた高い志をもっていた。
この皇子は、この地方を統冶する役についていたから、竹採り村にもたびたび足をはこんでいた。そのときこの皇子はかぐや姫に会っているのだ。姫は美しいばかりではない。その物腰に気品があり、言葉遣いも優雅で、何よりもあたたかい心をもっている。皇子はたちまち恋に落ちてしまったのだ。この村を幾度も訪れるようになったのは、なんのことはない姫に会うためだったのである。
この日、皇子は大変な決意かためて姫の館にやってきた。このところ都から大納言やら中納言、はたまた大臣までやってきて、姫をめとらんと猛烈な攻勢をしかけている。このままでは姫が奪われてしまう。彼らに奪われる前に、おれがせしめなければならぬと心をかためてやってくると、爺さんにその決意を切り出した。
「造麻呂(つくまろ)殿、なにやら最近、都から右大臣だとか大納言だとかしきりにやってきて、猛烈な求婚攻勢をなされていると聞きますが、もしそれらの方に姫をやってしまうと造麻呂殿は、姫に二度と会うことができませぬぞ。やつらは都につれていき、屋敷のなかにとじこめ、そなたたちとの縁を断ち切ってしまうにきまっております。そんな冷酷なやつらに姫をあたえてはなりません。私に姫を下され。幸いにも、私の任地はこの地、姫と住む新居もこの近在に建てるつもりです。そうしたら造麻呂殿は、いつでも姫とは会えるのです」
そしてさらに、
「最近、私の部下がけしからぬことを上申してまいりました。天侯が不順だったこともあって、今年のわが群の税の収入がひどく凋落しているためでありますが、その部下は造麻呂殿の蔵を探索すべきだといってきたのです。なんでも造麻呂殿の蔵には黄金が積み上げてあり、これに税をかけて納入していただくと、わが群の一年分の収入になるというのです。私は愚かなことを申すなとその部下を叱ったのでありますが、しかし事態の進展によっては、造麻呂殿の蔵を一度探索してみなければならぬかもしれません」
これははっきりいって、爺さんに対する脅迫といったものだった。爺さんはその脅迫に青くなって、どうしたものかと姫に相談すると、
「あの石作皇子様が、そのようなことをおっしゃったのですか」
「そうなのだ。これは卑劣な脅迫というものだ」
「あの皇子様は、もっと高い志を持っている方だと思っていましたけれど」
「いやいや、所詮は我々から税をたっぷり奪いとっていくお役人なんだ」
「そうですか。それではお爺さん、こういたしましょう。天笠の国にお釈迦さまがいつも座って、修行をなさっていた石があります。その石はお釈迦さまがお亡くなりになったとき、悲しみのあまり一夜で真っ白になってしまったのです。その仏の石から小さな鉢をつくって、それを持ち帰ってきて下さったら、そのときはじめてその話を、真剣に考えてみましょうとおっしゃって下さい。もちろん三年後のことですが」
それは名案と、爺さんは客間にもどって皇子にそのことを伝えた。するとするどく切れるこの皇子は、
「三年とは、どういう意味でございますか」
とたずねるので、爺さんはあの車持皇子に伝えたようなことをいうと、
「それでは、三年間は姫はどこにも嫁がぬという意味でございますか」
「はあ、そういうことになりますか」
「三年間、ひたすら私を待つということでございますね」
「まあ、そういうことで……」
と爺さんはなんだかあいまいにこたえたが、しかし皇子はきっぱりと、
「わかりました。それが姫のお望みならば、三年待ちましょう。しかし三年後に姫は私の妻になる、とこう理解してよろしいのでございますね。では念書をしたためてほしいのです。三年後に、たしかに姫は私に差し上げるという一筆を。口約束ほどあてにならぬものはありませんからなあ」
爺さんはどうしたものかと迷ったが、どうせ仏の石などあるわけがないと、さらさらと皇子の差し出した紙に筆を走らせたのだ。
五人目の最後の皇子が石上(いしのうえの)まろたりという中納言だった。中納言といえばこれも高い位で、それなりの力や人格をそなえているものだが、この皇子といったらいったいどこに骨があるのかと思われるばかりの、なよなよとした人物であった。この皇子が毎日していることといったら鳥を観察することで、一日中鳥をおいかけているのだ。いまでこそバードウォッチャーなどという仕事があるが、その当時はそんなことを毎日にしていようものなら、気がちがったお人だといわれるのが落ちなのだ。
どうしてこんな人物が中納言などという位についているかというと、これは一にも二にもこの皇子の父親が政治の中枢をになう大変な権力者だったからだ。しかしこの烏の観察が好きな皇子にとっては、中納言なんていう位は、むしろ迷惑なものだったのだろう。
この皇子は、さまざまな鳥の生態の観察を、朝から夜まで、それも何日にもわたって観察するために、しばしば馬に食料をつんで山や森に入っていく。あるとき、嘴の黄色い珍しい鳥をおいけているうちに、この竹採り村まできてしまったのだ。草の茂みにかくれてその珍しい鳥が現れるのをじっとまっていると、そこにこの世の人とは思われぬばかりの美しい女が歩いてきた。皇子は一瞬にしてその女にひきつけられ、もう鳥の観察はそっちのけにして、ふらふらと後をつけていった。するとその女は広壮なお屋敷に入っていくではないか。そこでこの皇子も気づくのだった。ああ、あの人こそ、都でさんざん噂できいたかぐや姫なのかと。
もうそのときから皇子の情熱は、鳥の観察ではなく、姫の姿を見ることにかわってしまったのだ。朝から夜まで、雨の日も、風の日も、屋敷の近辺をうろうろしながら姫が現れるのをまっているのだ。
爺さんも婆さんも気味がわるくて仕方がなかった。そこで村の屈強な男たちにたのんで、その男を捕らえることにしたのだ。男はあっさりと捕らえられ、爺さんの前につれてこられた。爺さんはあなたどういう方なのだ問いただすと、
「私は中納言石上まろたりでございます」
と男はあっさりと身分をあかした。
「そうでありましょう。あなたさまのそのお言葉の使い方、そのお召し物、そして馬に付けられた鞍やお持ち物。たしかにあなた様は高い位のお方でありましょう。さればなおのことおたずねしますが、なぜこのようなことをなさるのですか」
と爺さんたずねると、涙をいっぱいためた皇子は、
「どうか姫を私に下さい。私はもう姫がいなければ生きてはいけませぬ。悪いとわかりながら、姫の館のまわりを毎日うろつくのは、姫がほしい、この胸に姫をお抱きしたい、もうその一心なのです。どうか私を助けると思って姫を私に下さい」
といっておいおい泣きだすのだった。心やさしい爺さんは、なんだかすっかり気の毒になって、とても冷たく追い返すことができず、さて困ったものだどうしょうと姫に話すと、姫は、
「その方は断っても、きっとまたこの屋敷のまわりを毎日うろつくのでしょうね。仕方ありません。その方にこういって下さい。唐の国には五色に光る子安貝という小さな貝があるのです。その貝はある特別な燕からしか生まれてこないのです。その燕を見つけだし、その巣のなかに生みつける子安貝をもってきて下さったら、そのとき結婚のお話を考えてみましょう。ただしそれは三年後です、とまたつけ加えて下さいますか」
それは名案と爺さんは客間に戻り、そのことを伝え、そしてきびしく、もうこの屋敷のまわりをうろつくのは、これできっぱりとおやめになって下さいと申し渡すのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
