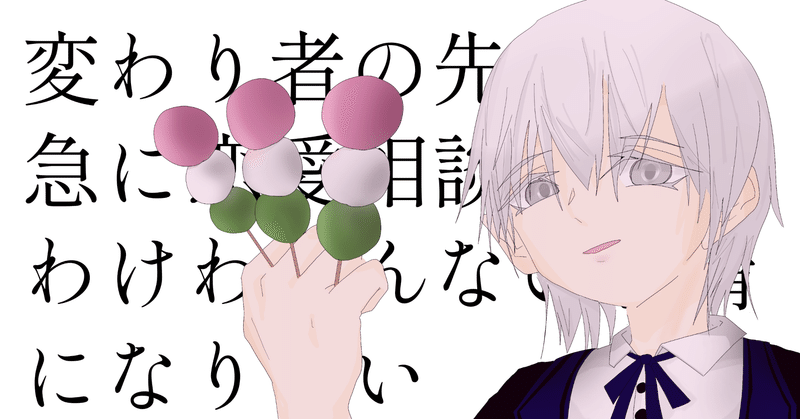
変わり者の先輩から急に恋愛相談をされて訳わかんない感情になりたい
立藤高等学校の屋上は閉鎖されている。
4月、新入生たちは屋上入り口の無骨な南京錠を見て高校生活最初の失望を経験するのだ。それでも私が昼休みの度にその閉ざされた扉を見に行くのを辞めなかった理由は、自分自身よくわからない。逃避先を求めたのか、あるいは奇跡を待っていたのかもしれない。気まぐれに触った南京錠があっさりと開き、鎖が水のように流れ落ち、眼前には青空が広がる。そんな小さな奇跡を。
初夏の頃だった。
閉ざされた扉の前に女子生徒が座り込んでいた。短く切り揃えた白髪と涼しげな横顔は、白昼夢のような神秘を湛えていた。よく見ると、彼女はスコープのような怪しげな機械で鍵穴を覗き込んでいる。すぐに合点がいった。彼女はこの南京錠の合鍵を作ろうとしているのだと。
それから3日間、鍵穴を覗く彼女を覗く私、という怪奇的な構図は続いた。そして4日目の昼、彼女はポケットから取り出したやけにのっぺりとした鍵を南京錠に差し込み、ひねった。カチリと音が鳴り、扉が開く。快晴の光が漏れ出て、彼女の髪を白飛びしそうなほどに照らした。
そして、目を細める私に彼女はこう言ったのだ。
「後輩くん、私と君のひみつだよ」
彼女が投げたもう一つの合鍵を私が取り落とすと、「しまらないなあ」とけらけら笑った。
「いらっしゃい、瑞樹。すっかり常連だね」
今日も彼女は屋上のぼろいベンチに腰掛け、昼食をとっていた。指の間に3本挟んだ三色だんごをもちゃもちゃと咀嚼している。
「なんすかその食べ方」
「ウルヴァリンみたいでかっこいいだろう。その上、おいしい。おだんごX-Menだ。おだんごX-Menは、悪と昼ごはんを菓子パンで済ます後輩を許さない。おら喰らえ、必笑だんご剣」
「あ、クソ、やめてください。ぜんまい侍でしょそれは」
ダハダハと笑いながら口元にだんごを押し付けてくる先輩を押しのける。屋上で会うようになって間もなく気がついたことだが、彼女は様子がおかしい。取り止めのない会話の端々から悪ふざけに繋げられる糸口を巧みに見い出し、うんざりするほどのダル絡みをする。ダル絡みの端々からも、ダル絡みをする。ダル絡みの連鎖、カスのぷよぷよである。
それでも私がこのストレスフルな環境に赴くのは、教室よりはましだからという理由に他ならない。総勢36名の不透明な会話のざわめきの中に所在なく居残る苦痛に比べれば、動作不安定な先輩の奇行に曝され、たまにおっぱいが当たるこの環境は快適と言ってもいい。
「ほら見てよ、今から校庭でPKしてるサッカー部のところに爆竹を投げるよ」
「マジでやめてください!!」
「必殺技が出たと、思うかもね」
「ラシャ瑞定期」
冬が来ても先輩は屋上にしつこく居座っていた。本当にどこから持ってきたのかわからない石油ストーブにあたる先輩の白い肌が、橙に照らされている。
「『いらっしゃい、瑞樹。すっかり常連だね』がなんJで流行ることないですから」
「長文乙。後輩顔真っ赤で草」
「次にその口調で喋ったら殺しますからね」
先輩は最近、おもしろなんJ民まとめ動画を倍速で観ている。『Z世代たるもの、ね』と言っていた。
「心が狭いンゴスねぇ、後輩くんは。教室で浮きまくりだろ」
「なんJ民の上位種やめてください。浮きに浮いた結果ここにいるんですよ」
先輩はあとで殺害するが、正直なところいきなり図星をつかれ動揺した。この奇人の目にも、やはり私は教室からあぶれた落伍者に見えているのだろうか。うまく取り繕えた自信がない。
「私はねえ、最近席替えで見ごたえのある男が隣に来て面白いんだ。くそ真面目な顔してるくせに、無用ないたずらを誰にも気づかれずにやるのが生き甲斐なんだってさ」
「……へえ、先輩も人間を面白がれるんですね」
「教室に飾ってる校訓を模写したやつと入れ替えたり、何食わぬ顔で架空の委員会の広報紙を配ったり。気づいたのはたぶん私だけだ」
「それは……先輩と話が合いそうな阿呆ですね」
彼女の口からクラスメイトの話題が出るのは初めてのことだった。それも『面白い』とまで評価するとは。彼女が興味を抱くのは自分のことかさんぽセルの現在の売れ行きのことだけだと思っていた。私の口はいつも通りに動いていただろうか。
結局その日は始業5分前のチャイムを待たずに屋上を後にした。教室に入ろうとしたが、男女グループの甲高い笑い声が漏れてきて、やめた。始業1分前まで往来の少ない階段の踊り場で曖昧に立って過ごした。名前のわからない焦燥が心に絡みつき、私の重心をずらしているような気がした。
「例のいたずら男がさぁ。あ、名前、上奈真園|《うえなまその》って言うらしいんだけどね。机の中でミニバラ育ててた」
「いやー、今日の真園は凄かった。いつにもましてまばたき少ないなーって思ったら、完全に形状が一致してる陶器製のマネキンだったよ」
「今日の真園は椅子の脚にバネつけて地味にビヨビヨ跳ねてたくらいか。これはそろそろでっかいの来るよ」
「はははは!瑞樹聞いてよ、あいつにやられた!上奈真園|《うえなまその》って名前、大ウソだった。『うそのなまえ』のアナグラムは自分で気づきたかったなあ〜」
あの日から先輩の話題に上奈真園(偽名)の奇行がのぼることが増えた。真園のイカレと反比例するように、先輩の私に対する奇行は減っていった。狂人は自分の上をゆく狂人と対面すると大人しくなるのかもしれない。
一度だけ、言ってみたことがある。
「面白半分でそんなに観察しちゃ彼も迷惑ですよ」
『面白半分』という部分に、万感の思いを込めるように。先輩が彼を『さんぽセルがハードオフに売り出されるようになるのはいつかな』くらいの感情でしか見ていないと肯定してくれることを願うように、言った。
「そ、うだね。いや別に……いや、まあ、うん。」
「はは、ほどほどにしとくよ」
先輩は歯切れ悪く、なにかを取り繕うように曖昧に笑った。
菲薄で実体のない和気藹々が充満するあの教室と、先輩のいる屋上。どちらがましなのか、私にはもうわからなかった。
「や、瑞樹。まあまあ座って、これでも食べな」
その日の先輩はやけに丁重に私をもてなした。
腐りかけのベンチにハンカチを敷く先輩はもはや不気味だった。
「なんでうなぎパイ……」
「静岡の県言葉は『接待』だからね」
「県言葉というものが仮にあったとして、『接待』の2文字をその故郷に刻まれた静岡県民が居た堪れないですよ」
軽妙で軽薄で、肩の力を使わないやりとり。
安心する会話。
「それで、どうして俺は先輩の気色悪い接待を受けなければならないんです」
「あぁー……と。あの、あのね。相談があって」
これもう終わるんだなあ、と、私はどこか俯瞰するような心持ちでいた。明日が先輩の卒業式だから、という理由だけではない。おそらくこれから先輩に持ちかけられる『相談』によって、私の屋上は、先輩といるこの屋上は決定的に失われる。
「あの、真園がね。あいや、偽名なんだけどさ、その……どえらく頭のいい大学に行くらしくて。私とは違うとこ。それで……」
「せ、席が隣じゃなくなっても、大学が違くなっても、現行の関係性を継続したいんだ……っ」
はい、終わりました。
「その迂遠な言い回しはなんなんですか。契約書読んでるのかと思いましたよ」
「うるさい!うなぎパイを喰らえ」
「銘菓で瞼を圧迫するのをやめてください」
これ俺ちゃんと喋れてるのかな。脳みそと口がどんどん離れていっている気がする。もう一回くらいおっぱい当たんねえかな。最後なんだから。
「先輩さあ、恋愛相談するならもっと早くにしてくださいね。あした卒業式ですよ?」
「れんあっ……言い出せなかったんだよ、瑞樹とはふざけ合ってばっかりだったから」
「俺はふざけられた認識しかないんですが」
もう、キモくなってきた。このラノベみたいな先輩も。ラノベと、はは、ラノベみたいな小手先のウィットに富んだやり取りなんかしちゃって、気持ちよくなってる俺も。
「わかりました。先輩、あした俺は屋上に来ません」
「え、なんでさ」
「馬鹿がよ。だから、卒業式が終わったあとその真面目きちがいをここに呼び出して告白してください。ここの合鍵作ったの、俺と先輩しか知らないでしょ。そういうの、たぶんそいつ好きですよ」
俺がここの鍵を開けるべきだった。先輩が目をつけるより先に。そうして中から錠を掛けて、誰も、誰一人も入れなければよかったんだ。先輩かわいいなあ。色白でちっちゃくて。この辺に陰毛とか落ちてないかな。
「そうか……なるほど……あ、明日かあ」
「陰ながら応援してますよ。話を聞く限りでは、彼も先輩のことは憎からず思っているはずです」
「……うん、頑張るよ私は。瑞樹、ほんと今日だけじゃなく、いろいろありがとうね」
「こちらこそ、ここの扉を開けてくれたときから、先輩は俺の憧れでしたよ」
先輩が私に手を差し出してきた。手ちっちゃい。
これで、おわり。
「……え、なんか手がヌメあったかいんだけど」
「その辺にあった鳥のうんこ触っときました」
「おン前!!!死んでしまえ!!!」
「ダラシャシャシャシャ!!!」
初めて聞けた先輩の罵声を背に受けながら屋上のドアを閉めた途端、私は小さいゲロを吐いた。
口を抑えた手にうんこが付着していることに気がつき、もひとつ吐いた。
うなぎパイの味がした。
卒業式は行かなかった。午前中に体調不良を理由に教室を出て、その足で屋上入り口へ向かった。
鍵穴を無茶苦茶にして開けられなくしてやろうかと思ったが、やめた。
そのまま呆然と立っていると、あのとき彼女が開け放った扉から漏れ出た白い光だとか、ベンチでうたた寝していた彼女が起きるまで隣に座っていた時間だとか、私の頬をつねる指から香るハンドクリームの匂いだとか、三色だんごに行儀よく並んだ歯型だとか、そういう記憶が押し寄せてきて私は、泣いてしまいたくなった。でもそれをするとこれまでの全てが陳腐になってしまうような気がして、できなかった。必死で耐えた。
階下から、在校生が椅子を引きずって教室へ帰っていく音が聞こえ始めた。ほどなく、卒業生の足音と嗚咽、談笑にふける声が近づいてくる。
そして、彼女が来た。用具入れの陰に隠れた私には気づかず、屋上へ出ていく。
胸元につけられたわざとらしく赤い薔薇のコサージュは、彼女には全く似合っていなかった。
「あいつ、卒業証書の筒6本持ってたなあ。」
先輩と真面目きちがいが並んで出ていったあとの屋上から、私は眼下の桜と卒業生の帰路を眺めていた。
「面白いんだなあ、やっぱ」
俺と違って。先輩の悪ふざけに呆れて腐して覇気のないツッコミして、そのくせ昼休みをそわそわしながら待ってたキモい俺と違って。
自嘲的な感情が溢れてきてたまらなくなる。
「あ、先輩いた」
彼女の髪は季節外れの雪みたいに白くて、離れていてもすぐにわかる。屋上以外でそれを見ることは、ついぞなかったけれど。大声で呼んでやろうかと思ったところで、先輩の名前も、その隣を歩く上奈真園の本名も知らないことに気がついた。名前、聞いとけばよかった。真園はどうでもいいけど。卒業式出席してたら、名前呼ばれるしわかったかもなあ。
「ここからさあ、『センパーイ!大好きで〜した!!』って叫んだらさ、卒業生全員あたし!?って顔してこっち向くかもね」
先輩の真似が上手くなった。結局のところこの一年で得られたものはそれだけだ。曇り空の晴れ目みたいに現れた先輩は、それが終わったら消えてしまって、温めたものも、照らしたものも、全部うそにしていく。
「投げちゃおっかなあ、爆竹」
彼女らの足元でそれが爆ぜたらどうなるだろう。きっと真園がぼそっとうまいこと言って、先輩が笑って、俺に中指立ててはにかんで、終わり。
つまらないことだ。
だから俺は、もっと面白くしたくて、先輩から貰った屋上の合鍵を力いっぱい投げた。
中空で乱反射して見えなくなった。
2人は気付くこともなく、不揃いの歩幅で歩いていく。
面白いなあ。私は笑った。
マシュマロでのリクエストでした。
https://marshmallow-qa.com/messages

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
