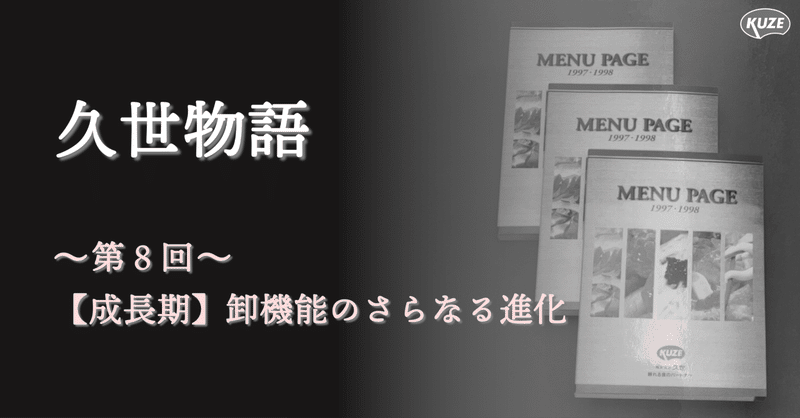
久世物語⑧【成長期】卸機能のさらなる進化
2024年、当社は創業90周年を迎えます。
語呂合わせで『クゼ』と、まさに久世の年。
90年という長い歴史の中には創業者や諸先輩の苦労や血の滲むような努力があります。
どのような思いが受け継がれてきたのか、私たちがどんな会社なのか。
「久世物語」をお届けいたします。
今回から【成長期】に突入します!
前回はこちら
【第8回】卸機能のさらなる進化
メニュー提案力の強化
1980年代に入ると、外食産業の競争はますます激化し、卸にもこれまでとは違った機能が求められるようになった。
健吉は、かつて好評を得たポーション・コントロールのように、顧客のニーズを先取りしたきめ細やかな対応がこの競争を生き残るカギだと考えていた。
1990(平成2)年、健吉が代表取締役に就任する。
フルライン化を推し進め、躍進著しい久世がこの時期注力したのが、顧客満足のさらなる向上である。
その1つがメニュー提案力の強化で、きっかけは社員食堂などの取引先を専門に担当するビジネスレストラン課の設立にはじまる。
社員食堂は、時期によって売上の増減がある外食チェーンとは異なり、毎月一定の売上を見込めるため重要な位置を占めていた。
限られた予算と素材を使い、バリエーション豊かなメニューを提案する取り組みが始まった。
しかし、その道のりは想像以上に厳しかった。それまでは外食専門の卸として営業に回っていた担当者が、急に「これからはメニューも提案します」と言っても、厨房の人間には相手にされない。
「レストランで働いたこともない問屋の営業に何がわかるんだ」と追い返されることも少なくなかった。
業務用専門卸から、外食を中心としたフードサービス全般の提供へと、久世の内部は確実に変貌を遂げていたものの、それを周知させる仕掛けが必要だった。
そこで、健吉はまず、大学や短大の栄養科出身者を集め、メニュー開発を支援する体制を整えた。
急ごしらえの部署の中で、仕事は自分たちで作り上げねばならない苦労に、1年を待たず退職したり、社員食堂へ他社へ引き抜かれた者もいた。
しかし、健吉はメニュー開発支援体制の構築にこだわり、これを推し進めた。
ほっかほっか亭から始まった「メニューページ」
ビジネスレストラン課が立ち上がる少し前、1970年代後半に取引が始まったほっかほっか亭の全店舗には、久世の黄色いファイルが置かれていた。
鮭弁用の鮭や海苔弁用の海苔など、PB製品を含めた40~50品目の弁当用素材とともに写真が掲載されている商品カタログ兼注文書のようなものであった。
ほっかほっか亭向けの素材は、産業用給食や社員食堂などの他の業態にも使えるものが多かった。
そのため、商品カタログを渡すとお客様から喜ばれ、注文につながることも多かったという。
現在のものとは比べ物にならないほど少ない情報量であったが、商品カタログは当時としては画期的なものであり、営業活動に非常に重宝されることとなった。

こうして始まった食材カタログは、特販課がPB製品を企画・開発するようになったことでさらにその重要性を増してゆく。PBを含めた商品の多品種化に伴い、売り手とユーザー間の商品認識にギャップが出始めていたことも大きな要因であった。
そして、1993(平成5)年に久世の総合食材カタログ「メニューページ」の第一刊が刊行された。

そして、創業60周年を迎えた1995(平成7)年には第二刊が発行され、記念式典と刊行記念を兼ねた食材発表展示会が池袋サンシャインシティで催された。
およそ400ページの中には、PBを含め、96メーカーによる2100種類の食材がカラー写真とともに紹介され、食品業界の慣例によって第一刊では掲載を見送った価格や納期も明記された。
カタログの食材を使い、和洋中などのジャンル別に料理を紹介するレシピ集なども用意されていた。
このメニューページは、久世の提案型営業を支える重要なツールとして、多くの取引先のもとで活用されることとなり、今でも受け継がれている。
メニュー開発課の設立
バブル崩壊後、「中食」概念の誕生とともに惣菜市場は拡大を続けていた。
久世の取引先でも惣菜の取り組みを強化するところが増え、営業担当者に食材情報の提供やメニュー提案が要望されるようになった。
メニューページの刊行によってメニュー提案ニーズの高まりに手ごたえを感じた健吉は、1995(平成7)年頃「メニュー開発課」を設立する。
メンバーは、5名のメニュー支援担当スタッフである。
さらに、外食専門の経営コンサルタント等と提携し、店舗設計や立地開発、メニュー構成などのアドバイスを行える体制を整えた。
この年、本社ビルが完成した。本社ビル内には、さまざまな業態のユーザーを想定した厨房設備に加え、ライティングや撮影機材もそろったクッキングスタジオも開設され、料理雑誌として名高い「dancyu(ダンチュウ)」の撮影が久世のクッキングスタジオで行われたこともあった。
このクッキングスタジオを会場に、取引先に対して月に1回、メニュー開発課による「デリカ・惣菜セミナー」を実施することになった。
それはやがて、テーマに沿った商品やメニュー提案、トレンド情報を提供する「食材セミナー」へと進化し、さらに数千人の来場者が訪れる現在の展示会「フードサービス・ソリューション」の開催へとつながっていく。



こうして、「食にまつわることすべてに関わり、外食を中心としたフードサービスに徹したい」という健吉の強い思いは、メニュー提案課の設立をきっかけに次々と具現化する。
顧客にとって必要なものを求めて現場に足を運び、きめ細かい情報収集を通じて次の一手を打つ。あくまでもお客さま視点にこだわる営業活動の徹底が、顧客との信頼関係を構築していった。
(次回へつづく)
