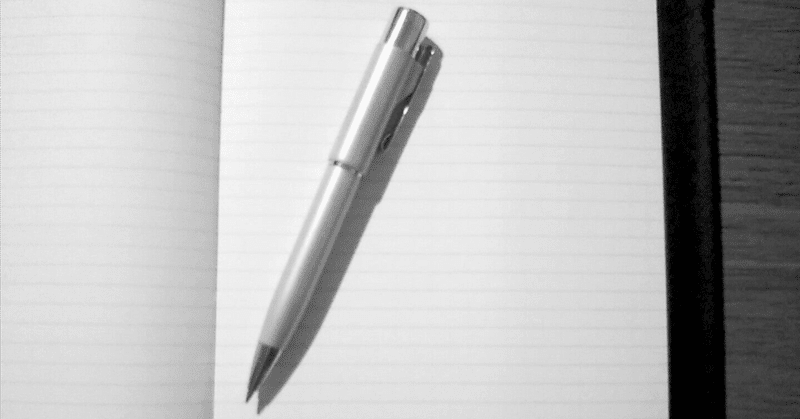
「ライター」という言葉に惑わされていた過去の自分へ【取材・執筆・推敲 書く人の教科書】
今、自分は「マーブルスクール」というオンラインスクールで、インタビューや編集、広報など、ライターとして活動していくなかで必要な「+α」のスキルを日々、学んでいる。
そんな「マーブルスクール」の課題図書として読んだのが「嫌われる勇気」の著者としても有名な古賀史健さんの「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」という本だった。
ようやく読み終えた時に、真っ先に頭に浮かんだのは
これから先、この本を何度でも読み返すだろうということ。
自分の書く文章に迷ったとき。
ライターとして、新たな壁にぶち当たったとき。
何かが足りないけど、その「何か」が分からなくて途方に暮れているとき。
未来の自分がどのような立場におかれているかはまだわからないけれど、今、読んだ「この本」から得られる学びと、紆余曲折を経て、もう一度「この本」を読み返したときに得られる学びは、また違ったものになっているだろうと思った。
だからこそ、今、この本を読んで感じたことを
あますことなく書き残しておきたい。
まだライターとしての実績もなく、これから先「書く仕事」をしている姿を想像できていない今の自分が、それでも心にズドンと刺さった言葉や文章を記しておきたい。
そういう思いに駆られて、この文章を書いてみる。
◇
「ライター」とはどんな存在なのか
この本で何度も登場する言葉が、以下の文言。
「ライター」とは取材者である。
そもそも、この本には文章を書く人にはもれなく刺さるであろう金言、いわゆるパンチラインが頻繁に登場する。毎ページメモしているのではないかと錯覚するほど、短い間隔で盛り込まれている。
そのなかでも、何度となく刷り込まれるのが
「ライター」とは「取材者」であるという意識。
それはインタビューや文章を書くことに限らず、日常の中においてもそうだと、著者の古賀さんは述べている。
人と相対していなくても取材はできる。気になる事象を拾って、自分の興味をどんどん広げていくことで、自分なりの考えが生まれる。
何かを観察し、推論を立てて、仮説を考えること。
その流れが、自然と体に染みつくことこそが
「取材者になる」ということなんだと、あらためて実感した。
違和感の正体である「雑さ」を、どこまでもしつこく追いかける読者になろう
また、上記の文章でも言及されているように「書くこと」ではなく「読むこと」に焦点をあてることで、より「ライター」は「取材者」であるということを認識させられた気がした。
その後も、「読む」と「聴く」が同義であること、その理由が語られることで、取材は「わかる」に辿り着くまでの冒険だと、最後には自然と納得せざるを得なかった。
取材対象者のことを圧倒的に好きになるまで、時には、嫌いになりそうな情報さえも説き伏せるほど、しつこく「調べて」「考える」ことによって、やっと「書く」ための土俵に立つことができる。
「ライター」であるためには、人に対してだけでなく、日常の中で「読む」から「分かる」に繋がる一連の流れを、自然と実行できなければならないということを、この本を読んでひしひしと実感した。
◇
「比喩」や「たとえ話」はあくまで文章をわかりやすくするために
「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」を読んでいて、とても印象に残っているのが、古賀さんが文中で使う「比喩」や「たとえ話」のわかりやすさ。
ぼくはたくさんの資料にあたるとき、架空の牧場をイメージする。
ライターは、みずから光り輝く恒星ではない。
上記の文章だけでは
あまり具体的なイメージがわかないかもしれない。
でも、前後の文章を読んでから、この一節に目を向けてみると、不思議なことに、一瞬で頭の中に具体的なイメージが思い浮んでくる。
まるで、今まで曖昧なイメージでしか理解できていなかった事柄が、どんどん輪郭を持っていくみたいに、文中で述べられている考えがすんなりと理解できるのだ。
そして「比喩」や「たとえ話」が積み上がるごとに、輪郭を描いていた薄い線はくっきりとした濃淡によって、より鮮明になっていく。
古賀さんが、導入部分として用いる「比喩」や「たとえ話」には、読者を置いてけぼりにすることなく、一段ずつ階段を登っていくための「手すり」のような役割を果たしていると感じた。
自分の企画を、あるいは原稿を、「そこに『きびだんご』はあるか?」の目で読み返してみよう。
実際、第5章の「構成をどう考えるか」では、昔話でお馴染みの「ももたろう」を「模範例」として扱っている。
一見、原稿の構成と「きびだんご」がどう繋がるのか
てんで想像もつかない。
でも、この第5章を最初から最後まで読んでいると、絵本こそが構成力を鍛えるための最高の手本であること、そして「ももたろう」という誰もが知る物語にさえも、読者を引き込む構成が成されていることを、肌から実感できるだろう。
後に、古賀さんは「レトリック」は想像力の補助線の役割であり、書き手の技巧をひけらかすものではないと述べている。
この「きびだんご」は、まさに読者の頭の中を整理するために必要な「たとえ話」だったように思った。
◇
「ライター」と名乗っていいか迷っていた過去の自分へ
この本は間違いなく、「ライター」の境界線がどこまでかわからず、どうすれば「ライター」だと自信を持って名乗れるだろうかと悩んでいた過去の自分に、確固たる道標を与えてくれる本だった。
そして、同じように「ライター」の境界線に惑わされてきた人々にとっても「文章を書き続けるための道標」となるものを見つけることができる本だと思う。
実際のところ「マーブルスクール」のインタビュー講座を受けている中でも、この本に書かれていることがベースとなっているように感じる言葉が多くあった。
あらためて、今、現役で活躍しているライターさんたちにとっても、この本は文章を書く礎になっているのだと、身をもって実感している。
きっと、これから先「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」何度でも開くことになる。そう、確信を持って断言できるほどの言葉や文章が、この本には詰まっている。
だからこそ、次にこの本を開く時までに
しっかりと「書くこと」に向き合っていよう。
まずは、このnoteから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
