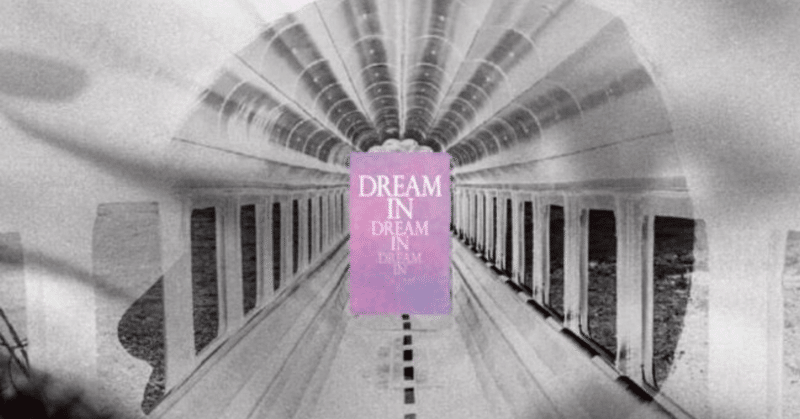
傾聴という、ラグジュアリー / Cornelius『夢中夢』 レビュー
音の減衰をここまで意識したのは、一体いつぶりだろう。夜、誰もいない街へと出て、手を叩いてみる。「パンッ」と渇いた音がマンションの壁へと当たり、反響を伴って、徐々に空気の中へと消えていく。どこか遠くに飛び立っていったような気もするし、元からどこにもなかったような気もする。
思えばCorneliusの作品——とりわけ2001年の『Point』以降——には、音の減衰をはっきりと感じられるデザインが施されていた。音数を絞るのみならず、アグレッシブなパンニングを施して、発音のタイミングも再考し、トラック全体の「容積」は押し広げられた。結果的に構成音の輪郭は強調され、“Audio Architecture″のミュージックビデオないしVJのように、空気の震えは「もの」としての触感を獲得する。 前作『Mellow Waves』のリリース時に行われた高橋健太郎氏によるインタビューでも、Corneliusはその試みについて述べていた。
2001年の『Point』 から、点のように音を置いていくというデザイン性はあったと思うんですけれど、2006年の『Sensuous』 を聴いた時に、これは何がこんなに気持ち良いんだろう?と考えて、そうか、同時発音しないんだと気づいた。ベースを鳴らす時にはベースだけをどーんと鳴らすんだみたいな。
Cornelius 『Point』の頃から近いことはやっていた。音数は少なかったし。でも、まだ音が重なってる部分はあったのが、リミックスの仕事とかいろいろやっているうちに、どんどん『Sensuous』 に向けて、そこが厳密になっていったんですよ。
『Point』以降、Corneliusの施すデザインは、革新的かつエッジなものとして受容されてきた。しかし、それによって描写される風景は、決して近寄りがたいものではなかったように、今となっては思える。音数を絞ったトラックを作る人物が、冷血なミニマリストである必要は全くない。
前作よりおよそ6年ぶりとなった最新作『夢中夢』で、Corneliusは先述したサウンドデザインを継承 / 深化させつつ、より豊かなタッチでたおやかな一枚絵を描いてみせた。使っている画材は同じはずなのに、よりポエティックな、生暖かい風景がそこには広がる。
坂本慎太郎が作詞を担当したオープニングトラック“変わる消える″から、既に減衰は用意されている。というよりむしろ、既に減衰も終わり、喪失にも近い感慨がそこでは歌われている。だからこそ《好きな人いるなら / 会いに行かなきゃ / 今 すぐ はやく はやく》という後半のヴァースはポジティブで、新たな振動の開始を予感させてくれる。坂本慎太郎の過去作と比べても特段ストレートな、慈しみに溢れた詞の展開だ。
続く“火花″では、左右にパンニングされたギターのフレーズがイントロから耳を惹く。装具を排したクリーントーンだ。時々挿入されるブラッシングの音色も楽しい。“時間の外で”の不規則なタイミングで鳴るエレピも、アンビエント・ポップ調のトラックの中では、不意に吹きさす微風のようで優しい。
過去作と比較してもバンドによる演奏への目配せを予感させるが多いのも、『夢中夢』の特徴だ。“火花″やブルー・ナイルを思わせるベースラインが牽引する“蜃気楼”。静謐な音像の中でほんのりとレイドバックした演奏を聞かせるインストナンバー“Night Heron”。本作はセッションではなく、今まで通りDAW上で製作されてはいるものの、これらの最新曲を引き連れたライブへの期待が高まる。
大きいうねりの中で聞かせるインストナンバーは、これまでCorneliusが追求してきた路線の正当な継承とも言えよう。“Too Pure”は、これまでアルバムに一曲は収録されていたギターによる小品のような枠に収まりつつも、フレーズのループによる円環構造と都度挿入されるハーモニクスやSE——小鳥の鳴き声にも、防犯ブザーにも似ている——による「崩し」の対比が、ロウな魅力として存在している。『Mellow Waves』収録の“Surfing on Mind Wave Pt2”のような、シンセサイザーによるダイナミックな波の曲線。タイトルトラック“霧中夢”ではその波の中に、“時間の外で”のエレピのような不規則な要素を混入させ、こちらを傾聴へと誘う。
そう、傾聴。『夢中夢』を聞いて、一つ気づいたことがある。自分にとって、「傾聴」とはラグジュアリーな体験に他ならない。ミニマルかつ、発音のタイミングまで丹念に練られたサウンドデザイン。それらは私に、音の始終の観察を欲望させる。耳をそばだてて『夢中夢』に集中している時間。それは代替不可能で、ややもすれば奢侈品で、だからこそ手元に置いておきたくなる。目や耳などの感覚器官を絶えず喚起される環境下において、本来の機能のみを豊かに倍増させる作品の鑑賞は、ラグジュアリーな体験そのものだ。
映像における視点誘導の技術のようなもので、『夢中夢』の中でリスナーはその都度「何を聞くのか」を提示される。そうした聴取体験のデザインは、『FANTASMA』のオープニングトラック“MIC CHECK”でバイノーラル録音を採用し、特製ヘッドフォンを初回限定版に同梱した数十年前から意識されていたテーマなのかもしれない。
傾聴の中で、Corneliusと再び遭遇する。その上で、本作を聞いて歌唱へと意識が向くのは必然のようにも思える。他の構成要素と歌が並列になった上で、温かみを感じる声の魅力を、傾聴によってもう一度発見する。整然とした手続きによって、『夢中夢』の詞とリスナーは出会う。
《本質 目に見えない / 心の目開けば 感じられるの?》と問う“蜃気楼”。A.C.ジョビン“三月の水”にも通じる手法で言葉を配置した“Drifts”。「All Things Must Pass」という英題を採り、万物の諸行無常を唱える“無常の世界”。底なしのポジティブでもなければ、光の介在が感じられないほどのネガティブでもない。ただ、どちらかといえば、ほんの少しポジティブなのかもそれない。減衰が予定される空気の振動を前にして、それでも喉を震わせ、歌っている人がいる。その存在の否定されなさ、揺るがなさ。そば立てられた耳で声を聞くことは、それだけでゆったりと誰かの存在を肯定している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
