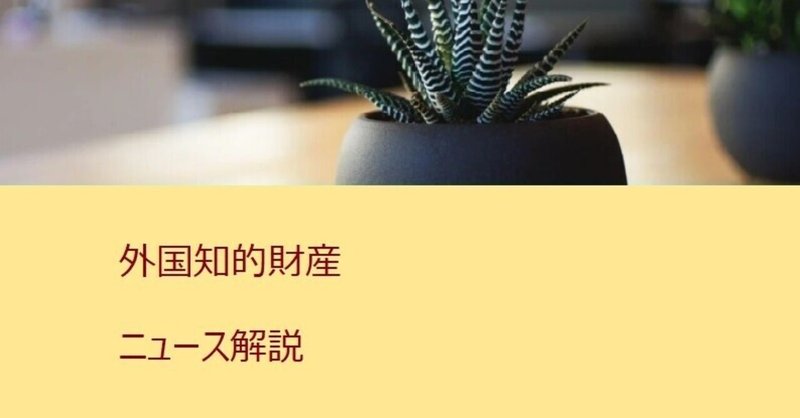
中国 最高知識産権法廷2020年度年次報告公示、第二審63%増加(2月26日)
2月26日付、最高人民法院知識産権法廷は2020年度の年次報告書を公示ました。注目するポイントは以下の通りです。
1. 統計データ
2020年度に第二審の最高知識産権法廷が受理した技術関連知的財産事件は3,176件と前年に1,231件増加し、対前年比+63%増、審決は2,787件と前年に1,354件増加し、対前年比+95%増加した。結審率は76%(前年係属512件を含む)である。引き続き高い増加率を示している。
受理内訳は、民事事件が986件増加し1,948件と前年比+102%、行政事件は429件増加し670件と前年比78%と行政事件の増加が目立っている。
処理内訳は、民事事件が1,156件増加し1,742件と前年比+197%、行政事件は352件増加し494件と前年比248%である。平均審理期間は、民事二審は121.5日、行政二審は130.7日と4か月強となっている。裁判官一人当たり82.5件を担当しており、前年比73%増加している。
民事事件の新規受理内訳は、発明特許権侵害435件、実用新案特許権侵害754件、特許出願権及び特許権帰属163件、コンピュータソフトウェア360件、技術契約67件、営業秘密44件、植物新品種40件、独占30件、集積回路配置設計5件、その他50件であり、権利帰属紛争は前年度の9件から163件に急増した。前記の営業秘密以下の紛争はいずれも昨年より増加した。
一方、行政事件の新規受理内訳は、権利確定審判事件が622件、行政による処理事件が17件、その他の行政案件が31件である。行政%を占める権利確定審判事件の内訳では、特許出願却下再審226件、実用新案特許出願却下再審18件、意匠特許出願却下再審2件と出願関係が全体の39.5%を占める。発明特許権無効175件、実用新案特許権無効149件、意匠特許権無効52件。これらは対前年比178%増であり、特に意匠特許無効事件は前年度の13件から52件に増加した。
裁判結果の審決2,787件の内訳は、原審維持1,667件(59.8%)、控訴却下539件、調停158件、再審や改審405件、その他18件である。さらに、この内民事事件1,742件の内訳は、原審維持779件、控訴却下463件、調停158件、再審や改審339件、その他3件である。また行政事件494件の内訳は、原審維持430件、控訴却下22件、再審や改審39件、その他3件である。
なお、外国、台湾、香港、マカオが関係する事件については、受理376件と全体の12%、前年比+116%増で、民事288件、行政148件であり、審決は281件全体の10%、前年比+187%増で、民事185件、行政96件であった。
2.特徴
2020年の全体的特徴としては、全体的に2倍増の急激な増加がみられ、行政事件は約3倍の勢いとなっている。そして、新しい技術分野や新業態の事件の受理が比較的多く、戦略的新興産業の事件が478件(受理比13%)で、この内訳は新世代情報276件、バイオ医薬94件、ハイエンド装備50件、省エネ・環境保護33件、新材料21件、新エネルギー3件、新エネルギー自動車1件である。こうした事件は、先端技術から日常の衣食住に関わるものまであり、国や業界の基準関連、有名な企業や製品かんれんするなど社会的影響が大きく、注目度が高いために、裁判放映の平均視聴数は1.9万回以上で、視聴数が10万回を超える事件が47件あった。事件審理の特徴としては、民事事件では立証の困難な事件が多く、証拠保全、現場検証などの立証の緩和措置が採られ、立証妨害に対する責任の判断などがある。行政事件では公知の常識や常用設計などの認定に対する合理的な立証や説明を行政機関に求める判断が目立っている。
2.1特許民事事件の特徴
①実用新案特許権侵害の全体での構成比が2019年の47%から38%に下がった。
②特許出願権及び特許権の帰属に関する紛争数が2019年の9件から163件に急増した。主に職務発明、営業秘密、技術契約の法律問題に関連しており、企業の特許権の権益保護と従業員の職業選択の自由との間の複雑な課題が露呈している。
③特許大口一括事件が2020年下半期は大幅に124件から40件に減少し、裁判所の関連措置が効果を示した。裁判所はこうした事件に対して、合議体が「法に基づき合理的に規制し、源流管理を奨励し、商習慣を尊重し、信義誠実の原則」という司法政策を確立し、賠償基準の差別化、賠償額の精緻化を通じて、権利者の遡及権を積極的に導き、権利濫用を防止する関連措置を積極的な行った。
④複雑な技術的事実を明らかしなければならない事件が増加し、侵害判断、公知技術の抗弁などに関し、裁判所は積極的に当事者に補助専門家の招聘や技術調査官の参加で対応している。
⑤地方行政機関が公共サービスを展開する中で権利侵害行為に関与し、民事訴訟の共同被告となる場合も多い。
2.2 特許行政事件の特徴
①広範な技術分野に及んでおり、特に発明特許に関し、意匠は少ない。技術分野は機械、電気、通信、医薬、化学、光電、材料などの分野で概ね全分野である。特許出願拒絶査定不服と特許権無効裁定不服事件は401件で全体の65%を占める。
②争点は進歩性と新規性で全体の90%以上を占め、進歩性が主である。その他は、明細書の開示、クレームのサポート、補正範囲などである。
③再審と改審事件が増加し39件で、比率8%と前年比倍そうしている。
④控訴者は特許権者と特許出願人を主である。特許権者、特許出願人による控訴事件は377件で84.9%占める。無効宣言控訴事件での請求者による事件は44件と9.9%を占める。国家知識産権局による控訴事件は30件と6.8%を占める。
2.3 営業秘密事件の特徴
①事件数は2019年の12件から44件と4倍弱に急増した。関連技術分野は機械、化学工業、バイオエンジニアリング、医療製薬、コンピュータ、通信、機器の自動化など。
②権利者の立証能力が低い。事件の9件では被疑侵害者に非侵害の認定されるなど、権利者による秘密保護措置、技術秘密形成時期、または侵害事実の立証が不十分な事例が多い。
③関連法律問題が多元化している。営業秘密の認定や主体証明、接触や授受、秘密保持措置の認定、侵害の認定、及び罰則賠償の適用などの法律問題などが含まれる。
2.4 7.コンピュータソフトウェア事件の特徴
①事件数は2019年の142件から360件と1.5倍に増加した。主にコンピュータソフトウェア開発契約とコンピュータソフトウェア著作権侵害でそれぞれ69%と21%を占める。
②一審の賠償額のみを対象とする控訴が多く、298件を調停または撤回での決定が118件と40%を占めた。
③事件の争点は集中しており、開発契約紛争では主に当事者がソフトウェア開発義務及び違約責任を履行したかどうかで、侵害紛争では主に技術対比に集中する。
相変わらず侵害事件の多い中国ですが、懲りない面々が$欲しさに悪いことをやっている世界です。当職はこれまで中国で三桁に近いかなりの数の訴訟の支援や協力をしてきましたが、これだけの数があると、日本の訴訟件数はゴミのように少なく、日本では実際の実務経験をつめる機会はないということですね。
■
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
