
反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題――心情から読み解く〈信頼〉の不在とその行方
反出生主義について1年前に執筆した原稿がようやく刊行されました。
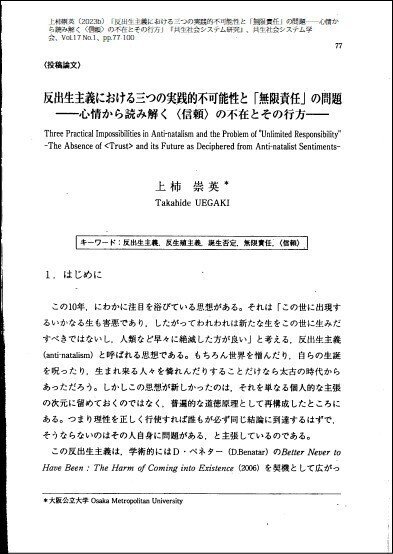
反出生主義とは、「この世に出現するいかなる生も害悪であり、したがってわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではないし、人類など早々に絶滅した方が良い」という主張を普遍的な道徳原理として掲げる思想で、ベネターの『Better Never to Have Been : The Harm of Coming into Existence』(2006)を通じて世界的に知られるようになりました。
本論もベネターについては触れていますが、切り口はかなりユニークではないかと思っています。反出生主義について書かれた論考の多くは、反出生主義の理論的枠組みの正誤に焦点が当たりますが、本論の場合そうではなく、人々がなぜ反出生主義に惹かれるのかという心情の方に力点をあてているからです。
(追記:また、先行きの不透明さや格差といった経済問題に絡めて論じる方もいますが、本論はそのアプローチとも異なります。詳しくは注の22を参照)
今回の論考を通じて、「無限責任」という概念に行きつくことができました。これは本来一人の人間が背負えるはずのない責任を、それでも一人で負わねばならないと思ってしまう現代人が抱える強迫観念のことです。
私たちは、生きている限り、誰かに影響を与えずにすむことも、また自分の人生の全責任など背負いきれるはずもないのに、誰も苦しめず、誰も傷つけず、誰にも迷惑をかけまいとして焦燥してしまっています。未来を正確に予測することも、未来を意のままにできることもないはずなのに、生まれ来る誰かの人生の全責任をたった一人で背負わなければならないと感じてしまっているわけです。
本論が主張するのは、この「無限責任」という歪な世界観=人間観こそが、実は人々を反出生主義へと誘う結果となっているのではないかということです。つまり「無限責任」が要求する、そもそも実現不可能な“あるべき人間”の理想に駆り立てられ、「そんな責任など背負えるはずがない」、「そんな人間が新たな命など生みだす資格はない」と追いつめられた人々が、「この世に出現するいかなる生も害悪であり、そもそもわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではない」と聞いて、どこか救われた気がしてしまう。そうした私たちの世界観=人間観に潜む病理こそが、真に問題にされるべきではないのか、ということです。
本論では、
「反出生主義者は、決して無責任な人々なのではない。おそらく誰よりも責任を感じるからこそ、そして真面目に生きようとするからこそ、人々はかえって反出生主義者になる。世界や人間を心底憎んでいるから、人々は反出生主義者になるのではない。おそらく誰よりも世界や人間を祝福したいと願い、その高すぎる理想に屈折したからこそ、人々は反出生主義者になるのである。」
「したがってわれわれの社会が、この先も互いの生の責任を分け合おうとすることなく、〈信頼〉を育くむことを怠り、ありもしない自立の幻想に浸り続けるのだとしたら、人々はますます反出生主義者に転向せざるをえないだろう。」
と書きました。しかしここでの〈信頼〉については、実は、迷いもあるのです。私に反出生主義を考えるきっかけを与えてくれたある方が言ってくださったように、「そのような〈信頼〉など、人類は一度として手にしたことなどなかったのではないか」と、私も心のどこかで、ふと思うことがあるからです。私もまた、「無限責任」に苦しむ現代人の一人なのかもしれません。
反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題
1.はじめに
この10年、にわかに注目を浴びている思想がある。それは「この世に出現するいかなる生も害悪であり、したがってわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではないし、人類など早々に絶滅した方が良い」と考える、反出生主義(anti-natalism)と呼ばれる思想である。
もちろん世界を憎んだり、自らの生誕を呪ったり、生まれ来る人々を憐れんだりすることだけなら太古の時代からあっただろう。しかしこの思想が新しかったのは、それを単なる個人的な主張の次元に留めておくのではなく、普遍的な道徳原理として再構成したところにある。つまり理性を正しく行使すれば誰もが必ず同じ結論に到達するはずで、そうならないのはその人自身に問題がある、と主張しているのである。
この反出生主義は、学術的にはD・ベネター(D. Benatar)のBetter Never to Have Been : The Harm of Coming into Existence(2006)を契機として広がっていった(1)。しかし本論が注目したいのは、それが学術界を超えて少なくない人々の共感を密かに呼んでいることである。それはなぜなのだろうか。その背景にあるものとは何なのだろうか。このことを考察するのが本論の目的である。
本論では、まずベネターが提示した反出生主義の基本的な枠組みについて確認し、その問題点について考える。その際特に着目したいのは、この思想を現実に落とし込むことによって生じる不可能性の数々である。反出生主義の枠組みは、思考実験としては成功しているものの、それは純粋に理念の世界の産物でしかない。本論では、このことを「苦痛除去の不可能性」、「選択の不可能性」、「自立の不可能性」という三つの実践的不可能性の観点から独自に分析し、この思想がいかに人間的現実と乖離した前提から構築されているのかということについて見ていこう。
だが本論にとって重要なことは、それでも少なくない人々がこの思想に惹かれてしまう根源的な理由である。本論では、反出生主義に共鳴する人々の心情に着目することによって、その背景に、自身のあらゆる行動の全責任を無制限に負うべきだとする「無限責任」の思考が潜んでいることを指摘したい。
反出生主義者は自身が意図せずして誰かを不幸にしてしまうことを恐れているのであり、自身の身勝手な理由から、将来不幸になるかもしれない何ものかを生みだすことが許されるのかと苦しんでいる。だが、考えてもみてほしい。そのような責任など、そもそも一人の人間が背負えるようなものだったのだろうか。問うべきことは、そもそも現実的には想定しがたいはずの責任を、それでも負うべきだと感じてしまう、われわれの歪んだ「世界観=人間観」なのである。
本論では、こうした「無限責任」という名の幻想が、歴史的にはつい最近になって現れたものに過ぎないことについて確認する。そしてわれわれの社会においては、実際に互いの生の責任を分け合うための〈信頼〉が欠落していることに目を向けたい。もしもわれわれが、これからも社会全体として〈信頼〉を育むことができず、ありもしない自立の幻想に浸り続けるのだとしたら、人々は「救い」を求めて、ますます反出生主義に傾倒せざるをえないだろう。
1.反出生主義とは何か
1)反出生主義の定義について
本論では先に、反出生主義を「この世に出現するいかなる生も害悪であり、したがってわれわれは新たな生をこの世に生みだすべきではないし、人類など早々に絶滅した方が良い」と主張する思想であると定義した。しかしこの定義は、実はベネターを強く意識したものであり、必ずしも標準的なものではない。
例えば森岡正博(2020)は、反出生主義を「生まれてこない方が良い」思想という形で広く捉え、ベネターの主張が、古代から続く「誕生否定」の思想的系譜に位置づくものだとしている。その理解に立てば、今日の反出生主義は、古代ギリシャや古代インドから西洋近代のA・ショーペンハウアー(A. Schopenhauer)、E・M・シオラン(E. M. Cioran)らを経て継承されてきた、「誕生否定」をめぐる新しい思想形態である、ということになるのである。
とはいえK・シングルトン(K. Singleton)が述べるように、原語である’anti-natalism’ に着目すれば、反出生主義は生殖を推奨する‘natalism’の対抗思想としても位置づけられ、その思想的核心は、「(私が)生まれてこなければ良かった」というよりも、あくまで「(新たな存在は)生まれてくるべきではない」と主張する点にあると言うこともできる(Singleton 2020、 2021)。加えてその主張の特徴が、道徳原理の表明である点からすれば、やはりそれはこれまでの一般的な「誕生否定」の思想とは一線を画しているとも言えるだろう(2)。
以上のことを踏まえ、本論では以下のように整理しておきたい。
まず、さまざまな経緯によって、人が「(私は)生まれてこなければ良かった」と考えることは、時代や文化を超えた人類全体の普遍的な体験だと言える。森岡が「誕生否定」の思想と呼んでいるのは、こうした「ペシミズム的体験」を基盤に、それを思想という形にまで高めたものだろう。
「ペシミズム的体験」は、しばしば「このような苦しみに満ちた生が待っているのなら、生まれくる子どもたちは可哀想だ」、「このような苦しみに溢れた世界など、滅んでしまった方が良い」といった言明となって噴出する。そして今日の反出生主義が、こうした次元にとどまるものなら、実は話は早いのである。というのも誰かがそうした「ペシミズム的言明」をしたところで、何ものかの生きる価値、存在する価値について、他人がとやかく決めつける権利などどこにもない、と多くの人々は考えているからである。
しかし繰り返すように、反出生主義はそうした主張の仕方をしているわけではない。そうではなく、理性を正しく行使するなら誰もが同じ結論に達するはずで、そうならないのは、その人が感情的であったり、思考の仕方を間違えていたりするからだと主張しているのである。反出生主義の背景には、間違いなく「ペシミズム的体験」が存在するものの、われわれはいったん、それを単なる「ペシミズム的言明」とは区別しておく必要があるのである(3)。
2)ベネターの反出生主義と非対称性の問題
それでは反出生主義の主張が、実際にどのような形でなされているのかについて見ていきたい。ここで重要になるのは、ベネターが前掲書で言及した、快楽(pleasure)と苦痛(pain)の非対称性をめぐる分析である(4)。
ベネターはまず、以下の命題を一般的に妥当するものとして取りあげる。
(1)苦痛が存在しているのは悪い(【命題①】とする)
(2)快楽が存在しているのは良い(【命題②】とする)
ここまでは容易に同意できるだろう。これらは人間的生において、苦痛の総量を最小にし、快楽の総量を最大にすることが正しいとする、功利主義の基本的な前提でもある。そしてここには、明確な対称性があるのである。
ところがこれらを否定型にすると、その対称性は崩れてしまう。つまり単純に、「苦痛が存在しないのは良い」、「快楽が存在しないのは悪い」とはならないのである。
まず前者で言えば、例えばわれわれが歯医者に行くのは、歯痛を取り除くことが良いことだからである。そしてこのことは、特定の苦痛を現に感じている主体がいなくとも妥当する。例えば現実に飢えた人々がいなかったとしても、飢餓自体が存在しないことは良いことだからである。
ところが、特定の快楽が存在しないことは、必ずしも悪いとは言えない。例えばわれわれは、飢餓に苦しむ人を見て彼らの苦痛を取り除く義務を感じるが、退屈だと落ち込んでいる人を見てわざわざその人を楽しませる義務があるとまでは感じない。このことをベネターは、快楽があることは良いことではあるが、快楽がないことは必ずしも「悪くない(not bad)」と表現する(Benatar 2008: 41-42=2017: 51)。
もっともそこには例外があるだろう。それは、すでに特定の快楽を享受していた人から、それを取りあげる場合である。例えば趣味のジョギングができなくなることは新たな苦痛をもたらし、悪いことだと言えるからである。
したがってここからは、以下の命題が導かれることになる。
(3)苦痛が存在していないことは良い――たとえその良さを享受している人がいなくとも良い。(【命題③】とする)
(4)快楽が存在していないことは、悪くない――そうした不在がその人にとって剥奪を意味する人がいない限りにおいて。(【命題④】とする)
そしてベネターはこの論理を用いて、新たな存在の出生を問題にしていく。まず、存在者Xが存在する世界(シナリオA)と、存在者Xが存在していない世界(シナリオB)があるとする。このとき「シナリオA」では、程度の差はあれ苦痛も快楽も存在するだろう。しかし「シナリオB」では、そもそもXは存在していないので、苦痛もなければ快楽もない。これまでの【命題】に従うのであれば、「シナリオA」は良くも悪くもあるが、「シナリオB」は苦痛が存在しない良い面だけがあり、悪い面はないということになる。
したがって、総合的に考えれば、「シナリオA」よりも「シナリオB」の方が優れているということになり、われわれは「シナリオB」を選択すべきだということになるのである。つまり“非存在”は例外なく“存在”に勝るのであって、いかなる理由があっても、新たな命を産みだすことは極力避けるべきだということになる。
なぜなら生まれなければ悪い面は皆無であるが、生まれてしまうと、何らかの形で必ず悪い面が生じてしまうからである。こうして生殖を禁止し、人類がゆるやかな絶滅に向かっていくこと、それこそが理性の行使によって導かれる道徳的に正しい結論だ、ということになるのである。
なお注意を要するのは、この結論が、存在者Xが実際に感じている苦痛や快楽の総量とは無関係に導かれるという点である。われわれはしばしば、快楽の総量が苦痛の総量を上回るのであれば、存在者Xの生は良いものだと考えてしまう。しかし繰り返すように、快楽が存在しないことは悪くない。そして存在者Xが生まれてこなければ、苦痛自体が存在しないため、それ以上に勝る事態はないのである。
またベネターはここで、すでに生まれてしまったものが非存在になること(自殺)を推奨しているわけでは決してない(Benatar 2008: 212=2017: 220)。それは【命題】(4)の「剥奪」に抵触するおそれがあるからである。問題になっているのは、あくまで生殖の是非についてなのである。
3)反出生主義への反論や誤解
さて、以上の議論は納得できるものだろうか。ここでは前述した森岡による反論を二点に絞って取りあげておこう(5)。
まず森岡は、ベネターが「存在/非存在」の比較と「生成/非生成」の比較を十分に区別できていないとする。そしてベネターの枠組みが普遍的に妥当するなら「私が生まれてきたこと」と「私が生まれてこなかったこと」の比較においても言えるはずだが、主体としてのこの私は「私が生まれてこなかった宇宙」を想定してそれを価値づけることはできないので、両者はそもそも比較不可能だとしている(森岡 2020:282-289)。さらに別の論考では、先の【命題】(4)「快楽が存在していないことは、悪くない」が、ベネター自身の直観に過ぎず、その根拠が十分に示されていないと述べている(森岡 2021a:5、 18)。
森岡の指摘は確かに一理あるだろう。だが、反出生主義者からは次のような反論がありそうである。まず、森岡は「この私」をめぐる生成の問題について論じているが、「この私」以外の存在者Xについては、われわれは「Xが生まれてこなかった宇宙」を十分想定することができる。このことが存在者Yや存在者Zにも成り立つなら、「この私」にも成り立つと推論するにはそれなりの妥当性があるだろう。また【命題】(4)については、もし快楽の不在が悪いと仮定するなら、われわれには絶え間なく世界に快楽を生みだす義務があるということになってしまう。しかしここでの「人々を幸せにする義務」は、常識的に見て「人々を不幸にしない義務」ほどの拘束力を備えていない。その意味において、この直感には十分な妥当性があるといったようにである。
なお、前述したシングルトン(2021)は、反出生主義が混同されやすい立場について複数挙げ、それぞれの違いを以下のように整理している。
まず反出生主義は、①善悪そのものが存在しないとする「道徳的ニヒリズム」ではない(むしろ道徳的な善を突き詰めた結果として生殖を否定している)。また②能力の高い人間、特定の属性を持つ人間ならば生まれてきて良いと考える「優生思想」や「差別主義」でもない(能力や属性とは無関係にすべての人々の出生を否定している)。
さらに③子育て自体を忌避する「チャイルドフリー」でも(子育てをする反出生主義者もありえる)、④理想的な人口管理下では生殖が許される「新マルサス主義」でも(反出生主義は例外なく出生を否定する)、⑤性交や恋愛や婚姻を否定する「反性交」、「反恋愛」、「反婚姻」でも(生殖をもたらさないのであれば、いずれも問題ない)、⑥人類のみの絶滅を想定する「反ホモサピエンス出生主義」でも(理論的には感覚を持つすべての存在の出生を否定している)、⑦絶滅そのものを目的とする「絶滅第一主義」でもない(絶滅は生殖を否定した結果に過ぎない)、といったようにである。
2.反出生主義の実践的不可能性
1)「苦痛除去の不可能性」という問題
とはいえ、本論は一連の議論にひとつも問題がないとは考えていない。というのも、以上の議論は思考実験としては十分に成立しているものの(6)、それをわれわれの生の現実に落とし込もうとするやいなや、そこにはさまざまな矛盾が引き起こされることになるからである。
最初に指摘したいのは、苦痛の除去をめぐる問題である。前述のように、ベネターの議論において非存在の優越性を結論づけるためには、その大前提として、【命題】(1)「苦痛が存在しているのは悪い」がなければならなかった。そして確かに、一見この命題は公理として同意できそうである。実際、苦痛に満ちた拷問が地上から消滅することは多くの人々にとって望ましいことだろう。しかし人間的な生の現実は、これほど簡単にはいかないのである。
最初に思考実験をしてみよう。ある世界Wでは、高度に発達したメタバースが生活の舞台となり、人々は脳以外の身体を捨てて、チューブと電極を通じて直接情報機器に接続されているとする。また脳の生体管理は高性能のシステムが完璧にこなしてくれるため、人々はそのことを忘れ、アバターとなって人生の諸局面をメタバース内で完結できるとする。
するとどうだろう。人々はチューブと電極を通じて、メタバースからあらゆる快適な刺激を味わうことができる。脳以外の身体を持たないために、臭い、汚い、きつい、痛い、醜いといったあらゆる不快から恒久的に解放される。作り込まれたバーチャル人格が友人でも恋人でも望み通りの関係性を演じてくれるので、対人関係においても不快な思いを限りなく縮小させられるのである。
問題は、もしも【命題】(1)が普遍的に妥当するなら、ここでの「脳人間」世界は道徳的に望ましいと結論づけなければならないということである。しかし「脳人間」は、はたしてそのような世界に生きる意味を見いだすことができるのだろうか(7)。「脳人間」たちは、はじまりこそ目の前の「意のままになる世界」を貪り食うだろうが、いずれは迫り来る虚無と退屈とに耐えられなくなり、ついには喜んで自ら生命維持装置の電源を切るのではないだろうか――。
われわれが考えなければならないのは、こうした矛盾がなぜ生じるのかということである。手がかりとなるのは、そもそも人々が「苦痛を除去してほしい」と主張するときの、「苦痛」とは何かということである。
想像してみてほしい。登山の喜びは道中の疲労があるからこそ味わうことができる。勝利の充実感は仲間との不和や諍いを乗り越えて手にしたときほど深くなろう。ところが時間が経過していくと、喜びや充実感は薄らいでいき、かえってその記憶の存在が新たな苦痛の種になることもあるのである。
このことが示すのは、人間的な生における「苦痛」のすべてが、歯痛や拷問のように単純明確なものではないということ、その大半は出来事として経験される全体のごく一側面であって、その一部だけを特定して取り除くことはできないということである。
実際われわれが「苦痛を除去してほしい」と主張するとき、本当に望んでいることは、しばしばまったく別のことであることがある。したがって「苦痛」が存在することを過度に一般化して「悪い」と断言することは、人間の現実に反していると言える(8)。現実における「苦痛」とは、常に、誰にとっての「苦痛」なのか、どのような形で「苦痛」なのか、それがなぜ「苦痛」として感じられているのかといった文脈に即して、個別的に論じなければならない問題なのである(9)。
興味深いことに、ベネターはこうした「苦痛除去の不可能性」について一面では気がついている(10)。ところが彼は、「苦痛」を特定して取り除けないのであれば、やはり例外なく非存在は存在に勝る、そして「存在することは例外なく悪い」という結論へと飛躍してしまう。
しかし、われわれがここから学ぶべきことは別にある。それは【命題】(3)と(4)をめぐる非対称性以前の問題として、人間的現実においては、その大前提であるはずの【命題】(1)がそもそも成り立たないということなのである(11)。
2)「選択の不可能性」という問題
次に指摘したいのは、選択をめぐる問題である。繰り返すように反出生主義は、新たな命の出生を悪だと断じ、一切の生殖を否定する。しかしここには、そもそもわれわれが人類(あるいは感覚を持つすべての存在)の出生をコントロールできるという隠れた前提がある。
もちろんそれは、理念のうえでは可能なのかもしれない。実際われわれはイヌやネコを病院で去勢できるし、そもそも異性と接触することを忌避していれば、子孫が生まれてくることなどありえないはずだからである。だが人間的な生の現実は、やはりこれほど単純なものではないのである。
実際、生の現実に目を向けてみれば、われわれの眼前に広がっているのは圧倒的なまでの選択不可能性であることが分かる(12)。例えばわれわれは、明日誰と出会い、誰と出会わずにすむかを自己決定することができるだろうか。1年後に自身がどのような姿をしており、10年後に何をして生きているのかということを、意思の持ちようによって変えることができるだろうか。
このことは当然、生殖についてもあてはまる。一人で生きられない人間は、望まなくても誰かと関わっていかなければならない。そしてさまざまな巡り合わせによって数多の関係性に巻き込まれていき、たとえ自身で生殖を行わなくとも、さまざまな理由や状況によって、誰かの生殖を助けてしまうこともあるだろう。われわれは忘れているが、歴史的にはつい最近まで、人類は文字通り生殖をコントロールすることなどできなかった。そうでなければ、口減らしのためだといって、わざわざ生まれてきた我が子の首を絞める必要などなかったのである。
またベネターは、人類が絶滅に至るための方法についてあれこれ検討しているが、人類の絶滅など、なおさらコントロールできるような代物ではない。たとえ地球が荒廃しようとも、文明が崩壊しようとも、人類はそう簡単には絶滅しないからである。劣悪な環境のなかでも必ず生き残り、社会を再建しようとする人間がでてきてしまうし、生まれてきてしまうだろう(そうした状況で再興された社会が、現代の価値観からして生存したいと思えるものであるかどうかはさだかではないが)。絶滅を真に成し遂げたいと思うのであれば、われわれはそうした人々を一人一人殺して回り、永遠とも思える徒労の果てに、ようやく目的を完遂できるのである。
物事を理念の世界で完結できると信じている人々の奇妙さは、彼らがしばしば神のごとき万能感に基づいて世界を語ろうとする点にある(13)。彼らはどこか、「あるべき何か」さえ確定できれば、あとは指をパチンと鳴らすだけで、そうした世界を選択できると考えているかのようにさえ見える(14)。
その奇妙さを喩えるなら、明日のわが身さえ意のままにできない人間が、宇宙の存続さえ意のままにできる神の目線に立って、ウマやイルカに向かって、「真理に照らすとあなた方はいますぐ断種手術をすべきだ」と説教して回るがごときものである(ウマやイルカからすれば迷惑な話でしかなく、そのような「真理」につきあう義理もないだろう)。ここでの問題は、選択可能な理念の世界の想像物を、選択不可能性に満ちた現実にそのまま持ち込もうとすることの安易さなのである(15)。
もっとも反出生主義者ならば、次のように反論するだろう。実現が困難であるということは、「真理」を否定する根拠にはならない。実際奴隷制が存在した時代には、少なくない人々が奴隷制の廃止などありえなし、それを批判することには意味がないと考えていた、といったようにである。
だがわれわれは「真理」なるものに対して、とりわけそれを現実に持ち込む際においては、よくよく慎重になるべきではないだろうか。例えばもし、その「真理」が間違いだったと判明したなら、彼らはどうするつもりだろうか。それが理念の世界であれば、前言を撤回するだけで済む。しかし現実で起こしてしまったことは、決して訂正することなどできない。ここでわれわれが想起すべきなのは、歴史上で「真理」とされたもののうち、後に間違いだったと見なされていないものの方が少ないという事実である。例えば何万人もの死者を出したポルポトの改革は、「真理」と見なした歴史法則を現実に持ち込んだ結果でもあったのである。
3.反出生主義の背景にあるもの
1)「反出生主義的心情」の所在
とはいえ本論の目的は、反出生主義を取りあげて、その粗探しをすることでは決してなかった。本論においてより重要なことは、こうした反出生主義の主張について、なぜ今日少なくない人々が共感を覚えているのかという問題である。
これまで見てきたように、確かに反出生主義の新しさは、古代から続く「ペシミズム的言明」を道徳的原理にまで高め、生殖を道徳的な悪だと断言した点にあった。だが人々がその主張に魅力を感じているのは、はたしてそれが理屈として成功して見えるというだけのことなのだろうか。本論が問いかけたいのは、むしろその根底には「反出生主義的心情」とでも言うべきものがあるのであって、その“心情”に寄り添い、それを正当化してくれるからこそ、人々は反出生主義に惹かれてしまうのではないか、ということである。
ここで手がかりとなるのは、前述したシングルトンが挙げている、反出生主義を支持する三つの理由である(Singleton 2021:5-8)(16)。
(1)生まれることで誰かに悪影響をもたらすから(【心情①】とする)
(2)生まれることでたくさんの苦しみを経験するから(【心情②】とする)
(3)子どもを作ることは自分勝手なことだから(【心情③】とする)
以上の指摘は、さまざまな点で示唆に富んでいると言える。まず【心情②】からは、反出生主義の背景にはやはり「ペシミズム的体験」が深く結びついているということが分かるだろう。反出生主義者の主張は、しばしば「ハエの入ったスープ」や「一点の汚れもないキャンバス」によって喩えられる (17)。つまりどんなスープも一匹ハエが入っていれば台無しになる、純白なキャンバスも一点の汚れがあれば台無しになるといった具合である。
もちろんこうした比喩からは、彼らがどこか過度な潔癖さを求めていることも示唆できる。だが重要なことは、それ以上に彼らが、生を例外なく「ハエだらけのスープ」や「汚れに汚れたキャンバス」だと感じているということの方だろう。つまり彼らは、そうしたスープを飲み続けることにも、キャンバスを正視し続けることにも耐えられない、それならいっそのことスープもキャンバスも存在しない世界の方が良いはずだ、と主張しているのである。
問題となるのは、【心情①】の扱いについてである。シングルトンはその「悪影響」の例として、具体的には絶滅動物や人間同士の大規模な争いなどをあげている。しかし人々が反出生主義に魅せられる契機となりうる「悪影響」には、より身近な問題が含まれているのではないだろうか。
例えば、人は生まれてしまうことによって、誰かを傷つけてしまったり、誰かを不幸にしてしまったりすることもある。そしてそのことを悔いること自体は、確かに「ペシミズム的体験」の範疇なのかもしれない。しかし現代社会においては、どこか他人に余計な負担をかけ、不快な思いをさせることへの異様な怖れ、何かに躓いたり、誤ったりすることによって他人から否定されることへの異様な不安で溢れかえっているようにも見える。つまり現代を生きる人々にとっての「ハエ」や「汚れ」には、自身がもたらすかもしれない、あらゆる迷惑や、不快や、わざわいなどが含まれているのではないかということである。
次に【心情③】であるが、この問題は、しばしば「同意不在論」という形で取りあげられてきた(18)。つまり、生まれてくる人間は決して同意して生まれてきたわけではない。その意味において、生殖はある種の暴力、反道徳的な行為なのではないかということである。しかしこの心情からうかがえるのは、それとは異なる別の論点である。
手がかりとなるのは、むしろベネターも用いている「ロシアンルーレット」の比喩だろう(Benatar 2008: 92=2017: 102)。例えばここに6発中、あたればとんでもない不幸に見舞われるとされる弾が入ったロシアンルーレットがあるとする。このときあなたは、見知らぬ誰かの眉間に向かって、それを撃ち込むことができるだろうか。何ものかを誕生させるということは、実はそれに等しい行為である。たとえあなたに子どもがほしい理由があるからといって、それはあなたが行おうとしている行為に見合うほど正当なものなのだろうか。それはあなたの単なるわがままや身勝手さではないのか。彼らが感じているのは、おそらくこうしたことだからである。
人々が反出生主義に惹かれるのは、一連の理論が、人々の抱えるこうした心情に寄り添い、それを正当化してくれるからであるように思える(19)。そしてそうだとすれば、枠組みや論理の正当性をめぐる論争をいくら繰り返したところで、それに惹かれる人々が救われることもないだろう。真の問題は、これらの心情に込められている苦しみの意味、苦しみの理由にこそあるからである。
2)「無限責任」の牢獄と「自立の不可能性」という問題
ここで改めて考えてみたいのは、先に見た【心情①】と【心情③】が、歴史的には最近になって現れてきたものではないかということである。
例えば口減らしが行われていた時代、はたして人々はそのような悩みに苦しんでいたのだろうか。ただでさえ隣人と関わり、協力しなければ生きていけなかった時代、良くも悪くも人が他者に影響を与えるということは、あまりに自明で問われることさえなかっただろう。
自身の不甲斐なさに「ペシミズム的体験」をすることはあっても、それは誰もが経験しうる卑下や負い目の範疇であって、そこではお互い様だという基本認識が共有されていたからである。同様に子どもを産むという行為は、そもそも個人的な問題であるとは見なされていなかった。それはときに世間の目なざしやしがらみのためであり、現実問題としても、自分以外のさまざまな人々のためであるとの共通認識があったからである。
したがってここで問うべきことは、いまを生きる人々が、なぜこれほどまでに徹底して自らの生に対する責任を負わされているのか、いや、生に対する責任を負わねばならないと感じているのかということである。誰とも関わりを持たずに生きることなどわれわれにはできないし、ましてや関係性がもたらす影響のあり方をコントロールすることなど不可能である。同じくわれわれは、いまなお生殖を意のままにコントロールなどできていないし、生殖が純粋にその人だけのためではないという事実も少しも変わっていない。
それにもかかわらず、われわれは自らの行動が引き起こすあらゆる責任を、自分一人で負うべきだと想像してしまう。生まれ来る誰かの人生の全責任を、この私こそが負うべきだと考えてしまう。だが、考えてもみてほしい。そのような「無限責任」など、そもそも生身の人間が背負えるものなのだろうか、と。
こうしてわれわれは、一連の議論に隠されたもうひとつの前提に直面することになる。それは、自身の生を他者の生と切り分けて考えることが可能で、自身のあらゆる行為の帰結を自らの責任とすることができるとする前提である。そしてその前提は、これまで見てきた「苦痛除去の不可能性」や「選択の不可能性」と同様に、ことごとく人間的現実に反したものなのである。
では、この「自立の不可能性」をめぐるわれわれの錯覚は、どこからもたらされたものなのだろうか。
前述のように、人々が「苦痛の除去は可能である」と錯覚したのは、苦痛のなかに、歯痛や拷問など、実際に特定して取り除くことが可能なものが含まれていたからであり、それが理念の世界において、言ってみれば拡大解釈されてきたからであった。
同様にして、現代のわれわれは、高度な社会システムに依存することを通じて、自己決定がある程度保障された環境を生きている。そのため誰とも直接関わらずに、一人一人があたかも「自己完結」して生きられるような気がしてしまうのである (20)。それぞれの生が自立していると想像されるために、われわれは生の帰結の全責任を一人で負うべきだと想像してしまう。だがわれわれの眼前に広がっているのは、依然として圧倒的なまでに自立不可能な数々の人間的な現実なのである。
したがって問題の根幹にあるのは、ひどく歪んだわれわれの「世界観=人間観」だと言うべきではないだろうか。いつの日からかわれわれは、現実にはありえない「あるべき人間」、「あるべき社会」、「あるべき世界」を想像し、それを現実に強要するようになった(21)。そして生の現実においては、他者に影響を与えずにすむことも、自身の生の全責任を背負うこともできやしないのに、誰も苦しめず、誰も傷つけず、誰にも迷惑をかけまいとして、その理想と現実のはてしない乖離さえも自己責任として背負おうとしている。だがどれだけ現実を否定したところで、そのような「あるべき世界」が現実に訪れる日など来ることはない。人々が「真理」に即した存在であろうとしてもがけばもがくほどに、人々はかえって現実に裏切られることになるのである。
要するに、この恐るべき現実否定の無間地獄こそ、「無限責任」という名の牢獄の背後にあるもの、そしてあの心情に隠された苦しみの根源にあるものではないか、ということなのである(22)。
3)〈信頼〉なき世界のゆくえ
それゆえここで気づかされるのは、そもそもわれわれは問いの立て方を間違えてきたのではないかということである。
例えば反出生主義者は、他者に悪影響を及ぼし、新たな命を誕生させることに「正当な理由がない」と非難する。しかしすべての行為に正当性を求めるのであれば、われわれは他の命を奪って食べることにも、病原菌を駆逐することにも、そして空気を吸うことにさえも正当な理由を示さなければならなくなる。
また反出生主義者は、生殖を含め、われわれが結局他者を手段として扱っていると非難する。しかしグローバル社会に埋め込まれた80億もの人々のうち、生を実現する手段として他者の助けを必要としていない人間など一人として存在しない。これらも結局、一連の議論で何度となく見受けられてきた拡大解釈のひとつに過ぎないのである(23)。
われわれが問わねばならなかったのは、むしろわれわれがどうしようもなく他者に影響を与えてしまうという現実、どうしようもなく他者の助けを必要としてしまうという現実を前に、いかにして人はより良く生きることが可能なのかということではなかっただろうか。そこにある負い目と残酷さとを否定することなく、それでも前を向いて、一人一人がより良き生を引き受けていけるための手がかりこそ、われわれが必要としているものではなかっただろうか。
思えば近代的な医療が普及する以前、人は怪我や病や栄養失調などによって簡単に命を落とした。新たな命は、端的に言って、残された者たちが生きていくために必要としていたのである。しかし同時に、だからこそ人々はこの世界に生まれてきてくれた新たな命に感謝し、生まれ来る人々が困らぬように手を尽くすべきだとする倫理を構築してきた側面がある(24)。人間は、その始まりから集団的な生存の実現を目指して生きてきたのであって、互いの生が互いの生存を支える契機になるということは、世代内においても、世代間においても、人間存在が生きることそのものだったのである。
結局のところ、われわれが見失っているものとは、〈信頼〉なのではないだろうか(25)。それは、より良く生きようとしてもなお意のままにならない現実を前に、自身の苦しみは決して自身だけのものではないと思える〈信頼〉であり、たとえ自身が不甲斐なくとも、そうした自身を受け入れ、居ても良いと言ってくれる場所があるはずだと思える〈信頼〉である。そして、たとえ目に見える成果が得られなくとも、より良く生きようとした人々の痕跡には意味があると思える〈信頼〉であり、来たるべき何ものかもまた、そうして去っていった人々の生き方をいつかは祝福してくれるだろうと思える〈信頼〉である。
現代を生きるわれわれは、結局何ものをも〈信頼〉していないし、〈信頼〉することができない。だからすべてを一人きりで背負おうとするしかないのである。そもそも背負えるはずのないものを背負おうとして、結局は破綻してしまうのである。
多くの人々は誤解しているのではないだろうか。反出生主義者は、決して無責任な人々なのではない。おそらく誰よりも責任を感じるからこそ、そして真面目に生きようとするからこそ、人々はかえって反出生主義者になる。世界や人間を心底憎んでいるから、人々は反出生主義者になるのではない。おそらく誰よりも世界や人間を祝福したいと願い、その高すぎる理想に屈折したからこそ、人々は反出生主義者になるのである。
4.おわりに
以上を通じて本論では、反出生主義に含まれる三つの実践的不可能性について取りあげつつ、心情として、なぜ少なくない人々がその主張に惹かれてしまうのかという問題について掘り下げてきた。
繰り返すように、反出生主義の論理は、結局のところ理念の世界においてのみ輝くものであって、とても人間の現実に耐えうるものではなかった。われわれが何をどのように語ろうと、人類は続いていくし、絶滅することもないだろう。それはわれわれが、人生を、そして世界をどれほど憎んでいても、明日は来てしまうし、世界はなくならないのと同じである。
本論が主張したかったのは、ならばその現実に一度は向き合い、寄り添ってみるべきではないかということである。苦痛の除去も、完全な選択も、完全な自立もありえない生の不可能性を前提として、それでもより良く生きるとは何かということこそ、真に問われるべきことではないかということである。
反出生主義者の苦しみは、「世界観=人間観」の歪みによって自ら生みだしてしまった恐るべきデーモン――そもそも背負えるはずのない「無限責任」という名の――がもたらした自縄自縛の苦しみである。
しかしその背景には、根源的な〈信頼〉の不在という、個人の次元ではどうにもならない問題があった。したがってわれわれの社会が、この先も互いの生の責任を分け合おうとすることなく、〈信頼〉を育くむことを怠り、ありもしない自立の幻想に浸り続けるのだとしたら、人々はますます反出生主義者に転向せざるをえないだろう。
ここでは最後に、本論において十分踏み込めなかった論点を二つだけ取りあげておきたい。
ひとつ目は、こうした現実離れの「あるべき人間」という理念に囚われ、「無間地獄」に陥っているのは、はたして反出生主義者だけなのかという問題である。
実際他の人々も同じではないだろうか。別の命を奪って生きること、生まれてしまったこの時代を生き、与えられた環境、与えられた身体を死ぬまで背負っていかなければならないこと、しがらみのなかで生きざるをえないために、ときに望まない自分を演出したり、望まない共同を引き受けたりしなければならないこと、現代を生きるわれわれは、そのひとつひとつに破滅的なまでの理不尽さを感じてしまう。
だが、人間の生というものは元来そうしたものではなかったか。意のままにならない現実に向き合い、現実とともに生きる力を、われわれ現代人はますます失いつつあるようにも見えるのである(26)。その意味において、「世界観=人間観」の歪みはこの時代を共有する人々全体の問題である。そうした〈有限の生〉を生きるための作法や知恵こそが、改めて求められていると言えるのである。
ふたつ目は、人間が生きることの究極的な意味や目的など、結局あるとは言えないという主張についてである(Benatar 2008: 82-83=2017: 93)。
実は筆者は、この主張については基本的に同意している。しかし反出生主義の主張が奇妙なのは、それを宇宙的な次元で証明できないからといって、直ちに生は続けるに値しないし、生まれてくるにも値しないという結論へと飛躍してしまうところである。
この背景には、おそらくキリスト教(一神教)文化圏特有の事情があるように思える。つまり人間は神の姿を型取って創造された特別な存在であり、そのような被造物に、神によって与えられた特別な使命や目的がないわけがない、といった信念の裏返しなのではないか。
したがってその発想は、全人類にとって決して普遍的なものではなく、われわれはそのことにいちいちうろたえる必要などないのである。
生きる意味とは、生の当事者たちによって見いだされてきた、どこまでも人間的な世界の産物に過ぎない。それでもそれがかけがえのないものだと言えるのは、何ものかが見いだした言葉や、美や、役割や、願いが、来たるべき別の何ものかを勇気づけ、彼らが再びより良く生きるための意味を見いだす拠り所として、はての先まで受け継がれていくためである。〈信頼〉とは、目で見て触り確かめることができないものを、それでも信じることを指す。そして自らは前を向いておのれの道を進んで行くことを意味している。生きる意味なるものがあるとするなら、それはそうした〈信頼〉のなかからこそ見いだされることになるだろう。
〔注〕
反出生主義をめぐる日本の学術動向については、森岡(2021b)が詳しい。反出生主義は2010年代になって急速に広がり、2017年にはベネターの邦訳書が刊行されたり、2019年には『現代思想』(青土社)が特集を組んだりするなどして注目を集めている。
森岡も、後に反出生主義を「すべての人間あるいはすべての感覚ある存在は生まれるべきではない」(森岡 2021b:52)と主張するものとして再定義し、ベネターの立場を「狭義の反出生主義」と位置づけている。
中川(2020)は、「(新たな存在は)生まれてくるべきではない」という命題と、「(私が)生まれてこなければ良かった」という命題の関係性を分析哲学的に考察し、少なくとも後者から前者を導くことは困難であるとの結論を述べている。ただし反出生主義的な思考において、両者に結びつきがあることは間違いなく、本論では、そこにあるものこそ「世界観=人間観」の歪み、そして後に見る「無限責任」という信念なのではないかと考えている。
以下の論点は、ベネターが前掲書(Benatar 2008=2017)の第二章で展開した議論を筆者なりにシンプルな形で整理したものである。ここでベネターはさまざまな反論を想定して精密な議論を展開しているが、本論での説明は必要最小限のものに留めた。
これ以上は踏み込まないが、ベネターの非対称性が誤りだと主張する試みは、成否は別としていくつも存在する。例えばT・メッツ(2019)は、ベネターが非対称性の根拠としてあげた社会通念が、苦痛の不在は「悪くない」、快楽の不在は「良くない」とした場合でも十分に説明できるとしている。
反出生主義が思考実験として成功している理由は、生きること自体が根本的に苦しみを伴うという明白な事実がある一方で、その主張の背後に「苦痛のない世界こそが正しい世界である」との隠れた前提を置いているためである。この主張に同じ土俵から挑むのは得策ではなく、われわれはその背後に潜むものにこそ目を向けるべきなのである。
筆者は以前、この「脳人間」世界の思考実験を別の角度から踏み込んで論じたことがある(上柿 2021b)。
このことは、功利主義が万能ではないことを示すひとつの根拠にもなるだろう。功利主義が有効なのは、数値化可能な政策判断といった限定された局面であって、それを生の本質にまで拡大解釈してはならないのである。
したがって【命題】(1)を否定したからといって、ただちにいじめや拷問が正当化されるということにはならない。なお、実はベネターの前掲書には苦痛の不在が「悪くない」と仮定した場合についての言及がある。しかしベネターはこのことを考察に値するものでさえないと考えていたようである(Benatar 2008: 39=2017: 49)。
前掲書(Benatar 2008=2017)の第三章における記述を参照のこと。
厳密に言うなら、【命題】(1)も【命題】(2)もともに、「良くも、悪くもない」というのが本論の立場である。
このように主張したからといって、それゆえ犯罪行為であっても正当化されるということにはならない。むしろ刑法において常に情状酌量の余地が検討されるのは、われわれの選択行為がそもそもそうした不可能性を帯びている側面があるからである。
吉田(2021:85-86)は、「デジタル化」された世界の中で完全な個の自由を成し遂げたつもりでいる人々のことを、皮肉を込めて「世俗的な神」と呼んでいる。「為したいことを為せる神」にでもなった気でいる人々は、その実「為せることのみを為したいと思い込んでいる矮小な方向指示器」のごとき存在に過ぎない。それと似て、「万能であることはすなわち虚無を意味して」いるのは、理念の世界に住む人々もまったく同じなのである。
品田(2021)は、反出生主義をめぐる諸論点を、人類を滅亡させる力を持つ魔王と、魔王の前に集められ、その是非について討論させられる10人の人間たちをめぐる物語として描いた。同書の舞台設定は、こうした点からも示唆に富んでいると言えるだろう。
この意味での不可能性として酷似しているのは、「命あるものを殺して食べることは道徳的な悪である」という理念の世界の命題を、そのまま現実に持ち込んで、実際に人々の摂食行動を禁じようとする場合などである。
反出生主義者の心情を理解するための手がかりとして、以下のサイトも有益である。「無生殖協会ウェブサイト」(2022/10/07閲覧)、「An Antinatalist Handbook(日本語版)」( 2022/10/07閲覧)。
前者は品田(2021:29)、後者は森岡(2020:54)を参照。ただし品田は、この喩えを必ずしも反出生主義への批判としては用いていない。
例えば森岡(2020:299-300)を参照。また本論ではこれ以上は踏み込まないが、この問題は、「非同一性問題」――たとえ未来に生まれてくるものに対して危害を加える行為であっても、その行為を行わなかった場合にはまったく異なる存在が誕生することになるため、その行為は単純に悪いとは言えなくなる――にも繋がる論点でもある(加藤 2019、 Singleton 2020)。
稲垣(2022:42)は、反出生主義の広がりについて、人々が自らの生の苦しみや残酷さを前にしたとき、「絶滅」や「終わり」を想像することで、かえって力みすぎた心の荷が降ろされ、「絶妙な力加減」のもとで明日を生きられる効果があるからではないか、と指摘している。本論の枠組みから言えば、ここでの「力み」こそ、まさしく「無限責任」がもたらす重圧に相当しよう。
筆者はこれまで、この問題を〈生の自己完結化〉と呼ぶ形で詳しく分析してきた(上柿 2021a、 2021b)。
これ以上は踏み込めないが、この問題の根底には、西洋近代哲学そのものが抱えてきた深刻な矛盾があるように思える。それはJ・J・ルソー(J. J. Rousseau)からI・カント(I. Kant)に至る系譜によって確立されてきた、「われわれはあるべき理念に相応しく現実を書き換えるべきだ」とする特殊な信念の問題である。筆者はそれを〈無限の生〉の「世界観=人間観」と呼び、これまで考察を試みてきた(上柿 2021b)。
こうした心情の背景として、確かに先行きの不透明さや経済格差といった問題も関わりがあると言えるだろう。しかし振り返れば、この30年間常に世の中は不透明であったし、これだけではなぜ格差社会の上位にも反出生主義者が存在するのかということが説明できないだろう。
前述した功利主義の問題と同様に、ここでの手段と目的とをめぐるI・カント(I. Kant)の枠組みもまた、拡大解釈を行うことで、途端に理念と現実とをめぐる矛盾を引き起こすことになるのである。
もちろんすべての人々が“善良”であるはずもなく、その試みの大半は、振り返ってみれば空回りに見えるものばかりなのかもしれない。しかし未来を予見できない人間存在にとってできることとは、結局それぐらいことではなかっただろうか。
〈信頼〉とは、盲目的に何かに身をゆだねることではなく、あやふやで、触れて確かめることができない何かを、それでも信じられることを指す。その願いは結果的に叶わないかもしれないが、叶わなければ仕方ない、しかし可能性がある以上そうであることを願いたい――そういった心情である。〈信頼〉には心の強さが求められるが、それ以上に求められるのは、人々が〈信頼〉を共有できるだけの社会的土壌、人間的基盤だろう。
増田(2020)はこの問題を、理想のレールを絶え間なく追い続けなければならない徒労から、人々が自身の居合わせる環境に生きること、環境に存在することの「重さ」に耐えきれなくなる問題として描いている。このことは、現代社会に拡大する自己肯定感の慢性的な低下の問題とも無関係ではないだろう。われわれが〈信頼〉できないのは、自分自身でもあるのである。
〔参考・引用文献〕
稲垣諭(2022)『絶滅へようこそ――「終わり」からはじめる哲学入門』晶文社
上柿崇英(2021a)『〈自己完結社会〉の成立――環境哲学と現代人間学のための思想的試み(上巻)』農林統計出版
上柿崇英(2021b) 『〈自己完結社会〉の成立――環境哲学と現代人間学のための思想的試み(下巻)』農林統計出版
加藤秀一(2019) 「「非同一性問題」再考」『現代思想』、山口尚訳、青土社、vol.47-14、pp.136-145
品田遊(2021)『ただしい人類滅亡計画――反出生主義をめぐる物語』イースト・プレス
中川優一(2019)「人生における「悲哀」と「あり得たはずの未来」」『現代生命哲学研究』、第8号、pp.21-32
中川優一(2020)「産むことと生まれてきたこと――反出生主義における「出生」概念の考察」『現代生命哲学研究』第9号、pp.54-79
増田敬祐(2020)「存在の耐えきれない重さ――環境における他律の危機について」『現代人間学・人間存在論研究』大阪府立大学環境哲学・人間学研究所、第4号、pp.313-378
水島淳(2021)『ひよこでもわかる反出生主義入門』(Kindle版)
メッツ・T(2019)「生まれてこないほうが良いのか?」『現代思想』、山口尚訳、青土社、vol.47-14、pp.94-113
森岡正博(2020)『生まれてこないほうが良かったのか?――生命の哲学へ!』筑摩選書
森岡正博(2021a)「デイヴィッド・ベネターの誕生害悪論はどこで間違えたか ――生命の哲学の構築に向けて(12)」『現代生命哲学研究』、第10 号、pp.1-38
森岡正博(2021b)「反出生主義とは何か――その定義とカテゴリー」『現代生命哲学研究』、第10 号、pp.39-67
吉田健彦(2021)『メディオーム――ポストヒューマン時代のメディア論』共和国
Benatar, David ([2006] 2008). Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence. Oxford University Press(D・ベネター(2017)『生まれてこない方が良かった――存在してしまうことの害悪』小島和男/田村宜義訳、すずさわ書店)
Singleton, Kei. 2020. Review of Suffering vol.1: Anti-Natalism (Japanese Edition). TheRealArg Books
Singleton, Kei. 2021. 『[超要約]アンチナタリズム入門』(2022/10/07閲覧)
(出典)上柿崇英(2023b)「反出生主義における三つの実践的不可能性と「無限責任」の問題――心情から読み解く〈信頼〉の不在とその行方」『共生社会システム研究』、共生社会システム学会、Vol.17 No.1、pp.77-100
