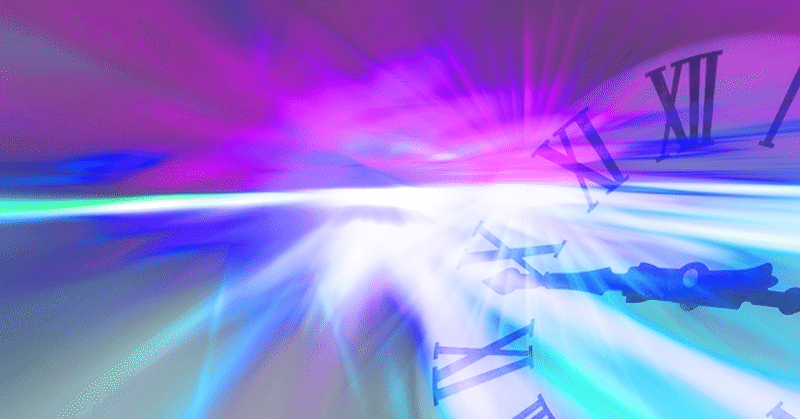
【長編小説】サイクロジック 第2話「Electric Carnival」(1)
眩い快晴が未来学園を照らし上げる。
いつもならば鬱陶しく感じるほどのこの暑さだが、今日この日、文化祭当日に限ってはその温度は祭りを盛り上げるための一つのシチュエーションにしか成り得ない。
『これより、第八回未来学園祭を開始致します』
放送部のアナウンスが大量に設置されたスピーカーによって校舎全体に響き渡り、それと同時に未来学園の正門が開き始めた。
「――さあ、まずはわたがしを買いに文化部A棟へ向かおうよ! ほらほら、こんなところでへばってちゃ駄目だよ? 何てったって誠也君はボクの彼氏なんだからさ!」
喧噪が聞こえ始める中、俺は深山先輩に右手を引っ張られながら見回りという名の食道楽の付き添いを行っていた。
深山宮子(ふかやまみやこ)。
未来学園三年一組の生徒であり、風紀委員長でもある彼女とこのように行動を供にしているのには理由があった。
俺は溢れ出る汗を拭いながら二週間前に突然開かれた文化祭実行委員と風紀委員合同による緊急会議のことを思い出していた。
◇
俺の脳裏を、ノイズが往復し続ける。
『ねえ二人とも、どうしよう』
『どうしたというのですか。まさか会議で用いるスライドを用意していなかったなんて言わないでしょうね』『どうしましたか、宮子先輩』
『……』
『……まさか』『……先輩?』
『スライドを用意するの忘れてたや』
俺の脳裏を、ノイズが幾度も往復し続けている。
『……宮子、あなた』『宮子先輩、どうして今の今までそれを黙っていたのですか!?』
『し、仕方ないじゃん! 昨日の夜いきなり顧問の先生から電話がかかってきて「原稿を送るからスライドを作成して明日発表してくれ。いいか、パスワードは一回しか言わないからよく聞いておくように」なんて言われてもさ! ボク寝惚けてたもん! デスゲームで一度しか言ってくれないパスワードじゃないんだから聞き逃すに決まってるじゃん!』
『パスワードはどこかに保存されていないのですか?』『……』
『分かんない。先生用の共有フォルダのどこかにはデータがあるはずだけど……』
『絶望的ですね』『……』
『……ごめんなさい、どうしよう』
『……』『……』
『 (´;ω;`)ブワッ』
「……なあ洸一、風紀委員長の本名って確か深山宮子先輩、だったよな?」
「そんな名前だった気がするが、それが一体どうかしたのか?」
会議の場には程よい緊張感があるものの喋ったらいけない程のものではない。空気の淀みを見つけてクラス委員長の洸一に小声で話しかけると、退屈していたのか素早い返事が帰って来た。
「いや、何でもない。少し気になっただけだ」
ノイズが再び始まった。
『……かみのん? りんちゃん?』
『……プレゼンの内容は何となく予想できるので即興でスライドを作ります。無茶を言いますが、りんはどうにかしてパスワードを入手して原稿を手に入れて下さい』『了解です』
『……二人とも、ありがとう!』
会話から幾秒も経たぬ内に、一人の女子生徒が視線を壇上から逸らさずに片手で電子携帯を動かし始めた。俺の記憶が正しければその女子生徒の名前は未来学園三年生の副風紀委員長、神野真紀先輩である。神野先輩、つまりかみのん。
同じようにソワソワとし始めたのは先日、都市伝説研究サークルで知り合ったオレンジ色の髪の少女、潴溜りんである。潴溜りん、つまりりんちゃん。
心なしか、壇上で説明を続ける教師の隣で静かに座っている深山先輩の顔色が少し晴れたように見える。ガラガラと崩れていく風紀委員長の完璧なイメージを俺は一緒になって能動的に破壊する。どうやら完璧な風紀委員長という虚像は神野先輩と潴溜が作り上げたものだったらしい。
「文化祭実行委員と風紀委員の諸君、今日は休日だというのに集まってもらって申し訳ない」
ようやく本題に入り始めた教師の言葉に、壇上の深山先輩の顔が一気に強張る。どうやら彼女の出番が近付いてきたらしい。
「本日君たちに集まってもらったのは他でもない、先日未来工業本社において何者かが社長室に侵入するという事件が発生した。未来警察はⅠSコーポレーションの人間が未来工業の技術力を狙ったものと見ている。我が校は未来工業と密接な関係にあり――」
「へー、未来区に潜伏する企業スパイなんて噂もあながち間違いってわけじゃなかったんだな。……誠也、一体どうしたんだ?」
ノイズに少し集中力を傾け過ぎていたらしい。様子がおかしい俺を心配してくれたのか、洸一が俺の顔をじっと覗き込んでいた。
「何でもない。ちょっと考え事をしていただけだ」
夏休み最終日。洸一との一件から落雷の影響で『メッセージの文章を盗み見ることができるようになった』ことが発覚した俺は、時折脳裏にこうやってノイズが走るようになっていた。
ノイズとはいってもそれはあくまで突発的なもので、そこまで酷いものではない。しかし今は多くの生徒が会議に集中していることが災いしたのか、深山先輩たちのグループメッセージの内容だけがダイレクトに頭に流れ込んできているらしい。面識は潴溜以外にないものの、ここまで事情を知ってしまったら情が移るというものだ。
『――私事で申し訳ないのですが、未来学園の職員用の共有フォルダをクラッキングしてもらえないでしょうか』
そんなことを考えていた瞬間、俺の脳裏をとんでもないノイズが走り抜けていった。
『ファイルの入手に成功しましたので、神野先輩の電子携帯に送信しておきました』
『ありがとう。よく入手できましたね、りん』
『私の身内にクラッカーの名手がおりますもので、協力を要請してクラッキングして頂きました。借りを作るのが少々面倒ですけどね』
『ごめんねかみのん、りんちゃん! 助かったよぉ』
『お礼を言っている暇があったらあなたは早く原稿に目を通しなさい。あなたのアカウントにログインしておいたのでプレゼンのタイミングで配布できるよう私はギリギリまでスライドのクオリティを上げておきますから』
『待って待って! ちょっと待って!』
「――以上の事情により、今回の文化祭においては文化祭実行委員と風紀委員合同による見回り活動を行うことになった。見回りについては、風紀委員長の深山宮子さんに説明を行ってもらう」
教師が深山先輩に促すと、最前列に座っていた深山先輩がゆっくりと壇上に登った。
「えーっと、皆さんこんにちは。風紀委員長の深山宮子です! 私からは文化祭当日に文化祭実行委員と風紀委員合同で行われる見回りについての詳しい説明を行わせて頂きます。それではスライドを配布しておりますので、共有フォルダからダウンロードを――」
深山先輩の発言したタイミングに併せて、共有フォルダにスライドがアップロードされる。
スライドは完璧に纏められており、とても即席とは思えないレベルに仕上がっていたところを見るに神野先輩の要領の良さを感じさせる。
そして深山先輩の説明が終わると同時に会議はつつがなく終了し、生徒たちは帰路に向かって散り散りに歩き始めた。
「誠也、俺たちもそろそろ帰ろうぜ」
「ああ。少し待って――」
先ほどのメッセージの内容について軽く尋ねようと潴溜を探して席を立ち、目立つオレンジ色の髪を視界に収める。
「……あっちか」
教室の奥で深山先輩や神野先輩と談笑している彼女を見付けて声をかけようと近付いていく。
先程のメール。
その動機はバカバカしいものでありながら、アレはれっきとした犯罪行為だ。そして俺の脳裏には先日、都市伝説研究サークルでジルドから聞いた二つ目の都市伝説の内容がフラッシュバックしていた。
『未来区に潜伏する企業スパイ』
潴溜はもしかしたらその一味であるか、もしくは何らかの繋がりがあるのではないか?
近付いてからどうやって先ほどのメールの内容について尋ねようかと思考を巡らせていると、潴溜よりも先に思いがけない人物が俺に話かけてきた。
「――ねえ、君、名前は? ボクは三年の深山宮子っていうんだけど」
まさかの人物からのコンタクトに若干戸惑いながらも、自分の名前と学年を反射的に脳から捻り出す。
「俺は二年十五組の天野誠也です。今日は文化祭実行委員として――」
肩まで伸ばしたゆるふわのミディアムパーマに、爛々とした深山先輩の笑顔が視界いっぱいに映り込むと、
「――一目惚れしました。突然ですが、ボクと付き合ってください」
彼女はまるで気心の知れた友人に挨拶するかのように俺に向かってそう告げた。
「は……?」
まさかの出来事に教室に僅かながらに残っていた生徒たちの挙動が止まる。
思わずフリーズする俺の身体をよそに、深山先輩が心配そうに小首を傾げる。そして、合点がいったようにぱっと目を輝かせると、再び口を開いた。
「――一目惚れしました。突然ですが、ボクと付き合ってください」
「……いや、決して聞き逃したわけではないんですけど」
ゲームのバックログ再生じゃないんだから。
◆
時は戻り、同時に未来学園高等部二年十五組の教室へと場面は移る。
二年十五組の出し物は『ギャルゲー式メイド喫茶』。これはクラス委員長である洸一の打ち出した肝入り企画であり、洸一曰くリアルギャルゲーとのことである。一体何を言っているのかは分からないが、教室内は人でごった返しているところを見るにかなり秀逸な企画内容だったのだろう。
ギャルゲー式メイド喫茶、これはメイドとして働くクラスの女子たちのメイド服に『幸福指数の計量化システム』を搭載した小型装置をリンクさせ、メイドが喜ぶような対応を見せれば幸福指数が上昇し、その度数に応じて景品が貰えるというギャルゲー的なレクリエーション要素を含んだメイド喫茶、らしい。
「お、帰ってきたか誠也。こっちはかなり盛況だぜ」
執事服で受付の後ろにある景品を整理していた洸一が汗だくの俺にタオルを投げ入れてくれる。
「悪いな任せっきりにして。すぐに着替えを済ませるから休憩しておいてくれ」
「仕方ねえって、今の今まで見回りだったんだろ? ……そういえば、深山先輩とは結局付き合ってるのか? どうせ一緒に過ごしてたんだろ」
「……どちらにせよいきなりだったからな。とりあえず文化祭が終わってから返事をするということにしてもらっていたんだがどうやら深山先輩には上手く伝わらなかったらしい」
「はっ、煮え切らねえ奴だな。とっとと付き合っちまえばいいじゃねえか。……けど、おかしいよな。どうしてか俺はすぐに答えを出せなかったお前の気持ちが何となく分かるような気がするんだ」
「……ああ、そうだな。何故か俺はすぐに返事をすることができなかった。……大会に出場できなかったせいなのかは分からないが、心の中にぽっかりと大きな穴が開いているんだ」
俺はそう言うと、黙って洸一の隣で作業を行い始めた。
◇
「まあ、何にせよだ。お前と深山先輩のカップルを俯瞰で観た俺の見解を示そうじゃないか」
午前の部の日程が終わり、つかの間の休息を得た俺たちは二年十五組の教室で休んでいると、突然洸一が謎の講釈を垂れ始めた。
「……というと?」
だからといって洸一が大声で俺の恋愛事情を教室中に垂れ流す理由にはならないのだが、身も心も疲れ切っているのでもうあまり深く考えないことにする。
「――深山宮子は、ボクッ娘だ」
「それがどうかしたのか?」
「よく聞け誠也、これは漫画やアニメの世界じゃないんだ。ボクッ娘なんて自然に淘汰され、死滅していく存在なんだ」
「けど俺らの周りにも何人かいるだろ。陸上の高橋とか、このクラスで言えば篠崎とかさ」
「いいか誠也。リアルに存在するボクッ娘は2つのパターンに分けられる。それは天然モノと養殖モノだ。養殖モノは自分の容姿と行動に明確な自信を持っていてあえてボクという一人称をファッションやキャラ付けとして使用しているパターンで、それに対して天然モノは似合っていて可愛いから誰からも注意されず、現在まで使い続けているという奇跡のパターンだ。お前の挙げた二人は俺の見立てでは前者だな」
洸一が聞き耳を立てていたクラスメートの女子に後頭部を思いっ切りはたかれる。遠目をやるとギリギリ聞こえそうな位置で篠崎が接客していた。
「じゃあ深山先輩もその養殖モノの可能性が高いということか?」
「いいや違う、俺の見立てでは深山先輩は後者だ」
「……けどお前、さっき自分で天然モノは奇跡のパターンだって言っていたじゃないか」
「ああそうだ、考えてもみろ。幼い頃から男子に混じって遊んでいたせいか、一人称が自然とボクとなった女子は少なからず存在する。しかし彼女たちは成長し、やがて女子だけのグループで過ごすことが増えていく。そんな中でも鉄の意志を持ってボクという一人称を使い続け、かつそれが似合っていて可愛いから誰からも注意されず、現在まで使い続けているという奇跡の天然モノ。……それが深山宮子という在かもしれないんだ」
俺は洸一の打ち出した非の打ちどころのないボクッ娘理論に何も口出しすることができず、かといって反論する気もさらさらないのでただただ頭を縦に振るばかりだった。
◆
「――二週間、持たなかったか」
「気を落とさないでください園宮先輩、私もまさか宮子先輩と天野先輩がこんなことになるなんて想像だにしていなかったものですから」
「この世は残酷なものね、りん。結局夢でご飯は食べられないということかしら」
「……校舎、燃やしたりしないでくださいね? 園宮先輩はもう学割なんて効かないんですから」
「けど、おかしいわね。アタシが目を光らせていたうちは誠也に浮いた話なんて一つもなかったっていうのに急にこんなことになるなんて」
洸一の演説の終盤、後ろのテーブルでそんな会話が耳に入った気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
