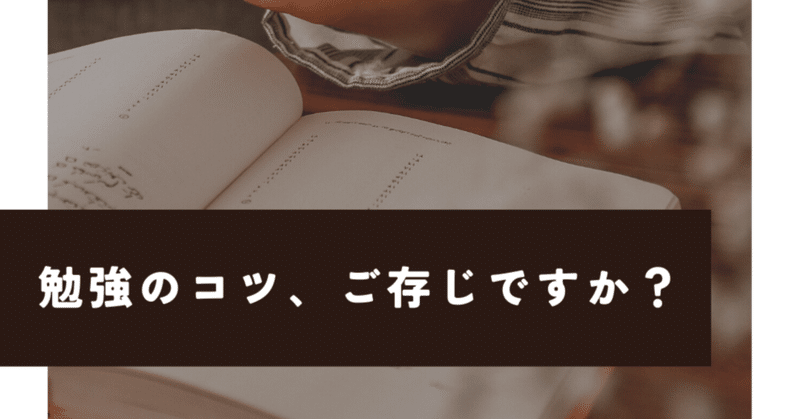
難関資格に上位1割で合格できる「資格勉強に向けて最初にやるべきこと」3選
おはようございます。現役信用金庫マン 兼 中小企業診断士事務所代表の山西です。
さて、前回、前々回と、起業する人や経営者にオススメの資格をご紹介いたしました。
言うまでも無く、理論と実践は両輪のため、経営者として実務を積むことと併せて、経営の基礎知識を習得する必要があります。
実践なき理論は空虚であり、理論なき実践は無謀である
経営の基礎知識は、資格勉強で習得するのが一策です。
しかし、得意不得意があるのが、資格試験。何度も同じ資格に落ちてしまった経験がある人も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回の記事を読んで頂くことで、経営の基礎知識習得に向けた試験勉強のポイントを理解できるようになることを目指しています。
私の資格試験の経歴
私自身は、大学入学から社会人として働いている約13年の間に、職業柄、少なくとも30以上の資格試験を受けてきましたが、幸い、一度も落ちたことはありません。
その中には、難関国家資格である「中小企業診断士試験」やIT系国家資格の「応用情報技術者試験」、さらには国際資格である「認定事業再生士試験」も含まれています。
そして、単に合格するだけでなく、短期間かつ余裕を持った点数で合格し続けることができました。
個人的に一番難しかった試験は中小企業診断士試験です。一次試験、二次試験にストレート合格できる人は、約4%と言われています(一次試験合格率約20%×二次試験合格率約20%=約4%)。
平成28年に受験しましたが、一次試験があまりにも難しい年だったため、加点措置だけでなく、合格基準そのものがその年だけ引き下げるという前代未聞の措置が取られました。

(本来の合格基準は「総点数の60%以上」)
そんな難しい年でしたが、上位1割に入って余裕をもって合格することができました。合格者の平均勉強期間も平均3年程度ですが、約9か月で合格することができました。
他にも
・日商簿記3級:100点合格(勉強期間約30日)
・日商簿記2級:86点合格(勉強期間約40日)
・銀行業務検定 財務3級:92点合格(勉強期間約20日)
・銀行業務検定 財務2級:86点合格(勉強期間約40日)
など、単に合格するだけでなく、比較的短期間で高得点を取れました。
このように連戦連勝できたのは、試験勉強を始める前にあることをしていたからだと思います。
今回から3回に亘って、実務に活かす資格勉強のポイントをお伝えいたします。
資格勉強の最初にやるべきこと3選
最初にやるべきこと①:試験内容を覚える
見落とされがちですが、これが本当に大切だと思います。
試験内容というのは、
・試験時間
・試験形態(マーク式、論述式等)
・合格基準(合格点、足切り点、科目合格等の仕組み等)
・電卓の持ち込みの可否
・科目名
・試験範囲
・科目ごとの試験順
などのことです。
当たり前ですが、試験内容が分からなければ、勉強のアプローチ方法も定めりません。どれくらいの点数を狙うのか、カテゴリーごとにどういう濃淡の付け方で勉強するか、など。
しかし、試験直前になって、
「あれ、合格点何点だっけ?」
「え、電卓持ち込めないの!?」
なんて声を、周りでもよく聞きます。
かく言う私も、そんなことを言う1人でした。
中小企業診断士試験の勉強を始めて間もないある時、中小企業診断士試験の合格体験記で、「最初にやったことは、科目名と科目ごとの試験順を覚えること」というのを見かけました。
中小企業診断士試験について言えば、周りを見ても、科目名を正式名称で全て言える人は多くありませんでした。
また、中小企業診断士試験の「財務会計」については、電卓持ち込み不可ですが、試験直前でもそのことを知らない人も少なくありませんでした。
合格体験記を読んでなるほどと思い、試験内容をきちんと理解し直しました。そのお陰で試験へのアプローチ方法も修正し、勉強を効率的に進めることができました。
例えば、科目ごとの試験順が分かれば、試験当日の過ごし方が分かりますし、試験範囲が分かれば勉強する項目の順番や濃淡を考えやすくなります。
見落とされがちですが、まずは試験内容をきちんと理解しましょう。
最初にやるべきこと②:合格体験記を読む
先ほども触れましたが、合格体験記を読むのも非常に大切です。
合格に必要なポイントを手早く知れるからです。
資格によって合格のポイントが異なることもあれば、共通するポイントがあったりもします。それを合格体験記を複数読むことで洗い出し、効率的に合格できるロードマップを敷くことができるようになります。
私も中小企業診断士試験の勉強を始めて間もない頃に合格体験記を20名分ほど見ましたが、非常に参考になりました。
仕事が長時間に亘るため勉強時間を中々確保できない中、何とか時間を捻出して合格した方、過去問を5年分ではなく10年分やったことで手広く知識を修得して、当日の試験に対応できた人など、実のある内容が盛りだくさんでした。
私はTACの合格体験記を見ましたが、予備校に限らず、ネット上にある合格体験記でも問題ないと思います。
そして、可能であれば、不合格体験記を読むことも大切です。合格者が合格のコツと思っていたことが、不合格者も実践している可能性があるためです。
幅広く合格体験記を読むことで、合格のポイントを手早く学ぶことができます。
最初にやるべきこと③:目標を明確に決める
基本的なことですが、本当に大切なことです。
どこを目指すのかゴールを明確にしなければ、アプローチ方法が定まりません。また、勉強への意識付けも乏しくなってしまいます。
目標の設定方法については、「SMARTの法則」が有名で、こちらの法則に倣って目標設定するのがよろしいでしょう。
参考までに、私の場合、中小企業診断士試験の一次試験に取り組む際には以下のように目標設定しました。
・目標点数:平均65点以上(7科目同時合格)
・勉強期間:9か月
・勉強時間:1,000時間以上
・過去問を何年分やるか:10年分
・過去問を何周やるか:5周
これらの目標を日次目標に落とし込んで、毎日見返してチェックしていました。
そして結果として、4つの目標を全て達成しました。
当たり前ですが、目標を達成できたのは、目標を設定したからです。
サッカーでもバスケでも、ゴールが無ければ点を入れることができません。資格試験でも、合格したいなら目標を立てる必要があります。
最初に目標があるか無いかで、取組み方、姿勢が大きく変わります。
意識付けや効率的なアプローチ、さらにはモチベーションアップのためにも、ぜひ最初に明確な目標を設定することをオススメします。
次回予告
今回は、資格試験に合格するために最初にすべきことをご紹介しました。
次回は「難関資格に上位1割で合格できる『超絶オススメ勉強法』5選」をお伝えします。9月16日(土)投稿予定ですので、ご覧ください。
当noteでは、経営力強化につながる記事を毎週土曜日に投稿いたします。仕事のご依頼、お問い合わせは画面下の「クリエイターへのお問い合わせ」よりお願いします。

投稿者(山西良明)プロフィール
【経歴】
・現役信金マン
2014年より信用金庫で勤務中。営業、業務推進、融資審査、事業支援を経験。
・中小企業診断士事務所代表
信用金庫で働きながら、2021年に中小企業診断士として個人事務所を開業。認定経営革新等支援機関としても登録済み。
【現在の業務内容】
・経営力強化支援
創業/経営改善/事業再生等に向けた経営力強化支援を行っています。事業者様とともに事業内容を見直し、共同で事業計画書を策定、フォローしていきます。
・補助金採択支援
補助金の採択に向けた支援を行っています。
・資金繰り相談対応
資金繰りの分析から資金調達(融資等)の支援まで行っています。
・金融機関向けシステム開発協力
金融機関向けの様々なシステム開発に関して、情報提供や助言による協力を行っています。
【主な保有資格】
・中小企業診断士
コンサルタントとしての唯一の国家資格。2017年取得
・販売士(リテールマーケティング)1級
BtoCのマーケティング資格。2018年取得
・応用情報技術者
IT系国家資格。2021年取得
・認定事業再生士
事業再生の国際資格。2022年取得
【趣味】
・マラソン
2時間30分切りを目指し、週6~7日走っています。
・読書
海外SF、文芸誌、ビジネス書をよく読みます。愛読書は『三体』『V字回復の経営』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
