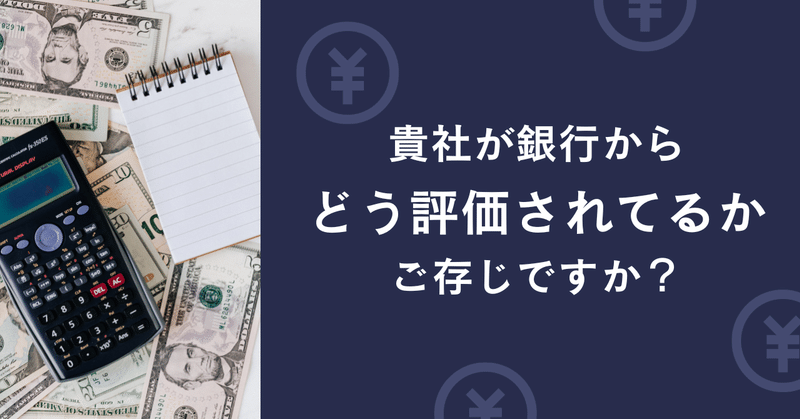
経営における「信用」の正体
おはようございます。現役信用金庫マン 兼 中小企業診断士事務所代表の山西です。当noteでは、経営力強化につながる情報を経営者や支援機関に向けて発信しています。
最近は、アフターコロナや物価高騰などで多くの企業がダメージを受けています。そんな中、銀行がみなさんの会社をどのように評価しているかご存じでしょうか。
実は、金融機関は取引事業先を5段階の「債務者区分」に分類しています。
この債務者区分の分類ルールを知ることは、自社の経営状況を見つめ直す上で非常に重要です。なぜなら「債務者区分=企業の客観的な信用度」であり、その信用度を決める構造を理解することに他ならないからです。
資本主義の父と言われる渋沢栄一も「信為萬事本」(信ヲ萬事ノ本ト為ス)という言葉を大切にしていた通り、ビジネスにおいて信用はとても大切な要素です。
信用度を決定づける構造を知り、信用を築くことができれば、ビジネスにおいて有利に戦うことができます。
今回は、金融機関による債務者区分の分類ルールについてはお伝えします。
①「債務者区分」とは
「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいう。
債務者区分とは、貸出先の返済能力に応じた5段階の区分のことです。信用リスクの管理を強化するための手段として導入されました。
その契機となったのは、バブル崩壊です。貸出先の業況悪化に伴い、金融機関の不良債権はどんどん増えました。金融機関は融資リスクをより明確に把握し、管理する必要性を痛感した訳です。
債務者区分の分類は、金融検査マニュアルに基づき行われます。
補足:金融検査マニュアルとは
金融検査マニュアルは、金融機関の資産である貸出金の健全性(=貸出先の健全性)を評価する基準を示すものです。
金融機関が適切なリスク管理とコンプライアンス体制を保持し、健全な経営を行うことを確保する目的で1999年に作成され、金融機関の内部監査や監督機関による外部監査の基準として使用されていました。
同マニュアルは、財務の過度な重視や画一的な規制が時代にそぐわなくなり、2019年12月に廃止されましたが、金融機関は引き続き金融検査マニュアルに準じた債務者区分の分類をしていることが多く、金融庁としてもその方法を否定していません。
個別の金融機関の内部管理態勢の構築に当たって、方針や規程の整備・ 周知、適切な人員配置と権限分配、リスク管理部門や内部監査部門の独立性や牽制機能の発揮、PDCA の重要性等といった検査マニュアルにおいて従来から前提とされていた基本的な考え方は今後も引き続き重要であるが、当局は、一律の内部管理態勢の構築を求めるのではなく、個別の金融機関の個性・特性に照らして実効的な内部管理態勢が構築されているかどうかや、経営理念・戦略が組織全体に浸透し、これらと整合的に営業推進やリスク管理が行われているか等を評価していく。
②5段階の債務者区分
金融機関は、中小企業を以下の5段階の債務者区分で分類します。
債務者区分(1):正常先
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者を言います。
多くの企業が正常先に分類されます。
債務者区分(2):要注意先
要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある 債務者など今後の管理に注意を要する債務者を言います。
また、要注意先となる債務者については、要管理先である 債務者とそれ以外の債務者とを分けて管理することが望ましいとされています。
債務者区分(3):破綻懸念先
破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金 融機関等の支援継続中の債務者を含む)をい言います。
破綻懸念先になると、新規の融資受け入れは困難になり、既存の融資条件の見直しも求められることがあります。
債務者区分(4):実質破綻先
実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者を言います。
リストラや経営再建が必要とされる場合があります。
債務者区分(5):破綻先
破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、 民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者を言います。
財務状態が完全に崩壊し、返済能力が失われている企業を指します。法的手続きや倒産処理が必要とされる場合があります。
債務者区分は以上となっています。
では、この債務者区分の分類基準はどうなっているのでしょうか。
③債務者区分の分類基準
債務者区分の分類基準は、一言でいうと「返済能力」です。
しかし、返済能力と言っても様々な要素が考えられます。具体的にどのような基準で分類されているのでしょうか。
「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいう。
金融検査マニュアルによると、
・財務状況
・資金繰り
・収益力
により返済能力を見ると記載してあります。
しかし、これらの数値面以外にも様々な面を考慮するよう促しており、分類基準は以下のように示されています。
債務者区分は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等により、その返済能力を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる 債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援 状況等を総合的に勘案し判断するものである。
特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする。
同マニュアルによると、数値面以外にも、
・技術力
・販売力
・成長性
・役員報酬の支払い状況
・代表者の収入や資産、保証状況と保証能力
なども勘案して判断するよう記載があります。
要は「あらゆることを勘案して判断してね」という感じですが、それだと分類がきちんと行われているか判断基準が曖昧になってしまいます。
同マニュアルには、判断基準が曖昧にならないよう、債務者区分ごとにある程度明確な分類指標が定められています。
分類基準(1):正常先
特段指標は定められていません。
要注意先以下に該当しなければ正常先となります。資産超過、黒字、債務償還年数10年以内であれば、ほぼ間違いなく正常先に分類されるでしょう。
なお、債務償還年数は以下の式で算出されます。
債務償還年数=要返済債務÷キャッシュフロー
細かい算出方法は金融機関によってマチマチです。
例えば、要返済債務に運転資金を含めるか、要返済債務から現預金を差し引くか、キャッシュフローはどの数値を使うか(当期純利益+減価償却費、EBITDA、フリーキャッシュフロー等)ということに明確なルールはありません。
分類基準(2):要注意先
A:貸出条件に問題のある債務者(金利減免等)
B:履行状況に問題がある債務者(元本返済・利息支払の事実上延滞)
C:業況が低調・不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者
等が要注意先に分類されます。
AやBについては、客観的に返済能力が認められないため、正常先とは言い難いです。場合によっては、後述する破綻懸念先以下に該当する可能性もあります。
Cについては、基本的に債務超過企業、赤字企業が該当します。
しかし、赤字企業すべてが該当する訳ではありません。マニュアルでは以下の通り示しています。
赤字企業の場合、以下の債務者については、債務者区分を正常先と判断して差し支えないものとする。
(中略)
(イ)赤字の原因が固定資産の売却損など一過性のものであり、短期間に黒字化することが確実と見込まれる債務者。
(ロ)中小・零細企業で赤字となっている債務者で、返済能力について特に問題がないと認められる債務者。
他にも正常先と見ていい条件は色々ありますが、主なものを挙げています。
要は、赤字だったとしても、それが一時的なものであったり、返済自体に懸念がなかったりすれば、正常先と判断して差し支えないということです。あくまで「返済能力」に基づいて債務者区分が分類されるためです。
一般的には、2期連続赤字だと一時的と言いづらいため、要注意先に該当する可能性が高くなります。
分類基準(3):破綻懸念先
破綻懸念先への分類基準は以下の通りです。
現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営 破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。
まとめると、
A:実質債務超過
B:業況が著しく低調(慢性的な赤字)
C:元本及び利息の最終回収について重大な懸念がある
を全て満たすような事業先が債務者区分として分類されます。
ただし、AとBを満たす場合でも、Cにおいて重大な懸念があると認められない場合は、要注意先にとどめることが可能です。マニュアルにも以下のような記載があります。
金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、当該債務者は要注意先と判断して差し支えないものとする。
イ.経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内で あり、かつ、計画の実現可能性が高いこと。 ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね 10 年以内となっている場合で、経営改善計画等の策定後、経営改善計画等の進捗状況が概ね計画どおり(売上高等及び 当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保されてい ること)であり、今後も概ね計画どおりに推移すると認められる場合を含む。
ロ.計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が原則として正常先となる計画であること。ただし、計画期間終了後の 当該債務者が金融機関の再建支援を要せず、自助努力によ り事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合 は、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先 であっても差し支えない。
ハ.全ての取引金融機関等(被検査金融機関を含む)におい て、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できること。 ただし、被検査金融機関が単独で支援を行うことによ り再建が可能な場合又は一部の取引金融機関等(被検査 金融機関を含む)が支援を行うことにより再建が可能な 場合は、当該支援金融機関等が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意さ れていることが文書その他により確認できれば足りるも のとする。
ニ.金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等に止まり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。
「合理的」であり「実現可能性の高い」計画は、合実計画と呼ばれます。
中小企業再生支援協議会では、合実計画の要件を定めており、この基準が一般的にも使われています。非常に大切な基準なので、覚えておくと有益だと思います。
・実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する内容とする。
・経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目処に黒字に転換する内容とする。
・再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる内容とする。
上記以外にも細かい基準はありますが、上記3点を押さえておけば、おおよそ事足ります。
なお、最近では、債務償還年数(有利子負債の対キャッシュフロー倍率)が15年以内であれば正常先とする金融機関も増えつつあります。
そして、上記要件は、現在では「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に引き継がれています。
破綻懸念先として分類されると、新規融資が出せない場合がほとんどになります(明確な返済原資がある場合は除く)。破綻懸念先から抜け出すためには、合実計画を作成する(もちろん実行も)必要があるでしょう。
分類基準(4):実質破綻先
実質破綻先の分類基準は以下の通りです。
事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良資産を内包し、あるいは債務者の返済能 力に比して明らかに過大な借入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しが ない状況、天災、事故、経済情勢の急変等により多大な損失 を被り(あるいは、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない状況で、元金又は利息について実質的に長期間延滞している債務者などをいう。
「実質的に長期間延滞している」とは、原則として実質的に6カ月以上延滞しており、一過性の延滞とは認められないものを言います。
分類基準(5):破綻先
破綻先の分類基準は以下の通りです。
破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、 民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。
破綻先の基準は非常に明快で分かりやく、法的等手続きによる再生等処理が行われていると該当します。
以上をまとめると、企業の信用の正体は「返済能力」であり、「債務超過かどうか」「黒字かどうか」「有利子負債とキャッシュフローのバランス」でほとんど決まる訳です。
④債務者区分の構造を知ることで経営に活かす方法
私の経験上、自社の債務者区分を経営者が知る場面は非常に少ないと思います。また、金融機関側も債務者区分を聞かれても回答できない場面が多いと思います。
しかし、債務者区分の分類ルールを知ることは、中小企業経営者にとって非常に重要です。
ビジネスの根幹となる自社の信用状況を知るために、債務超過かどうか、黒字かどうか、債務とキャッシュのバランスは適正かどうかに常に気を配る必要があります。
その上で、芳しくない企業様は、信用が乏しい根本原因を探し、改善していく青写真を画いていくことが大切です。信用状況が芳しい企業様は、さらに良くしていくためのシナリオを描いていくと良いでしょう。
信用を築いていくために、信用が足りているかどうか、足りていない場合は足りない理由は何か、信用を増やしていくためにはどんな目標を立て、どんなシナリオを描いていくべきかを考えていく必要があります。
まとめ
・信用=返済能力
・返済能力とは、利益・債務超過かどうか・キャッシュフローと債務のバランスのことです。
・債務者区分は、信用状況によって銀行が貸出先を区分したものです。
・信用を築いていくためには、①信用が足りているかどうか②足りていない場合は足りない理由は何か③信用を増やしていくためにはどんな目標を立て、どんなシナリオを描いていくべきか、を考えていく必要があります。
次回予告
次回は「事業性融資の金利が決まる仕組み」についてお話します。11月11日(土)投稿予定ですので、ぜひご覧下さい。
当noteでは、毎週土曜日に、経営者や経営支援者に向けた経営力強化につながる投稿を行っています。仕事のご依頼、お問い合わせは画面下の「クリエイターへのお問い合わせ」よりお願いします。
投稿者(山西良明)プロフィール
「強い企業を作る」ことを理念に、中小企業の経営力強化に向けたサポートをしている経営支援者です。「資金繰り支援」と「本業支援」という両輪の経験を「現在進行形で」持っていることを強みに、徹頭徹尾やり切る持ち前の性格で支援しています。
【経歴】
・現役信用金庫マン
2014年より信用金庫で勤務中。営業、業務推進、融資審査、事業支援を経験。
・中小企業診断士事務所代表
信用金庫で働きながら、2021年に中小企業診断士として個人事務所を開業。認定経営革新等支援機関として登録。
【現在受け付けている業務内容】
①経営パートナー契約
中小企業様とのパートナー契約により、経営力強化を目的として、毎月訪問(又はリモート相談)で支援をしています。
②事業計画書協同策定・実行支援 創業/経営改善/事業再生等に向けた経営力強化支援を行っています。事業者様とともに事業内容を見直し、共同で事業計画書を策定、フォローしています。
③資金繰り改善支援
資金繰りに関する分析および提案、実行・フォローに至るまでのトータル支援をしています。資金繰り改善支援の一環として、融資承諾支援、補助金申請支援も行っています。
(1)資金調達支援
利益向上を目的としたご融資の承諾に向けたご支援を行います。お借入に関する事業計画書(設備投資計画や創業計画書等)策定支援および交渉に関する諸支援です。
(2)補助金採択支援 利益向上を目的とした補助金採択に向けたご支援を行っています。持続化補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金など。メインは補助事業計画書策定支援です。補助金交付決定金額の10%を基本とした成功報酬制で受け付けています。
【主な保有資格】
・中小企業診断士
コンサルタントとしての唯一の国家資格。2017年取得
・販売士(リテールマーケティング)1級
BtoCのマーケティング資格。2018年取得
・応用情報技術者
IT系国家資格。2021年取得
・認定事業再生士
事業再生の国際資格。2022年取得
【尊敬する人】
・三枝 匡(事業再生専門家)
・森岡 毅(マーケター)
【趣味】
・マラソン
地元大会で2時間30分切りでの優勝を目指し、年365日走っています。
・読書
海外SF、文芸誌、ビジネス書を読みます。愛読書は『三体』『V字回復の経営』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
