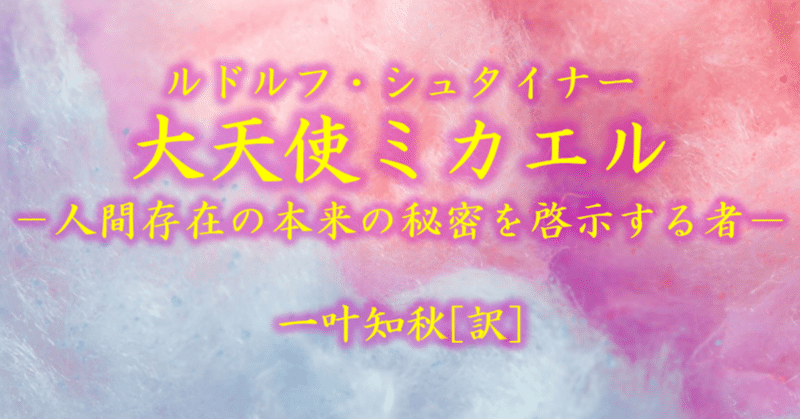
ルドルフ・シュタイナー『大天使ミカエル-人間存在の本来の秘密を啓示する者-』第二講
本講をお読みになる前に第一講からお読みいただくことをお勧めいたします。
1919年11月22日 ドルナッハ
■Ⅱ-1 昨日は、近現代の精神生活に染み込んでしまい、実際には今日でもわずかな人にしか正しい仕方では気づかれていない、あの誤謬についてお話ししました。この誤謬を指摘することで、私たちが既に霊学的な考察のとても重要な点に立っていることを、この議論から感じとっていただけたかと思います。人類の精神生活を豊かに進化発展させるためには、この点が明確になることが必要不可欠になります。昨日の講義では、ミルトンの『失楽園』やクロップシュトックの『救世主』のように、過去数世紀の遍く普及していた思考からまさしく生まれた文化的作品に注意を喚起しました。霊性を含めた世界の構造を二元論のイメージで把握できると思うだけでは、人間は自分にとって必要な真の神の概念を得られませんし、ひいては真のキリスト概念も得られないわけですが、このことを見抜かない場合、いったい人間の魂の生活にどんな危険が迫っているのか、それを、芸術的にも精神一般的にも傑出したこれらの文化的作品にこそ感じ取ることができるということにも注意を喚起しました。よりにもよって一方で善、他方で悪という、いわば二元論的な区別しかしなかったために、人々は、時の流れの中でルツィフェル的なもの、アーリマン的なものと呼ぶ必要が生じたものを全て、この二元論的な区別の悪の側に含めてしまうという過ちを犯してしまいました。そして彼らは、自分たちが世界の二つの要素を一緒くたにしてしまったことに気付かなかったのです。その結果、他方ではルツィフェル的な要素が事実において善の側へ押しやられてしまいました。言い換えれば、人々は神的なものを崇拝し、認識していると信じ、その名を呼んでいたのですが、しかしそれでもルツィフェル的な要素をこの神的なものに混ぜてしまったのです。そして、このことによって、私たちの時代でも、人類と世界の進化発展において神的なものの純粋な概念及びキリスト衝動の純粋な概念を得ることが非常に困難になっています。私たちは、何世紀にもわたる文化から、この二元論を正当と認めているがゆえに、一方では魂的なもの、他方では体的なものについて語ることに慣れてしまっています。そして、私たちに魂的-霊的なものを媒介する表象と、私たちに体的なものを媒介する表象との間の関連を、私たちは失ってしまったのです(☆1)。思考・意志・心情・感応(☆2)について語る場合、私たちが今日語るのは、ほぼ言葉の羅列以外のなにものでもなく、ほとんどの学校心理学がそうしているのです。私たちはこの魂的な要素について内的で内容のある本当の表象を得ることができません。そして私たちは、その一方では、霊や魂のない物質的なものについて語ります。それは、いわばこうした外的な硬い、石のような、霊も魂もない物質的なものを叩いているようなものであり、その物質的なものから魂的なものへ架橋できないのです。
■Ⅱ-2 私たちにとって二つの要素に分かれてしまったのは、遍く存在している霊的なもの、及び同時に霊的なものでもあるところの体的なものなのです。体的なものと霊的なものとの間にそのような橋を架けることは、単なる理論ではできません。そしてこの橋を架けられないがために、とりわけ私たちの学問的な思考全体が、こうした体的なものと霊的なもの、或いは体的なものと魂的なものの間の二分節という性格を持っています。人は次のように言いたがります。「一方ではあれやこれやの信条が、この霊的なものがどのように体的-肉体的なものに直接働きかけ、どのように体的なものにおいて創出活動するのかを説明できないまま、霊的なものを指し示すことに陥っている。そして他方、魂のない知識、魂のない自然観は、目下のところ外的な肉体ばかりを観察していて、体内プロセスの経過の中で霊的-魂的な力が働いていることをどこにも見て取ることができない」。このような観点によって19世紀から20世紀にかけて発展してきた自然科学の立場を概観する場合は、次のように考える必要があるでしょう。即ち、「私たちにとってそこに現われる全ての事象は、今しがた特徴づけられたことの結果として現れているのだ」と。もちろん、ここでも十分に議論を重ねてきた様々な前提から、真実が既に推論されうるのですが、現在この真実を覆い隠している誤謬が完全にわかるようになる前に、何よりもまずこの真実を補足する必要があります。人々は現在、魂的なものの話であるか体的なものの話であるかにかかわらず。人間は統一的な存在であると言います。或る人は魂的なものを統一的な存在であると言い、或る人は体的なものを統一的な存在であると言うのです。しかしながら、皆さんには既にお示ししたように、人間存在には何よりも、頭部のつくり全体と、それ以外に人間が携えている有機体のつくり全体との間に大きな対極があることが、私たちの考察からお分かりいただけたかと思います。後者を今はこれ以上分割しようとは思いません。ご存じのように更に分割できますが、今は一つにまとめようと思います(図3の右の部分を参照)。人間の進化発展が問われています。人間の頭部のつくりに関する人間の進化発展と、頭部以外の体のつくりに関する人間の進化発展とが、全く異なる仕方で問われなければならないのです。

■Ⅱ-3 頭部のつくりは感覚的知覚や思考や表象のための器官を含んでいます。その意味で、頭部のつくりに注目するならば——差し当たり外的な肉体のみを把握してみましょう——、無論、人間の宇宙的な進化発展をはるか昔に遡って振り返らねばなりません。そして、現今の人間の頭部のつくりにおいて表現されているものは、次第に進化発展し、形を変えてきたのだと言わなければなりません。それは古土星紀、古太陽紀、古月紀を経て進化発展してきたのであり、そして地球紀の間にも更に進化発展してきたのです。しかし、人間の頭部以外の有機体の方はそうではありません。人間全体に対して統一的な進化発展史を求めるのは全く間違っているでしょう。頭部のつくりは、今現在の地球紀の過去の各惑星段階——月紀、太陽紀、土星紀——を指し示しているということができます(図3参照)。最終的に人間の頭部として完結したものは、ずっと昔の進化発展にまで遡るのです。しかし、人間の頭部に、人間に属する頭部以外の有機体全体を付け加えるならば、土星紀にまで遡ってはなりません。むしろ次のように言わなければなりません。「人間自身が携えている頭部以外の有機体は、胸部のつくりという点ではせいぜい月紀にまでしか遡れないし(図3:垂直の境界線)、四肢のつくりは、地球紀の時点で初めて人間にもたらされたのだ」と。
■Ⅱ-4 たとえば次のようにイメージして述べる場合にのみ、人間を正しく観察することができます。次のことをイメージ的に把握してください。宇宙における何らかの有機的なプロセス、何らかの適応プロセスが、内的な成長プロセスと結びつくことで、人間は或る新しい四肢を付け加えることになる——このように仮説的にイメージすることはとても簡単にできます。そうイメージしてみると、人間の姿形全体を昔の進化発展まで遡るのではなく、「人間は、進化発展してきた点では遡らなければならないであろうが、ある時点では四肢の一つ一つが初めて付け加えられたのだ」と言えるでしょう。頭部と頭部以外の有機体に関してこんなふうに考えたくない気持ちになるのは、純粋に外見上の大きさからして頭部よりも頭部以外の有機体のほうが大きいからに他ならないでしょう。しかし本当のところは頭部のつくりが最も古く、頭部以外の有機体のつくりは、将来の萌芽を表しているにすぎないのです。進化発展に関して動物界と人間の関連を概して述べるならば、「人間の頭部の中にあるものは、かつての動物のつくりに由来する」とだけ言うことができます。人間の頭部は動物の形がとても大きく変形したものなのです。
■Ⅱ-5 私の著作や講義に慣れ親しんでいる方ならば、動物たちはあとになってから人間に加わってつくり出されていったものであることをご存じです。もちろん全く異なる物理的関連においてではありますが、人間は、まだ動物が全く存在しなかった頃、外見上は動物のつくりをしていました。その一方で、人間における動物のつくりをしていたものが、現今の人間の頭部になりました。頭部以外の有機体は、動物の進化発展と同時に頭部に初めて付け加えられたのですから、実際のところ動物系統とは関係ありません。そのため、私たちはそもそも、「差し当たり人間の最も高貴に見える部分である頭部は、動物にまで起源を遡ることができる。頭部に関して人間そのものがかつて或る種の動物の形をしていたのだ」と言わなければなりません。そして私たちが携えている頭部以外の有機体は、動物の進化発展と並んで、いわば有機的な付加物として、宇宙の進化発展の中にある頭部に授けられたものなのです。
■Ⅱ-6 今では、頭部はある意味で私たちの思考器官となっています。要するに私たちの思考器官は、動物系統を持つものになったと言っても過言ではないのです。ただ、それはもちろん一風変わった動物系統を持っています。現今では人間の頭部をしかるべく扱ってみても、恐らく解剖学的には動物の形を指し示すものをすぐに見て取ることはないでしょう。しかし、なおもよく見てみると、頭部器官の形を正しく解釈する仕方を理解しさえすれば、この頭部器官の形が動物性の器官をどのように変形させたものなのかを認識することになるでしょう。
■Ⅱ-7 進化発展の初期段階には生き生きとした生命に満ちていたものが、人間の頭部において既に死滅する途上にあり、逆行的な進化発展の中にあるのです。さて、以上のことに注目するならば、もちろん同時に、動物から人間の頭部への変形は、この頭部に既に逆行的な進化発展が含まれていることによって成立しているという事実にも触れなければなりません。かつて私は次のように述べました。「もしも人間が頭部だけだったら、そもそも決して生きることはできなかったであろうし、基本的に絶えず死んでいかなければならなかったであろう。というのも、人間の頭部それ自身の能力によるその有機的なプロセスは、生きるプロセスではなく、死ぬプロセスであるからだ」と。頭部の中にあるものは、頭部以外の有機体から絶えず新たに活力を与えられています。頭部もまた有機体の生命全般に関与していることは、頭部以外の有機体の生命のおかげなのです。頭部が組織されているのは、感覚的知覚能力と表象能力のためですが、それらだけに自分を委ねていたならば、頭部は絶えず死滅していったことでしょう。頭部は絶えず死ぬ傾向にあり、絶えず活力を与えられなければならないのです。私たちが思考し、感覚的に知覚するとき、私たちの頭部、神経系全般、そして感覚器官と神経系の結びつきにおいて、高まっていく生命プロセス、成長などに適した生命プロセスが生じるのではありません。というのも、そうした生命プロセスでは眠ることしかできず、深い眠りに沈み込むことしかできず、はっきりと思考することなど決してできないでしょうから。死が絶えず私たちの頭部に浸透し、絶えざる退行が存在し、以上に見たような有機的なプロセスが絶えず弱められることによってのみ、私たちの頭部の中で思考と感覚的知覚が根を下ろすのです。
■Ⅱ-8 唯物論的な仕方で脳のプロセスから思考や感覚的知覚を説明しようとする人は、頭の中でどのようなプロセスが生じるのかを全く分かっておらず、有機的な成長などと比肩しうるようなプロセスが生じていると思っています。そうではありません。感覚的知覚や表象と並行して生じることは、死滅プロセスであり、消耗プロセスであり、破壊プロセスなのです。有機的なもの、物質的なものは、まず消耗させられ、破壊されなければなりません。そうすると、思考プロセスが有機的な破壊プロセスの上に立ち現れます。
■Ⅱ-9 人は思考し、感覚的に知覚しますが、その時に並行している自分の有機体の内部に生じていることについては、何もわかっておらず、完全に無意識の内にとどまったままです。現今の人類はこうした事柄の本質を外的に推定しようとする仕方で把握するのです。私の著作『いかにしてより高次の世界の認識を獲得するか』の中に書かれているプロセスによって初めて、以上のような認識——人々がほとんど字面の意味だけで「魂的なもの」と呼んでいる感覚的知覚と思考ではなく、これらを超え出たより高次の認識——に徐々に昇っていくことができます。魂は、この書に書かれているような仕方でくぐりぬける発展のもとで、一方では思考や感覚的知覚に没頭し、同時にその時に脳の内部で生じていることを知覚することができます。その時には、通常ならたとえば(唯物論者が考えているような)成長プロセスとして感じられるものを知覚するのではなく、消耗プロセス——それはそれで常に頭部以外の有機体によって調整されなければならないところの消耗プロセス——を知覚するのです。
■Ⅱ-10 これは、私たちの頭部活動の本当の認識に付随している悲劇的な現象なのです。見霊能力者が思考し感覚的に知覚する時に、彼が頭部の有機的プロセスが活気づくのを観て楽しむということなど到底あり得ません。むしろその時に彼は、或る破壊プロセスに気づくに違いありません。その一方で彼は、「唯物論的な考えの持ち主は、思考し、感覚的に知覚する時にまさに排除されているような生命プロセスが人間の頭の中で生じていると仮定しているのだ」ということにも気づくに違いありません。まさに真実とは真逆のことを、唯物論は仮定しなければならないのです。
■Ⅱ-11 このように私たちは、人間の頭部のところで確かに動物性からの進化発展ではあるが、それは今、間違いなく逆行的な進化発展であり、消耗プロセスであることに取り組んでいます。私たちの頭部以外の人間の有機体は、上昇する進化発展の途上にあります。この頭部以外の人間の有機体について、私たちは、それが単に魂的-霊的なものに、そして人間における魂的-霊的なものの体験に何も関与しないなどとはおよそ思ってはなりません。頭部以外の有機体から頭部の中へと絶えず送られていくのは血液だけではありません。この世界を織り成し、私たちの有機体をも織り成している、あの魂的-霊的な思考像も絶えず血液の中へ入っていくのです。人間は現今の通常の状態ではこの魂的-霊的な思考像をまだ知覚していません。しかし人間がこの思考像において自分自身の存在から立ち現れるものを知覚し始めなければならないような時代がやってきました。ご存じの通り、私たちは単に眠ってから起きるまでだけ眠っているのではありません。私たちの存在のある部分は、一日中眠っています。私たちは本来、思考、表象、そして感覚的知覚に関してのみ目覚めています。感情の営みに関しては夢見ています。そして意志の営みに関しては完全に眠っているのです。というのも、欲することについて私たちは、ただその観念、理念のみを知っているのであって、その欲することのプロセスを知っているわけではないからです。そもそも意志の営みは、私たちの意識にとって、眠りについてから目覚めるまでの寝ている間の営みと同様に、無意識的に営まれています。しかし、「唯一どのような経路で真に神的なものの知は人間に達することができるのか」と問うならば、頭部を通る経路、即ち感覚的知覚と思考を通る経路をではなく、頭部以外の有機体を通る経路を参照するように指示することしかできません。「人間はその頭部を一連の長い進化発展の中で進化発展させてきた。その後、頭部以外の有機体が付け加えられた。頭部は既に逆行的な進化発展をし始めている。そして人間が自分の神的なものと感じうるものは、頭部を通してではなく、頭部以外の有機体を通して人間に呼びかけるはずのものである」。このような、大きな途轍もない秘密があるのです。つまり、「ルツィフェル的な存在たちだけが、最初に頭部を通して人間に呼びかけた」ということをはっきり認識していることが重要なのです。そして「頭部に付け加えて頭部以外の有機体が人間に作られたことで、神々は人間に呼びかけることができるのだ」と言うことができます。旧約聖書『創世記』の最初には「神は、輝ける光を人間にお与えになった。そこで人間は生命ある魂となった」と書かれているのではありません。「神は生命ある息を人間に吹き入れられた。そこで人間は生命ある魂(を持つ者)となった」と書かれています。ここでは、「頭部のではない活動、つまり頭部以外の有機体の活動を通して神的なものの衝動が人間にもたらされる」ということが正しく認識されています。
■Ⅱ-12 以上のことから、「最初にこの神的なものの衝動は、或る種の無意識的な見霊においてのみ、或いは少なくとも無意識的な見霊によって与えられたものの理解を通じてのみ、人間にもたらされえたのだ」ということも理解できるでしょう。皆さんが旧約聖書を見れば——このことは他の考察からも知ることができますが——それが無意識的な見霊の成果であることが分かるはずです。旧約聖書の成立に共に力を尽くした人たちも、このことが分かっていました。今日はここで旧約聖書の成立についてお話しすることはできません。しかし、以上のような事柄について重ねてきた多くの考察の中に、古代ヘブライ民族のラビのところで次のような意識がどのようにいたるところで見つかるかを、なおも指摘しておきたいと思います。彼らの神は彼らに、直接的に感覚的知覚を通して呼びかけてきたのでも、通常の思考を通して呼びかけてきたのでもありませんでした。つまり頭部が媒介となる全てのものを通して呼びかけてきたのではないのです。むしろ、彼らの神は、夢——彼らがその言葉で理解しているのは通常の夢のことではなく、現実と区別がつかなくなった夢のことです——を通して呼びかけてきたのです。現に神が彼らに呼びかけてきたのは、「モーセに向かって茨の茂みから呼びかけてきた」とか、それに似ているような見霊的契機を通してでした。古代ヘブライ民族のラビのところではこのような意識がいたるところで見つかるのです。そして、この古代のその道に通じたラビたちは、神の呼びかけが彼らにもたらされることをどのようにイメージするかと尋ねられたとき、次のように答えました。「私たちに向かって呼びかけてくださる主は、その名は言い表しえないが、その御顔を通して私たちに向かって呼びかけてくださる」と。そして彼らは彼らの神の御顔のことを「ミカエル」と呼びました。私たちが大天使のヒエラルキアに数え入れているあの霊的な力、ミカエルです。彼らは、彼らの神を、見霊能力者をもってしてもその現象の背後で不可知なものであり続けていると感じていました。しかし見霊能力者は、彼の魂の内的な在りようによって自分の神のところにまで高まったとき、ミカエルに呼びかけられたのです。このミカエルが呼びかけたのは、人間が普段の意識状態とは異なる状態に、つまり確かな見霊状態になることができたときだけでした。普段はただ、眠りについてから目覚めるまでの間に働いているもの、或いは、識閾下(無意識)に留まったままの意志——意志はそもそも日中目覚めている間でさえも眠っています——によって生きているものが、この見霊状態によって意識の中に入り込んできたのです。
■Ⅱ-13 それ故に、ヘブライの秘密教義においてヤーヴェの啓示は「夜の啓示」と呼ばれ、ヤーヴェの啓示はミカエルの啓示を通して「夜の啓示」と感じられたのです。人々は、一方では感覚的知覚と人間の知性的思考を通して世界が与えてくれるものに従って世界を覗き込み、次のように思いました。「この方法で、諸々の認識がもたらされる。差し当たりは神的なものを含んでいない知が、人間に近づいて来るのだ」と。その一方で、次のようにも思いました。「人間がこの意識状態から別の意識状態(見霊状態)になる時、神の御顔ミカエルがその人に呼びかけ、人間存在の本来の秘密を啓示する(☆3)。即ち、神の御顔ミカエルは、外的な感覚的世界では知覚できず、脳と結び付いた知性をもってしては考え出すことができない、あの霊的諸力と人間との間に橋を架けるものを啓示するのだ」と。
■Ⅱ-14 ですから、次のように言わなければなりません。「キリスト以前の時代の人々は、一方では現に地球上での活動のための規準としてあった感覚的世界の認識に目を向けることができた。その一方で彼らは、あの超感覚的世界の認識にも目を向けたのだ」と。人間はあの超感覚的世界の認識を、もしも意識が眠りについてから目覚めるに至るまでの眠っている間にも目覚めているままであるということがあれば、およそ通常の意識の限りで持てるでしょう。しかし、当時の人間は超感覚的世界の認識を、通常の意識ではまだ持っていなかったのです。人間は、目覚めている時、霊的存在たちに取り巻かれています。人々はそのことを知っていました。この霊的存在たちは人間を創造した存在たちではありません。旧約聖書が書かれた当時、人々はそのように考えていました。この存在たちはルツィフェル的な存在たちなのです。旧約聖書がそこに由来するところの時代において、旧約聖書の中で人々はそのように考えていました。一方で、人類にとって創造的-神的と感じられた存在たちは、眠りから目覚めまでの間に人間存在に働きかけたか、或いは日中目覚めている時にも眠っている、人間存在のあの部分に働きかけました。旧約聖書が書かれた当時、人々は夜の支配者のことをヤーヴェ神と呼び、その夜の支配者の従僕、ヤーヴェの御顔のことをミカエルと呼びました。そして、彼らは預言的な霊感を通して、感覚界の認識によって幅広く得られる以上のこと(より高次の世界の認識によって得られること)を概念的に捉えていましたが、彼らは預言的な霊感一切を意味するものとして、ミカエルのことを考えていたのです。
■Ⅱ-15 では、こういったことの全ての背後にはどのような意識が隠れているのでしょうか?ヤーヴェを取り巻く霊的諸力が存在する領域から育まれてきた意識です。一方で、人間の頭部のつくりはルツィフェル的な存在に取り巻かれてきました。「人間の頭部が人間の有機体から突き出ているという形で、人間は自分の頭部を通してルツィフェル的な存在たちの方に向いていた」というのが、古代の全ての神殿が保ってきた秘密でした。そしてその秘密によって人々は、本当に真実のすぐそばに近づいたのです。彼らは、頭部が人間の有機体から突き出ていることで、ルツィフェルが人間の有機体から突き出ているということを、或る意味で知っていたのです。人間の頭部を動物から現在の形にした力は、ルツィフェル的な力なのです。そして、人間が神的なものと感じるべきである力は、頭部以外の有機体の夜の状態から人間の頭部の中へと流れ込むのでなければなりません。以上が、人間がキリスト以前の時代に知りえたことであります。
■Ⅱ-16 その後、地球の進化発展プロセスの中に「ゴルゴタの秘儀」が打ち込まれました。私たちはもちろん、「ゴルゴタの秘儀」とは、ナザレのイエスの体を通して或る超地上的(神的)存在と人間-地球存在の進化発展プロセスとの合一を意味すること、即ち、私たちがキリスト存在と呼んでいるこの存在がゴルゴタでの死を通して人間-地球存在と合一したことを知っています。このことによって地球の進化発展プロセスの中に何が起こったのでしょうか。そもそも、このことによって地球の進化発展プロセスは初めてその感覚を得たのです。人間がこの地球上で進化発展し、自分の諸感覚並びに頭部と結びついた知性——これらは最初ルツィフェル的な起源を持っています(☆4)——を備えており、外なる地球世界、即ち太陽や星々が地球へ降り注いでいる光の世界を知覚しているが、その一方で神的なものを知覚するためには睡眠状態に留まらなければならなかったとしたら、地球はその感覚を持たなかったでしょう。覚醒時の人間は地球と一体を成していますから、人間が今述べたような存在であったのでは、地球がその感覚を獲得することはなかったでしょう(☆5)。睡眠時の人間は自分と地球存在との関連を最初は意識していないのです。キリスト存在が死を経た人間の体の中に宿ったことによって、物質化した地球の進化発展過程の内に衝撃のような何かが起きたのです。全てがこの地球の進化発展の中で或る新たな感覚を得たのです。まず、人間が日中、普段起きている間でも、即ち普段の意識状態でも、次第に創造的-神的諸力を認識することができるようになる可能性が生じました。ただし、このことについては、今日でもなお誤謬が蔓延っています。なぜなら、旧約聖書の預言者たちが夜の支配者ヤーヴェとその御顔ミカエルの啓示に満ち満ちていると感じていた時代に覗き込むことができたあの超感覚的世界を、人々が今や日中目覚めている時にも覗き込むことができるようになるには、ゴルゴタの秘儀が起きてから今日までに経過した歳月がまだ十分ではなかったためです。それは或る過渡期を必要としました。しかし、19世紀の経過とともに——東洋の叡智全体が、全く異なる観点から19世紀のこの経過の重要性を指摘していますが——今まで成就しなかったことが成就したと、人々が認識せねばならない時代がやってきました(☆6)。人々の中の潜在能力が、今や目覚めの時を迎えて、今まではミカエルを通して夜の啓示でしか伝えられていなかったことが、昼の啓示を通して見ることができるようになったと、人々が認識しなければならない時代がやってきたのです。
■Ⅱ-17 しかし、それにはまだ大きな誤謬が先行する必要がありました。いわば或る「認識の夜」(☆7)とでも言うべきことが先行する必要があったのです。しばしば述べてきたことですが、いつも単に「我々の時代は或る過渡期だ」とだけ言うような人に、私は決して同調しません。確かに、どんな時代も過渡期であることは私にもよくわかります。しかし、そのような形式的で抽象的な捉え方に留まりたくありません。というのも、或る特定の時代の過渡がどこに存在しているのかを、はっきりと示すことこそが大切だからです。私たちの時代の過渡は、人々が「今まではただ夜の認識でしかなかったことが、昼の認識を通じてももたらされるに違いない」と認識する定めにあることに要点があります。これは言い換えれば、「ミカエルは、かつては夜を通じて啓示する者であった、そして我々の時代には昼の間に啓示する者となる定めにある」ということなのです。夜の霊であったミカエルは、昼の霊になる定めにあるのです。ゴルゴタの秘儀は、夜の霊であったミカエルが昼の霊になることに関与したのです。
■Ⅱ-18 しかし、私たちが今日思っているよりももっと速く人々の間に普及するのを助けるべきであったこの認識には、さらにより大きな誤謬——人類の進化発展においてそもそも可能であった考えられうる限り最大の誤謬——が先行していなければならなかったのではあるのですが、しかしその誤謬は、今日も未だ多くの学者集団に、特に重要で本質的な真実であるかのように思われています。人間の頭部の起源は、近世の人類には完全に隠蔽されてきました。人間の頭部と結びついているルツィフェル的な霊性は、完全に隠蔽されてきたのです。既に述べましたように、人間は身体的にも統一的なものと捉えられました。人間の身体の系統が問題となると、実のところは人間におけるルツィフェル的なものだけが動物系統であるのに、「人間の身体はまるごと動物系統である」という回答が返ってきました。しかし、かつて人間の創造神がそれを通して人間の睡眠時に人間に呼びかけたところのものは——その傍らで動物たちが生じた後で——最初は人間の頭部に付け加えられたものとして生じたのです。それでもまだ今日の人々は、人間の身体に関する全てを一緒くたにした上で「人間の身体はまるごと動物系統である」と語るのです。それは、人類にもたらされた、或る「認識の罰」とでも言えるようなものです。ここで私は「罰」という言葉を、少々解釈を変えた意味で言っています。
■Ⅱ-19 では、頭部の系統と頭部以外の有機体の系統に関して私たちが最初に述べておいたことが本当の経過である一方で、人間が「人間の身体はまるごと動物系統である」という虚構をでっち上げたこの傾向はそもそもどこに由来するのでしょうか。一体「人間の体はまるごと動物系統である」という虚構を人間に吹き込んだものは何なのでしょうか。
■Ⅱ-20 結論から先に言いますと、それはアーリマン的な存在たちです。ゴルゴタの秘儀と現代との間に経過した歳月、即ち、ある意味でゴルゴタの秘儀を理解するための準備期間であったこの歳月の中で、古代異教の叡智——人々がそれによって最初はキリスト教をも把握しようとしたところの古代異教の叡智——が表舞台から退き、新しい霊性の認識がまだ十分に成熟しておらず、アーリマン的な要素が人類の進化発展の中へと次第に忍び込んだのです。そして人々は、人間の頭部のルツィフェル的な要素を認識しなかったことで、人間の頭部以外の有機体の中で神的なものが相手にして戦っていたアーリマン的な要素も認識できなくなったのです。それで「人間の身体はまるごと動物系統である」という、純粋にアーリマン的な虚構が生じたのです。
■Ⅱ-21 「人間の身体はまるごと動物系統である」というのは、アーリマンによって吹き込まれたことなのです。こうした学問は純粋にアーリマン的な性格を持っています。私たちに「人間の頭の中にはルツィフェル的な像がある」ことを指摘するあの古代異教の叡智の隠滅が、「人間の身体はまるごと動物系統である」という妄想を生んだ原因です。人間の頭部の系統に関する一つの事柄をもはや正しく見抜くことができなくなったことで、もう一つの事柄を正しく見抜くことも学ばなくなったのです。かくして、「人間存在はまるごと動物と近縁である」という説が人間観へと忍び込んだのです。そして、基本的に近世の文明の進化発展の中で世界観に浸透したこと、即ち、「ちょうどこの世における善と悪、天国と地獄が対立しているのと同様に、人間の頭は最も高貴なものにされ、他の部分はこれに対立している」という、三体性に取って代わった二元論が、人間存在を把握する仕方にも忍び込んだのです。本当は、次のことを知っておくべきだったのです。「人間が世界の中で自分の頭部を通して苦労して手に入れるものは、確かに差し当たり世界の叡智のおかげであるが、しかしそれはルツィフェル的な叡智である。そしてこのルツィフェル的な叡智は、ようやく徐々に他の諸要素によって浸透されるに違いない」と。
■Ⅱ-22 人類の進化発展が土星、太陽、月の進化発展を経て、地球の進化発展が始まった後で、ルツィフェル的存在を人間の頭部のつくりへ組み込んだ、あの霊的な力、それがミカエルの力です。『ヨハネの黙示録』に「そしてミカエルによって彼に敵対する霊たちが地上に投げ堕とされた」とあります(☆8)。つまり、ミカエルによって彼に敵対するルツィフェル的な霊たちが投げ堕とされたことによって、人間は初めて彼の理性、即ち人間の頭部に芽生えるものに満たされたのです。
■Ⅱ-23 かくして、自分の敵対者を人間に送ったのはミカエルでしたが、それは、人間がこのミカエルへの敵対的要素、即ちルツィフェル的な要素を受容することを通して、差し当たり彼の理性を受け取るためでした。その後、人類の進化発展の中にゴルゴタの秘儀が起こりました。キリスト存在がナザレのイエスの死を経て、人類の進化発展と結びついたのです。
■Ⅱ-24 準備の時代は過ぎ去りました。ミカエル自身が超感覚的世界の中でゴルゴタの秘儀という事象に関与しました。ミカエルは19世紀の最後の三分の一以降、人類の進化発展の中で全く特別な位置を占めてきました。第一にミカエルとの関係における人間というこの位置を正しく認識することによって立ち入る必要があるのは、たとえば私たちが人間の頭部と頭部以外の有機体に関して今日提示しようと試みているような秘密に立ち入ることです。
■Ⅱ-25 本質的なのは、「人々は人間の頭部の本当の起源を認識しなかったので、人間の有機体全体の起源に関して妄想に陥るほかなかった」ということが人々に明らかになるべきだということに違いありません。人々は、ルツィフェル的な教養がまず人間の頭に根づいたのだとは思いたくなかったので、人間の頭部と関連があるものは人間の頭部以外の有機体と同じ起源に帰されるに違いないという妄想に陥ってしまったのです。人類はこれらの秘密を見抜かなければなりません。人類は、単純な頭の理解、単純な地上的な叡智或いは利発さによって与えられるかもしれないものを、それ自体の内部から新しい神的秘密を把握することによってこれらすべての事柄について改善せねばならない、などという認識に対し、大胆かつ勇敢に向き合えるようにならなければなりません。そしてまず、回心の前に間違いなくあった大きな誤謬、即ち「人間の身体はまるごと動物系統にその起源がある」という、進化論の唯物論的解釈の中に含まれている誤謬を正すことができなければならないのです。
■Ⅱ-26 これが、そもそも私たちの前に立っているこの人間の中に、一方でただ身体に宿るだけの単なる霊的-魂的なものを、他方で魂なき体的なものを見て取るのではなく、たとえルツィフェル的な仕方であっても、人間の頭部で働いている具体的-霊的なもの、そして人間の身体全体で働いているこの具体的-神的-霊的なものを再び見て取れるようになるための、ただ一つの道でしょう。ただしこの具体的-神的-霊的なものには、頭部以外の有機体においてはアーリマン的本性をもつ敵対者がいるのです。
■Ⅱ-27 イマギナツィオン的に言えば、ルツィフェル的なものはミカエル衝動によって人間に組み入れられたと指摘することができます。そして今度は、ミカエルが成ったものによってアーリマン的なものが、人間から取り除かれなければならないのです(☆9)。私たちの外的な学問の立場から見ると、今日、解剖学や生理学などを通して認識する事柄、或いは人間の外的な感覚的観察において目の当たりにする事柄が真実であるかのように、私たちの意識に対して人間は向かい合っています。私たちは全身の隅々にまで宿っている霊的なもの、即ち体的なものを伴った具体的-霊的な存在を見るようにして、人間を見て取ることができるようにならねばならないのです。私たちは次のことを意識しなければなりません。「生きている人間の中に流れている血液は私たちが滴らせる血液とは異なり、特別な仕方で霊化されているものなのだ」と。そして、血液を通して脈動している霊のことを知らなければなりません。私たちは、神経系がまさに痺れる一場面などで、神経系を通じて脈動している霊のことを知らなければなりません。私たちは全ての個別的な生命現象の表出の中に霊的な要素も見て取ることができなければならないのです。
■Ⅱ-28 ミカエルは強い力の霊です。ミカエルは、人類の進化発展に入り込んで、一方での抽象的な霊性と他方での物質性とを別々に捉えない能力を与えてくれるに違いありません。人々はこの物質性を打診したり切断したりしますが、それが霊的なものであってもその外的に顕現した現象形態に過ぎないことを露知らずにいます。ミカエルは、物質的なものの中のいたるところに同時に霊的なものを見て取るというかたちで、物質的なものの本質を見通すことができる強い力であり、それが私たちに浸透していかなければならないのです。人類意識の或る太古の段階について指摘されていたことですが、この太古の時代に、霊的な意味で「コトバの内には生命があった」(☆10)、「そしてコトバは肉となり、私たちの間に住んだ」(☆11)と福音書記者ヨハネは述べています。コトバが肉と一つになったのです。そしてミカエルの啓示がこのことを先導したのです。これらは全て、人間の意識の中のプロセスであり、それがそこに暗示されています。逆のプロセス、福音書記者ヨハネの言葉に別のことを付け加えなければならないという、逆のプロセスが始まらなければなりません。人類が地球と共に没落しないようにするために、霊界からキリスト衝動によって地球と一つになったもの、そして人類と結びつかなければならないものを、人間がどのように受け容れるのか、そのことを見てとる力が私たちの意識の中に生じなければならないのです。人間がどのようにしてその頭部の中にだけでなく、そのからだ全体の中に霊的なものを受け容れるのか、人間がどのようにして霊的なものに完全に貫かれるのか、そのことを見てとらなければならないのです。キリスト衝動だけがその助けとなることができます。しかし、ミカエル衝動によるキリスト衝動の解釈も、その一助となるに違いありません。そうすると、先の福音書記者ヨハネの言葉に次のことを付け加えることができるでしょう。即ち「そして、肉は再びコトバとなり、コトバの国に住むことを学ぶ、その時が来なければならない」と。
■Ⅱ-29 四つの福音書の最後(『ヨハネによる福音書』の最後)には、「他にも書かれていないことが数多くある」(☆12)と書かれていますが、それは決して誰か或る後世の加筆者による創作なのではありません。このことと共に、人類に徐々に明かされうる事柄が示唆されています。福音書はそのままでなければならない、触れてはならないかのように見ている人は、福音書をよく理解していません。私が皆さんにいつも言ってきた言葉ですが、福音書は次のキリスト・イエスの言葉に従って解釈されなければなりません。即ち『マタイによる福音書』に記されている最後の言葉、「私は地球紀の終わりまで、いつも汝らと共にいる」という言葉です(☆13)。そして、この言葉の意味は次の通りです。——「私は汝らに、福音書が書かれた時代にのみ私自身を啓示したのではない。私は、汝らが私への道を求めるならば、いつでも私の昼の霊ミカエルを通して汝らに呼びかける。汝らは、さらに続いていくキリストの啓示によって、確かに第一の千年間の福音では知ることができなかったが、第二の千年間の福音では知ることができることを、福音書に付け加えることが許されるであろう。そして、それに続く数千年間では常に新しい事柄を、そこに付け加えることができるのだ」——。というのも、『ヨハネによる福音書』に書かれている「太初にコトバがあった」(☆14)、「そしてコトバは肉となり、私たちの内に住んだ」ということが真実であるように、「人間の肉は再び霊化されなければならない。そうなれば、神の秘密を見るために、コトバの国(☆15)に住むことができるようになる」ということも全く同様に真実であるからです。「コトバの肉化」が最初のミカエルの啓示であり、「肉の霊化」が第二のミカエルの啓示であるに違いないのです。
【訳者註】
☆1)「魂的-霊的なものを媒介する表象」「体的なものを媒介する表象」と言われるところの媒介する(vermitteln)の意味が取りにくいかもしれない。ここでの「媒介する」は、一般的な意味で、つまり「双方の間に立ってとりもつ」という意味で使われている。「表象」が何と何の間に立ってとりもつのかといえば、それは第一講■Ⅰ-24以降で述べられている「事柄(Sachen)」と「名称(Namen)」である。「魂的-霊的なもの」或いは「体的なもの」ということでその「事柄」と「名称」をとりもっているのが「表象」という理解である。
☆2)通常は霊-魂-体、思考-感情-意志の三分節の対応に慣れている読者にとって、ここで「思考・意志・心情(Gemüte)・感応(Fühlen)」と四分節で語られているところが目につくかもしれない。これは、感情の部分が厳密には内面から生じるGemüte(心情)と、外部からの刺激で生じるFühlen(感応)からなっているという事情を表していると思われる。そしてこの四分節的理解は、最終的に第六講■Ⅵ-21以降において述べられている「二つの魂的プロセスの交差」「世界の思考内容と人間の意志の交差」に関する理解において最大限に拡充されることになると思われる。
☆3)本講義の副題にある通り、大天使ミカエルが「人間存在の本来の秘密を啓示する者」だということがここで語られている。
☆4)ミカエルがルツィフェルを投げ堕としたのは紀元前8世紀頃、つまり七大天使(オリフィエル、アナエル、ツァハリエル、ラファエル、サマエル、ガブリエル、ミカエル)をもって約300~400年ずつで一巡する時代の周期でいうと、「こんにちのミカエルの時代」の一周期前の「古いミカエルの時代」のことであり、「ギリシャ-ラテン文化期」が始まった頃のことである。このことは本講義では全体を通じて自明の前提となっていて、講義内では漠然とわかる程度で直接明確には言及されていない。しかし、このことを踏まえておかないと、講義全体を読み誤る可能性があるので注意が必要と思われる。
☆5)このくだりは、第一講の冒頭でミカエルの力が働きかける第一の対象が「地球の利発さ」と言われていることと関連している。つまり、「人間の利発さ=知性(知性と感覚的知覚)」は、同時に「地球の利発さ=知性(知性と感覚的知覚)」であるということ。第一講の(☆2)も参照。
☆6)これは1899年にいわゆるカリ・ユガ(暗黒時代=人々が神的存在から遠ざけられ、霊的堕落を引き起こしている時代)が終わり、それと共に新しい光の時代が霊的に始まったということ。
☆7)■Ⅱ-17から■Ⅱ-21までで語られているのはカリ・ユガの時代の認識状況と、☆4で述べたその時代の終わりへの移行の詳細である。「認識の夜」「認識の罰」などといった表現はカリ・ユガの時代の認識状況を表した表現であると思われる。この時代においてアーリマンの上昇が原因で「人間の体はまるごと動物系統である」という認識が一般化していた状況は、■Ⅳ-33から■Ⅳ-35で語られる「父なる神(内なる神)が見出せない」=「無神論」=「病気」の状況であり、その対極として見出される「父なる神(内なる神)が見出せる」=「人間の三分節的に調和の取れる有機体がまるごと神から生まれたものである(薔薇十字会のマントラの最初の一文“Ex deo nascimur”にあたる)ことを認識している」=「健康」との対応を考える必要がある。これは後述される「ミカエルが成ったものによって人間からアーリマンが取り除かれなければならない」ということ、「肉の霊化」と直接関係していると思われる。
☆8)『ヨハネの黙示録』12章7節-9節を参照。
☆9)ここは読み方に特に注意が必要な箇所であると思われる。原文は次のようになっている。In Imaginationen gesprochen, können wir zurückweisen darauf, wie das Luziferische dem Menschen einverleibt worden ist durch den Michael-Impuls; durch dasjenige, was der Michael geworden ist, muß ihm nun wiederum das Ahrimanische genommen werden.私訳は上に掲載した通りである。原文では「;」を挟んで時代が離れている。本講義では、ミカエルがルツィフェルを投げ堕としたのが紀元前8世紀頃≒ギリシャ-ラテン文化期が始まった頃であるのに対し、「アーリマンの上昇」が紀元後15世紀頃≒ゲルマン文化期が始まった頃とされ、ミカエルは19世紀の最後の三分の一以降、人類の進化発展の中で全く特別な位置を占めてきたと言われている。そして本講義全体を通じてこの「こんにちのミカエルの時代」では、「ミカエルが成ったものによって人間からアーリマンが取り除かれなければならない」と言われている。ここのihmは最後の受け身を表しているgenommen werdenとの関係から、主語であるアーリマンが「人間から」「取り除かれる」と取る必要があると思われる。「ミカエルが成ったもの」という表現は奇妙に思われるかもしれないが、つまるところは、■Ⅱ-28や本講義にて後々語られる、人間に入り込んでいく必要のある「強い力」「強さ」ということで説明されていることに該当すると思われる。そう見ると、この文章は「ミカエルが成ったもの」という表現で「ルツィフェルの救済⇒聖霊への甦生」、「ルツィフェル的知性の救済⇒聖霊的知性への甦生」ということが関わっていると思われる。それについては第一講の☆2のnoteを参照。なお、■Ⅱ-28のこの「強い力」「強さ」を理解するためには、その対極である「弱さ」がどういうことなのか、ということが理解する必要がある。「強さと弱さ」の対極については、この■Ⅱ-28と共に第三講の■Ⅲ-28、第四講の■Ⅳ-38、第五講の■Ⅴ-24、第六講全体などを参照。この対極は、弱さから強さへの変容という意味で、本講義を理解する上で重要な対極である。特に■Ⅲ-28、■Ⅳ-38との関連で言えば、「強い力」は「御霊(聖霊・外なる神)が見出せない」=「(ルツィフェル的)知性が人間を弱くしている」の対極として位置づけることができる。「ミカエルが成ったもの」という言い方に、このように「ルツィフェル的知性(弱さ)の救済⇒聖霊的知性(強さ)への甦生」の意味が含まれているとすれば、それはちょうど薔薇十字会のマントラの三番目の一文“Per spiritum sanctum reviviscimus(聖霊によって甦生する)”に相当することが語られていることになると思われる。このことにより、ミカエルの道に続くキリストの道も含めて、アーリマンに対する武装が成立して、それを取り除くことができるという説明になっている。
☆10)『ヨハネによる福音書』1章4節を参照。
☆11)同書1章14節
☆12)同書21章25節を参照。
☆13)『マタイによる福音書』28章20節を参照。シュタイナーは通常「私は世の終わりまで、いつも汝らと共にいる」と言われるところの「世」(Welt)を、「地球紀」(Erdenzeiten)と置き換えている。ゴルゴタの秘儀以来、キリスト存在そのものは地球に宿っているということと併せて考えることができるだろう。
☆14)『ヨハネによる福音書』1章1節参照。
☆15)進化発展の第八天体領域(天体領域Ⅷ)のこと。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
