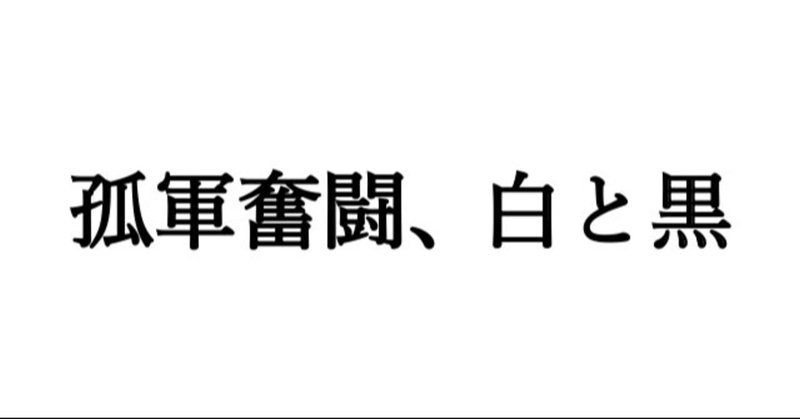
短編小説「孤軍奮闘、白と黒」
屈折した光によって曲がって見える絵筆を透明なバケツの中で泳がせる。丸い空気が転がるように浮かんでくる。毛先は水の中で自由になって、乾いているとき空気の中で見せるような姿になる。引き上げると毛の色が濃くなった。水滴が滴り落ちる前に雑巾で押し付けるように拭う。
「なんか眠くなってこない?」
琴葉があくび混じりの声で尋ねてきた。
「眠いかも」
「お昼食べたらさあ、まともに起きてらんなくない?」
「午後物理だよ?」
「うわぁ完全寝るわ。もう、ギブアップ」
琴葉は絵筆を置いて、道具を脇に片付けて机に突っ伏した。長い髪が頭の後ろで広がる。私は持ち替えた細筆でまだ描こうと思う。
昼休みは毎日琴葉とここへ逃げて(・・・)くる。美術部は自由参加だが、昼休みに活動するのは私たちくらいだ。私がここにいることを嗅ぎつける者はそう多くない。
そう多くないけれど、ときどきはやってくる。招かれざる客が。足音がして、うんざりしながら目を向ければ、廊下の窓が開いていて、そこから三人の男子が興奮した様子でこちらを確認している。
彼らは部員でもないのに扉を開けて入ってくる。古い金属のレールが引っ掛かるような音を上げる。扉を閉めることもなく何事か相談しだしたかと思えば、先頭の生徒がためらいながらこちらへ近づいてくる。他の二人はにやけながら彼を押し出そうとする。
「あの、篠田さんですか?」
「そうだけど」
「篠田さんのお母さんって、咲木(さくき)歌乃(かの)さんですよね? サイン貰えませんか」
「悪いけど……」
私は描く手を止めないで断ろうとするけれど、相手はそれを遮って食い下がる。
「母が、すごいファンで、どうしても欲しいから貰ってきなさいって言うんですよ」
青ネクタイだから、中学生だ。中学棟からここまでなんて一番離れているだろうに、良くわざわざ来るものだ。
「そういうの、全部断ってるんで」
「……そうですか」
言い返されないうちに、できる限りそっけない声でダメ押しする。
「私は咲木歌乃のマネージャーでもファンクラブの役員でもないんで」
三人組は残念そうに去って行った。足音が聞こえなくなってから、姿勢はそのままに顔の右側だけこちらに向けて琴葉が言う。
「相変わらずきっついねえ」
「あれくらい言わないと理解しないから」
この言葉はちょっと不正確だった。私は理解を求めているわけじゃなくて、ただ単に二度とああいう無神経なお願いをしないでほしいだけだ。
琴葉は私の気持ちを分かっている人間だ。何人かは分かってくれる。でも大概の人は私のことを有名女優の娘としか認識しない。私が生きているのは私の人生なのに、まるで母が主役の物語に出てくる娘の役みたいな扱いをされる。それが耐えられない。母は日本中で知られているから、すなわち私の存在も日本中の人が知っている。咲木歌乃の長女。一人娘。それがいつも私にくっついてくる最初の情報なんだ。
私はここ数年ずっとオセロゲームをしている。私のことを篠田美由樹だと認識している人が白で私の持ち石。咲木歌乃の娘だと認識している人が黒。生まれたとき全員黒だったのを、私の努力でいくつかひっくり返した。できることなら全ての石を白にしたい。まずは手近なところから増やしていくんだ。少しずつ。
駐車場へ続く階段は木陰になっていて涼しく静かだ。煉瓦造りの表面がほとんど影で塗りつぶされていて、木漏れ日が落ちるところだけ本来の赤褐色に映えている。頭上で葉擦れの音が重なっている。誰もいない。この学校に四年通っているが、ここで他の人を見た記憶がない。いつも一人きり。だからここへ来るともう学校にいる気分ではなくなる。今は、パブリックな時間とプライベートな時間の境目の、穏やかな二分間。
固いアスファルトの上に、滲むほど濃い白の塗料で駐車スペースが区切られている。停まっている五台の車は遠くからでも見分けられるが、私が見つけるより早く扉が開いて、グレーのプジョーから紺色のスーツを着た滑川さんが出てきて、こちらに向かって笑顔を見せる。私はまるで小さい子みたいに駆け寄る。
「おかえりなさい、美由樹ちゃん」
「ただいま!」
この挨拶が交わされると、今日も一日終わったなと実感する。身体が軽くなって緊張が緩むのだ。
車の中は石鹸の香りがする。生きてきて一番嗅ぎなれた香りだ。斜め左に滑川さんの頭が見える。短い灰色の髪の毛はよく梳かれて揃っている。白い手袋をはめた手で行うハンドル操作がいつ見ても上品だ。
「ねえ、イケオジって知ってる?」
「イケてるおじさんってやつかい?」
「滑川さん、それだよ絶対」
「イケてないおじさんの略だけどね」
「そんなことない。超かっこいい」
「参っちゃうな」
頬の端の皺で苦笑いしているのが分かる。私はこの年を取った穏やかな紳士のことが本当に大好きだ。車の中はもうプライベートな空間だから、完全にリラックスしてしまう。
「何だか眠くなってきちゃった」
「寝てていいよ。着いたら起こすから」
滑川さんの車は文字通り私の乳母車だったし、今もそうだ。
目を閉じて、頭の中がオフになるのを感じながら、滑川さんのことを思い返した。彼はうちの運転手だけど、母は仕事のときはほとんどマネージャーに送り迎えされていて、普段ずっと仕事をしているから、滑川さんの車に乗ることは稀なのだ。だから彼は事実上私の専属運転手のようになっている。何人かいるうちの人たちもそう認めている節があって、それがすごく嬉しい。
昔は、もしかしたらこの人がお父さんなのかもしれないと思っていた。そうだったらいいな、と願ってもいた。家政婦はたまに代わるのに、運転手は私が生まれたときからずっと代わらず滑川さんなのだ。小学生の頃自分が生まれてからどう育ってきたか調べてまとめる授業があったが、父と自分の写真を貼る欄には迷わず滑川さんとの写真を選んだ。実は一時期確信すらしていた。今でもこの人が父親だったらどんなに幸せかと考える。でも酔っぱらった母がとうとう白状した名前は滑川さんとは程遠い、会ったこともないアナウンサーだった。そのことを聞いた日から、それまで母にも滑川さんにも誰にも似ていなかった私の顔は、まるで魔法が解けてしまったかのようにそのアナウンサーに似ていった。年齢を経るごとに似ていくのを感じた。画面越しでしか見たことのない人間との血のつながりを確信するのは非常に気持ちが悪くて、年を取りたくなくなり、誕生日ケーキのろうそくを吹き消すあの行事が嫌になった。だから私はもう三年は誕生日にケーキを食べていない。
カメラ目線のあの顔を意識の中から消し去ろうと奮闘するうちに自宅が近づいてくる。目を開けなくても音と車の動きで分かる。結局眠れなかった。
滑川さんが玄関の扉を開けて、私は中へ入り、
「高田さんただいま!」
と叫ぶ。すぐに家政婦の高田さんが出迎えてくれる。
「おかえりなさい。疲れたでしょう。おやつがあるから、荷物を置いたらダイニングへいらっしゃい」
私は重いリュックサックを手に持ち替えて最後のひと踏ん張りで階段を上がる。自分の部屋に入って、机の上にリュックサックを置いて、目を閉じていたために車でいじらなかったスマートフォンを確認する。それから普段着に着替えて一階へ降りる。
おやつはプリンアラモードだった。生クリームが付いたさくらんぼを真っ先に口に入れた。果実の甘さと人口の甘さが混じらないで舌に伝わる。半拍子遅れてはっきりとした酸味が口の中に広がった。次にプリンを少しだけスプーンで掬って味わう。買ってきた洋菓子店がすぐに分かる。
高田さんが私の向かいのソファーに腰かけて話しかけてきた。
「今日はどうだった?」
「またサインくれって言われちゃった。お母さんの」
「それで、どうした?」
「断ったよ」
「そりゃそうよね。学校だもの。断って正解よ。嫌ねえ人を使い走りみたいに。大丈夫? 気分悪くない?」
「もう平気だよ」
本当に言いたいことが何なのかは察しがつく。高田さんは一瞬ためらって、こう切り出した。
「ねえ美由樹さん。今日金曜日だから、素子さんテレビに出る日よね」素子とは母の本名だ。
「一緒に見よ。今夜はスイーツのお店に行くんだって。パンケーキ、好きでしょ?」
「うーん、ちょっと無理かな。約束あるし」
「そうなの」
高田さんは見るからにうろたえている。口から出そうになっている言葉を飲み込んで、相応しい言い方を組み立てているのだろう。私は気づかないふりをして、先に言葉を切る。
「だから、今夜は夕飯いらない」
「ねえ美由樹さん」
高田さんは両眉を下げて困った顔つきになる。私の目を見て、視線の力で私が目を逸らすのを阻む。
「夜遅くに高校生の女の子を呼び出す男なんて、百パーセントろくな男じゃないよ? おばさんには、分かるの。もうそんな人と会うのはやめにできない?」
「できないよ」
告げると、高田さんは穴が開いた風船みたいに迫力を失っていった。ちょうどプリンアラモードを食べ終わったので、ここにいる理由はなくなった。
「宿題してくるね」
「そう。分かったわ。何があっても、日付が変わる前には帰って来てね」
エプロンの端を指でいじりながら俯く高田さんを見ると少し胸が痛む。彼女は本気で心配して忠告してくれているんだろうし、関心を持つのは私への愛情なんだと理解している。でも、いくら母親代わりみたいなことをしても、本当の母親じゃないから、これ以上強くは言えないんだ。私はそこに付け込んでいる。
でも仕方がない。私は私のやりたいように生きる。
宿題を済ませてから、こっそり化粧をする。アプリで見た手順で化粧をすると、目鼻立ちがくっきりして別人のようになる。急に大人っぽくなった姿に将来の自分の顔を想像してしまう。チークを塗った頬はオカメインコみたいだ。
滑川さんの目を盗んで外へ出て、駅まで徒歩で行き、電車に乗る。私は一番ひっくり返りそうにない石をひっくり返しに行くんだ。
でも、私が誰と会っているのかバレたら、うちがひっくり返っちゃうかもしれない。待ち合わせ場所で手を振っているのはムラさんだ。彼は母のファンクラブの会員だ。クラブの旅行のときに知り合って、それから籠絡した。手を差し出すと、わざとらしく
「いいの?」
と確認を取り、嬉々として手を握ってくる。駅前からもう繁華街の騒がしさが始まっている。人込みの中をムラさんは進んでかき分けていく。私は手を引かれてついていく。柔らかい大きな手から汗が出てきて、私の右の掌に染み込むみたい。
ムラさんは滑川さんみたいな善良な紳士とは全く違うタイプだ。脂肪の付いたお腹が前に突き出していて髪の毛が薄く、身体中から煙草の匂いがする。典型的なオヤジだ。
「予約してあるよ。中華でいいんだよね?」
「中華食べたい食べたい! 行こ!」
街の喧騒にかき消されないように大声で答えた。
薄暗い個室で向かい合うとムラさんは
「お母さんは元気かい?」
と尋ねてくる。最初は毎回この質問から始まる。
「最近会ってないからわからない」
「そうか……。まあ忙しいからなあ。今日も番組あったな、収録だろうけど。美由樹ちゃんは元気かい?」
「びみょー。疲れてる」
「試験でもあったか?」
「ないけど、毎日の生活に疲れちゃうよ」
「分かるなあ。俺もそうだもん。美由樹ちゃんが何やってそんなに疲れているのか知りたいなあ」
しゃべらせることで私の気持ちを良くしようとしているのだ。私から質問してもあまり答えたがらず、
「それより美由樹ちゃんは……」
と聞いてくる。自分のことは隠したいのかもしれない。
会話の途中で数秒沈黙があった後、ムラさんはにやけて指摘した。
「鏡見て、気づくかい?」
「何に?」
「美由樹ちゃん、最近ますますお母さんに似てきて美人になった。やっぱり親子だなあ。男の子にモテて仕方ないだろう?」
誰も信じないだろうけれど、私たちは寝ていない。ただ夕食を一緒に食べて、お話しするだけだ。だからこの関係は恋人同士とか交際などではない。では、何だろう。断言できるのは、二人の間に漂う雰囲気は決して「年の離れた友だち」とかいう清潔なものではないことだ。もっと互いの欲求を満たしあうものに違いない。
私たちのデートは私が食事を終えるまで続く。ムラさんは私のペースに合わせて少しだけ料理を食べる。蓋をずらして温かいお茶をゆっくり飲んでいると、ムラさんは尻ポケットからお財布を取りだした。援助交際じゃないけど、ムラさんは毎回お金をくれる。会計はもちろんムラさん持ちなのに更にお札を渡してくる。今日もわざと数えないで何枚かお札をくれた。
「付き合ってくれたお礼さ」
私はそれを財布にしまう。お腹が膨れて、口の中に辛みが残っている。ムラさんは楊枝を使いだした。
なんとなく成功する気がしたから、私は久しぶりに言ってみた。
「ねえ、今日泊まらない?」
「何言ってるんだよ」
声が震えないように。余裕がないのがバレないように。自然と、だ。
「私ムラさんのこと、好きだよ。朝まで一緒にいようよ」
全力の演技にもかかわらず、強張った表情ですぐに答えが分かって、返事より先に落胆した。
「ダメだよ。いくら何でも。そこまで歌乃ちゃん悲しませることはできないだろ」
私は涙をこらえて横を向く。何で私より先に母のことを気にするのだろう。どうして歌乃ちゃんの気持ちは考えられて、私の気持ちを考えることはできないのだろう。まだダメなのだ。この人は私の背後に見える女優しか見えていない。
でもここで諦めたら今までの苦労が水の泡だから、耐えて次の約束を取り付けよう。私は盤面が全部白い石で埋まるまで戦い続けるのだろうか。きっとそうだろう。もう何年もそのためだけに生きているから。この戦いが全ての原動力であり、行動の根拠となっているんだ。
結局私たちは目を合わせずに店を後にした。通りの騒がしさは増していた。虚しさが景色を不味くした。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
