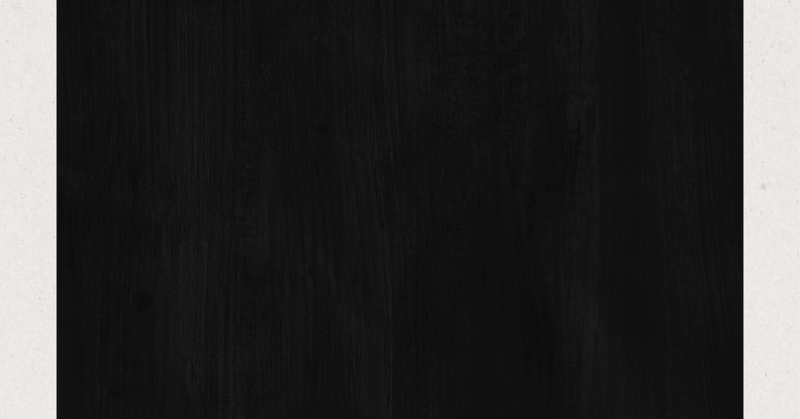
20240424
「僕はあと何回、満月を見るのだろう」これは僕が特に好きな一節で映画「シェルタリング・スカイ」で原作者のポール・ボウルズがナレーターのように語った話の一部.
人生100年時代と言われる現代で満月を見るのは平安時代の40年ほどの寿命だった世界とは程遠く軽いものになってしまっているかもしれない.しかも80年生きれば1,000回は満月を見ることができると言われている.だけど80年も生きれる保証はどこにもない.明日僕はこの世にいないかもしれない.そんな満月が毎回遠く、儚いようにも思えてしまう.
この映画の音楽を担当したのが音楽家の坂本龍一氏なのだが、この題名にもなっている数字の羅列は坂本氏がよく使うもので少し使わせてもらった感じである笑.僕の好きな音楽家の唯一の存在でもあって常に憧れの存在でもある.中学生の時にYMOの「Tong Poo」に出会い感動したのを覚えている.この「Tong Poo」は矢野顕子さんが詩を用いて「Tong Poo」を発表していたり坂本龍一のBTTBでピアノソロとして演奏されている.
他にも「音楽図鑑」から始まって「エスペラント」「未来派野郎」など一日中家の中で音楽が奏でられていた.エスペラントは特に特徴的で民族音楽をベースにしたような音色と独特なリズムが耳に残る.外で聞くと外音のノイズが徐々に協調し一つの音楽になっているかのように感じられる.これは一人の中の唯一の音楽祭が奏でられているようで楽しかった.
矢野顕子さんと言えば未来派野郎の「Ballet Mecanique」の詩を書いたことでも知られていて音楽を聞けばわかるように英語の詩から日本語の詩に変わった瞬間全く違う音楽になったかのように思えるほど雰囲気が変わることに驚く.
僕が坂本龍一の音楽を好むのは音楽の自我性を感じるからである.ウィーン派にハイドンやモーツァルト、ヴェートーベンがおり、新ウィーン派にはシェーンベルクやヴェーベルン、ベルクなどの有名人が並んでいるが新ウィーンがやったのは革新ではなく自分を作り出したことだ.
正にシェーンベルクは今日の12音技法を作り出したことで有名だが、なぜ作り出したのか.という謎は解けない.なぜならば新ウィーン派以前にウィーンはが音楽の全体の枠組みをこれ以上ないほど美しい構造を作り出した.しかしシェーンベルクは12音技法を作り出した.
坂本龍一は今まであったメロディの音楽と離れたテクノ音楽を作りだした.そこには独自性があるが僕は音楽家としての欲求が作り出したものだと感じる.いくら既存のメロディにマンネリを覚えても新しい音楽を作ることは容易ではない.坂本龍一が若者の1980年代はようやく機械学習などのシステムが生まれ徐々に今のコンピュータ各組ができた頃だ.その時代にコンピュータを使った音楽を試そうとする変わり者はそういない.
やはりそこに魅力を感じるのかもしれない.
僕は音楽の他に映画を見るのが趣味なのだが「戦場のメリークリスマス」も素晴らし作品だった.これは坂本龍一に限らず大島渚監督の素晴らしさを感じるものだったのだが、とにかく言語がカタコトなのが良い.悪く言えば耳が良くても聞き取りは不可能に近いかもしれないがカタコトによって当時の敵と日本の区別がハッキリと見せつけられる.
最後のシーンでハラ軍曹(ビートたけし)がローレンス(トムコンティ)に対して英語で話しかけるのは日本人としての威厳を捨て敵に降伏している感覚を感じさせる.
同性愛の映画と評価されることもあるそうだが、間違ってはいないのではないかと思っっていて、ヨノイ大尉(坂本龍一)がセリアズ(デビット・ボウイ)を特別扱いしているところに性的な愛を感じることや同性愛的なシーンが多いことから想起させられる.
しかしこれはヨノイ大尉の目線であってセリアズではないことは注記しなければならない.ネタバレにはなってしまうがヨノイ大尉にセリアズがキスをするのは「性的な愛」ではなく「人間としての愛」であってヨノイの行いを正そうとするセリアズの熱い思いがここに反映されている.
少し映画の評価みたいになってしまったが素晴らしい映画であると思ってくれたならば嬉しい.
僕は今まで坂本龍一の音楽を聞いて育ってきたのかもしれないと思うほど常に頭の片隅には音楽が流れていた.幼い頃はショパンの革命のエチュードにハマって音楽の先生に無理を言って弾いてもらったが、そのあとは時間があれば坂本龍一と検索して楽曲を聴く毎日を送っていた.幸運なことに僕が生まれた21世紀ではレコードではなくスマホが存在していたから楽なもので中学生以降はスマホで音楽を聞いて育つことができた.
しかし悲しいことに偉大な音楽にも寿命があった.2023年の3月28日明朝に亡くなった.僕はショパンやバッハが好きだったが、その人はこの世にはいないから常に故人の素晴らしい音楽を聴くのが当たり前だった.しかし自分が生きている内に尊敬する音楽家が亡くなってしまうのは本当に辛いものだった.
そこで僕は初めて「死」について感じることが多くなった.小学生の頃から「死」について考えることは多くて、ある時には死ぬことが怖くて寝ることができない日もあった.しかしそれは僕の想像の中の話であって実際に死を感じさせるものは映像の中でしかなかった.
自分が明日生きて生活できる保証はどこにもないことに気づき、かなり怖くなったのを覚えている.そんな時に、シェルタリング・スカイのあの一節を聞いてから死ぬことではなく老いていくことの儚さと美しさに惹かれるようになった.今でも時々この一節を思うことがあるのだが多くの人の生きる糧にもなるのではないかと思う.常に死は身近にあるものだが生きているうちに見れる美しいものはたくさんある.その見れるものはいつしか見えなくなるのに無限に見えることのように感じてしまう.
「僕はあと何回、満月を見ることができるだろう」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
