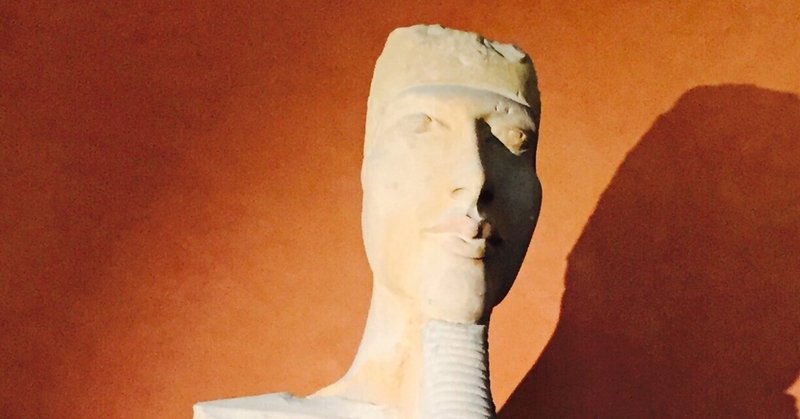
ライフリンク・メディア報道・新聞の社説から⑥
「孤独・孤立」は、凶悪犯罪を生む土壌にもなります。2021年12月に起きた大阪北区クリニック放火殺人事件で、死亡した61歳の容疑者のスマートフォンの電話帳には登録が1件もなかったといいます。容疑者の行為を他人を巻き込んで自殺する「拡大自殺」と推察する専門家もいます。この悲惨な事件の再発防止に向けて、事件を「孤独・孤立」から読み解こうとする社説があります。
2022年1月17日の毎日新聞社説「大阪ビル放火1カ月 悲劇繰り返さないために」は、「孤独・孤立は個人だけではなく、社会全体の問題でもある」と指摘しています。
大阪市北区の心療内科クリニックで25人が犠牲となったビル放火殺人事件から1カ月がたった。
61歳の谷本盛雄容疑者が死亡し動機の解明は難しくなった。それでも、捜査当局は真相究明の努力を尽くさなければならない。
谷本容疑者の自宅からは、36人が死亡した「京都アニメーション」放火殺人事件を報じる新聞紙面が見つかった。ガソリンも事前に準備していた。
クリニックの防犯カメラには逃げ惑う患者らの前に立ち塞がり、炎に飛び込む姿が映っていた。
離婚後、失業中の2011年には別居していた長男を包丁で襲う殺人未遂事件を起こしていた。
裁判所はこの事件の判決で、「さみしさや孤独感から自殺を考えるようになったが、一人で死ぬのが怖くなったため家族を道連れにしようとした」と認定した。
今回は、計画的に大勢の人を巻き込もうとしたとの見方が出ている。社会的に孤立していた可能性もある。
どこかで思いとどまらせることはできなかったのか。
孤独・孤立は個人だけではなく、社会全体の問題でもある。そうした見地から政府は実態調査などを進めている。
2022年1月17日の朝日新聞社説「無差別殺傷 孤立社会の病が見える」は、大阪北区クリニック放火殺人事件のほかに、京王線と小田急線で起きた無差別殺傷事件を取り上げました。
無差別に人々を襲い、自らも死を望む。そんな事件が続く。
本人の供述や犯行に至る経緯から見えてくるのは、社会からの孤立であり、人生に対する絶望だ。男子高校生が大学入試の会場前で受験生らを刺して傷つける事件も起きた。世代を超えた広がりを憂慮する。
昨年10月には、東京の京王線車内で乗客が刃物を持つ男に襲われた。20代の容疑者は失業や友人関係のトラブルから3カ月前に故郷を離れていた。警察の調べに「死のうと思ったができず、2人以上殺せば死刑になると思った」と話したという。
これに先立ち、8月に小田急線内であった刺傷事件でも、30代の容疑者は職を転々としてきた独り身の境遇を嘆き、「なんて不幸な人生なんだ」などと口にしたとされる。
そして大阪・北新地の雑居ビルでクリニックが放火された事件だ。25人が犠牲になった惨劇から1カ月が経つ。61歳の容疑者の男も死亡した。動機の解明は極めて困難になったが、当局は周辺への捜査を尽くし、真相に少しでも迫ってほしい。
男は11年前、家族に対する殺人未遂罪で懲役4年を言い渡されている。判決は、離婚後の孤独感から自殺を考えるなか、人を殺せば死ねるのではないかと思ったと認定。「家族以外との関わりを持つことができれば、更生は十分可能」と述べた。
しかし、刑務所を出た後も身寄りのない生活だったとみられる。防犯カメラに自ら炎に向かっていく映像が残っており、関係のない他人を巻き込んで自殺を図った可能性がある。
相次ぐ事件の原因や背景についても考察を深め、「望まない孤立」の解消に向けた手立てを、着実に進める必要がある。
病巣を探り、さらなる悲劇を防ぐことに、政府はもちろん、社会全体で取り組みたい。

新型コロナウイルスが社会の「孤独・孤立」を広げているという危機感から論考した社説もあります。
2021年4月11日の毎日新聞社説「政府の孤独・孤立対策 『まず自助』では救えない」です。
新型コロナウイルスの感染拡大が暮らしを直撃し、孤独や孤立の問題が顕在化している。
コロナ下の解雇や雇い止めは10万人を超えた。生活困窮の相談が急増し、昨年は11年ぶりに自殺者が増加した。
政府は内閣官房に対策担当室を新設した。だが各省庁が既に実施している関連施策をまとめるだけでは意味がない。実効性のある取り組みが求められる。
まず、失業や家族との死別などで、孤独や社会的孤立に追い込まれている人々の実態を具体的に把握する必要がある。
そのためには、この問題に取り組んできた市民団体などとの連携を強化することが重要だ。
子どもの居場所作りや女性の悩み相談、高齢者や生活困窮者への食料支援などで成果を上げているところも多い。
自殺は20代までの若年層の増加が目立つ。ネット交流サービス(SNS)を活用し、悩み相談に応じているNPO法人もある。対策の参考にしたい。
高齢者ら社会的弱者が孤立しやすい状況は、コロナ禍以前から指摘されていた。背景には、少子高齢化や過疎化、生活様式の変化などで人のつながりが薄れている事情がある。
さらに近年は、引きこもりの50代の子を80代の親が養って困窮する「8050問題」や、一人親家庭の貧困など新たな課題も浮上している。
孤独・孤立問題の実情はさまざまだ。これに応えるには、包括的な基本計画を立て、息長く取り組むことが欠かせない。
社会自体も変わらなければならない。
2021年1月26日の読売新聞社説「コロナと自殺増 きめ細かい支援で孤立を防げ」は、女性の「孤立」に焦点をあてています。
長引く新型コロナウイルスの流行が、女性や子供の暮らしに深刻な影響を与えたためだろう。
厚生労働省によると、昨年の自殺者数は2万919人で、前年を750人上回った。リーマン・ショック後の2009年以来、11年ぶりの増加となる。速報値のため、更に増える可能性があるという。
男性の自殺者は前年より減った一方で、女性は14・5%増えた。働く女性の増加が目立っている。再度の緊急事態宣言で、女性の就業が多い飲食や宿泊業界が打撃を受けている。昨年、非正規で働く女性は月平均約50万人減った。
在宅勤務の広がりで、育児や介護の負担も増している。昨年の家庭内暴力の相談は前年より5割増えたという。困窮家庭や一人親家庭を官民で支え、事態の悪化を食い止めねばならない。
孤独感が理由とみられる自殺が増えた点は見過ごせない。感染を避けるため家に閉じこもり、孤立している高齢者は多い。地域の見守りを手厚くする必要がある。
新聞の社説を見るシリーズは、いったん終わります。
写真は、パリのルーブル美術館にて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
