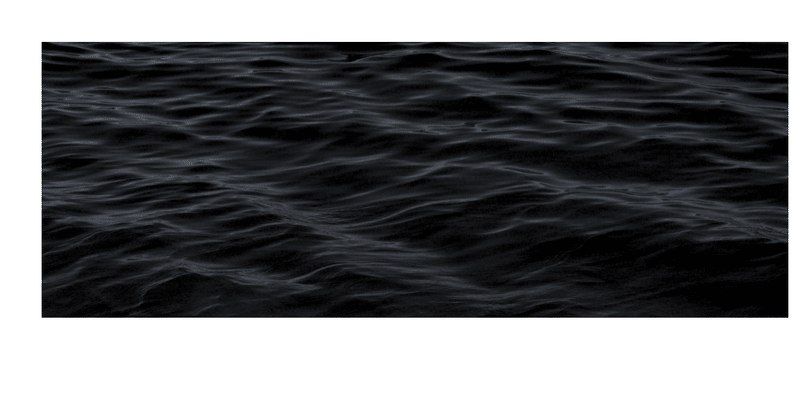
痣 第5話
▼第1話はこちら▼
襲来
「いえいえ。あなたがファミレスから真っ直ぐ帰宅されたことは、アパート近くのコンビニの防犯カメラ映像で証明されているんですよ」
「すみませんねぇ。関係者全員に話を聞くのが我々の仕事でして」
「西見さんは、あの後なにか予定があるようなことは言っておられませんでしたか? 人に会うとか……」
刑事たちは口々に言い、聞くべきことを聞いて去って行った。
気配が遠のくと、風岡つぐみはシリンダー錠のつまみをしっかりと横に倒した。
真鍮の冷たさが指から全身へと伝わる。
ついに、警察が自分という存在を把握した。
不自然ではなかっただろうか。
ファミレスでの一件については、執拗な取材攻撃に辟易したためという話で通したが──。
ここ数日、つぐみは満足に眠れない日々を過ごしていた。
あの記者のせいだ。
あの女が肉にフォークを突き立てた瞬間。自身の身が竦むのを感じた。捕らえられたと思った。
死してなお。否、この世に実体が存在しないからこそ。
あの女の凄まじい執念はつぐみを苛んでいた。
まるで、あの女の情念が自分の元へ刑事を差し向けたようではないか。
警察は、便宜上話を聞きに来ただけと言った。
本当にそうだろうか。
愛想の良いことを言いながら、目つきだけは悪かった。
無意識に舌を打つ。
──あなたの傍にいる五百扇雪彦さんは、靴の踵を踏む癖はありますか。
あの時、西見凛は本当にこれが最後の質問になると思っていただろうか。
踵を踏む──。
あの男は、本当に五百扇雪彦だろうか。
押し寄せる猜疑心から、つぐみは雪彦と距離を置いている。
すぐにでも違う土地へ向かおうかと考えたが、それは余りにも不自然な行為であった。
この名前なら自分は無関係だ。
にも関わらず、真綿がジリジリと首元に迫るこの感覚は何だろう。
あまりにも呆気ない、西見凛の死。
そして自分は、彼女の死の直前に行動を共にする現場を目撃されながら辛くも容疑を逃れている──。
それは、影彦の遺体が発見されてから現在に至るまで、一連の出来事を裏で操ってきた者が存在することを意味した。
つぐみは浅い呼吸を繰り返す。
つぐみに都合が良いように、裏から事件を操る存在。
その存在は、どこかで自分を見ている。
その存在は、風岡つぐみの過去を知っている。
そこに思い至った時、つぐみは玄関のドアノブを強く握りしめていた。
ここにいれば安全だ。
鍵をしっかりかけて、外に出なければ。
外でゴソッと音がした。
ドアノブに触れているつぐみには、安全である筈のシリンダー錠に外側から異物が差し込まれた感触が確かに分かった。
玄関をロックするために横に倒したつまみが、ゆっくりと回転していた。
「雪彦さん……?」
一縷の望みをもって、つぐみは震える声で呼びかける。
つぐみの自宅アパートの鍵を持っているのは彼だけだ。
微かな金属音と共にドアが外側へ開く。
果たして。
ドアの向こうに立っていたのは、五百扇雪彦ではなかった。
「俺の金、どうしてくれた?」
茶髪の男が、潰したような声で言った。
つぐみは呆然と男を見上げる。
金──。
その響きは、何故か山間の空気を想起させた。
迫り来る山々から吹き下ろされる木枯らしのような。
「そうそう、それだ。その目つき」
男がつぐみを覗き込んだ。
濁った黒目が、つぐみの強張る頬をなぞるように動く。
「印象を変えてみたところで、その目つきは変わらねえや。なァ?」
男がニタァッと歯を剥き出した。
分かった。
茶髪の、濁った目の男。
ボロ小屋に充満する臭気が、つぐみの鼻腔に蘇る。
あのボロ小屋のような家で、母は猫撫で声でこの男の名を呼んでいた。
──テツ。
助けを呼ぶか。
先刻ここを辞したばかりの刑事たちが、つぐみの脳裏に浮かぶ。
「すぐ分かったぜ。てめえが俺の金パクったてなァ」
テツの言葉で我に返った。
ここへ来たということは、この男は全てを知ったのだ。
どういった経緯で知ったかは不明だが、警察沙汰にしては、つぐみの身も危うい。
冬枯れの草の間から覗く、グレーのナイロン生地。
テツが言う金とは、あの金しかない。
「人、殺してまで手に入れた金ぇェェッ!! このガキがあぁっ!!」
テツがサバイバルナイフを手に突進してくる。
「いやあぁぁっ!」
躊躇している場合ではない。
助けを呼ばなければ。
今の名前、今の顔なら無関係で通せる筈だ。
あっという間に部屋の中ほどまで押される。
つぐみは必死でナイフを避けようと、テツの右腕を掴んだ。
しかし、力では敵わない。
テツは、そのまま力任せに体重をかけてくる。
もつれ合って床に倒れた。
避けられない。
尚も揉み合った末、つぐみは自分の腕で身体を庇った。
深い呻きが耳に入ったかと思えば急に静かになり、次いで頬に生温かいものが流れてくる。
「い……いやあぁぁっ!!」
サバイバルナイフがテツの首を切り裂いていた。
赤黒い血液が滝のように溢れ、つぐみの顔や衣服を濡らしている。
揉み合っているうちにナイフがテツの方へ向いたのだ。
つぐみは、必死でテツの身体を押し退けた。
仰向けに倒れたテツの、虚ろな死顔と目が合う。
顔を背けた。遅れて、血の匂いを感知する。
口に当てた手にも血が付いていて、つぐみは堪らずその場に吐いた。
荒い呼吸を繰り返す。
危なかった──。
でも、この状況なら。
変質者、あるいは強盗の仕業ということにできるだろう。
テツはもう喋れない。
つぐみは、尚も肩で呼吸を続ける。
まだ死ぬわけにはいかない。
過去は、裏のままでなければならない。
思い知らせるのだ。
この世界に。
あの男に。
パシャリ……。
微かな音がした。
つぐみが顔を上げると、土足のままの五百扇雪彦が血だまりの中に立っている。
「雪彦さん」
つぐみは、雪彦に向かって縋るような声を上げた。
「男が……いきなり襲いかかっ……」
そこまで言って、つぐみはつと口を閉じる。
テツは、鍵を開けて押し入って来た。
この部屋の鍵は、つぐみの他には雪彦しか持っていない。
──どうして。
雪彦が口を開いた。
「ねえ。初めて会った時、よく読めたね。
僕の名前。五百扇って」
終幕
雪彦が、死体の向こう側から語りかけてくる。
「君は、意外とすんなり身体を解放したよね。
そういうことに興味があったのかな」
「雪彦さん……何を言ってるの?」
こんな時に。
「嬉しかったなぁ。何度も叫びそうになったよ。
”一香”ってね」
頭を吹き飛ばされる直前の人間のように、つぐみの目は不自然に揺れた。
彼は何かを思い出すように恍惚の表情を浮かべ、テツの遺体を覗き込む。
「この男、簡単に騙されたよ。
すぐ動くと怪しまれるから、スナックの裏に金を隠して時間を潰しとけって言ったらその通りに」
あの日、ボロ小屋のような家で母と同衾していたテツという男。
あれは犯行の直後──。
「あなたは……」
呆然と呟くつぐみに答えることなく、彼は歌うように続けた。
「あの場所に金を置かせたのは君のためだよ。
君は絶対来ると思った。都会へ。しかも海へね」
そうだ。鳥になりたかった。
札束を胸に抱いた時、これから得る自由はこんなにも重いのだと思った。
「そして魔女が君に囁いたんだ。偶然だと思った?」
あの時、初めて目にした東京湾は暗かった。
でも、運命だと思った。
「全部、僕だよ。僕と魔女が賭けをしたんだ」
君が、どう動くか。
眼前の男は、端正なマスクに禍々しいまでの笑みを貼り付けて告げた。
血に濡れたスニーカーは、そんな彼の踵までをすっぽりと覆っている。
「あなた、誰──」
つぐみが後ずさると、彼は不思議そうに眉を上げた。
「どうして怖がる? 小さな頃、君と僕は仲良しだったじゃないか。
ずっと2人だけで遊びたかったんだよ。雪彦なしでさ」
彼は、あくまでも無邪気だった。
つぐみの背を冷たいものが流れていく。
その男は、つぐみを見透かすように口の端を歪めた。
「全部、教えてあげるよ」
◇
僕は、ただ引きこもってた訳じゃない。
僕を蔑む全ての奴らに復讐してやる機会を待ってたんだよ。
君だってそうだろう?
“東京湾の魔女”って存在を知った時には「これだ!」って叫びそうになったね。
それから僕は、来たるべき時に備えて身体を鍛え始めたんだ。
夜中にこっそり抜け出して、走り込みをしたこともあったな。
そうして時は満ちた。
魔女と契約を進める一方で、ここに転がってる馬鹿な男に強盗の計画を持ちかける。
尻尾を振って飛びついてきたよ。
簡単すぎて面白くなかったな。
それから僕は、痣を消しに行った。
僕が部屋にいなくたって、誰にも分からないんだ。
何て顔してるのさ。
君だって同じことしただろ。
僕らがすべきことは、顔を変えることじゃなかった。
これは証明さ。
痣があれば痣しか目に入らない。
この世界には、そういう唾棄すべき奴らしかいないっていう証明。
結果は見ての通りさ。
痣を消した途端、馬鹿が山ほど寄ってくるじゃないか。
まったく、碌な奴がいない。
ああ、話が逸れてしまったね。
事件の話をしよう。
あの日。
まず、あの欲まみれの爺をテツが殺った。
金を分けてる時に、雪彦と女が入ってきたよ。
あいつ、酷い形相だったなぁ。
もう一人の自分がいるとでも思ったのかな。
あとちょっとのところで逃げられたよ。
女を置いてだよ? いかにも奴らしいよね。
で、女も呆気なく殺されちゃった。テツに。
僕は、「後は任せろ」って言ったんだ。
テツは僕の指示通り、金をスナックの裏に置いて君のママのところへ行ったわけ。
屋敷に火をつけたのは僕。
雪彦を殺したのも僕だよ。
人間って、いざとなると凄い力が出るものだね。
探し出して、追いかけて。顔を潰してやったよ。
いつの間にか痣が消えた、自分と同じ顔をした人間に殺される。
どんな気分だろう。
聞いとけば良かったよ。
ともかく僕は、その瞬間から五百扇雪彦になった。
多分、君が金を持って逃げてた頃だね。
どんな顔してたんだろう。見たかったな。
僕は、雪彦として警察にも対応したんだ。
痣がないってだけで誰も気づきやしない。
陰で僕が嗤ってるとも知らずに。
ほんと、この世界には馬鹿しか存在しないね。
ところで。僕の金は一時期、雪彦と一緒にいたんだよ。
死人は金に手を出せないから。
あんなに金、金って言ってた奴が……これ以上愉快なことってないよ。
◇
「あの記者も……あなたが?」
つぐみが掠れた声で問う。
彼は笑った。
「僕がやっても良かったんだけどね。分かってるでしょ。
僕はあの時、岐阜で”雪彦”の骨を拝んでたんだ。ところでさ」
彼は急に笑いを消し、テツの死体を蹴り上げた。
血溜まりが跳ねる。
「人の話に水を差すなよ。
今、順を追って話してるんじゃないか」
固まりかけていた血液が、テツの身体の上でどろりと揺れた。
つぐみは悲鳴を上げることもできず、へたり込んだまま後退る。
「ああ、そんなに震えないで。
記者さんの話も後で出てくるから」
彼は、ケロリとして言葉を継いだ。
◇
さあ、今度は君の話だ。
東京湾の魔女に囁かれた君は、痣を消して新しい人生を歩み始めた。
ねえ、一香。
君は、そうやって顔を出していた方が素敵だよ。
待ち焦がれた。
僕との再会は、偶然じゃないんだよ。
あの時の君、本当に嬉しそうだったなぁ。
雪彦に復讐できると思ったんだろ?
もうとっくに死んでる雪彦を、一生懸命誘惑してたね。
あれで人を騙したつもりでいるなんて。
まったく、君は可愛いよ。
さて、やっと記者さんの話だ。
彼女は綺麗で頭が良かったね。でも知り過ぎた。
まさか、スニーカーから辿られるとは思わなかったよ。
──あなた、顔”は”変えてないでしょ。
魔女の存在を確信してる言い方だ。
はしたないね。
お喋りな女は嫌いだ。
胸にしまっておいてくれれば、死ぬことはなかったのに。
ああ、全部聞いてたよ。
君の鞄の底に、盗聴器を仕掛けておいたから。
君のことは何でも知っておきたくてね。
でも、殺したのは僕じゃない。
僕は、魔女に教えてあげただけだ。
あなたの正体がバレそうですよって。
あの素早い行動、鮮やかだったなぁ。
店を出てすぐでしょ?
さすが、東京湾の魔女だ。
何で魔女がそこまでしてくれたかって?
僕が賭けの勝者だからだよ。
さっき話しただろう。
僕は、君が動く方に賭けた。
そして、顔は絶対変えない筈だって譲らなかったんだ。
魔女は訝しんでたみたいだけど、結果はこの通り。
君も証明したかったんだね。
嬉しいよ。
でも。
じゃあ、何でテツに君を襲わせたんだと思う──?
「君が僕を忘れるから」
面白がるようだった彼の口調が、ガラリと変わった。
「君は僕を見つけてくれなかった!
痣が無いってだけで、僕を雪彦だと決めつけて!」
声が揺れる。
「許せないよね。同じ痣を持つ者同士なのに」
鼻から荒い息を吐きながら、彼は目を見開いたままニィッと口角を上げた。
「これはお仕置きだよ。
ついでに魔女に教えてあげたんだ」
この、馬鹿な共犯者の存在をね。
そう言って、彼はテツの死体を見下ろした。
「魔女は、今度はこいつに囁いたんだ。君の居場所。
魔女は、面白いことが大好きだからね」
──過去を隠し通せるかどうかは、あなた次第。
つぐみの胸に、5年前の囁きが去来する。
魔女との出会いも、雪彦との再会も。
何たる幸運かと思った。
いつか、雪彦が死ぬ前に。
自分の裏を明かして嘲笑ってやろうと決めていた。
復讐できる筈だった。
雪彦に。故郷に。この世界の全てに。
それが。
踊っているだけだった。
彼の掌中で。
「こんな筈じゃなかったって、思ってる?」
彼が血溜まりに腰を落とした。
テツの死体を挟んで、つぐみの顔を覗き込んでくる。
そこには、確かに幼い日の“五百扇影彦”の面影があった。
「嘘……。嘘嘘嘘!! あんたは雪彦の筈でしょう!?」
つぐみが金切り声を上げると、彼は子供のように無邪気な笑みを浮かべた。
「やっと、僕を見つけてくれたみたいだね」
──まだ悪夢の途中なのか。
つぐみは頭を振る。
違う。悪夢は5年前に終わったのだ。
金を手に、自分を閉じ込める山々を越えたあの瞬間に。
終わった筈だ。
記憶を辿る。
5年前。
田舎の畦道で、雪彦と連れの女に会った。
ボロ家に帰ると、母親とテツがいた。
追い出される形で外へ出た時には、既に雪が降っていた。
その時、足を引きずりながら走り去る何者かを見た。
店へ出て金を見つけたのはその後だ。
「思い出した……。
あの時、逃げるように走って行ったのは影彦だったわ!」
その頬に、赤黒いものが見えたから。
かつて、自分も持っていたものが。
彼は目を丸くし、一拍置いて哄笑した。
「君、見てたのか」
彼は腹を捩って笑い続ける。
その様は首が裂けたテツの死体よりも気味が悪く、つぐみは激しい吐き気に襲われた。
胸の詰まりが喉までせり上がってくる。
「あれは雪彦だよ」
彼は可笑しそうに目の端を拭った。
「言ったろ? あいつ、女を置いて逃げたんだ」
嘘だ。認められない。
それでも、つぐみの声は声にならなかった。
「どうして僕が雪彦に追いつけたと思う?
あいつ、まともに走れなかったんだよ。
スニーカーをちゃんと履けなかったんだ」
足を引きずる人影が、つぐみの瞼の裏で明滅する。
「踵を履き潰していたから」
もはや、眼前の男はつぐみにとって悪夢そのものであった。
悪夢は終わった筈だ。
認めるわけにはいかなかった。
「違うわ! だって私、見たんだもの! 影彦の顔には……」
赤黒い痣があった筈だ。
「落ち着いて」
彼はつぐみの手を取ると、その手を死体の方へ導いた。
裂けた喉元へ。
ビチャッと音がした。
テツの喉から流れ出た血液。
固まりかけていたそれは、つぐみの目の前で糸を引いた。
「こういうことだよ、一香」
彼は愉快そうに笑いながら、血で汚れたつぐみの手を自分の頬に擦りつけた。
その頬に、赤黒い血液がべっとりと付着する。
ああ、これだったんだ。
自分があの時、見たものは。
じゃあ、逃げていたのは。殺されたのは。
顔を血で汚した”雪彦”──。
思考を拒否するように、つぐみの目から光が消えた。
五百扇影彦は、そんな女の様を愛おしげに眺め、握った手に指を絡ませる。
「君にも同じものが付いてるじゃないか」
返り血がさ。
「後ろを見てご覧よ」
これがあると、君の肌の白さがより一層際立つんだ。
影彦は、女の頬を優しくなぞりながら囁いた。
女は、命令に忠実な機械仕掛けの人形のように回れ右した。
ドレッサーの鏡に、もう一人の自分が映っている。
水浜一香は目を瞠った。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
