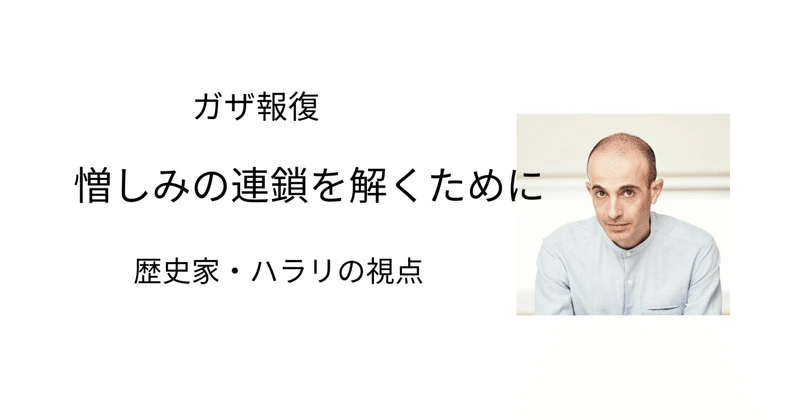
ガザ報復 歴史家・ハラリの視点
憎しみの連鎖を解くために
イスラム組織ハマスのイスラエル侵攻が、パレスチナ自治区ガザ地区へのイスラエルの報復空爆を招き、交戦が激化しています。イスラエル軍のガザへの地上侵攻も進む中、周辺国も巻き込む中東戦争への拡大のリスクが高まっています。戦禍に巻き込まれた犠牲者は、これまでの中東戦争を超える勢いであり、肉親、知人を奪われた双方の憎しみが高まるばかりの現状です。「今は憎悪で自分を見失いそうになる」。こう率直に語るのは著名な歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏です。抗争の背景には宗教、民族も絡みます。この“苦しみの海”から人々をどう救うか。人間はその知性を持ちうるのか。今回の戦禍の当事者でもあるハラリ氏の、最近の論評とこれまでの著述から、その方策を探ってみます。
Ⅰ 侵攻直後の論評から
憎しみの当事者として
ユヴァル・ノア・ハラリ氏は累計発行部数が2100万部を超える「サピエンス全史」などで世界的に知られています。その著作、論評は、7万年の人類史を斬新な視点で見直し、人間の認知革命、宗教、科学の果たした役割から人間至上主義の限界、危機までを見通し、各国の読者から大きな共感を得ています。
その彼が、まずハマスの残虐な攻撃を受けた当事者として、最近のテレビインタビューと論評で怒り、憎しみの連鎖と当事者としての限界について語ります。
1. 当事者の限界 大切な第三者
(テレビ朝日 報道ステーション・インタビュー:2023年10月20日より)
ハラリ氏は居住するイスラエルで今回の侵攻を体験しました。そこから「テロリストは意図的に民間人を襲っただけでなく、考え得る最も残虐な方法で拷問・殺害し、それを公開しました」と指摘、「その目的はイスラエルと地域全体の数百万人の心に、“憎しみの種”を植え付けることでした」と受け止めています。
この目の前の惨状に、冷静な歴史学者も「私自身の家族や友人に深く影響を及ぼし、ひどい苦しみを与え続けている問題であるため、現時点では私は客観的になることができない」と自分の怒りを率直に認めています。
そして「この“苦しみの海”に呑まれている人々は、他人の苦しみと共感することができなくなってしまうのです」と当事者としての対立解決の難しさ、限界を教えます。
絶対的な正義の限界
その限界を踏まえ、解決に必要な「未来を左右する」のは「イスラエル人でもパレスチナ人でもない、第三者の言動だ」と強調しています。
同時にたとえ信用できる情報でも「結論を急がないようにして欲しい。被害者が加害者かの二者択一で考えがちですが、歴史においてそんなことはほとんどありません。被害者と加害者が同じであることがほとんどです」と警告します。
「どちらかが『絶対的な正義』で、もう片方が『絶対悪』だと思い込まないようにすべきです。『絶対的な正義』を探し求める人は、必然的に争いに導かれてしまいます。なぜなら、どんな譲歩もできなくなってしまうからです」
怠った平和の努力
今回のハマスの侵攻の背景に、ハラリ氏はイスラエル政府の要因も認めます。「ネタニヤフ政権はパレスチナ都心の平和を築く努力を怠ってきました。ネタニヤフ政権はイスラエルの占領に関して増々過激な立ち位置を取るようになり、時にはパレスチナに対して人種差別的な世界観を選んでいて、それは大きな間違いでした」と批判します。
そして「今世界では多くの人が壁や境界線をつくる必要性を語っている。思考と口の間にも壁を作らなければなりません。頭に浮かぶ考えや感情はコントロールできない。しかし口から発するものはコントロールできる。何を言うか、書くか、するかに関しては責任を持つべきです」と意見表明には慎重さを求めます。
心のスペース
そして緊張の高まる今必要なことは「心に平和のための“スペース”を取っておくこと」だと語ります。今のハラリ氏たちのように“苦痛の海”につかりきりの当事者には、(それが)できないことだからです。
それゆえにそのスペースを持ち得ている「日本の皆さんで使ってください」と語り、その上で、日本に「政治・経済・文化の力を利用して紛争の悪化と戦禍の拡大、エスカレーション」を防いで欲しいと要望しています。
2.侵攻を招いたポピュリズム
(東洋経済ONLINE 2023年10月23日 より)
異質な残虐さ
ハマスの侵攻後、関係各国そして世界が一番危惧しているのはエネルギー危機につながる中東戦争への拡大です。イスラエルとパレスチナ自治区は1948年の第一次中東戦争以来1973年まで4度の戦争を経験してきました。
ハラリ氏はまず、自らが見聞きした状況をもとに、今回のハマスの攻撃の残虐は、これまでの4次に渡る中東戦争と異質なものであることに気づきます。
ハマスに攻撃されたキブツにはハラリ氏の「親族や友人がおり、ぞっとするような話を多く耳にした」。「テロリストたちは家を一軒一軒回り、組織に家族を皆殺しにしたり、子どもの目の前で親を殺したり、赤ん坊や老婆さえ人質に取ったりした」
「生き延びた人々は恐怖におののきながら、戸棚の中や地下室に身を隠し、軍や警察に電話し助けを求めたが、多くの場合、救助隊が到着した時にはすでに手遅れだった」
「私の99歳になる伯父と、89歳の伯母はキブツに住んでいた」。そこがハマスの手に落ちて連絡がつかなくなった。二人は「何十人ものテロリストが暴れ回り、人々を惨殺している間、ずっと自宅で身を潜めていた」。やがて「私のもとに2人が助かったと報告があった。だが多くの知人が人生で最悪の知らせを受け取った」
ナチスの魔手が再現
この伯父夫妻は第一次と第二次世界大戦の間に東ヨーロッパで生まれました。そして「ホロコーストですでに一つの世界を失った」
ハラリ氏は彼らから「ナチスの魔手から逃れるために戸棚の中や地下室に身を隠したが、誰も助けに来てくれなかった」という話を聴いて育ちました。
ハラリ氏は問いかけます。「イスラエルはこのようなことが二度と起こらないようにするために建国された」。「それにもかかわらず、なぜ今回の惨劇は起こったのか。イスラエルという国はどうして道を見失ってしまったのか?」
思い上がりの代償
「ある意味で、イスラエルの人々は長年の思い上がりの代償を払ってきたといえる」。ハラリ氏は今回の侵攻の背景の歴史をたどります。そして「歴代の政権と多くの一般国民が、私たちはパレスチナ人よりもはるかに強い、彼らはあっさり無視できる、と感じていた」と振り返ります。
「イスラエルがパレスチナ人との和解の試みを放棄し、何十年にわたって数百万のパレスチナ人を占領下においてきたことは、厳しく非難されるべきだ」と自らを反省します。
ただし「だからといってイスラム原理主義組織ハマスによる残虐行為は正当化できない」と厳しく批判します。「ハマスはイスラエルと平和条約を締結する可能性を容認したためしがなく、オスロ合意に基づく和平の進展を、ありとあらゆる手を使って妨げてきた。平和を望む者なら誰もが、ハマスを糾弾し、制裁を科し、人質全員の即時解放と、ハマスの完全武装解除を要求しなくてはならない」
元凶としてのポピュリズム
イスラエルのパレスチナ人への対応の失敗をハラリ氏は認めました。ではその事態を招いたイスラエルの責任、機能不全はなぜ生まれたのか。歴史学者は政治にはびこるポピュリズム(大衆迎合主義)を指摘します。
「歴史は道徳の物語ではない。イスラエルの機能不全の真の原因は、この国の不道徳とされているものではなく、ポピュリズムだ。何年にもわたってイスラエルはポピュリズムの強権的指導者ベンヤミン・ネタニヤフが支配してきた。彼はPRの天才だが、首相としては無能だ」
彼のネタニヤフ批判は痛烈です。「何度となく自分の個人的利益を国益に優先し、国民の内紛を誘うことでキャリアを築いてきた。能力や適性よりも自分への忠誠に基づいて人々を要職に就け、成功はすべて自分の手柄にする一方、失敗の責任は一切取らず、真実を語ることも耳にすることも軽んじているようにも見える」
そしてその政権を更に厳しく糾弾します。「ネタニヤフが2022年12月に樹立した連立政権は最低であり最悪だ」「彼らは治安状況の悪化をはじめ、イスラエルが抱える問題の数々を顧みず、際限なく権力を我が物にすることしか眼中になかった。その目標を達成しようと、極端な対立を招くような政策を採用し、その政策に反対する国家機関にまつわる言語道断の陰謀論を広め、国に忠誠を尽くすエリートたちに『ディープステート(闇の政府)』の売国奴というレッテルを貼った」
ハラリ氏は、治安に対する国防軍の参謀総長や国防相らの警告、警鐘を無視してたネタニヤフこそが「イスラエルが惨禍に見舞われる現状を招いた」と断じます。そして世界に対し「ポピュリズムがイスラエルという国家を蝕んだことを、世界中の民主主義国家は教訓として受け止めるべきだ」と呼びかけます。
最後にハラリ氏は「これまでのイスラエルの振る舞いには、とがめるべきことが多々ある。過去を変えることはできないが、ハマスに勝利した暁には、イスラエルの人々は現政権に責任を取らせるだけでなく、ポピュリズムの陰謀論やメシア侵攻の幻想も捨て去り、そして国内には民主主義を、国外には平和をというイスラエル建国の理想を実現するために、誠実な努力をすることが願われてやまない」と結び、世界の人々に理解と支援を求めています。
Ⅱ ハラリ氏の人類史観
ユヴァル・ノア・ハラリ氏の直近の論評には、人間の争い、憎悪、そして民族や宗教の対立とそこから生まれる残虐行為、ホローコーストなど、人類の暗部も触れられていました。では今回、ハマスに憎しみを抱きながらも自国政権の落ち度、大衆迎合の誤りを指摘したハラリ氏の視点の基盤はどこにあるのか、人間の歩みをどう見ているのでしょうか。
彼の主要著作の「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」と「ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの歴史」は、日本語翻訳で1000頁を超えます。両著書のポイントをたどりながら、彼の人類史観を探ってみます。
1.人類は災禍をどう生き抜き、どうなるのか
ユヴァル・ノア・ハラリの著作を読みなおす
今回のハマス侵攻、そして更に多くの犠牲者を出した世界大戦など、人間はこれまで、自ら限りない争い、カタストロフィを体験して来ました。そしてそれ以前は人類以外の動物、種との争いも耐え抜いてきました。その全史はどのようなものか。そして今がどのような時代なのでしょうか。
彼はそれを人間が言葉を生み出した7万年前からという長い視点で探索します。
「言葉による虚構」を利用することによって、人類は地上の覇者になりえた、というのが基本的な視点です。
他にも「狩猟採集生活から農耕生活の移行は人々の生活を苦しくした」など、ハラリは注目すべき論点を多く提示しています。
そして、今世紀になり人間は、電子工学や生化学のテクノロジーにより、自ら神になるかあるいは新たな神に支配されか、という瀬戸際にある、と説きます。
ハラリはこの21世紀が、人類史の中で自らの滅亡の危機さえある特筆すべき変革期にある、と警告しているのです。
ただしハラリは悲観論のみを提示するのではありません。その危機を乗り切るために、歴史を学ぶ大切さを指摘します。「歴史とは人々の将来の選択肢を提供するもので、史実を正確に読み取り、今起こりつつある問題を的確に解決する手段になる」ことを願っているのです。
ではまずハラリ、その人を簡単に振り返ります。
2.ユヴァル・ノア・ハラリとは

ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)は世界で今最も影響力のある歴史家、思想家、作家です。彼の著作は『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』が有名ですが、その著作は世界65か国語に翻訳され、合わせると2,750万部も販売されたというベストセラー作品となっています。
イスラエルが生んだ天才
ハラリは1976年2月24日、イスラエルのハイファで厳格なユダヤ教徒の家庭に生まれました。東ヨーロッパとレバノンにルーツを持つ両親の間に生まれた3人兄弟のうちの一人です。父親は兵器のエンジニアで国家公務員、母親は民間企業の会社員でした。
ハラリは3歳で本を読むことができました。8歳になると、ハイファにあるレオ・ベック教育センターで学びます。そこは、知能に優れた子供たちが集まる学校です。
その後イスラエルのエルサレム・ヘブライ大学で歴史学と国際関係学を学びます。同大学は中東地域随一の教育・研究レベルを誇り、世界大学ランキングセンターでは最高で世界22位に入るなど、世界的に評価をされている大学です。ハラリは歴史学の中でも中世史と軍事史を学びます。大学卒業後はイギリスのオックスフォード大学に進み、2002年に同大学ジーザスカレッジで博士号を取得しています。
現在はイスラエルに戻り、母校であるエルサレム・ヘブライ大学で歴史学の教鞭を取っています。

彼の研究は、歴史を長期的に見た際に生じる次のような疑問に焦点を当てています。
・歴史と生物学の間にはどのような関係があるのか
・ホモサピエンスと他の動物の間にある極めて重要な違いは何か
・歴史に正義はあるのか
・歴史に方向性はあるのか
・歴史が展開されることによって人々はより幸せになるのだろうか
・21世紀に科学とテクノロジーが提起する倫理的な問題は何か
彼の著書、『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』では、石器時代から21世紀までの人類の歴史を概観しています。自然科学、特に進化生物学の観点からも話が展開されることが特徴です。
彼はもう一つのベストセラー、『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの歴史』の献辞にて「この本をS・N・ゴエンカに捧げる」と述べています。ゴエンカはヴィパッサーナ瞑想を欧米や世界に広めた指導者です。
また彼は、肉や魚だけでなく、乳製品や卵も食べないビーガン(完全菜食主義者)です。彼は研究を進めていった結果、母牛と子牛との間の絆を人間が破壊していると認識し、自身がビーガンになったと言っています。
では、次の項からハラリの人類史の捉え方、現代の課題についてたどっていきます。
3.人類は21世紀までにどのような歩みをしてきたのか
【1】人類の三大革命
ハラリは著書「サピエンス全史」で、ホモ・サピエンスが地球上の生物としてもっとも繁栄した要因には、3つの革命があったと説明しています。
① 認知革命
1つ目は今から約7万年前に起きた「認知革命」です。
ホモ・サピエンスは約200万年から存在したと言われる人類の一種です。サピエンスは非常にか弱く、10万年程前にも中東のネアンデルタール人の縄張りに進出するもすぐに撤退しています。しかし7万年ほど前に突然アフリカを脱出し、かつて敗れたネアンデルタール人や他の人類を追い払い中東からヨーロッパや東アジアまで到達し、それに並行してイカダや弓矢、オイルランプなど様々な発明を成し遂げました。

この7万年前ごろから、サピエンスはなぜ勢力を拡大できたのか。ネアンデルタールを含む人類の他の種が滅亡していった中で、唯一サピエンスを勝者にしたものは何か。ハラリはそこにサピエンスの「認知革命」があったと指摘します。
言語能力
認知革命を生んだものは「新しい思考と意思疎通の方法」、つまり言語能力でした。
サピエンスが他より優れているのは、特にコミュニケーション能力と大勢で共同作業をする能力です。共同作業するのはアリやハチも同じだと思われるかもしれませんが、それらは身内で協力するだけで巣の社会体制を変革することはできません。オオカミやチンパンジーも群れますが、仲間うちで協力するだけで、サピエンスのように無数の他人と協力するというのは無理です。
この共同作業に必要なものがお互いの情報伝達能力です。言語ともいえます。「どんな動物も何かしらの言語を持つ」とハラリは言います。ではなぜサピエンスだけが大勢の共同作業を可能にするコミュニケーション力を持てたのでしょうか。
その秘密をハラリはサピエンスの言語の柔軟性にあるといい、さらにその言語が噂話によって発達したという説を取ります。
言語の柔軟性とは、限られた数の音声や記号をつなげて、それぞれいろいろな意味を持たせることが可能であることを指します。動物も周りの世界の状況を伝えるために鳴き声などを出しますが、サピエンスのような抽象化した記号を扱うものはありません。
噂話
もう一つのカギが噂話です。現代でも人々は「〇〇さんが~したらしい」というような噂話でコミュニケーションを図ることが多いのですが、例えば悪いことをした人は、その噂を流され所属集団において生活しにくくなるように、社会規範を強化するという側面が噂話にはあります。
狩猟採集生活をする時代のサピエンスにとって、社会的な協力は「生存と繁殖のカギを握っていた」のです。個々の人間がライオンやバイソンの居場所を教え合うだけでは十分ではなかった。「自分の集団で誰が誰を憎んでいるのか。誰と誰が寝ているのか。誰が正直で誰がズルをするのか」。このような噂話が群れの結束、存続に何よりも重要なのです。
噂話によって、サピエンスはより緊密で高度な協力関係を得ることができるようになりました。ただし、これによって秩序が保てる人数は、だいたい150人だと言われています。
しかし、サピエンスはその人数を遥かに超える都市や帝国を築いたりしていきました。これを可能にしたのが、サピエンスの言語が可能にした「見たことも、触れたことも、においを嗅いだこともない、ありとあらゆることを話す能力」(※1)でした。
「フィクション(虚構)」の創造力です。伝説や神話、神々、宗教という虚構が認知革命によって現れました。
虚構・ストーリー
人間は虚構を作り出し、それを信じることができる唯一無二の存在であり、お金、宗教、政治も誰かが作り出したストーリー(物語)なのです。特に宗教や神話などが分かりやすいですが、例えばキリスト教を信じている人間同士はその教えに沿った法や規則に従うため、全く知らない不特定多数の人々と協力し合えるわけです。
ストーリーはこのように有用で便利なものである反面、使い方によっては凶器にもなり得ます。宗教の対立が大きな戦を招き、やがて国家や貨幣、富が世界規模の戦争の引き金にもなります。認知革命によって生まれたストーリーは不完全な存在である人間が作った「ただの道具」に過ぎないことを理解し、妄信しないことをハラリは戒めています。
※1 虚構を作る意思疎通の方法を、なぜサピエンスだけが獲得できたのでしようか。ハラリはこの認知革命の鍵となる能力について「最も広く信じられている説によれば、たまたま遺伝子の突然変異が起こり、サピエンスの脳内の配線が変わり、それまでにない形で考えたり、まったく新しい種類のお言語を使って意思疎通したりすることが可能になった」と説明しています。そしてその変異がネアンデルタール人でなく、サピエンスのDNAに起きたことは「私たちの知る限り、まったくの偶然だった」と記しています。
②農業革命
2つ目は紀元前12000年ごろから始まったという農業革命です。
これは250万年前から狩猟採集生活をしていた人類が、農耕をするようになったというものです。それまでは様々な動物を狩り木の実や果物を拾って食べ、無くなれば食物を探し求めて渡り歩くという生活スタイルでした。
この狩猟採集生活について、ハラリはその食料事情や働く時間が短かったこと、感染症の少なさなどから「原始豊潤社会」とまで命名して評価していることが特徴です。
農業革命は食料となる小麦などの栽培とヤギなどの家畜化から始まります。小麦は紀元前9000年ごろまでに栽培植物とされ、馬は紀元前4000年までに家畜化されたといいます。農耕はかつては中東が発祥地と考えられてきましたが、現在では他の様々な地域で独立した形で発祥したというのが専門家の通説です。
定住から村落の暮らしが始まります。農業革命は雨、寒さなどからより守られる生活を人間に与えました。栽培により食料の供給量が安定して増え、人口の増加が始まります。定住は所有物を増やし、同時に栽培穀物の余剰も生まれ、それが蓄えとなり、貯蓄=富も生まれます。
「農業革命は人類にとって大躍進だった」というこれまでの学者の意見を紹介しながら、ハラリは「農耕民は狩猟採集民よりも一般に困難で満足度の低い生活を余儀なくされた」と否定的です。このハラリの見解は後述の「幸福について」で少し詳しく考えます。
農業革命によって「単位面積当たりの土地からはるかに多くの小麦が採取できるようになり、それによりサピエンスは指数関数的に数を増やした」のはハラリも認める事実です。そして群れはより大きな集団に代わり、やがて群落から部族集団、そして神話や宗教など共同主観的な虚構を基にする共同組織の国へと拡大していきました。そして穀物や家畜を持つことによって生まれる富の蓄積が、所有概念も生み出します。
そしてこの所有をベースにした共同組織の拡大は、その秩序を維持するためにヒエラルキーも生み出しました。
動物や家畜の所有は、人間の所有、奴隷制度となり、さらには男性が女性を所有するという家父長制度につながっていきます。
② 科学革命
科学革命は約500年前から始まったとハラリは説きます。ちょうどコロンブスがサンタマリア号などで、アメリカ大陸にたどり着いた時代です。
この500年にホモ・サピエンスは5億人から14倍の70億人(2019年で77億人)を超すまでになっています。人類の生み出す財とサービスの総価格は1500年に現代の価値にして2500億ドルと推定され、今日は240倍の60兆ドルになるといいます。人口も生産も爆発的に拡大しているのです。

無知の革命
これを実現したのが科学革命であり、ハラリはそれを「無知の革命」だったといいます。
近代以前の知識の伝統は、「この世界について知るのが重要である事柄は、すでに全部知られていた」でした。キリスト教やイスラム教、仏教、儒教などの宗教は、偉大な神々、あるいは唯一の万能な絶対神や賢者が存在し、その神たちが世界を構築し、すべてを網羅する知恵を持っていると伝えられていました。
しかし人間は、星空を眺めるうちに、宗教の教義とは違う天体の動きに気づきました。コペルニクスやガリレオの研究は観察の力を人々に気づかせます。そして同時期に生まれる大航海時代は、当時の人々の知らない大陸、世界の存在を明確にしました。従来の知識の伝統と違う近代科学が、人々を覚醒させます。
近代科学は(1)進んで無知を認める(2)観察と数学の中心性(3)テクノロジーなど新しい力の獲得、で多くの分野での新たな発見をもたらしました。
中世のヨーロッパにおける知識の公式としてハラリは、「知識=聖書×論理」を掲げます。
全ては神のもとにあり、その教えを網羅した聖書を論理的に読み込めばあらゆる知識は得られるというものです。そして科学革命はこれを「知識=観察に基づくデータ×数学」に変えたとハラリは解説します。「全知の神」から「無知の知」へ、です。知らないことがある、と知ったために、人間はそれを知ろうと新しい手法、手段を編み出します。これが科学となり、ほとんど変化のなかった中世から、爆発的な産業、科学の発展の時代が始まりました。
新しい大陸の発見は、国土の拡張、獲得を目指す帝国主義を生み、西洋各国の世界征服活動を招きます。そしてこの帝国主義は近代科学と深い結びつきを持つのです。
イギリスがインドを征服した際、考古学者や地質学、動物学、言語学者などの科学者が同行しました。ハラリはこれを事例に挙げ、同行した科学者の成果が現地の実情に即した統治を実現させたことを示します。この成果によって、イギリスは少数の派遣者で3億人のインド統治に成功します。
そしてインドなど植民地に同行した科学者による学問的成果は、帝国そのものに進歩的イメージを与えることになりました。帝国の征服は、教育や医療を施し、鉄道や用水路で国土開発を進め、正義と繁栄を約束するような幻影をも生み出したのです。
このように「科学者は帝国主義の事業に実用的な知識やイデオロギー面での正当性やテクノロジー上での道具を与えた」のです。同時に近代科学も「帝国の支援なくしては大きな進歩を遂げていたかどうか疑わしい」。「科学の領域のほとんどが、帝国の成長に尽くす僕(しもべ)として始まった」と、まさに帝国と表裏一体となった近代科学の一面をハラリは描いています。
科学革命は農業だけでなく、あらゆる部門の生産量の増加につながりました。「明日はより多くの小麦が期待できる」。未来への期待、信頼です。ハラリはその将来への信頼が信用の発生を生みだしたと説きます。生産増による利益や信用を支えに将来に投資するという新しい資本のリサイクルの発生です。そこから「生産利益は生産増加のために再投資されなければならない」という「資本主義の最も神聖な掟」が生まれたとし、資本主義登場への道のりも解説しています。

【2】人間至上主義の登場
中世は「知識=聖書×論理」の時代であり、すべての知識は聖書=宗教にありました。その意味で科学革命は知識の源泉を聖書=宗教から引き離して行きました。「過去300年にわたって、宗教は次第に重要性を失っている」とハラリは書きます。
ただしこれは有神論、神の存在を信じる宗教のことであり、「宗教を自然法則の宗教まで加えれば、近代は強烈な宗教的情熱が残り、史上最も残虐な政争の時代」だとハラリは新しい宗教について語ります。
このハラリの言う自然法則の新宗教とは、自由主義や資本主義、共産主義、国民主義、ナチズムを指します。そして有神論の宗教と区別し、「人間至上主義」の宗教とします。
これらは通常イデオロギーとも言われます。しかし「宗教が超人間的な秩序の信奉に基づく人間の規範や価値観の体現」であるなら、「ソビエト連邦の共産主義は、イスラム教と比べても何らそん色のない宗教」だとハラリは説きます。
人間至上主義はホモ・サピエンスの生命と、幸福と、力を神聖視します。人間が「他のあらゆる動物や他のあらゆる現象の性質と根本的に違う」というのが信念です。「その性質が宇宙で起きる一切のことも意味を決める。至福の善はホモ・サピエンスの善」というのです。
人間至上主義は人間性を崇拝します。しかしこの人間性の定義の仕方で3つの宗派に分かれます。
この中で、ハラリが最も重要とするのが今世界に広まっている「自由主義の人間至上主義」です。
これは人間性とは個々の人間の特性で、個人の自由を最も神聖なものと考えます。「個々の人間の内なる核心が世界に意味を与え、倫理的・政治的権力の源泉になる」と言います。そして内なる声を侵入や害から守る戒律として「人権」を掲げます。
二つ目が「社会主義的な人間至上主義」です。社会主義者は人間性は個人でなく集合的なものとし、ホモ・サピエンスという種全体を神聖な存在とします。そして全人類の平等を求め、人間の皮相的な特性、人種や貧富などによる差別、不平等を人間性に対する「最悪の冒涜(ぼうとく)」だと考えます。
自由主義的、あるいは社会主義的人間至上主義はともに神を否定はしません。自由主義的人間至上主義はキリスト教と併存し揺るぎはありません。
この一神教と縁を切ったのが三つ目の「進化論的な人間至上主義」でした。代表例がアドルフ・ヒトラーが総統を務めたナチス・ドイツです。
ナチスは進化論に影響を受けています。人類は不変なものでなく、進化も退化もしうる存在だと考えます。「ナチスの最大の野望は人類を退化から守ること」であり「最も進んだ形態であるアーリア人種を保護し、ユダヤ人やロマ、同性愛者、精神障害者のような退化したホモ・サピエンスは隔離され、皆殺しにさえしなければならない」と主張した、とハラリは記します。

ユダヤ人でかつ同性愛者であるハラリは、ナチス、進化論的人間至上主義に多くの説明を加えています。注目すべきはナチスの人種論は「1933年当時の科学的知識をもってすれば、ナチスの信念は常軌を逸しているとは到底言えなかった」という当時の実態です。
白色人種はアフリカやインドの人間より知能が高く、倫理的である、という学者や政治家は多く、この白人至上主義が「少なくとも1960年代まで、アメリカ政治の主流のイデオロギーだった」と歴史学者ハラリは振り返っています。
ヒトラーの敗北、ナチスの崩壊によって、進化論的人間至上主義は消え去ったかに見えます。しかしハラリはその将来は「不明だ」と注意しています。後ほどこのレポートでも紹介しますが、生物学的方法を使ってホモ・サピエンスをアップグレードする事業が、再び流行している現状があるのです。そして「人間の生物学的作用に関して深まる知識を使って、超人を生み出そうと考えている人は多い」ともハラリは言います。
「各個人の中に自由で永遠の魂が宿る」という伝統的なキリスト教の信念が、現代の自由主義的政治、司法制度を支えています。しかし過去200年に進歩した生命科学はこの基盤を揺るがしています。「人体内部の研究する科学者たちは、そこに魂の発見ができなかった」のです。人間の行動は自由意志でなく、「ホルモンや遺伝子、シナプスで決まり、チンパンジーやオオカミ、アリの行動を決めるのと同じ方法で決まる」。
この進化論的人間至上主義に沿うような現代の生化学の知見は、さらに人間自らの存在をも脅かす存在になりえます。この人間至上主義が、人間を失墜させる。このパラドックスをさらに見ていきたいと思います。
【3】データ至上主義
「データ至上主義」とは、森羅万象がデータの流れでできている、という認識が前提になっています。この認識法のポイントは、「生物もデータである」という点にあります。当初は少し違和感がありますが、その認識方法の説明にハラリは今の生命科学が「生き物を生化学的アルゴリズムと考えている」と説明します。
アルゴリズムとは「計算をし、問題を解決し、決定に至るために、利用できる一連の秩序だったステップ」で「計算の時に従う方法だ」とハラリは定義します。そして生き物の生存活動も、このアルゴリズムで把握できる、とする今の生命科学を紹介します。この定義を支える説明が、「ホモ・サピエンス全史」、「ホモ・デウス」だけではやや物足りなさを感じますが、私たちの生命活動の発端となる精神、感情についてハラリはこう説いています。
「私たちの精神的・感情的世界は、何百万年もの進化の過程で形成された生化学的な仕組みによって支配されており、神経やニューロン、シナップス、セロトニンやドーパミン、オキシトンのような様々な生化学物質からなる複雑なシステムで決定される」
つまりこれらがシステムである限り、進歩した科学、特に電子工学でこの活動が捕捉でき、生き物の活動の分析が可能だというのです。
このように考えるデータ至上主義を支えるのは、20世紀末から急速な進歩を遂げている生命科学とITです。特にITの中でも、ディープラーニングの開発で急激に能力を高めている人工知能が、生物アルゴリズムの存在の裏付に貢献しています。
その可能性を読み込みながら、ハラリはデータ至上主義が科学の二つの流れで誕生した、と解説します。
一つは、今紹介したように生命科学では生き物を生化学的アルゴリズムで認識できるようになったことです。そしてもう一つは、その生物アルゴリズムの解読を可能にする高性能な電子工学的アルゴリズムが設計できるようになったことです。そしてこの二つに数学的法則が当てはまることが示され、これによってデータ至上主義が成立したというのです。つまり、「データ至上主義は動物と機械を隔てる壁を取り払った」のです。
データ至上主義において「生き物はアルゴリズムで、キリンもトマトも人間も単に異なるデータ処理の方法に過ぎない」のです。「個々の生き物だけでなくハチの巣や、バクテリアのコロニー、森林、人間の都市など様々な社会全体も、データ処理システムと見なされている。経済は欲望や能力についてのデータを集め、決定を下す仕組みだ」。森羅万象の全てがデータであり、処理が可能になるのです。
データ至上主義は「音楽学から経済学、はては生物学に至るまで科学のあらゆる学問領域を統一する単一の包括的な理論」であり、「すべての科学者に共通の言語を与え、学問領域の境界を越えて見識を円滑に伝え得る」とその全能さをハラリは強調します。
データ処理の差が生む社会体制
この全能のデータ至上主義は、社会の基本構造の読み取りにも新たな視点を提供します。
かつての人間至上主義は、資本主義と共産主義、そして全体主義という大きな体制構造を19世紀から20世紀にかけ生み出しました。
その社会体制について、データ至上主義は「競合するデータ処理システムの差」がこれらの体制の違いだと説きます。
21世紀初期の世界は、自由市場による資本主義と国家統制下にある共産主義が競い合っています。データ至上主義はこの競合を、イデオロギーでも、倫理上の教義、政治制度でもなく、情報処理の違いで生まれていると説明するのです。
結論から言うと資本主義が情報の分散処理であり、共産主義が集中処理をして体制の統治、コントロールをしていると区別しています。
資本主義はすべての生産者と消費者を直接結びつけ、相互に自由に情報を交換させ、各自に価格などを決定させ、データを処理します。この情報交換の中で、需要と供給に応じた価格設定ができています。
投資、株式取引はデータ処理システムの中でも最も速く効率的なものと言えます。世界中の誰でもが参加でき、政治、社会、経済あるいは自然環境までの要素が、株価に反映される。まさにすべてのデータ処理の典型ともいえます。
そして自由市場では、あるデータ処理者が判断を誤っても、他の処理者がその補正をします。
この資本主義システムと違い、共産主義は中央の単一の処理者がすべてのデータを処理し、あらゆる決定をします。この典型だった計画経済を展開したソビエト連邦は、1991年に崩壊しました。共産主義はこれ以降衰退に入ります。分散型データ処理の資本主義が、集中型データ処理の体制に勝利したかに見えた時代しばらく続きます。
「資本主義が冷戦に勝ったのは、テクノロジーが加速度的に変化する時代は分散型の処理が集中型の処理より巧くいったからだ」と喧伝され、イデオロギーの終焉さえ広く流布しました。20世紀後半は分散処理がうまく機能した時代でした。
しかし2008年のリーマン・ショックで、世界経済は大きく減速します。そしてその後、世界経済を復活させた大きなエンジンが共産党支配の中国になるのです。
今、世界中を新型コロナによるパンデミックが襲い、各地で都市閉鎖になり、経済は再び大きな衰退を余儀なくされています。その中で中国は、コロナ禍の発祥の地でありながら、欧米に比べるとその後の感染抑制に成果を挙げました。
社会、経済の統制力が有効性を発揮しているのです。集中型データ処理の優位性が再び注目を集めているのです。
データ至上主義のリスク
21世紀に入り、データ処理技術は分散型も集中型もさらに急速な進歩を続けています。そして扱うデータ量も天文学的な数量に膨張しています。その膨大な情報の処理は、益々個々人の理解を超えるものになっています。
これまで人間は「データを洗練して情報にし、情報を洗練して、知識に変え、知識を洗練して知恵に昇華していた」。そしてその知恵をもとに、科学、文化での創造、発展を築いてきました。しかし間もなく「厖大なデータに人間は対処できず、そのためデータを洗練して情報にできない。知識を知恵にすることなど望むべくもない」時代が到来するとデータ至上主義者は断定します。そして「データ処理は電子工学的アルゴリズムに任せるべきだ」と言い切るのです。
膨大な情報に対する人間の限界は、すでに政治の世界にも露出してきています。
19世紀から20世紀までは、政治と有権者はテクノロジーより一歩先行し、その道筋を統制し操作して来ました。選挙制度、政党、そして議会に、有権者の意向を反映させ、それを踏まえた政治が施行される、というモデルが機能していました。
しかしいま、「データの量と速度が増すとともに選挙や政党や議会のような従来の制度では、データを効率的に処理できなくなってきている」。そして「テクノロジー革命は政治のプロセスより早く進み、議員も有権者もそれを制御できない」とハラリは指摘します。
この指摘を理解するには、もう少しハラリに裏付けの事実を求めたいところですが、ここ数年に拡大した政治家のX(ツイッター・Twitter)などネット媒体の利用状況を見ると、情報の有用性は別にしても、量そのものが爆発的に増えている実態に納得がいきます。
この状況を生む拠点となるのがサイバースペースであり、FacebookやLINEなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)です。
これらの媒体でやり取りされる情報は、真偽を確かめる暇もなく政治家、有権者の間をそれこそ即時に飛び交い、それぞれの考え方、行動に大きな影響を与えます。そしてそこに集まったビッグデータをもとに、政治や社会の認識の仕方、政治志向などの誘導さえ可能になってきています。今や有権者の自由な意識、考え方をベースにした選挙制度も、その信頼性が問われる事態が生まれているのです。ハラリの指摘する制御不能の事態が始まりつつあります。
ブラックボックスのサイバースペース
そしてさらに大きな問題は、ネットワークなど電子メディアで成立する仮想空間のサイバースペースにあります。
「サイバースペースは今、私たちの日常生活や経済やセキュリティにとって極めて重要だ」とハラリは強調します。それなのに「いくつかのウエブの設計から一つを選ぶという重大な選択は、それが主権や国境、プライバシー、セキュリティのような従来の政治的な問題に関連しているにもかかわらず、民主的なプロセスを通しては設計も選択も行われていない」とハラリは問題提起をしています。
「ウエブの設計者たちが人々の目が届かないところで決定したため、今日のインターネットは自由で無法なゾーンであり、国家の主権を損ない、国境を無視し、プライバシーを無効にし、ことによると最も恐るべき世界的なセキュリティのリスクとなっている」。ハラリはこのように大きな危機意識を抱いています。
サイバースペースは、今恐ろしいほどの勢いで進化しています。そのテクノロジーを理解できる専門家は限られ、大半の国民、有権者にとってブラックボックス的な存在になりつつあります。
本来であれば、この事態を政治がコントロールすべきかもしれません。しかし「今日の民主主義の構造では、肝心なデータの収集と処理が間に合わない。たいていの有権者は適切な意見を持つために必要なほどの生物学や人工頭脳学を理解していない」のが実情です。そのため「従来の民主主義政治は様々な出来事を制御できず、将来の有意義なビジョンを私たちに示すことができないでいる」と現代の政治の限界を説いています。「政府というカメはテクノロジーというウサギに追いつかない」のです。
民主政治の機能不全は、有権者からすると自分の権限が失われていくことになります。
「イギリスでは権力がEUに移ったかもしれないと思い、ブレグジット(イギリスのEU離脱)に賛成票を投じる。アメリカでは有権者は既成の体制が権力をすべて独占していると思いドナルド・トランプや(左派の)バーニー・サンダースのような反体制の候補を支持する」ことが目立つ世界情勢です。しかしその背後にある状況は「権力がどこに行ったのか誰もわからないというのが悲しい真実なのだ」とハラリはいいます。
機能低下の民主主義制度の下で、「今日の政治家は一世紀前よりはるかに小さなスケールで物事を考え」、有権者は自分の権限を見失う。その状況は、やがて新たな制度やそれを描く予言者への待望に繋がっていきます。
4.ホモ・デウスか、新たな予言か
人類は20世紀まで、人間至上主義の世界を展開して来ました。
ロックやヒュームやヴォルテールの時代に、人間至上主義者は「神は人間の産物だ」と主張しました。18世紀には人間至上主義者が世界観を神中心から人間中心に変えることで、神を主役から外したのです。
そして人間は新たな神になる可能性も見せ始めました。超ホモ・サピエンスの登場です。
20世紀に生まれた遺伝子工学は、「40億年続いた自然選択の体制を変えようとしている」とハラリは説明し「地上に生命が誕生して以来の最も重要な生物学的革命」だと注目します。
そしてその生命の法則を変える3つの方法として、生物工学、サイボーグ工学、非有機的生命工学を解きます。
生物の形態や能力、欲求、欲望の改変を目指すのが生物工学であり、サイボーグ工学は有機的な器官と非有機的な器官を組み合わせます。そして非有機的生命工学は、独自に進化を遂げられるコンピュータプログラムやコンピュータウイルスのようなものです。この生命工学では、遺伝進化の手法を模倣し、遺伝的プログラミングの作成を目指しています。そしてそれらが非有機的な独自の進化を遂げると予想しています。
これらのテクノロジーは、すでに医学の部門でも研究、開発が進んでいます。再生医療やアンチエイジングが進化し、一部では傷んだ臓器の交換も始まりつつあります。
これまでの医療技術は、疾患からの回復が目的でした。しかしこの生命工学は、わたしたちの生理機能や免疫系、寿命だけでなく、知的能力や情緒的能力まで改変できる可能性を示唆しています。
そしてそれらの成果を踏まえ、今や富裕層においては、老化の防止やよりレベルの高い身体的機能の獲得という目的に利用され始めているのです。医療が人間の能力を高めることに専念するようになり始めているのです。
新しい超人
歴史を通して、上階級の人間たちは底辺層より賢く、強く、全面的に優れているという自惚れを持ちました。「これは自分にも相手にとっても欺きでしかなかった。しかし将来の医学では、この上流階級の自惚れは客観的事実になりえる」とハラリは予測します。多額な費用をかけて、知力を維持、構造させ、身体さえも若返らせる。ハラリの言う「新しい超人エリート」の誕生です。
20世紀まで、人は農民、労働者、あるいは兵士としてその生産などに欠かせない存在であり、彼らの健康を広く維持する方策がとられました、この大衆の時代には、病院と下水道設備の建設など、公衆保険サービスの実現による万人の健康と活力の確保が、国家と社会の課題でした。
しかしAIなどテクノロジーの発達は、その人々から多くの仕事を奪う可能性があります。ロボットによる工場生産から無人のサイバー攻撃が主役の戦場になる時代に、人々は労働を「搾取」される対象ですらなく、存在の必要がない「無用者階級」になりつつあるのです。そして社会の生産性からいえば「一部のエリートをアップグレードする方が社会にとって効率的」という時代が現実味を帯びてくるのです。
この「一部のエリート=超人」の特徴をハラリは、「感情も欲望も含めて、ホモ・サピエンスそのものを変える」「子供も設けず性行動もとらず、思考を他者と共有でき、私たちの1000倍もの優れた集中力と記憶力を持ち、決して怒りもしなければ悲しみも持たない。それでいて私たちの想像もつかない感情と欲望を持ち、永遠に若さを保つ」などと例示しています。
また別のところでは「人間の本質的な特徴の一部を持ち続けるものの、意識を持たないが最も高性能のアルゴリズムに対しても引けを取らないような、アップグレードされた心身の能力を持つ」とも記し、この存在を「ホモ・デウス」(神格化した人間)と表現します。
更に人間を超えて
人類は7万年前の第一次認知革命で広大な共同主観的領域、虚構を手に入れました。それにより、神々や国家、企業という虚構を生み出しました。都市や帝国を築き、貨幣や書字を発明し、前世紀には原子を分離し、月に人間を到着させました。
これらは「サピエンスのDNAの小さな変化と脳のほんのわずかな配線の変更から生まれた」のだとすれば、「私たちのゲノムにさらにいくつかの変化を加え、脳の配線をもう一度替えれば第二の認知革命が引き起こせる」。ハラリはこのようにテクノロジーの万能を信じる者たち「テクノ人間至上主義者」の出現も予測します。そして彼らは「ホモ・デウスは想像もつかないような新領域へのアクセスを獲得し、銀河系の主になるかもしれない」と壮大な想像を働かせています。
この神格化した人間の予測とは別に、ハラリはホモ・デウスに代わりうる存在も紹介しています。
21世紀の今、データ至上主義者が人間至上主義者に向かって言います。「神は人間の産物だが、人間の想像力そのものは、生化学的なアルゴリズムの産物に過ぎない」。そしてハラリは「21世紀にはデータ至上主義者が世界観を人間中心からデータ中心に変えることで、人間を主役から外すかもしれない」と予測します。
新たな全能者
私たちはかつてない演算能力と強大なデータベースを利用する優れたアルゴリズムを開発しつつあります。人間至上主義が「汝の感情に耳を傾けよ」と命じたのに対し、データ至上主義は「アルゴリズムに耳を傾けよ」と命ずるのです。
そしてそのアルゴリズムは、当初は人間の専門家によって書かれます。重要なアルゴリズムは巨大なチームによって開発されます。しかし「チームの各メンバーが理解しているのはパズルのほんの一部で、アルゴリズム全体を本当に理解している人はいない」のです。
さらに機械学習や人工知能のニューラルネットワークの台頭、ディープラーニングの能力向上により、アルゴリズム自身が独自に進化し、自らを改善し、自分のミスから学習します。これらのアルゴリズムは人間が把握できない天文学的な量のデータを分析し、パターンを見出し、人間の頭では思い浮かばない方策を考案します。「もとになるアルゴリズムは、当初は人間によって開発されるかもしれないが、成長することによって自らの道を進み、人間がかつて行ったことのない場所にまで、さらには人間のついていけない場所にまで行くのだ」。
このようなハラリの予測には新たな全能者の存在が浮かんでいます。その存在についてハラリは「すべてのモノのインターネット」という表現を使います。
「すべてのモノのインターネット」が「だれと結婚すべきか、どんなキャリアを積むべきか」という個人の人生を判定し、そしてやがては「戦争を始めるべきかどうかまで教えてくれる」。そんな時代は目前に迫っているハラリは警告しています。
このデータ至上主義の神となった「すべてのモノのインターネット」は、「まず人間至上主義に基づく健康と幸福と力の追求を加速させるだろう」、とハラリは予測します。そして21世紀の課題である不死と至福と神のような創造の力を得るために、途方もない量のデータを処理することが「すべてのモノのインターネット」の役割になります。
そしてハラリは人間に変わってその役割を果たすアルゴリズムは、人間の権限も代行する、つまり権限の移行が生まれると考えます。「人間からアルゴリズムへと権限が移ってしまえば、人間至上主義のプロジェクトは意味を失うかもしれない」。私たちは健康と幸福と力を与えてくれることを願って「すべてのモノのインターネット」の構築に励みます。
しかしそれが軌道に乗れば「人間はその構築者からチップに、さらにはデータに落ちぶれ、ついには急流に呑まれた土くれのようにデータの奔流に溶けて消えかねない」。半導体の小片、チップでしかなくなった人間は簡単に歴史の中に捨て去られるのです。
このようにデータ至上主義は新しい神、宗教を生み出す可能性があります。この新宗教の至高の価値は「情報の流れ」だとハラリは言います。
ではそしてこの宗教の中で、個々人の価値はどうなるのでしょうか。
データ至上主義者は、人間の経験は共有されなければ無価値だといいます。自分の中に意味を見出すことはできない、と考えています。私たちは「ただ、自らの経験を記録し、大量なデータフローにつなげさえすればいい。そうすればアルゴリズムがその意味を見出して、私たちにどうすべきかを教えてくれる」
データ至上主義の時代に「人間が他の動物より優れたものにしているのは何か」。ハラリはこの問いへの答えをこう記しています。
「人間の経験それ自体にはオオカミや、象の経験より少しも優れていない」。しかし「人間は自分の経験を詩やブログに書いてネットに投稿し、それによってグローバルなデータ処理システムを豊かにできる」。それゆえに「人間のデータは価値を持つ」というのです。そしてその価値は経験することにあるのではなく、あくまで経験を「自由に流れるデータ」に変えることにある、としています。
人間の経験の価値は、データ処理のメカニズムにおける機能に即して評価されます。もし人間の機能よりもっと巧く果たすアルゴリズムが開発されれば、人間はその価値を失うのです。運転手、石、法律家、詩人、音楽家・・・どの仕事も制作も、優れたコンピュータに取り換えられるのです。
人間の経験の神聖さ、感情の豊かさ、重さなどは評価されません。「愛」は「急激なホルモン分泌」により「一対の哺乳動物が肉体的に惹かれあうこと」でしかないのです。
データ至上主義へ懸念
「データ至上主義は、人間の経験をデータのパターンと同等と見なすことによって私たちの権威や意味の主要な源泉を切り離し、途方も無い規模の宗教革命の到来を告げる」こともあり得るとハラリは予測します。同時に、この教義を批判的に考察することも必要だと指摘しています。
意識を持つ知能=人間を、意識を持たない優れたアルゴリズムに取り換えることによって失われるものはなにか、とハラリは問います。
生き物がただのアルゴリズムというのは、データ至上主義の間違いかもしれない、とも予想します。しかしたとえ間違いであっても、データ至上主義はそれだけで退けられないとも彼は言います。
「多くの宗教は、事実に関して不正確でも途方もない人気と力を得た」。キリスト教や共産主義にそれができたのなら、データ至上主義にも十分普及、繁栄する可能性はあるといいます。
かつてキリスト教は「人間は神と神の構想は理解できない」と説いてきました。そしてデータ至上主義は「人間の頭では新しい支配者であるアルコリズムは到底理解できない」という論法を取ります。人間に理解不能なものに支配され、人間がチップのように捨て去られる可能性にどう対処するのか。この事態をハラリは警告しています。
5.幸福について
前項までで、ハラリの主要著作である「サピエンス全史」と「ホモ・デウス」のポイントを概説してきました。人類はサイボーグ工学や再生医療によって、非死を獲得するかもしれません。あるいは「すべてのモノのインターネット」という新たな神に隷属するかもしれません。その未来にも獲得すべき、守るべき幸せはあるのか。ここでこの両著作に共通する人類にとっての「幸福」について、彼の考えを追ってみます。
歴史学に見落とされた「幸福」
人間にとっての「幸福」という概念やその歴史的検証が、実はハラリの専門とする歴史学では「研究を始めたのはほんの数年前のこと」だと明かします。「現在私たちはまだ初期の仮設を立て、適切な研究方法を模索している段階にある」というのです。
「歴史書のほとんどは史実を語るが、それらが各人の幸せや苦しみにどのような影響を与えたのかについては、何一つ言及していない。人類の歴史理解にとって最大の欠落」とまで断言しています。
冒頭にも書きましたが、今世界を襲う紛争やパンデミックで、私たちは将来への不安を一層拡大し、同時に幸せについて考えざるを得ない時代でもあります。こここで「考察の不足」を意識しているハラリの幸福論をまとめてみます。
農耕生活は人間を不幸にした
人類の三大革命で紹介しましたが、幸福という観点でのハラリの農業革命についての見方を簡単に振り返ります。
狩猟生活から農耕への移行、その後の展開についてはすでに概説しましたが、結論としてハラリは「農耕生活は人々を幸せにしなかった」と断定していました。
さらに、彼はまず人間の身体能力からも「ホモ・サピエンスの身体は農作業に適していない」と指摘します。「人間の体はリンゴの木に登ったり、ガゼルを追いかけるため」であり、もともとは「雑食性の霊長類。多種多様なものを食べて栄える」種族だったといいます。そして農耕生活の中心的食物の小麦など「穀類はミネラルとビタミンに乏しく、消化しにくく、歯や歯肉に非常に悪い」。そのために現代人も悩まされている椎間板ヘルニア、関節炎など多くの疾患が農耕移行によってもたらされた、としています。
そのように人間の身体機能に不都合な農耕生活に切り替えても、多くの人間には経済的豊かさも、幸せも与えられなかったのです。
「平均的な農耕民は、平均的な狩猟民より苦労して働いたのに、見返りに得られる食べ物は劣っていた」。そして「農業革命で食糧の総量は増えたが、よりよい生活やより長い余暇には結びつかなかった」。農耕民はカロリー摂取をわずかな種類に頼る。悪天候や害虫、イナゴによる飢饉で多くが命を落とす。逆に豊作時は穀物の備蓄が生まれ、さらに定住生活により人々の「所有物が増え、避難がしにくい」。そして争奪が起き、強者の収奪、支配が生まれます。農耕への移行、農業革命はこうして「人口爆発と飽食のエリート層の誕生につながった」とハラリは社会の変化を説きます。
「農業革命は計算違いだった」と言い切るハラリの歴史検証は、大方のこれまでの見方を覆すだけに、大きな注目を集めました。
農耕生活の始まりは「安楽に暮らせる時代の到来に程遠い」。農耕民は「狩猟民より一般に困難で満足度の低い生活を余儀なくされた」というハラリは、「農業革命は史上最大の詐欺だった」とまで断じています。
ただし今回、紹介している著作では、この農業革命批判に対比してハラリが幸福度が高いという狩猟生活の豊かさは、その裏付けに不足感が否めません。
「狩猟採集民は何重もの(穀物など食料の)種を頼って生きている。一つの種が入らなくても他のもので補うし、移動もできる」。「狩猟採集民はもっと刺激的で多様な時間を送り,飢えや病気の危険が小さかった」などと指摘していますが、発掘や遺跡資料などによる裏付けの不足を感じます。
農耕生活によって急速な人口増加が生まれたことは史実によって確認されています。
「以前より劣悪な条件下で有っても多くの人を生かしておく能力こそが農業革命の神髄だ」ともハラリは論じますが、人口が増えるというのは、出産と成長の可能性が高まったことであり、それは一つの幸福の指標ではないか、という素朴な疑問も生まれます。
狩猟生活時代、世界の人口は横ばいでした。人口が増えない、それはまず食料確保の厳しさ、不足です。不十分な食料を追い求める苦労。それを回避できた場合の安息。幸福度は明らかに農耕民の方が高いのではないのでしようか。
このように狩猟採集民の幸せについては実証、根拠が不足を感じますが、このハラリの農耕生活不幸論で、逆に狩猟生活時代の再検証が進むことを期待したいと思います。
外的側面からの幸福
ハラリは、幸福という概念を、社会制度的な外面からと、人間の内面的な受け止めと両面から考察しています。
外側からの幸福という視点での農業革命について、上記のようにハラリは幸福度が増えたという見方を退けています。そしてそれに続く人間至上主義、そこから生まれた科学革命については、特に20世紀後半以降近代医療の勝利や暴力の激減、飢餓のほぼ一掃などを掲げで、幸福の増大を認めています。そして当面、共産主義をしのぎ「今や一つの倫理体系にまでなった」資本主義について、「第一の原則は経済成長が至高の善である。正義や自由や幸福まで、すべてが経済成長に左右される」と説きながら、成長によりもたらされる豊かさを、幸福のカギとして説明しています。
むろん富と幸福の相関は「一定の水準までで、そこを超えると富はほとんど意味を持たなくなる」と断りもつけています。
内的側面からの幸福
ただし、これまで見てきたように豊かさによる幸福は、相対的でもあります。
過去500年、科学と産業の革命を経て人類は前例のない豊かさを享受しています。しかし「私たちは本当に幸せになったのか」と問いかけて、ハラリは人間の感じ方、心、社会、倫理、精神的側面から幸福を考えます。
「この数十年、心理学者と生理学者は、何が人々を真に幸福にするかを科学的に解明するという困難な仕事に取り組んでいる」とハラリはいいます。
幸福とはお金なのか、家族なのか、健康なのか。まず何を計測すべきなのかが課題になります。そして幸福とは「たった今感じている快感であり、自分の人生の在り方に対する長期にわたる満足であれ、私が心の中で感じているものだ」とハラリはまず説明します。この内的要素を外部からどう計測するか。いま心理学者や生理学者は、一例として被験者に質問票を渡して、その回答を記録するという方法をとっています。
質問対象は富や政治的自由、離婚率など多岐にわたりますが、見落としてはならない点として、「家族やコミュニティが、富や健康より幸福に大きな影響を与えることだ」と注目します。「愛情深い配偶者や献身的な家族、温かいコミュニティに恵まれた人は、孤独な億万長者より幸せだろう」と説くハラリは、逆に現代は「コミュニティと家族が破たんをきたし、次第に孤独が深まる世界に私たちは暮らしているのだ」とも指摘し、「過去2世紀の物質面の劇的な状況改善が相殺されてしまっている」と警告しています。
そしてそれらの質問票によるもう一つの重要な発見として、「人間の期待」を挙げます。
富や健康、コミュニティは幸福の判断の重要な要素だが、「その度合いは主観的な期待との相関関係によって決まる」というのです。
「状況が改善すると、期待も膨らむもので、結果として客観的な条件が劇的に改善しても満足が得られないことがある。状況が悪化すると、期待もしぼむので、結果として大病を患ってもなおそれまでとほとんど変わらず幸せでいる場合もあるのだ」。
この結論にはさほどの意外性はありません。後ほど触れますが、預言者や詩人、哲学者は何千年も前から「持てるものに満足する」大切さを説いていました(※1)。
幸福が富や健康、社会的関係など客観的な条件だけで決まるのであれば、歴史の調査研究は比較的容易だったと考えられます。しかし現代の研究者が「幸福が主観的な期待に基づく」との結論に達することで「歴史学者の仕事が格段に難しくなった」ともハラリも認めています。
「毎日シャワーを浴び衣服を着替える現代人と、何か月も体を洗わず、着替えもほとんどしなかった中世の農民に満足感の違いはあるのか」とハラリは問いかけます。マスメディアと広告によって、先進国の生活標準を知らされた第三世界の人々の渇望、不満の増大。アンチエイジング医療による不老不死を目指す富裕層と、それに対するこれまで死の公平さで自らの不満を癒してきた貧しい者たちの怒りの増幅。現代の幸福、それへの満足観は、人々を分断しているとハラリは例示しながら、期待による幸福度の検証の難しさを説いています。
人生の意義と幸福
ここで内的側面からの幸福について、さらに別の観点を紹介します。
それは人生の意義と幸福との関係です。
ハラリはノーベル経済学賞受賞のダニエル・カーネマンの研究を紹介します。その事例は、子育ては日々大変な苦労があるのに、親たちが子どもこそ幸せの源泉だと断言することです。カーネマンはここから「幸せかどうかは、ある人の人生全体が有意義で価値あるものと見なせるかどうかにかかっている」と結論します。
人生の意義という視点からすれば、「中世の人は確かに悲惨な状況にあった」が、「死後に永遠の至福が訪れると信じていたならば、信仰を持たない現代人よりずっと大きな意義と価値を自らの人生に見出していただろう」とハラリは推測します。
死後の至福はキリスト教はじめ多くの宗教が約束しています。そして善や美、正義についていても客観的な尺度があると説いてきました。その時々の人間の「感情はあてにならない」(※2)のです。
一方、現代人の多くはこれと真逆の判断をするようになりました。
現代人の幸福は、この後説明する生化学の視点からの「快感」と人生の「意義」の二つが中心の要因になっています。そしてこの両者に共通するのが幸福とは「主観的感情である」という考え方です。
この幸福主観論は、「現代人の最も支配的な宗教」で、自由主義から生まれているとハラリは指摘します。自由主義では、個人の物事の善悪、美醜などの是非はみな個人が何を感じるかで決まります。「私が良いと感じるものは良い、私が良くないと感じるものは良くない」(ジャン・ジャック・ルソー)なのです。
(※1)「持てるものに満足する」とは、快楽の追求の危うさ、無意味さの指摘でもあります。古代ギリシャの哲学者エピクロスは2300年前に、快楽の過度の追求が人間の不幸を招くと弟子たちに警告しました。仏陀はその200年前に快楽は儚く無意味な気の迷いに過ぎず、苦しみを招くだけだ、と説いたとハラリは紹介しています。
「自分の感情はすべて束の間のもの。感情の追求をやめると心の緊張が解け、満足する。どんな感情もあるがままに受け入れる。真の幸福とは私たちの内なる感情とも無関係のものだ」とハラリが紹介する仏陀の幸福感は、次項で取り上げる、生化学的な見方との共通点が多いのです。つまり快感や幸福感は「沸き起こった時と同様にたちまち消えてしまう」のです。
(※2)「感情はあてにならない」と考えるのはキリスト教徒だけでない、とハラリは説明しています。ダーウィンやドーキンスも同じだといい、利己的な遺伝子説を書き加えます。
同説では人間も他の生物と同じで、自分の遺伝子の複製に有利な選択をするよう自然選択によって仕向けられます。例えば男たちがあくせく働いたり、競い合ったり、戦ってして一生を送るのも、彼らの感情ではなく、DNAに操られ、怒り、あるいは快楽に誘惑されているに過ぎない、というのです。
生化学から見る幸福
この幸福の計測について、さらに注目されるのが生物学者の進める生物学的要因や遺伝子的要素からのアプローチです。
「私たちの精神的・感情的世界は、何百万年物進化の過程で形成された仕組みによって支配されている」。そしてそれらは「神経やニューロン、シナップス、セロトニンやドーパミン、オキシトンのような様々な生化学物質からなる複雑なシステムで決定される」とハラリは生化学の見地からの説明をします。
宝くじに当選したり、家を買ったり、昇進したり、真実の愛を見つけたと思い喜び、幸福になるのは、「血流にのって全身を駆け巡っている様々なホルモンや、脳内のあちこちで激しくやり取りされている電気信号に反応している」だけだというのです。
ただしこの幸福の水準は、「生化学システムによって比較的安定した状態に保つようプログラムされている」ともいいます。
「幸福と不幸は、進化の過程において、生存と繁殖を促すか妨げるかという程度の役割しか担っていない」。セックスの経験のように「私たちはあふれんばかりの快感を一時的味わえるかもしれないが、そうした快感は長続きしない」というのが生物学者の考えです。
それを受けハラリは続けます。「純粋に科学的な視点から言えば、人生に全く何の意味もない。人類は目的も持たずやみくもに展開する進化の過程の所産だ」。「人々が自分の人生に認める意義はいかなるものも単なる妄想に過ぎない」
そして現代人が人生に見出す人間至上主義的思考や国民主義的意義、資本主義的意義もまた「妄想だ」とハラリは言い切ります。「幸福は人生の意義についての個人的な妄想を、その時々の支配的な集団的妄想に一致させることなのかもしれない」。
「これはなんとも気の滅入る結論ではないか」とハラリは自ら展開した論理の帰結に戸惑い、「幸福は本当に自己欺瞞あってのものなのか」と問いかけてこの論考をひとまず終えています。
おわりに
2013年のオックスフォード大学における研究では、コンピュータアルゴリズムの利用拡大で、20年間に米国内の約半数の仕事が深刻な危機に襲われる、と予測しています。無用者階級の増大です。一方で「すでに世界の1%の最富裕層が世界の富の半分を所有している」時代です。これ以上の富の階級分離を回避し、無用者階級への没落を防ぐための教育はあり得るのか。21世紀の人間の育成、教育についてハラリは以下のように記しています。
「2030年や40年に求人市場がどうなっているか、私たちにはわからない。今日すでに、子供たちに何を教えればいいのか見当もつかない。現在子供たちが学校で習う事の大半は、彼らが40歳の誕生日を迎える頃にはおそらく時代遅れになっているだろう」
サイボーグ人間やホモ・デウス失墜、虚妄の幸福論など、夢も明るさも乏しいハラリの未来予測を紹介してきました。いわばハラリの“悲観史論”が続きました。
しかしあえて厳しい未来を予測すること。そこに「歴史書の意味がある」とハラリは書き留めています。
歴史書は「歴史は変えられるという前提に立つ」とハラリは説きます。
「歴史の研究」とは、人々に「通常なら考えられない可能性に気づくよう仕向けること。過去から解放されること」が目標だといいます。そして人々が「いま何が起こっているかを理解し、自ら決断し、今後の展開をなすがままに成るのを避けること」。これが自らの著作の使命だとハラリは考えています。
ハラリの一連の著作はこの狙い、使命を十二分に果たしており、それが数千万という読者を生み出している理由だと、納得が出来るのではないでしょうか。
そしてハラリの歴史観が「今起こりつつある問題を的確に解決する手段」になりえるかどうか。ハマス侵攻に対する冒頭のハラリの認識や、対応姿勢に今後も注目したいと思います。
著書紹介

ホモ・サピエンスがなぜ地球上の生命の覇者になれたのか。その要因を7万年の人類の歩みから考察しています。認知、農業、科学の3大革命をもとに、言語によって虚構を操り、国家そして貨幣まで生み出した構図、そして「幸福」という視点から人間とはどのような存在かを斬新かつ鋭い視点で教えています。

サピエンス全史を踏まえ、飢餓と疫病と戦争を克服し始めた人類の行方を探ります。近代以降の人間至上主義を振り返り、科学とテクノロジーの進歩によって新たに生まれたデータ至上主義を解説。その中に人類が飲み込まれてしまう危険性を指摘しながら、その危機を回避するための知恵を、俯瞰的かつ論理的に紹介しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
