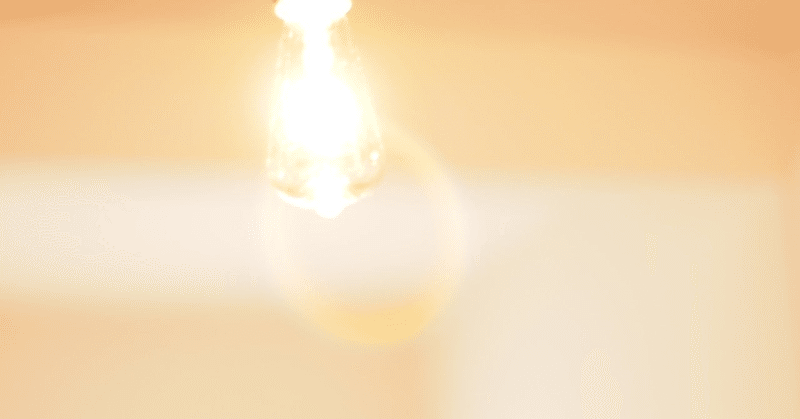
井戸川射子さん『共に明るい』ー言葉にならない何かの尊さー(書評)
言葉は世界のほんの一面に過ぎず、見えているものも氷山の一角でしかない。言葉によって表される前にただ世界は存在し、その中でそれぞれ自我をもった人と人が、見える影響や見えない影響を与え合って生きている。それだけのことであり、人は孤独でもないし言葉によって痛いほど繋がってもいない。言葉の力で定義された一つの形でないからといって関係性が偽物というわけでもない。そういった曖昧さに、本書は光を当てる。
本書に描かれているものを、私は簡単に要約することができない。むしろ、要約しないことによって本書の特徴を浮かび上がらせることに近づけると考える。敢えて言えば、同じバスにたまたま居合わせた人々の心象、たまたま居合わせた人間同士が時間を共にする様子、浮気性の男性とその彼女の心象、などが短編の形で描かれている。だが、本当に描かれているのはそういった書かれているものではなく書かれていないものの方なのだ。
何かを言えば、零れ落ちていく何かがある。誰かの視点で見れば、零れ落ちていく世界がある。本書では、誰かの視点に依ることなく、また何かの文脈に依存することなく、ただ日の光が差し込むように人々に、動物に、世界に、光を当てている。また、登場人物の属性についても、最初にその属性を明示するのではなく、話が進む中で浮きあがるような構成を取っている。もしかすると、登場人物の人間は知っている誰かであり、貴方であり、私である。登場人物に対する認識を「属性」や「固有名詞」、また語り手と相手の心理的距離に依存させずに書ききる。
人を他者として属性や固有名詞の中に押し込めたり、心理的距離をもって相手を見たりすることは、裏を返せば自分に孤独をもたらすということだ。なぜなら、自分も相手からそのような認識で見られているという前提に繋がり、自分を役割や関係性という檻に閉じ込めてしまうことになるからだ。
「私ね、二度目に会った人と話す、っていうのがあんまり上手くできないの」と語る登場人物。彼女と出会った彼は、「彼らは来たいときがあればそれぞれ来る、どちらかがあのベンチに座っている、目が合えば手だけ振り合う。肩でも叩きに行きたいが、嫌な想いをするかもしれないので慎む」といった(敢えて言うならば)関係性を育んでいく。近いことや、強制された接点の継続だけが関係性ではない。この二人の姿をどう受け取るかは、読者に委ねられている。
本書は、言葉で掴んでしまおうとすれば掴めない。むしろ、掴めないからこそ存在する曖昧さの尊さを描いている。その言葉にならない尊さを、読者は登場人物と共に理解するより前に感じることができる。それこそ、本書のタイトルである「共に明るい」ということだと、私は思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
