
ふたりきりで明かした、かわいい憎しみに殴られた夜(戸田真琴)
エッセイアンソロジー「Night Piece〜忘れられない一夜〜」
「忘れられない一夜」のエピソードを、毎回異なる芸能人がオムニバス形式でお届けするエッセイ連載。

戸田真琴
セクシー女優・文筆家・映画監督。写真集に『The light always says.』(玄光社)、著書に『あなたの孤独は美しい』(竹書房)、『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』(KADOKAWA)がある。2019年に監督した映画『永遠が通り過ぎていく』が2022年4月1日よりアップリンク吉祥寺ほかにてロードショー予定。写真作品のディレクションや衣装スタイリング、Podcast、小説の執筆など活動は多岐にわたる。
他人にお腹を殴られたのはその1回限りで、それが世にもへろへろとした軌道・柔らかい拳によるものだったことは幸運と言っていいのかもしれないけれど、ともかくまったく痛くなく、そんなことよりも殴り主の精神状態のほうが私は心配で仕方なかった。
「あんたなんか、死ねー!」(記憶が定かではないけれどたぶん彼女が言い捨てるならこの程度の妄言だと思う)とかなんとか言いながら拳を振り抜き、よろめく私をライブハウスの入口に置いて、彼女は街へ走り出した。

茶色いヒールのショートブーツ。夜の下北沢だ。垢抜けきっていない、メルヘンチックな服装をした女の子が泣きながら走って行って安全だなんて言いきれない。
しばらく呆然としたものの、私は追いかけた。田舎者には迷路のような道の上で、小慣れた街の住人たちとすれ違いながら彼女を探す。閉店後の店の前、自販機の影に彼女は隠れて泣いていた。他県から来ていることを知っていたので、
「電車、大丈夫なの?」
と聞く。すると、もう終電は過ぎ去ったようだった。
何度も言うが、彼女は夜の下北沢に置いていくのはちょっと危険だ。チェックとフリルの短いスカート、黒いボブカットにふくよかな童顔で、お世辞にも強そうには見えない。めそめそと泣いていて、悪い人に誘われても今にもついて行ってしまいそう。持ち前の騒がしさで暴れても勝てない相手もきっといる。この街で彼女のことを知っているのはほとんど私だけかもしれなかったから、そのぶん選択肢がなかった。
「ちょっと歩くけど、うちに来る?」と聞くと、せっかく閉まりかけた涙腺をまた全開にして、ぎゃあぎゃあと泣きながら、
「あんたのこと、大っ嫌いで、大好きなのー!」
と、言われた。戸惑うふりをしながら私は、それはなんとなくわかってたよ。と、思った。
そして、引っ張るように駅に向かい、電車で少しの間揺られて、駅から歩いて15分、私のボロアパートに彼女を泊めることにした。

夜中の住宅街を歩いている間、彼女はぽつりぽつりと、悪態をつき続けた。
「都会に住んでると思ってたけどけっこう田舎じゃん(笑)」「こんな何もないところに住んでんの?」「うわーけっこうボロそうなアパート」「家賃、親から出してもらってないの? 私は光熱費も全部払ってもらってるし仕送りももらってるけど」「お父さん、お金欲しいって言えばくれるんだー」
きっといろいろな思いが混じり合う中で、一貫して柔らかいトゲで傷つけようという態度を決め込んでいてくれることが、むしろ心地よかった。
彼女は当時観に行っていたバンドのライブでよく見かけていた女の子だった。年代も近く、同じ空間にいることが多かったので、いつからかお互い意識するようになり、そしていつからか、彼女はSNSなどに私の悪口を書くようになっていた。
「お腹殴ったの、ごめんね。でもあんたが悪いんだよ」
私は、「SNSで“腹パンしてやりたい”って書いてたの知ってたからいいよ。わかってたし」と、返す。私たちがファンをしているバンドのメンバーと、私がよくおしゃべりしていたのが本当に気に食わなかったようだった。
彼女は親しい友達とSNS上でよく私の陰口を叩いていた。文句をつけるところを見つけるのが下手なのか、「名前がダサいから親もきっとダサいに違いない」といったような、「おまえのかあちゃんでべそ」と同レベルのことを言っているのがおもしろかった。
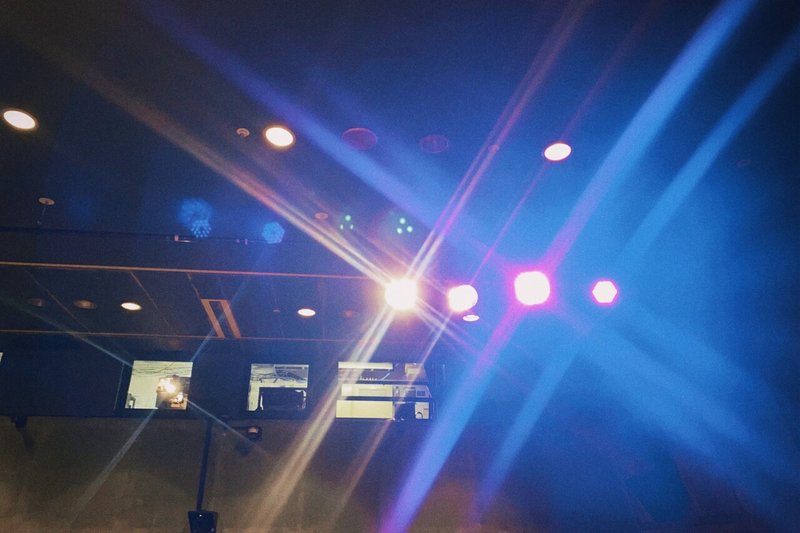
それから私たちは始発まで、と約束して私の部屋で夜を明かした。部屋の中では、ほとんど初めて人に見られる天蓋やバラ模様のフリルだらけの布団、白いうさぎのぬいぐるみやドーナツ型の時計が、張り詰めて静かにそこにいる。モネの『日傘をさす女』、ターナーの灯台と船の絵、黄色みがかった世界地図、小鳥のネックレス、薔薇の花のドライフラワー。好きなものがたくさん壁に飾ってあって、私も大概メルヘンチックだった。
家にあったのは濃縮還元のオレンジジュースだけで、それをミスタードーナツのポイント特典でもらったピンク色のマグカップに注ぐ。持って行くと、受け取り損ねた彼女はマグカップから手をすべらせ、かけ布団の端と、床をオレンジジュースまみれにした。
「ごめんね、ごめんなさい」と謝る彼女に対して、私は本当に謝らなくていいよ、と思っていた。とりあえず淡々とタオルで拭いていく。バラ模様の布団からオレンジの香りが広がって、タオルで叩くごとに舞い上がる。花畑にいるみたいだった。
「本当は初めて見たときすごくかわいいと思ったの。服装とか、こういう部屋にある好きなものとか、すごくわかるって思うところが多くて、私、あなたみたいになりたかったの」
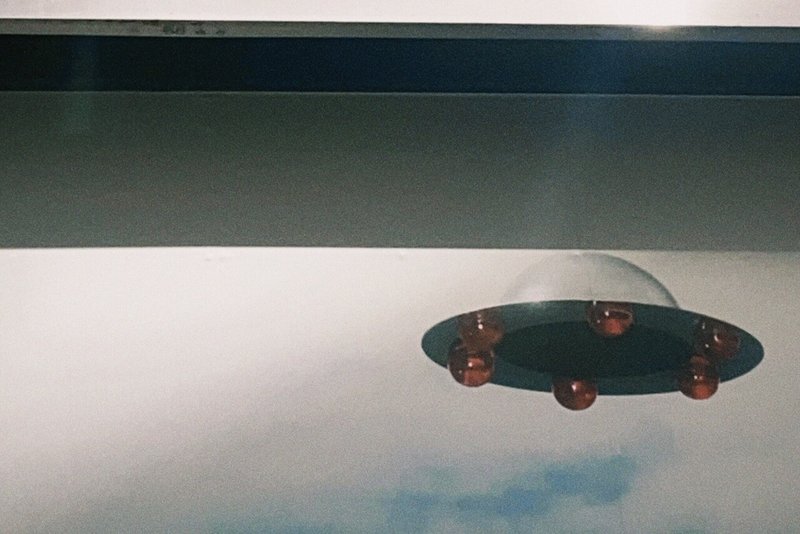
当時の私は今と比べてもかなり精神的にトガっていたし、自分のことを絵本の登場人物なのだと思い込んでいるようなところがあって、そのこだわりが服装や振る舞いに表れていた。
流行り廃りのない、ずっと昔の物語に出てきても遜色のないデザインのワンピースしか着なかったし、靴もおとぎ話の中を走って行けそうな革のメリージェーンしか履かなかった。いつも右耳の上に花のバレッタをつけていて、日傘をさして歩いた。本当に、心からそうしていたら、物語の中だけを生きていける。つまらない大人になんかならないでいられると、信じて疑わなかったのだ。
申し訳なさそうに、恥ずかしそうにうな垂れる彼女を見ていると、そういう凝り固まった理想が、少しずつほつれていくような気がした。うまくいかない日々を生き、手にしたいものが手に入らず駄々をこねる姿が、こんなにかわいくておもしろいのだということを、私は知らなかった。さっきから、殴られても悪態をつかれてもジュースをこぼされてもちっとも怒る気にならないのは、私がこの子を、かわいいと思っているからなのだとわかった。
私は、あなたは私にならなくていいよ、そのままでいいところがいっぱいあるもの。と、繰り返し言った。それは本当のことだった。私は他人を殴ったこともなかったが、「本当は好きなの」だなんて、もっとずっと、言えたことがなかった。

夜もとうとうふけ込んで、ちゃんと歩いて帰りたいならそろそろ眠りにつかなきゃだめだよ、と私が言うと、オレンジジュースの香りの布団の中で、最後に彼女は聞いた。
「私のこと、本当にいいところがあるって言うなら、具体的にどういうところなのか教えてほしい。私のいいところってどんなところ? 私は私のいいところなんてわからない」
ゴブラン織の花柄のカーテンの隙間から、青く静かな星々がのぞき、心配そうに瞬いている。目の奥がすう、と透き通っていくのがわかる。人のいいところだけを見ようとする訓練は、こういうときのためにあるのだ。
少しだけ時間を置いて、私は答えた。
「イノセントなところ」
彼女は、しばらく黙って、それから、
「イノセントってどういう意味……?」
と、聞いた。
私は吹き出して、しばらく笑って、それから、本当に楽しくなった。
「そういう、わかんないこととか、あと好きとか嫌いとか、全部虚勢を張らずに口に出すようなことだよ」
そう言ってもなかなか納得しない彼女は、それのどこがあなたよりいいところなの?と聞くけれど、教えてあげないことにした。
夜が明けて、彼女は始発より少し遅い朝の電車で帰って行った。朝日で黄色く染まった部屋には、オレンジの香りだけが残っている。ただ好きだと思われることよりも、同時に憎まれることのほうがおもしろいだなんて、一丁前に達観したふりをして、大概メルヘンチックなまま薔薇模様のふとんで眠った。

こんな思い出話は大概時間を経て美化されているだろうし、実際の私たちはもっと俗っぽい、どこにでもいる少女だったのだと思う。私はこんなにかっこよくなく、彼女もこんなにかわいくもなかっただろう。
だけれど、ふたりで夜を明かしたことだけは、夜空の星々が知っているのだ。かわいい憎しみに幸あれと、美化した記憶を撫でてみる。
忘れないひとつの夜のお話。

文・撮影=戸田真琴 編集=高橋千里
