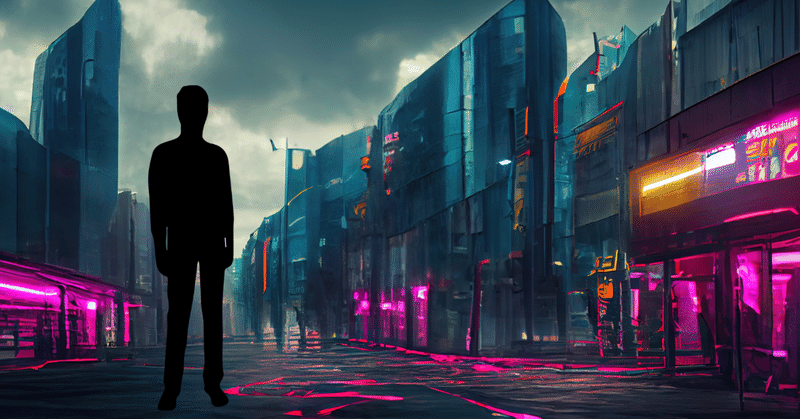
ケケケのトシロー 8
キダローに勇気を出せと言われたトシローは、あのやんちゃな兄ちゃんがまた無茶を言って暴力をふるう現場に出くわす。ボロボロにされるおじさんを見て思わず止めに入ったトシロー。そして勇気をだして金の要求を断るが、案の定、また袋叩きにあってしまった。
(本文約3400文字)
「ほれ、はよ立たんかい」
キダローが手を差し出す。それに掴まり立ち上がろうとしたが、腕も腰も
痛くてどうにも踏ん張れない。
「痛っ、あかん、あちこちが痛くて力がはいらないよ」
「ほんま、情けないやっちゃ ケケケ ほれ、これを」
キダローは自分が纏っていたケープを脱ぎ、俺の肩にかけてくれた。すると嘘のように痛みがなくなり、普段よりもスムーズに立ち上がることができた。
「これは一体……」
俺はケープの裾や生地を触ったりしてみる。模様のない濃い灰色で、表地は何かの皮のようだ。裏地は起毛が覆い暖かい。結構な厚みがあるようにも思うがとても軽く、両肩から肘の部分までをすっぽり覆っていても動きづらさは感じない。それよりも不思議なのは身体の痛みが消えたことだった。
「なんで? 痛かったのが治ってしもたで」
「そうやろのー、ケケケ 今、お前の身体は一時的に他所にあるからな ケケケ」
「は、何言うてんの? 俺の身体はここにあるがな」
俺は自分の手足を見て確認をする。胸を触ってみると貧弱な胸はちゃんとある。
「今のお前に言っても分からんやろけどな ケケケ ほな、それ脱いでみ」
ケープを肩から外してみると、また痛みが全身に戻ってきた。
「あたたたたた」
「お前、ケンシロー※₁か? トシローやろ? ケケケ はよ、もう一回羽織れ」
俺はケープを羽織る。そうすると痛みはなくなる。なんだ? 本当に身体がここにないみたいだ。
「なんでんの? この不思議なのは」
「まあ、ええから、とにかくついてこい」
店の自転車置き場を出て、駅の裏側へ回り込むように歩いていく。こちらは店舗が少なく古くからの住宅街が並ぶ地域だ。そう言えば痛みは消えたけれど鼻血は止まってるのか? 手で触ってみるが鼻水しかつかない。これは救急車より役に立つなと思いながらキダローの後をついていく。あいつは外見は俺と同じ爺さんだが、足腰は強そうで、さっさと先へ進む。痛みはないが、もたもたしているとおいていかれそうになる。
暫く歩くと古い神社の鳥居が見えた。たしかこの社は宮司が普段いないところのはずだ。小さな神社であり、祭りごとの時には他所から宮司が来て執り行いもするが、氏子が毎日の手入れを行うだけのところと聞いたことがある。キダローは石の鳥居をくぐると、社務所かと思われる平屋の引き扉の前に立ち、なにやら低く気合のような声を短く発したあと、慣れた様子で扉を開けて俺を誘う。
「さ、ほれ、入れ ケケケ」
誘われ中に入ると、低い上がり框で仕切られた八畳くらいの板間があり、その三分の一くらいは数段に重ねられた長持で占領されていた。
「あの、なんでんの、ここ。あんたの家ではないでっしゃろ?」
「ケケケ 家ではないな。まあ、専用の倉庫みたいなもんや ケケケ」
キダローはそう言いながら長持の蓋を一つ、二つと開け、なにやら探し出した。
「あの、倉庫、言うけど、鍵もかけてないのと違いました? ようけ荷物おいてるのに、泥棒にはいられません?」
「そんな心配はいらん。ここの鍵はわしや。わしに無断では絶対に出入りできん」
キダローは『あれ? どこやったかいな~』とも言いつつ何かを探している。
「もしも入ったらどうなりますの?」
「扉も窓も開かんから入れん」
「いや、もし、開けっぱなしのところ入られたらよ」
「しつこいな、入られへんねん!」
「なんで? 鍵空いてたら、扉は開きますやん」
「ほな、お前、さっきの引戸、開けてみい」
キダローは探し物の邪魔をするなと言わんばかりのもの言いだ。
俺は振り返り、後ろ手に閉めたはずの引戸に手をかけ、開けようとするが扉は全く開かない。鍵があるのかと見てみるが、戸板が二枚あるだけで、鍵などが付いている様子もない。玄関扉の枠がひずんで開きにくいという感じではない。言えば重い。まるで鋼鉄かコンクリートの壁を無理に動かそうとしている感じだ。つまり、動かない。
「はんまや、何で? さっき俺、締めれたのに」
「俺が閉まれと念を送った。 あ、あったで! ケケケ」
キダローは『ほれ、お前の』と俺にケープを差し出した。今、借りているケープと同じように見える。多少、黴っぽいが。
「これやるから、それ、俺のやつ、返せ。それはお前にはちょっとまだ、荷が重いからな ケケケ」
「重いって、めちゃ、軽いけどな、これ」
言われるままにケープを脱ぎ、キダローに返す。痛みがまた襲ってきた。
「いたた」俺はもらったケープを羽織ろうとするが、どうも黴っぽく、それを洗濯したタオルを干すときのように振って拡げた。
「あー!やめとけ!」
キダローが叫んだ時には、ケープは板間を全部覆いつくすほどの大きさになってキダローも何もかもを包んでしまった。
「あほ、ぼ…… カスー…… はよ、もう一回……」
大きくなったケープのなかでキダローが何かを叫ぶが、あまり聞き取れない。
「え、聞こえへん? もう一回、何?」
「もう…… ふ…… もが」
キダローが暴れているのはわかるが、何を言いたいのかが分からない。しかし、身体の痛みも増してくる。俺はとにかくそれを羽織ろうと、痛みを堪えて大きくなったケープを引き寄せるように力をいれるが、びくともしない。何回か試すがどうにもならず、俺は掴んでいたケープの端を上下に振った。するとケープは元の大きさに戻ってきた。ついでにキダローと沢山の長持が俺に向けて飛んできた。
「うぎゃー」俺は咄嗟にケープを飛んでくるキダローの前に拡げる。するとケープが盾のようになり、飛んできたキダローと長持がそれにぶつかって俺の前で山になって落ちた。
「あがが、お前な~」
「すんません、もしかして、俺のせいですかね」
「使い方教える前に、振り回すな…… ケ イタタ」
「すんません、すんません」
俺は謝りながら、新しいケープを羽織り、長持を元通りに片付け、キダローと共に神社を後にした。キダローも頭を打ったのか、かなり痛そうにしていたが、返したケープを纏うと何事もなかったかのように闊歩していく。
これはほんとにすごいケープだと、俺はなんだかスーパーマンにでもなったかのような気分だった。
また川沿いの道を歩く。しかしいい歳のジジィが二人、今時、こんなの羽織って並んで歩いている様子を、周りの人はどう思うのだろうか? すれ違う人の視線を気にしているが、俺達に特別の興味を示す人はいない。
「キダローはん、俺の顔、腫れてません?」
「え? ああ、アイツにやられたとこか? あざになってるで ケケケ」
「うえ~、恥ずかしいなあ」
「恥ずかしいか? ケケケ」
「そりゃ、人前、ひどい顔して歩いてたら、恥ずかしいですがな」
「心配すな ケケケ お前は今、ここを歩いてるけど、他の人間には一切、興味のない存在になってるねん。そう、陰の状態やな」
「見えへんゆうことですか?」
「いや、見えてないわけではない。印象に残らんのよ ケケケ」
俺は最初にキダローに出会った時のことを思い出した。確かにシルエットのようであり、顔や服装やそういったものがなぜか記憶に残らなかった。
「このケープのせいでっか?」
「そうや、あ、そうや使い方教えながらいこか」
「修行とか、せなあかんのでっか?」
「修行? そんなんいらんねん。これは使える奴は使えるし、使えん奴は1000年修行しても使えん。初めから決まってるんや『ケケケの掟』や」
「『ケケケの掟』? ほな、さっき俺が大きく出来たいうことは、俺は使える奴いうこと?」
「そうやの ケケケ ちょっとわしもさすがにビビったけどな、いきなりやから。お前はケケケの天分を持ってるのは間違いない」
「うへ~。俺、そんなヒーロー的な才能あるんですか」
俺はかなり嬉しかった。やっぱりスーパーマンみたいやん。
「まあ、お前の情けなさぶりは天下一品やからな。ケケケ 正真正銘の弱虫のあかんたれの卑怯者の泣き虫の……」
「そこまで言うか」
俺は一気に落ち込む。まあ、その通りだが。
「ただ、悪人にならん勇気だけはある」
「そんなん誰かって、大抵の人はそうでっせ」
「それはそうやけどな…… ここからが…… 『ケケケの掟』を守れるかというと、誰でもええとはいかんのよ ケケケ」
キダローは口角をあげ、夕陽に染まりかける川向うを見た。俺は俺で早く洗剤を持って帰らねば真由美にまた叱られると思っていた。
※₁ ケンシロー 北斗の拳
エンディング曲
NakamuraEmi 「かかってこいよ」
ケケケのトシロー 1
ケケケのトシロー 2
ケケケのトシロー 3
ケケケのトシロー 4
ケケケのトシロー 5
ケケケのトシロー 6
ケケケのトシロー 7
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
