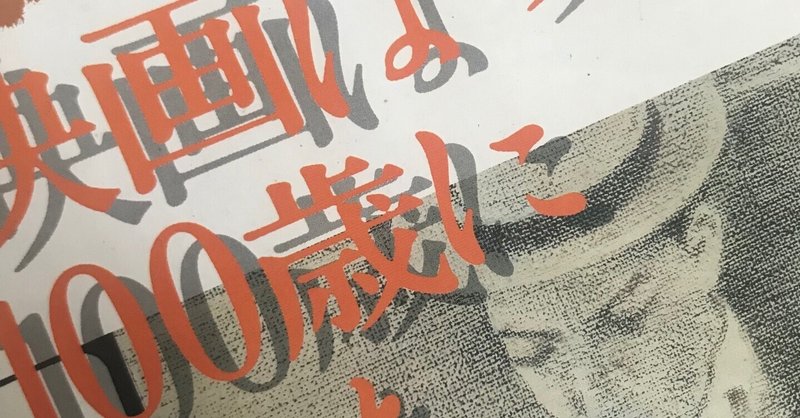
吹替史講義①「吹替と活弁〜羽佐間道夫からAマッソまで」
吹替は、声優は、映画史においてどのような役割を果たしてきたか、について考察するシリーズ第1弾。今回は、活弁をはじめとする話芸の伝統文化が吹替または声優に与えた影響と共通点について考えていきます。
まだサブスクも、VHSもLDも、洋画劇場も、そもそもテレビさえなかった1880年代、人々が映画を観るには映画館に行くしかありませんでした。当時発明されて間もないサイレント映画にはまだ声も音もなく、そこには映像と音楽隊の生伴奏、そして弁士の声だけがありました。
さて、トーキー映画にだけ存在する「吹替」に対し、サイレント映画には「活弁」というものがあります。驚くべきことに、世界の映画史を振り返っても「活弁」がここまで発達したは日本だけだそうです。アメリカやヨーロッパではあまり発達しなかった「活弁」は、日本ではトーキー映画が流行する1930年代の中ごろまで当たり前のように普及していました。もともと日本には落語、漫才、講談、浪曲、義太夫という伝統的な語りの文化芸術がありました。世界でほとんど日本でだけ「活弁」が発達したのは、時に朗々と、時にケレン味たっぷりに謳い上げる「活弁」向きのパフォーマンスの素地があったこと、そして観客が語りの文化に慣れ親しんでいたことが影響しているに違いありません。
これらの伝統を吹替に取り入れようとしたのが「ロッキー」の吹替で有名な羽佐間道夫です。羽佐間は若手時代にチケット売りのアルバイトをしていた寄席で、古今亭志ん生、桂文楽、三遊亭圓生といった名人たちの芸に触れました(志ん生にはそば屋に連れて行ってもらったなんて信じられないエピソードも!)。また、竹本駒之助(現在は人間国宝)のもとで浄瑠璃を1、2年学んだこともあるともいいます。
美声の羽佐間がわざとらしいダミ声を使った演技を実践するのは浪曲からの影響でしょう。羽佐間がシルヴェスター・スタローンの吹替を務める際、海に向かって大声で「浄瑠璃」を語って喉を嗄らしたという逸話はあまりにも有名ですが、彼を師と慕う山寺宏一は羽佐間について次のように述べています。
たとえば日本の古典芸能、落語、そして浪曲とか、ほかの色んなですね、ことに詳しくて。あれの彼のこういう語りの、ここが、この間とこの声の出し方、ここが痺れるんだね、みたいな。それを自分の仕事に活かそうっていう情熱を持ってらっしゃる方で。
また、彼らは活動写真の弁士である「活弁」という呼び名を嫌い、もっぱら「説明者」を自称しました。これはかつて吹替やアニメで人物の声を演じる者が「声優」と呼ばれるのを嫌い、「アテ師」「俳優」などを自称したことと似ています。
「活弁」は、すでにそれ自体で完成しているサイレント映画を上から自由に味付けをし、ローカライズし、物語を変容させてしまう映画の破壊者であるという批判もあります。(無論、吹替も同様です。しばしばネットでは、吹替字幕論争が勃発し、吹替は本物の俳優の声ではない、字幕は台詞の半分も訳せていない、などという批判が飛び交います。)
しかし、そんな真っ当な意見とは裏腹に、映画をより分かりやすくエモーショナルに装飾してくれる「活弁」は大衆に受け入れられ、大人気を博しました。実際、観客は映画そのものではなく、好みの弁士を選んで映画館に通ったのです。まるで「ダイ・ハード」を野沢那智で観るか、樋浦勉で観るか、村野武彦の吹替で観るか、決めるように。
もちろん、先述の通りアニメや吹替は、講談とも切っても切り離せない関係があります。たとえば、「クレヨンしんちゃん」のマサオくんでおなじみ一龍斎貞友や「宇宙戦艦ヤマト」の森雪役の一龍斎春水(麻上洋子)は声優でありながら講談師としても活動していますし、山寺宏一は落研出身、関智一はどういう訳か立川志ら乃に弟子入りした経験があります。まるでかつて義太夫語りだった上田布袋軒や、テキ屋をやっていた坂田千駒が弁士になったように。
ここで批評家の四方田犬彦の文章を引用しましょう。
映画が映像と音声の結合であるという、そもそもの定義に立ち止まるならば、外国映画を鑑賞している人間は、映画を体験しているのではなく、実は映像と文字言語の結合、すなわち漫画を体験しているのだ、という結論になります。
ここで抑えておくべきなのは、視覚体験として誕生した映画が、日本でだけ発達した「活弁」によって、トーキー映画の発明以前に、すでに視覚(映像)と聴覚(声の演技)の体験として受け入れられていたことです。つまり日本の吹替文化は、洋画劇場のあった時代より以前に、いいえトーキー映画の発明以前に、すでに「活弁」という形で存在していたと言えます。そしてこの映像と聴覚の体験は、2020年にAマッソの「映像漫才(©︎柿沼キヨシ)」として新たな革命が起こりますが、それはまた別の機会にしましょう(しません)。
さて、今回は、吹替史講義①と題して「吹替と活弁」について考察してきました。次回は吹替史講義②「吹替とラジオドラマ」について書こうと思います(書けるかな…)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
