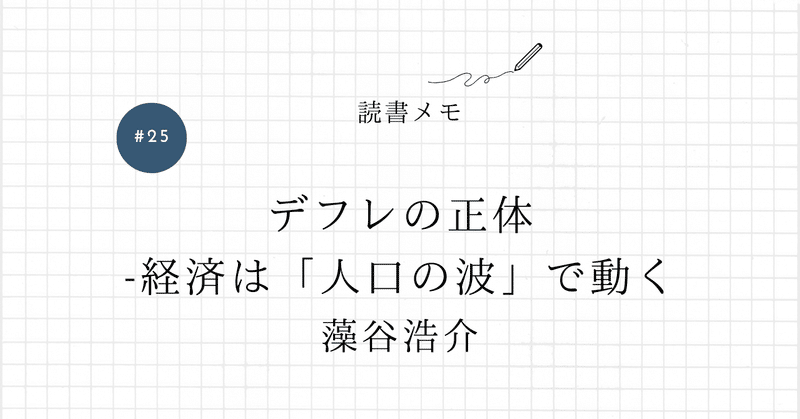
読書メモ:デフレの正体
基本情報
『デフレの正体‐経済は「人口の波」で動く』
藻谷 浩介
2010年6月10日 発行
以前コメントでらんたさんにご紹介頂いた本書。発行は、10年以上前だが、らんたさんの仰る現在でも通用し、納得できる良書であった。
発行された当時と比較し、多少の状況変化はあるものの日本の経済の現状の原因に関しては、大きくは変わっておらず納得できるものであった。
日本経済の不振の原因を「人口」に観点から検討、解説されている。
構成
第1講 思い込みの殻にヒビを入れよう
第2講 国際経済競争の勝者・日本
第3講 国際競争とは無関係に進む内需の不振
第4講 首都圏のジリ貧に気づかない「地域間格差」論の無意味
第5講 地方も大都市も等しく襲う「現役世代の減少」と「高齢者の激増」
第6講 「人口の波」が語る日本の過去半世紀、今後半世紀
第7講 「人口減少は生産性上昇で補える」という思い込みが対処を遅らせる
第8講 声高に叫ばれるピントのずれた処方箋たち
第9講 ではどうすればいいのか①
高齢富裕層から若者への所得移転を
第10講 ではどうすればいいのか②
女性の就労と経営参加を当たり前に
第11講 ではどうすればいいのか③
労働者ではなく外国人観光客・短期定住客の受入を
補講 高齢者の激増に対処するための「船中八策」
感想
著者である藻谷さんは、日本経済の不振は「内需不振」に原因があり、国内の消費が進まないことを2010年当時から指摘している。
その内需不振は、生産年齢人口(15~64歳の現役世代)が減っていることが主因であり、景気ではないとしている。そもそものお金を使う人数が減っているのだから、国内でお金が回ることはないわけである。
この状況は、生産年齢人口の上限をあげようとしたり一時的な対策は検討されていたように思うが、2010年と2024年を比較しても大きくは変わっていない。
また、藻谷さんはそこで以下の3つの対応を提示している。
①生産年齢人口が減るペースを少しでも弱める。
②生産年齢人口に該当する世代の個人所得の総額を維持し増やす。
③個人消費の総額を維持し増やす。
そして、具体策として以下の3つを提案している。
①高齢富裕層から若い世代への所得移転の促進
②女性就労の促進と女性経営者の増加
③訪日外国人観光客・短期定住客の増加
2024年に見ても違和感は感じられない。
具体策の②女性就労促進と女性経営者の増加は、2010年に比べれば共働き世帯が半数近くになっていることを考えると進んでいるが、女性経営者はまだまだではないだろうか?
そして、③は、新型コロナで一時期減ったが、現在はオーバーツーリズムが問題になるぐらいなので、だいぶ増えてきていると思う。
問題は、①の所得移転である。
藻谷さんの提案では、国の税の再分配による方法よりも企業による対策を推している。
国はすでに借金をしており、相続税での工夫はあるが、それよりも高齢富裕層向けの商品・サービスを企業が作り、稼いだお金で給料を上げて若い社員に移転するというものである。
ここ4~5年は、国からの強いプッシュもあり、賃上げが2010年頃と比べると進んでいると思うが、所得の移転が進んでいるようには思えず、また、賃上げしてもそれが消費に繋がっているとも思えない。
結果的に物価は上がっているが、内需が拡大しているともと思えない。
本書内でも触れているが、やはり将来・老後への不安があり、物価も上がっているため、消費拡大には繋がっていないように思う。
老後への不安に関して、藻谷さんも「年金」制度に関して、抜本的な見直し案を提示されている(ざっくり言うと世代間扶養ではなく、世代内共助)。
一考の余地はあると思うが、藻谷さんの案は現実的には難しいのではないかと思う。制度の中身もさることながら年金制度を抜本的に見直しができる政治状況にはそうそうならならいと思うからである。
(憲法改正と同じぐらい難しいのではないかと思う)
私自身は、将来・老後への不安は間違いなく消費不振、内需不振につながっており、日本経済へも当然影響していると考えている。
また、本書で指摘されている通り「人口減少(具体的には生産年齢人口)」は、間違いなく悪影響をおぼしており、この傾向が当面変わることがないのも事実だろう。
藻谷さんが本書内で指摘されているように、抜本的な原因を探り、そこを対策する必要が2024年の現在も必要だろう。
一人でできることは限られているが、まだまだ私自身の勉強不足を痛感させられた一冊であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
