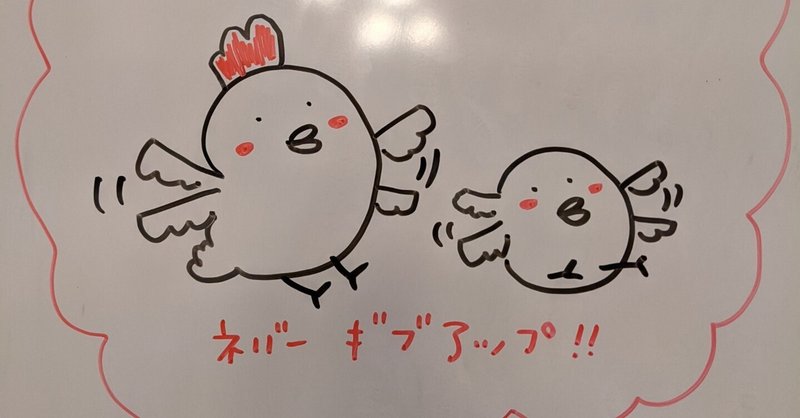
不思議なことに
芝居に関わりはじめてから、不安が消えた。
今までのわたしなら、絶対あり得ないことだ。
すごく安定している状態でも
公演が決まった途端に、心が揺れ始める
そんな人間だったのに
一体なにが起きているんだろう。
不思議過ぎて、面白くなってくる。
気づいている。
母の死の後から、変わったこと。
救いを求めていた。
この闇から抜け出す方法などないと思った。
ここは地獄だ。そう思った。
その瞬間からなにかが切り替わったのだ。
だから、脳みそで色々考える前に
わたしは気づいたら稽古を見学に行っていた。
正直、あんなに恐れていた芝居を
そんなに簡単にやろうとするその心理が
自分で全くわからなかった。
非常時、だった。
非常時、わたしはいつも
誰よりも行動が早いのだ。
普段は誰よりものんびりでぼんやりだけれど。
命に関わる
精神のある種の破綻に関わるなにかだった。
母の死は。
考えることではなかったのだ。それは。
わたしはたくましく
誰よりも野生的に、生き直さなくてはならない。
そうしなければ、枯れていくだけだ。
母を失ったわたしには
モチベーションなどほんとうのところ
ないに決まっているのだから。
ひとつだけ。
ひとつしか、方法はなかった。
板に立つこと。
それ以外に、わたしが暗く
入り組んだ袋小路にしゃがみ込むことを
回避する術はなかった。
芝居をやれば生きられるのだろう。
どうせ。
そう思った。
もう認めるべき時だ。
もう10年もたった。あれから。
すべては時効で、すべては笑い話だ。
どうせ。
どんな悪夢を見ても
この世の地獄を見ても
離れられなかった。
何もかも失っても
心を病んでも
それでも
芝居は、わたしから離れてゆかない。
どうせ。
わたしはそんな人間なのだ。
母は、それを知っていた。
わたしが時間稼ぎをしていることに
気づいていた。
時間稼ぎをしたまま
一生を終えたい。そう思っていた。
芝居が大嫌いで、憎くて
許せなくて、過去にしたくて
わたしから離れてほしかった。
でも、それは不可能だった。
母が死んだ時
芝居が出来たら、楽になれる。
そう思った。
稽古をすれば、台詞を言えば
きっとすごく楽になれる。
それだけが頭を支配した。
叫びだしたくて
やるせなくて
命が大嫌いで
死が大嫌いで
神様が大嫌いで
そのことを、伝えかった。
生きている、誰かに。
それが演劇だったと
遠い頭で、思い出していた。
動き出した歯車に
巻き込まれてつぶされそうだけれど
うまくかわしながら
回り続けていけるように。
わたしは、どこまでも無限に
心から強くなりたいと願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
