
時代の変わり目と共に現れたSSW達による其々の内省

今日、ご紹介するのは、70年代初頭のSSW達の作品です。
60年代におけるロック・シーンの主流であったサイケデリック・ロックやフラワー・ムーヴメントの熱気は、ウッドストック・フェスティバルで一つのピークに達しました。
しかしながら、70年代の始め、ロック・シーンは、60年代のアイコニックであったビートルズやジミ・ヘンドリックスやジム・モリソンらを失い、その狂騒も次第に沈静化していきます。
そうした時代の変わり目においてシーンで支持を受けたのは、「パフォーマーが自分の経験を下敷にした曲をみずから歌う」(1)ことを特徴とするSSW達でした。
彼らが発表した内省的な作品群は、其々モチーフこそ違えど、長期化した戦争や暴動とそれら一連のデモストレーションによる疲弊と重なり合うかのように、人々の心に寄り添うような形となりました。
そして、同時代のSSWによって築かれた音楽的なスタイルや社会的なスタンスは、やはりその後のオルタナ系のSSW達においても参照される事となり、ロック・ミュージックにおけるSSWの在り方としてもある種の普遍性を持つものとさえなったのです。
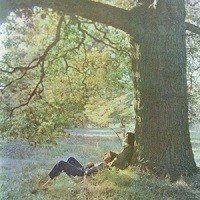
『John Lennon/Plastic Ono Band』/John Lennon/Plastic Ono Band(1970)
作品評価★★★★☆(4.5stars)
ビートルズのリーダーとその伴侶による前衛的な作品群とそれに関連するパフォーマンスの積極的な展開は、目論見通りにセンセーショナルな事件となったが、それと同時に、同バンドからの離脱を示すものでもあった。
プラスティック・オノ・バンド制作によるレノンの1stは、アーサー・ヤノフなる博士による極端な心理療法の影響もあり、自身のパーソナリティがあまりにも赤裸々に曝け出された作品となり、スペクターらと共に創り上げた非常にミニマルなサウンドで宣言されたのは、ヨーコとの愛以外のものに対する決別であった。
ジョンのソロ・ワークスは、今作と次作によってひとつの完成をみるが、ロック史におけるロックンロール像というアングルから考察すれば、所謂「失われた週末」期の作品も興味深く、ジョンがプレスリーやディラン、あるいはリードやイギーとも異なる独自のスタイルを持つロックンローラーであった事を改めて認識させてくれる。

『After the Gold Rush』/Neil Young(1970)
作品評価★★★★☆(4.5stars)
L.A.のアーティスティック・コミュニティを拠点としていたカナダのSSWは、クレイジー・ホースやCS&Nらとのセッションで活動を軌道に乗せ、時代の寵児の一人として現代アメリカにおける一つの時代を背負い始めた。
ヤングの代表作である今作3rdは、前作と同様、盟友デヴィッド・ブリッグス監修の下で制作され、シンプルなスタイルでありながら独特な筆致を持つフォーク/カントリー・ロックとその寓意によって崩れゆく黄金時代の憂愁を描写した。
翌年、もう一枚の時代の風景画によって成功を収めたロックンローラーは、大衆からの期待に反するかのように、所謂「ディッチ・トリロジー」期へと沈んでいくが、後年の狂熱的な再評価を経て、その苦悩する様もまたロック史における一つのロックンロール像となった。

『Ladies of the Canyon』/Joni Mitchell(1970)
作品評価★★★★(4stars)
北米の各都市/フォーク・シーンでの活動を地道に積み重ねていたカナダの美術大学出身のSSWは、移住先の西海岸から発表した作品で自画像を与えたが、それはヒッピー・カルチャーにおけるある種のランドマークともなった。
リプリーズから発表された3rdは、フォーク路線の踏襲とそこからの僅かな逸脱によって展開され、ウエスト・コースト・ロックの中心地であるローレル・キャニオンを背景に、消え去りつつあるウッドストック幻想が繊細かつ儚げに描かれている。
SSW作品の金字塔となる次作によって、ロック史における最も偉大な作家の一人として数えられる事となったミッチェルだが、その後のアート色を混じえジャズへ接近していく意欲的なアプローチは、次なる世代からのフォローとの結びつきをより強くするものとなった。
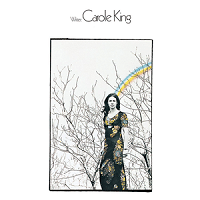
『Writer』/Carole King(1970)
作品評価★★★★(4stars)
50年代の華々しきポップスター/ニール・セダカ達などの楽曲を手掛けていた職業作曲家は、同じくブルックリン出身のユダヤ人であるパートナーのジェリー・ゴフィンとの別れと共に、東海岸のブリル・ビルディング一派から西海岸のローレル・キャニオン会派へと転身した。
ベールを脱ぎ始めたSSWによる処女作は、職人ゴフィン=キングによる鮮やかな手捌きと友人ザ・シティやテイラー達のらしい味付けで料理されたバラエティに富む楽曲が並べられているが、彼女の凛とした歌と佇まいは、個の作家が求められる時代と確かに呼応した。
次作にて大きな成功を手にしたキャロル・キングだが、才能に溺れる事なく、その名声に見合う堅実なキャリアの積み上げと多岐に渡った活動は、いつしかSSWにおけるロール・モデルの一つとなり、彼女は、長年に渡って市井の人々の良心的な存在であり続けている。
註(1)キャサリン・チャールトン『ロック・ミュージックの歴史 下 スタイル&アーティスト』佐藤実訳、音楽乃友社(1997)
それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が印象的だった楽曲を♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
