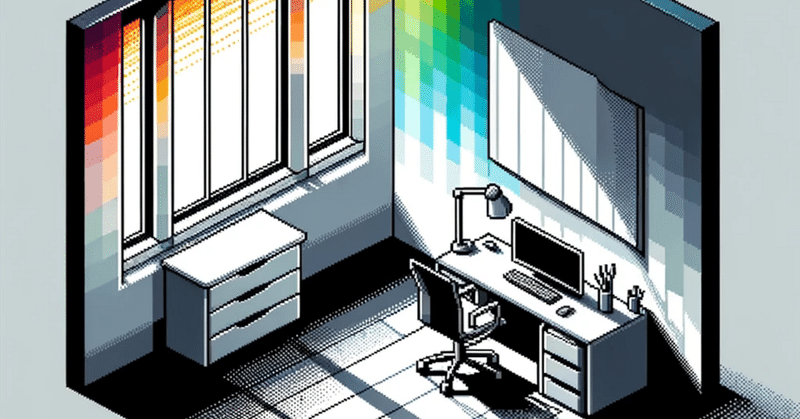
■りある
久保田ひかる
Ⅰ.メゾンドクレッシェンド二〇二号室の男
Kくんの無謀な試みの話をしようか。
まずは、君たちに見てもらう部屋を説明するとしよう。薄暗くて小さなアパートの一室さ。部屋の床にはカロリーメイトの空き箱と、空になった水のペットボトルが整然と並べられていてね。部屋の奥には一台のスチールデスク。安っぽい備え付けデスクライトの明かりの元で、一人の男が必死に何やら書いている。彼がKくん。本名は久坂孝雄と言うんだけれど、本人がKと名乗るつもりらしいからね。僕は付き合ってあげようと思っているよ。
これだけの説明で、賢明な読者諸君の脳内には、多分に陰を含んだ部屋が想像されているんじゃないかな。大体でいいのさ。ある程度イメージしておいてくれたら十分だ。僕は確信を持ってそう言える。何て言ったって僕は君たち読者を信頼しているからね。ところがKくんと来たら、その信頼が全くないんだ。読む誰かってのが厄介だからまあ仕方ないんだけどね。
最近巷じゃ、フォビアが大流行さ。閉所に高所に集合体なんてのはよく聞くね。ピエロに摂食、醜形、花なんかにも生理的恐怖を感じる人がいるらしい。別に価値評価を加えようってつもりじゃないのさ。皮肉めいて聞こえたらそれは謝るよ。僕はKくんの話をしたいだけなんだ。つまり、彼もフォビアになったんだね。今の彼は記憶が怖いのさ。
そうなるに至った経緯は、Kくんに代わって僕が簡単に説明するとしよう。彼に任せてしまったらどれだけ掛かるか分かったものじゃないからね。
例えば、Kくんには高校時代に付き合っていた彼女がいた。名前を青葉さんと言う。Kくんと青葉さんは高校三年の時に同じクラスだった。
初夏の頃、高校の体育祭の日さ。Kくんは、朝一の競技だった綱引きで負傷してね。救護室に運ばれたところで、当番だった青葉さんに引き取られた訳だ。同じクラスとは言えほとんど関わりのない者同士、救護室からグラウンドを眺めて世間話をしていた。それは競技と競技の間でグラウンドが空になっていた時のこと。何があったか、役員がグラウンドを疾走していてね。その姿勢と勢いがあんまり良かったものだから、Kくんは言ったんだ「フォレストガンプみたいだ」って。青葉さんはそれに笑ってくれたんだ。そこから映画の話が盛り上がってね。そんな出会いから彼らは仲良くなった。夏休みくらいには付き合う事になった訳さ。彼の初めての相手だって青葉さんだったんだよ?大学で離ればなれになってからは、あまり長く保たなかったけれど、Kくんにとっては大事な青春時代の相手さ。少なくとも彼の中ではね。
26歳になったKくんの元に、同窓会のお知らせが届いた。彼は出席で返した。数年来彼女のいなかったKくんは青葉さんの事を思いだして、淡い期待を寄せたりもした。当日は持っている中で一番爽やかな服を着て、美容院にだって行ったんだ。今の無精髭で脂ぎった髪の彼からは想像も出来ないけれど、彼はまだ人生に希望を持っていたんだよ。
ところが、同窓会には青葉さんらしき人はいなかった。ほんの数年の間が空いただけとはいえ、自分が気付けていないだけかもしれないと最初にはそう思ったんだね。Kくんは周囲の人々に青葉さんのことを聞いて回ったさ。すると何故か皆が口を揃えて言うんだ。「青葉なんていたか?」
気持ち悪くなって、彼は帰ることにした。ついでに実家にも寄ってみたんだ。会場から比較的近かったしね。それで、両親への挨拶もそこそこに卒業アルバムを引っ張り出して、頁を捲ってみた。なんと、そこには青葉さんはいなかった。驚いて、親にも聞いてみた。しかし、Kの高校時代に彼女なんていなかっただろうと、そう言うわけだ。
気味が悪くなって、彼はアパートに帰ったよ。
これが大体今から半年前、最初の事件。
青葉さんの事件が薄れないうちのある日、その日は休日だった。正確には、無理に家を出る必要がなかったといったところかな。
Kくんは昔から映画が好きだった。元気の出ない休日には、大好きな映画をお家でダラダラ見ながら過ごすことに決めていたんだ。
その日はどうしても、とあるSF映画が見たい気分だった。邦題は「二〇〇光年の別れ」。初めて見たのは大学生の頃だった。あらすじとしては、未来の世界を舞台に地球に迫った危機を救うべく、主人公達は百光年離れた惑星へとコールドスリープで向かい帰還するというもの。ただしこの映画の中心は彼らの宇宙旅行ではない。二〇〇年の間地球を離れるチームと地球に暮らす家族との別れ、そして帰ってきた後の社会との間で悩むチームの姿が丁寧に描かれる。Kくんはその異常な日常が大好きだったんだ。
部屋のベッドに腰掛けて、自慢のプロジェクターをセットしながら、サブスクで「二〇〇光年の別れ」を検索する。しかし、なかなか見つからないわけだ。確か以前に一度再生しているはずなのだが、どうにも見つからない。ただ、サブスクのラインナップは知らぬ間に変わることもあるものだ。仕方なく、彼は別のサイトで検索をかける。しかし、ここでも見つからない。ショッピングサイトで調べてみてもDVDやBlu-rayは売っていないし、試しに近くのレンタルショップに足を伸ばしても見つからない。インターネット検索にも引っかからないし、一緒に見た記憶のある友人に聞いてもやっぱりそんな記憶はないというんだ。
Kくんは勿論、消えてしまった青葉さんの事を思いだした。それから不安になってしまった。世界が自分にドッキリを仕掛けているような気がして、それから理性的に次の推測を連れてきた。それはつまり、Kくんの頭がどうにかしてしまったんじゃないかってね。どうしても気分を変えたくて、その日は代わりに「グレタ」を見ることにした。凄腕の女殺し屋の復讐映画である。これは、Kくんにとって始めて見る映画だった。それなりに気になっていた作品ではあったんだよ。状況が状況だったけれど、まあ多少気を紛らわす程度には面白かったんだ。
どうもおかしい、Kはその頃からかなりハッキリと恐怖感を感じ始めた。
確かにKくんは、世界に何かおかしなことが起きているんじゃないかってそんなSFめいたことも考えたんだ。自分の記憶に自信を持ってもいたんだよ。青葉さんの件も、映画の件も、彼にとって決して些細な事ではなかったからさ。しかし悲しい哉、卒業アルバムが、インターネットの情報が、周囲の人々が、全ての事実が、間違っているのはKくんだと示している。これでやっと彼も敗北を認める気になったのさ。異常と呼ぶにより相応しいのは、彼自身の記憶だった。
彼の記憶が虚偽になる速度は日に日に加速していった。ある晩に朝食用にと買ってきた食パンが翌朝には消えてなくなっていたし、隣の研究室の顔見知り程度の同期は一人いなかったことになった。大学にあった3か所の屋外喫煙所の一つは高く伸びた樹木に上書きされたし、ある時なんかは駅で道を尋ねてきた見知らぬ老人が一瞬目を離した隙にいなくなった。Kくんは異常が自分の世界を塗りつぶすまでの時間を考えることが多くなった。不安に駆られた結果として、彼は毎晩自分の記憶を確かめだした。例えば好きだったバンド、昔働いてたバイト先、通っていた学校。バンドはあったよ。けれど、好きだったアルバムの中の曲が記憶と違っていた。バイト先はあったよ。けれど、不思議な商品があった。チェーンのファーストフード店なんだけれど、ちょうど現在復刻発売しているドリンクがあってね。それが、どうやらKくんが働いてた頃の人気メニューらしいんだ。勿論彼には知らないドリンクさ。ちょっと美味しそうだったのが笑い話だね。もしバイト当時にそれを知っていたらKくんが飲まないはずがないようなもの。学校も似たようなものさ。いやいや、学校がなかった訳じゃないよ。けれど、学士時代の大学について調べるにあたって、記憶に残ってるという理由から大学三年の夏に見た講演会について検索したんだ。頑張ってホームページ上の記録を探し回ったにも関わらず、そんなものはなかった。代わりにKくんには全く縁遠いイベントが開催されていたってね。
Kくんがノイローゼになるまでそう長い時間はいらなかったよ。食品添加物を気にする人たちと一緒さ。わざわざ確かめに行かなければまあ生きていけるけれど、一度確認し始めちゃうとなんでもかんでも気になっちゃうわけだね。睡眠時間を削って自分の記憶を確かめる日々が続いて、自分の記憶と現実の記録との差はどんどん大きくなった。
彼の記憶は、日に日に彼だけのものになって行った。覚えていることが現実だと証明したい気持ちは波のように起こったさ。理性と感情が寄せては返しってね。Kくんだって好き好んで異常者になりたいような歳じゃない。ワクワクするほど若くなかったんだね。でも、世界が彼の記憶は虚偽だと示しているし、Kくんに“何が起きているか”説明する力なんてなかったからね。まずいことになっているという事しか分からなかった。K君に限らず人間てのは恐ろしいものだね。僕はこういう時に心からそう思うよ。どちらが傲慢なんだろうか。世界が自分の知っている通りの姿だと思っていることと、そうでないことに恐怖することとでは。
精神に変調を来しながらも、K君は昼間の生活を変えなかった。何故かと言えば簡単で、彼がなんとか自分にしがみ付いている理由であり、とびっきり恐れたことがそこにあった。それはつまり、彼を彼たらしめる、世界に突き刺した鋲のようなもの。好きだった人が消えてしまっても彼は彼でいられた。映画もそうだし、朝食のパンが消えた程度それこそ数日で記憶の隅に追いやれるような話だ。そんな彼はとある男の消失に心の底から怯えていた。
男の名はマイケル・ジョン・ハリスン。イギリス人のSF作家。K君の研究対象。
Kくんは世界の変化に、そして何よりハリスンの消失に怯える日々を更に一か月ほど過ごした。世界は“目まぐるしい勢いで変化”した。けれどハリスンは消えなかったし、そんな中でも研究は多少進んだし、研究に支障が出るような事は起きなかった。
面白いものだね。理解不能な異常の中に取り残された人間には選択肢が二つしかないらしい。つまり、諦めるか死ぬか、その二択さ。その頃には彼はもう自分の記憶を確かめるのをやめていた。変わりゆく世界を見ないことにするには思い出さないことが一番の方法だったんだ。
そんなある日の話さ。
お昼のこと、近くのカフェでナポリタンを食べていたKくんの耳に飛び込んできた。
「聞いたわよ佐々木さん。ついに離婚成立したらしいじゃないおめでとう。あ、もう佐々木じゃないのか」Kくんの隣のテーブルではOL4人組が何やら盛り上がっていた。
「そうなんです。やっとあのDV夫から離れられましたよ。離婚して、藤田に戻りました。でも職場では佐々木でいいですよ。」Kくんは野次馬根性で隣をチラと見る。佐々木兼藤田さんは控えめな感じの女性だった。
「藤田さん?佐々木さん?すごかったんですよ。私ちょっと見せてもらったんですけど、半年くらいだっけ?元旦那の行動を丁寧に丁寧に日記につけてて」また新たなOLが口を挟んでいる。それに今度はうっすらと笑みを浮かべた藤田が返す。
「だって、ただ離婚しただけじゃあの人への復讐にならないもの。ちゃんと慰謝料ぶんどってやろうと思って調べたんですよ。そうしたら、動画とか写真に加えて日記に証拠能力があるって出てきて。もちろん音声なんかも撮りましたけど、出来ることは全部しようってね。」
Kくんが飛びついたのはこの発言だった。今まで考えもしなかったけれど、日記が証拠として認められるという事実は彼にとっては衝撃だった。そして一つの仮定が浮かんできた。何故ハリスンは消えなかったのか。ハリスンの周辺の作家や、歴史的事実は不動だったのか。Kくんだって馬鹿げた想像だってことくらいは無論理解していたけれどね。でもほら、馬鹿げたことが起きているんだから仕方ない。こればっかりは僕も彼を擁護しようじゃないか。
ここまで説明したら、今暗い部屋のデスクでKくんが必死に書き物をしている経緯が分かってもらえたかな?
インターネットが、知り合いの記憶が、現実が彼の記憶を塗り替えている今、彼の記憶を証明してくれるのは彼自身のみだからね。嘘になってしまう記憶を正しく保有する術として、彼は日記を鋲に選んだってわけなんだ。
Ⅱ.日記について
Kくんの結末に興味があるかい?だとしたら君には加虐者の才能があるよ。こんな人間がハッピーエンドなんか迎えるわけがないじゃないか。だけどまあ、君がKくんを哀れんでいるよりは嘲笑っている方がずっと有りがたいね。だって、君がKくんを哀れんでいたら僕だけが悪者みたいじゃないか。
贅言はこの程度にしなきゃね。このお話しは僕じゃなくてKくんのものだからさ。そろそろKくんにも語ってもらわなくちゃあいけない。少し時間を戻そうか。記念すべき第一号をお見せしよう。
*
2023/08/28(月)
7:00 起床 朝食代わりにプロテイン摂取 顔を洗うなどし、着替えて家を出る
7:45 学校へ向かう。(徒歩及び電車)
8:30 研究室到着 メールを確認 喫煙
9:00 準備室から、注文していた論文が郵送されてきていたのを受け取る。
届いた論文に目を通し、内容をまとめる
12:00 昼休み ナポリタンを食べる 藤田(佐々木)の話を盗み聞く
日記は証拠たり得る ※重要
13:30 ハリスン語彙辞典の作成を進める。メスヴェト・ニアンについてやや進展アリ
15:00 ヒュームの人間本性論に取り組むも、難解。進展はなし
16:00 喫煙
18:00 退勤 喫煙
18:30 最寄り駅でスーパーに立ち寄る。
ノートとボールペン、カロリーメイトに水を購入。
18:50 帰宅 シャワーを浴びる
19:20 現在 部屋のデスクに向かって日記を書いている。
*
Kくんは肩肘張った妙な姿勢でノートにアウトラインを書き上げた。多少の興奮はあったよ、何か解決の糸口を見つけたような気でいたんだから。けれど、すぐに筆を止めてしまった。果たして、何を書くべきか。何から書くべきか。彼にとってはそれが問題だった。落書きに「デスクライトの明かりが薄暗い」などと書き足す。
書かなくていいこと、それは一つ明白だ。MJハリスンについて、これは既に大量に書いてきた。書いてきたことは消えていないはずだ。
だから消えちゃ困ること重要な事、まずはお昼のことを書こう、そう思ったんだ。
*
12:00頃、今日のお昼のこと、私がナポリタンを食べながら聞いた会話について記しておく。隣の卓では、OL4人組が何やら盛り上がっていた。
「聞いたわよ佐々木さん。ついに離婚成立したらしいじゃないおめでとう。あ、もう佐々木じゃないのか」
「そうなんです。やっとあのDV夫から離れられましたよ。離婚して、藤田に戻りました。でも職場では佐々木でいいですよ。」私は隣をチラと見る。佐々木兼藤田さんは控えめな感じの女性だった。
「藤田さん?佐々木さん?すごかったんですよ。私ちょっと見せてもらったんですけど、半年くらいだっけ?元旦那の行動を丁寧に丁寧に日記につけてて」また新たなOLが口を挟んでいる。それに今度はうっすらと笑みを浮かべた藤田が返す。
「だって、ただ離婚しただけじゃあの人への復讐にならないもの。ちゃんと慰謝料ぶんどってやろうと思って調べたんですよ。そうしたら、動画とか写真に加えて日記に証拠能力があるって出てきて。もちろん音声なんかも撮りましたけど、出来ることは全部しようってね。」
この会話から私は重要な発想を得た。世界は私の記憶にある姿を次々と消している。嘘にしてしまっている。少なくとも、私はそう認識している。いつか私が精神病として扱われる日が来たらこのノートも多少面白いものとして読まれるかもしれないが、まあそんなことは冗談だ。
消えていく中で、一切の影響を受けないものがあった。それがつまりMJハリスンについての研究成果である。これは、ハリスンの存在と彼が残した作品は勿論として、ハリスンの周囲の人物や社会状況、多岐に亘る学問分野の先行研究などなど、かなり広範な情報を基盤に成り立っている情報であるが、今のところ問題なく進んでいる。私はこれが幸運であるとそう思っていつ消えるかと冷や冷やしていたが、佐々木兼藤田の発言を重ねてみるとどうだろう?そう、書かれたことは確定される、書かれなかった事は自由に上書きされてしまう。私はこの重要な出来事、「日記≒記述は記憶の証拠たり得る」をここに打ち込んでおく。この記述は私が私の世界を留める為の第一の鋲だ。
*
どうだい?Kくんの満足そうな顔、君たちにも浮かぶだろう?ニヤついた気持ちの悪い顔さ。僕はどちらかというと好きじゃないかな。別に幸せに生きてくれようと不幸であろうと構わないんだけれど、間抜けなニヤけ面ってのはあんまり気持ちのいいものじゃない。そうなんだよ。彼はあんまりにも間抜けだったんだ。読者諸君はKくんよりも賢いだろうし、それに何より彼よりもずっと冷静にいられるだろうからその間抜けさにもう気づいているかもしれない。彼は決定的なミスを犯してしまった。
この晩、彼は満足げな顔をして眠った。翌日も彼はやっぱり大学に出て行ったよ。反逆者を気取ってね。
けれど、彼は手に入れたものよりも手放したものが無限に大きかったことに気づく事になる。
Kくんが通学している時点で、違和感が彼を襲った。確かマクドナルドがあった場所がミスタードーナツになっていた。よく飲み物を買うために寄ったコンビニエンスストアがあった場所には、庭の広い一軒家がたっていた。注意をして見ていくと、並んでいる家々の景観もなんだか違ったように見えてくる。おかしい、おかしさが分からないほど広いレベルで、おかしい、Kくんは足早に研究室に向かった。
デスクについた彼に背後から声をかけるものがあった。
「孝雄くん、ちょっと橋本教授から頼まれごとしてるんだけど協力してもらえない?」振り返ると、そこには見知らぬ同年代の女が立っていた。
「橋本教授?」相手の女の親し気な声が、単刀直入に名前を尋ねることを避けさせた。
「あれ?久坂君橋本さんの授業取ったことなかったっけ?独文科の先生で、今度学部生向けの授業で参考にする資料の一部をまとめてくれないかって」
「ああ、そうか。橋本教授ね。どんな授業してたっけ?」
「私がとった、院生向けのやつは、『Die unendliche Geschichte』の構造についての授業だったけど。今回の依頼は学部生向けの般教で、西洋現代SF作品を使って物語のリアルとフィクションとは何かってテーマでやるらしい。それで私らに依頼が来たってわけ」
「ああ、そうか。あれ、ごめん、ど忘れしたんだけど、君の対象は誰だっけ?」
「私はブラッドベリよ。現代社会とブラッドベリ的ディストピアについて、よく相談乗ってもらってるじゃない。」
「そうだったそうだった、ごめん。ちょっと最近頭がぼんやりしてて」Kくんの知っている世界には、同じ研究室にSF作家を対象にしていた人間はいなかった。
「疲れてるなら、今日は夕飯作って待ってるよ。」女の顔が柔和に変わるのが分かった。「来るでしょ?今夜、火曜だから私バイトないし。」
「そう、だね。他は誰かくるの?」
「ちょっと、どうしたの?心配になるからやめてよ。毎週火曜日の夜はあなたが私の家に来て泊ってるじゃない。友達呼びたければ構わないけど、もしかして何か怒ってる?」女は眉間に皺を寄せた。ここまで来て、やっとKくんにも何が起きているか分かってきた。
Kくんは、変なところで頭が回ったものだ。SF作家を研究してきた成果が出たのかな?女との会話は適当に濁して打ち切った。世界が変わった結果、「自分に彼女がいることになったらしい」と理解した彼はスマートフォンを取りだした。青葉さんの時も、「二〇〇光年の別れ」の時もそうだった。世界の変化は人間がやるドッキリみたいなレベルじゃない。やっぱりスマホにはトークの履歴があった。どうやら彼女は浜田美香と言うらしい。Kくんは彼女を「みか」と呼んでいて、半年ほど前から付き合っているらしい。自分が知らぬ女といちゃいちゃしている会話と言うのはなかなか苦しいものがあって、Kくんはすぐに見るのをやめてしまった。
「みか」のことを最低限把握しようと努めているうち、お昼になった。別に時間通りにお昼を摂ることを絶対としている訳でもなかったが、その日Kくんは確認しなければならない事があった。研究室を出ると、ノートを片手に昨日の喫茶店へと向かった。
果たして、そこにあったのは「ピザとパスタの店らぱん」だった。可愛らしい看板がかかっていて、やや浮世離れしたメルヘンなレストランが立っている。ご丁寧に店舗の前に置かれた立て看板にはおススメのナポリタンについて書かれていた。
慌てて日記を確認してみるとなるほど確かにそこには“喫茶店”の記述がない。Kくんは今更になって自分が相手取っているものの底意地の悪さに気が付いた。多分、もうあと数分あったら彼の決定的なミスに気が付いたんだろうね。彼の意識は別の存在に持っていかれた。
「二日連続で来ちゃったわね」
「昨日のナポリタン美味しかったんだもの」
「佐々木さん、今だったらなんでも美味しく感じるんじゃないの?」
「ちょっと、やめてくださいよ!否定しづらいんだから」数人の女性が談笑しながら連れ立って店に入っていった。彼が昨日見たOLの集団はそこにいた。Kくんの仮定は承認されていた。彼が書いた世界は確かにそこに残っていた。
その日の夜、Kくんは浜田美香の家に行った。夕飯を食べて、彼女の思い出話を聞いた。二人が付き合うまでの事、付き合ってからの事、知り合う前のみかの幼少期のこと、根掘り葉掘り聞き込んだ。みかは妙な顔をしながらも話してくれた。彼女は明るくて話の上手い女性だった。この上書きされた現実に矛盾を見つけ出そうとしてKくんは面倒な質問だって投げた。中でも、「俺たちが付き合ったのってどうしてだっけ?」という質問はなかなか巧かった。彼女が説明するだけでは足りない。Kくんが納得できなきゃいけない。けれどみかは事も無げに答えた。「色々あるけど、いつも二人で言ってるじゃない。私たち二人とも興味があって大事にしてることが狭くて少ないから、それを共有できる人間ってだけで随分居心地が良かったのよね。…勿論、そのせいで喧嘩も多かったけど。」みかは恥ずかしそうに笑って、Kくんはううむと唸った。
Kくんはみかを抱きしめて眠った。
翌朝、Kくんは目覚めた。目が覚めた時、彼は一人だった。部屋には彼以外、何もなかった。白く滑らかで冷たい床に、同じように白く滑らかな壁と天井があった。部屋には他に何もなかった。寝巻のままの彼だけがいて、浜田美香もいなければ家具もなかった。部屋を見回して後ろを振り返ると、まるで辻褄を合わせるように、空間には一冊のノートが突然落ちていた。
起き上がりノートを片手に外に出ると、そこには見知らぬどこにでもある町があった。真白な部屋も外観は普通のアパートだった。Kくんは、一晩何も書き進められていないノートを取り出して呆然とした。世界に狙われている、そうはっきりと自覚した。スマートフォンを開いてみると、みかとの会話履歴は消えていた。「ああ、事実俺が書いたものじゃないとダメなんだ」彼は一つ発見をした。半袖で暑いくらいなのに、画面には4月93日(腑)と表示されていた。
Kくんはノートの記述を頼りに、まず学校に戻った。学校はあった。研究室に彼のデスクはあった。それだけだった。パソコンを起動して、自分の記録を確認すると、やはりMJハリスンは存在した。
Kくんは家に帰った。随分と切ないシーンだったよ。知らないと確実に分かる町と知らないと確実に分かる人の間を歩き去っていく彼の姿の悲壮なこと悲壮なこと。何が一番Kくんにダメージを与えたかって、それは見知らぬ町は穏やかで、見知らぬ人々には笑い合う人間もあったって事さ。彼は自身が取り残されてしまったことを理解した。
彼の部屋からはあらかたの物が消えていた。彼の予想通りだ。デスクと筆記具、カロリーメイトと水が転がっていて、シャワー設備はあったがトイレはなくなっていた。デスクに座ってライトをつける。彼はもう目の前のノートに何を書いていいか分からない。頭の中で言葉が文章を形作るまでに大変な時間が必要だった。やっとの思いで「世界は俺の記憶の通りの姿をしていた。」と書いてみた。
窓辺に立って見つめた景色は全てが陽炎のように揺らめいていた。再び席に戻ると彼は先に書いた文に線を引いて削除した。削除しても窓の外の景色は変わらなかった。試みに、学校のあった場所の住所と記憶の限りの地図と外観を書いてみる。窓の外には遥か遠く、陽炎の向こうに何か明確な存在が生まれていた。
呆然とノートを眺めたKくんはある記述に目を奪われる。“書かれたことは確定される、書かれなかった事は自由に上書きされてしまう。私はこの重要な出来事、「日記≒記述は記憶の証拠たり得る」をここに打ち込んでおく。この記述は私が私の世界を留める為の第一の鋲だ。”
世界の在り方を規定してしまったのは彼だった。
*
書くということが世界を形作るとしたら、何を描くべきだろうか。何かを選んで描くということのなんと贅沢なことよ!それは圧倒的な信頼のある世界に裏打ちされているのだ。何者かを選ぶとは、選ばれなかった何者かをなかったことにするという、そんな単純な事にも気づかずに
*
結局彼は、レポート用紙の裏表紙に一言こう書こうと決めた。こう書くしかなかった。
“Kなんて人間は、世界と何の関係もなかった。”
けれどそれは果たされなかった。既に世界は■■■■■■■■■■■
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
